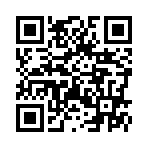一番学んだのは私
ファシリテーター仲間の勉強会。
進行役が、これまで実践し効果のあがった実習事例を報告し、メンバーに体験してもらうもの。
2グループに別れ、テーマを決めた。
同じ実習をテーマを変えて二回行う。
一回目はやりかたを理解するために、取り組みやすそうな楽しそうなテーマを、与えられた中から選ぶ。
メンバーそれぞれ、ばらばらな意見だったけど、まぁいいかとほぼ全員がなんとなく妥協したテーマで取り組んだ。
結果・・・・
一回目の体験では、思った以上に楽しく、メンバーのことを知ることができて、関係が近くなったきがした。いまひとつなテーマだと思ったのに!
これは意外。
二回目は、本番・・ということで、一回目で実習の構造(やりかた)を知ったので、もう少し実践的なテーマに取り組む。
しかしながら、今回はほかのメンバー全員が乗り気だけど、私だけ、乗れないテーマ。
でもま、時間もないしここで合意形成するまでの時間をかけるよりも、勉強会の本題である実習体験のほうが大事かと、納得の上で妥協。
研修であたえられたテーマだとしたら、参加者の中にいまひとつ乗り切れない人がいることもある。
そんな参加者ロールで、この実習を体験したらどうなるのかなー?という好奇心でそのまま参加してみた。
結果・・・
私は、乗り切れないままで終わった。
途中なんどか、乗れそうな場面があったんだけど、不完全燃焼というか、あれれ?とメンバーとの温度差は埋まらない。
「なんでなんで?」私にはたくさん聞いてみたいことがあるのだけど、この実習を限られた時間の中で完成させたいと思う、私以外のメンバーは、困った顔。
なんでかなー?
私だけ何が違ってるのかなー?私の反応はみんなと違うの?
前の日飲みすぎて、調子も確かに今ひとつだったけど。
そのせいかな?
テーマが、ぴんときてないからかな・・
途中から内側に入ってしまい、参加できなくなった。
きづいたひとりのメンバーが声をかけてくれたけど、「二日酔いだからかなー?」とやり過ごす。
入れない寂しい気持ちがあるけど、なんだかよくわからないのよ、どうしてなのか。
前に進めたいみんなと私の間には気持ちのずれがあって、邪魔をしてはいけないような気がしていたみたいだ。
結局、私ひとりだけ「チームビルディングに効果的」という体験はできず。
逆に疎外感。
終了後、なんでかなぁと、ふりかえる。
まったく入れなかったわけじゃない。
テーマには共感できなかったけど、メンバーの話を聞きながら沸いてきた思いがあった。
訊いてみたいことがあったし、そこにかかわっていったこともあった。
だけど、1回目と違って、2回目は私以外のメンバーのなかに、実習を最後まで体験したい。アウトプットを出したいという欲求がおこり、課題達成に向かう力が強くなっていた。
実習の意図した構造を省略するような動きになっていて、先に進めようというエネルギーが場にあったため、私のかかわり(構造上もとめられていること)はほかのメンバーにとって阻害要因に感じられていた様子。
(これは終了後にふりかえって、気がついたこと)
そこで自分なりにわかったこと。
A)この実習をチームビルディングに使うには、メンバーが興味の持てるテーマであることが望ましいこと。
B)興味のもてない人がいたとしても、実習の構造上、メンバーの思いや価値観や、表面にはすぐにでてこないものが明らかになっていく過程で、共感や、好奇心が生まれ、参画しやすくなり、チームビルディングにつながるであろうこと。
C)課題達成に意識が向きすぎて、実習の構造がいかされず、表面的なアイデアのみの共有でアウトプットにいたった場合、テーマに興味のもてない人は、参画できないで終わる可能性があること。
D)メンバー全員が興味をもって取り組めるテーマであれば、課題達成に意識が向きすぎて、多少実習の構造が生かされず、アイデアのみの共有で、その裏の思いや価値観が明らかにならなくても、効果がありそうであること。(ほかのメンバーの満足度は高かったので)
よってファシリテーターとして、この実習を活用する際の注意点は、
アウトプット(成果物)が目的にならないよう、実習の構造が生かされるよう、必要に応じて介入する。
そのためには、すべてのグループに目が届くような人数であることが望ましい。
上記が原則ではあるけれども、参加メンバーが共通の目的を持って、テーマに取り組む土壌があるケース(スポーツチームが優勝にむかってチーム力をあげるために活用する場合など)には、多少目が届かないような人数(グループ数)であっても、効果的であるようだ。(これは勉強会担当者の実践事例より)。
当初の私の目的の「チームビルディングに役立つ」という実感は体験できなかった。
が、この実習を実施するうえでの、ファシリテーターの留意点が明確になり、これをしっかり実施していれば、効果的であろうという感触を持つことができた。
今回、メンバーとして満足感を得られなかったことで、私自身はこの実習を活用する上で、大いに学びになったというのが、なんだかとても興味深い。
案外、今回参加者の中で一番学んだのは私かもしれない(^^)
進行役が、これまで実践し効果のあがった実習事例を報告し、メンバーに体験してもらうもの。
2グループに別れ、テーマを決めた。
同じ実習をテーマを変えて二回行う。
一回目はやりかたを理解するために、取り組みやすそうな楽しそうなテーマを、与えられた中から選ぶ。
メンバーそれぞれ、ばらばらな意見だったけど、まぁいいかとほぼ全員がなんとなく妥協したテーマで取り組んだ。
結果・・・・
一回目の体験では、思った以上に楽しく、メンバーのことを知ることができて、関係が近くなったきがした。いまひとつなテーマだと思ったのに!
これは意外。
二回目は、本番・・ということで、一回目で実習の構造(やりかた)を知ったので、もう少し実践的なテーマに取り組む。
しかしながら、今回はほかのメンバー全員が乗り気だけど、私だけ、乗れないテーマ。
でもま、時間もないしここで合意形成するまでの時間をかけるよりも、勉強会の本題である実習体験のほうが大事かと、納得の上で妥協。
研修であたえられたテーマだとしたら、参加者の中にいまひとつ乗り切れない人がいることもある。
そんな参加者ロールで、この実習を体験したらどうなるのかなー?という好奇心でそのまま参加してみた。
結果・・・
私は、乗り切れないままで終わった。
途中なんどか、乗れそうな場面があったんだけど、不完全燃焼というか、あれれ?とメンバーとの温度差は埋まらない。
「なんでなんで?」私にはたくさん聞いてみたいことがあるのだけど、この実習を限られた時間の中で完成させたいと思う、私以外のメンバーは、困った顔。
なんでかなー?
私だけ何が違ってるのかなー?私の反応はみんなと違うの?
前の日飲みすぎて、調子も確かに今ひとつだったけど。
そのせいかな?
テーマが、ぴんときてないからかな・・
途中から内側に入ってしまい、参加できなくなった。
きづいたひとりのメンバーが声をかけてくれたけど、「二日酔いだからかなー?」とやり過ごす。
入れない寂しい気持ちがあるけど、なんだかよくわからないのよ、どうしてなのか。
前に進めたいみんなと私の間には気持ちのずれがあって、邪魔をしてはいけないような気がしていたみたいだ。
結局、私ひとりだけ「チームビルディングに効果的」という体験はできず。
逆に疎外感。
終了後、なんでかなぁと、ふりかえる。
まったく入れなかったわけじゃない。
テーマには共感できなかったけど、メンバーの話を聞きながら沸いてきた思いがあった。
訊いてみたいことがあったし、そこにかかわっていったこともあった。
だけど、1回目と違って、2回目は私以外のメンバーのなかに、実習を最後まで体験したい。アウトプットを出したいという欲求がおこり、課題達成に向かう力が強くなっていた。
実習の意図した構造を省略するような動きになっていて、先に進めようというエネルギーが場にあったため、私のかかわり(構造上もとめられていること)はほかのメンバーにとって阻害要因に感じられていた様子。
(これは終了後にふりかえって、気がついたこと)
そこで自分なりにわかったこと。
A)この実習をチームビルディングに使うには、メンバーが興味の持てるテーマであることが望ましいこと。
B)興味のもてない人がいたとしても、実習の構造上、メンバーの思いや価値観や、表面にはすぐにでてこないものが明らかになっていく過程で、共感や、好奇心が生まれ、参画しやすくなり、チームビルディングにつながるであろうこと。
C)課題達成に意識が向きすぎて、実習の構造がいかされず、表面的なアイデアのみの共有でアウトプットにいたった場合、テーマに興味のもてない人は、参画できないで終わる可能性があること。
D)メンバー全員が興味をもって取り組めるテーマであれば、課題達成に意識が向きすぎて、多少実習の構造が生かされず、アイデアのみの共有で、その裏の思いや価値観が明らかにならなくても、効果がありそうであること。(ほかのメンバーの満足度は高かったので)
よってファシリテーターとして、この実習を活用する際の注意点は、
アウトプット(成果物)が目的にならないよう、実習の構造が生かされるよう、必要に応じて介入する。
そのためには、すべてのグループに目が届くような人数であることが望ましい。
上記が原則ではあるけれども、参加メンバーが共通の目的を持って、テーマに取り組む土壌があるケース(スポーツチームが優勝にむかってチーム力をあげるために活用する場合など)には、多少目が届かないような人数(グループ数)であっても、効果的であるようだ。(これは勉強会担当者の実践事例より)。
当初の私の目的の「チームビルディングに役立つ」という実感は体験できなかった。
が、この実習を実施するうえでの、ファシリテーターの留意点が明確になり、これをしっかり実施していれば、効果的であろうという感触を持つことができた。
今回、メンバーとして満足感を得られなかったことで、私自身はこの実習を活用する上で、大いに学びになったというのが、なんだかとても興味深い。
案外、今回参加者の中で一番学んだのは私かもしれない(^^)
ファシリテーショングラフィック・記録のとり方
効果的な板書の仕方。
ここでは模造紙を使った記録のとり方のご紹介です。
とってもアナログではありますが、これが優れもの!
結構マニアックな世界かもしれません。
この本で紹介しているほど、凝らなくても、基本を抑えておくだけで、
発言がぶれない!
誰かが前に言ったことが思い出せる!
次回の会議に「どこまで話したんだっけ?」「何がきまったんだっけ?」にならず、経過も含めて思い出せます。
一度手にとって見てください。
議事録のとりかた。記録のとりかた。板書のしかた。
へたくそです。嫌いです。コンプレックスがあります・・・
子供の頃から授業のノートはぐちゃぐちゃで、活用できた事ない。
でも東大入学者のノートのとりかたが、書籍化されて出ているのを読んだりすると、
やはり、ノートのとり方というのは大事だというのがよくわかる。
とはいえ、私はそれ(ノートの記録)をなんのためにノートするのか、がわかってなかったように思うのだ。ノートの記録=試験対策=「暗記」って思っていた。
で、暗記のために活用と思うと、もうとたんにダメ。意欲もなくなるし、だいたい、作ったノートで暗記なんか出来ない。
そのまえに「美しく、みやすく記録する」というところに意識の欠如があった気がするけど。
と、そんな背景を持った私は、「記録」「議事録」「板書」ちょー苦手です。
なのだけど。
5,6年前にファシリテーショングラフィックというのに出会いまして。
議論の見える化って大事なんだなって言うことを、体感。
その後、へたくそなくせに、っていうか、文字だけしか書けないけど、率先して板書をする。
ファシリテーショングラフィックっていうのは、グラフィック」っていうくらいですから、絵とか記号とかを使って「模造紙」にカラフルに話し合いの記録をとっていくんです。
大事と思われるところは大きく書いたり、盛り上がった所には、そういうことがわかるような印をつけたりね。
絵の得意な人が、工夫しながら書き上げていくのはもう芸術であり、
またそれを観ながら、話が活性化することもあり、次回の話し合いに、この模造紙の記録を張り出すことで、これまでの議論がすぐに思い出されたり・・
また縮小コピーして、議事録としても活用できる。
有益だなぁと思っているわけです。
でも私には出来ないんですね。絵がかけないから(涙) 字が下手だから。空間をうまく使えないから。
私の周囲にも優秀なファシリテーショングラフィッカーが出てきてくれないかなとひそかに思っているわけです。
↓これは一日習っただけの学生さんが書いたもの。


こちらは、指導者が書いたもの。
絵も苦手、空間把握して、予測して美しく仕上げるなんてのはチョー苦手なんだけどね、
記録する事で、議論がぶれなかったり、話が戻しやすかったり、誰かの発言が置いてきぼりになるのが避けられたり・・・いいことがたくさんあるんです。
また、どんな話し合いだったか?っていうのが思い出されるような記録ってのはいいなぁと思うんですよ。欠席者にも伝わるような。
それで、ときどき、チャレンジします。
臨場感がでる記録づくりに。
板書しながら、模造紙書きながら、途中で入ったチャチャを口語体でそのまんま記録したり、もりあがったところは、わかるように印をつけたり、あえて発言者の発言そのまんま、方言いれて書いたり。
最近は携帯で写真を撮って印刷し、そのまんま議事録として配布しちゃったりすることも。
先日はカフェでのうちあわせだったので、ホワイトボードもなく、手元用紙に「議事録」をとる役目だったのですが・・・
結局発言をほとんど記録する形になり。
だけどあとで読み返してみたら、話の流れがわかって面白かった。
「議事録」としての体裁を整える為、日付場所、時間、参加者名、テーマ書いて、この日の結論を書いて。
あとは、だらっと発言の要点を記録しておきました。
少なくとも参加した人にしたら、あの場でおこっていたことを思い出すきっかけになるだろうし、欠席したひとは、どういう背景でこういう結論になったのかっていうことがわかるのは有益じゃないだろうかと。
「記録」系は苦手という意識が強かったんですが、ファシリテーショングラフィックと出会ってから、「活用」に意識が行くようになったきがします。
絵はかけなくても、この「記録」がどんな風に役に立つのか、なんのための記録なのか?を意識する事によって、「記録」そのものが、ファシリテート・・・いろんなことを促進する役目を果たしてくれるんだなぁということに気がつきました。
というわけで、苦手意識はあっても、目的を遂行する為に出来る事として、チャレンジしていこうと思っています。
子供の頃から授業のノートはぐちゃぐちゃで、活用できた事ない。
でも東大入学者のノートのとりかたが、書籍化されて出ているのを読んだりすると、
やはり、ノートのとり方というのは大事だというのがよくわかる。
とはいえ、私はそれ(ノートの記録)をなんのためにノートするのか、がわかってなかったように思うのだ。ノートの記録=試験対策=「暗記」って思っていた。
で、暗記のために活用と思うと、もうとたんにダメ。意欲もなくなるし、だいたい、作ったノートで暗記なんか出来ない。
そのまえに「美しく、みやすく記録する」というところに意識の欠如があった気がするけど。
と、そんな背景を持った私は、「記録」「議事録」「板書」ちょー苦手です。
なのだけど。
5,6年前にファシリテーショングラフィックというのに出会いまして。
議論の見える化って大事なんだなって言うことを、体感。
その後、へたくそなくせに、っていうか、文字だけしか書けないけど、率先して板書をする。
ファシリテーショングラフィックっていうのは、グラフィック」っていうくらいですから、絵とか記号とかを使って「模造紙」にカラフルに話し合いの記録をとっていくんです。
大事と思われるところは大きく書いたり、盛り上がった所には、そういうことがわかるような印をつけたりね。
絵の得意な人が、工夫しながら書き上げていくのはもう芸術であり、
またそれを観ながら、話が活性化することもあり、次回の話し合いに、この模造紙の記録を張り出すことで、これまでの議論がすぐに思い出されたり・・
また縮小コピーして、議事録としても活用できる。
有益だなぁと思っているわけです。
でも私には出来ないんですね。絵がかけないから(涙) 字が下手だから。空間をうまく使えないから。
私の周囲にも優秀なファシリテーショングラフィッカーが出てきてくれないかなとひそかに思っているわけです。
↓これは一日習っただけの学生さんが書いたもの。
こちらは、指導者が書いたもの。
絵も苦手、空間把握して、予測して美しく仕上げるなんてのはチョー苦手なんだけどね、
記録する事で、議論がぶれなかったり、話が戻しやすかったり、誰かの発言が置いてきぼりになるのが避けられたり・・・いいことがたくさんあるんです。
また、どんな話し合いだったか?っていうのが思い出されるような記録ってのはいいなぁと思うんですよ。欠席者にも伝わるような。
それで、ときどき、チャレンジします。
臨場感がでる記録づくりに。
板書しながら、模造紙書きながら、途中で入ったチャチャを口語体でそのまんま記録したり、もりあがったところは、わかるように印をつけたり、あえて発言者の発言そのまんま、方言いれて書いたり。
最近は携帯で写真を撮って印刷し、そのまんま議事録として配布しちゃったりすることも。
先日はカフェでのうちあわせだったので、ホワイトボードもなく、手元用紙に「議事録」をとる役目だったのですが・・・
結局発言をほとんど記録する形になり。
だけどあとで読み返してみたら、話の流れがわかって面白かった。
「議事録」としての体裁を整える為、日付場所、時間、参加者名、テーマ書いて、この日の結論を書いて。
あとは、だらっと発言の要点を記録しておきました。
少なくとも参加した人にしたら、あの場でおこっていたことを思い出すきっかけになるだろうし、欠席したひとは、どういう背景でこういう結論になったのかっていうことがわかるのは有益じゃないだろうかと。
「記録」系は苦手という意識が強かったんですが、ファシリテーショングラフィックと出会ってから、「活用」に意識が行くようになったきがします。
絵はかけなくても、この「記録」がどんな風に役に立つのか、なんのための記録なのか?を意識する事によって、「記録」そのものが、ファシリテート・・・いろんなことを促進する役目を果たしてくれるんだなぁということに気がつきました。
というわけで、苦手意識はあっても、目的を遂行する為に出来る事として、チャレンジしていこうと思っています。