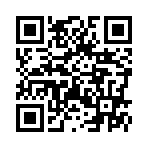江戸しぐさって知っていますか?
「江戸しぐさ」って知ってますか?
以前公共広告機構のCMが流れているので、見たことがあるかたも多いと思います。
私は前から気になっていまして、本を購入してはいました。
友人がコアメンバーとして活動しているJWCA(日本女性コーチ連盟)のイベントで、この江戸しぐさ語り部の会主催の越川禮子氏の講演があり、出席しました。
この越川さんというかたが、とても素敵な方でした!
今年84歳ということですが、とてもとてもそのような年齢には見えません。
きちんと整えられた髪、化粧、口紅、ミニのタイトスカートのスーツとヒール。
そして姿勢のよさとしっかりとした意志を感じる話し方。
参加者からは、驚きのため息がもれていました。
さて、江戸しぐさは、江戸の下町の商人たちの、哲学でありリーダーとしての行動様式です。繁盛しぐさともいいます。
1)たった一度の人生気持ちよく生きよう
2)戦はしない
以上の考えをベースに行動する、おもいやりの文化でもあります。
もう、この考え方だけでとても共感してしまいました。
いろいろなことを教えていただきましたが、印象に残っているのは「世辞」です。
「世辞」っていうのは「おはようございます。」などのあいさつのあとにいう言葉のことです。
たとえば「今日は良いお天気ですね」とか、「おでかけですか?」とか。
「どこに行くの?」というようなプライベートなことを尋ねるのは野暮なわけで。
あいさつも大事ですけど、その先にもう一言付け加えることで、会話がはじまったり、気持ちよくその場を過ごせるなんていうことは、よくあることですよね。
江戸ではこの「世辞」は9歳で身に着けなくてはいけないんだそうです。
「おでかけですか?」ときかれるのは、世辞で、別にどこに行くのかを聞きたいわけじゃなく、ただあなたと気持ちよくコミュニケーションがとりたいという心なんですよね。
そしたら「ちょっとそこまで。」って、そんなもんでいいわけですよね。
そしたら「気をつけて」って笑顔でお見送りできるし、相手も気持ちよく出かけていくことができる。
「いいお天気ですね」も。みたらわかることですよ。でも、それは別に天気のことを話題にしたいわけじゃないんですよね。
世辞ひとつとっても、江戸しぐさでは細かい決まりがあるというよりは、哲学を大事にした応用の文化なので、口承で伝えらてきたものなのだそうです。
ほかに、江戸しぐさには「尊異論」という考え方があります。
違いを尊ぶ。
外国人、赤の他人を大事にすることが平和につながる。
異文化を理解することから・・・と考えるのだそうです。
現代社会ではリーダーに必要なスキルとして、コーチングやファシリテーションなどが、欧米から輸入されてきていますが、実は日本にだって、この江戸しぐさがあったのです。
通じるものがたくさんありました。
ほかにもたくさんの知恵があるのですが、現代人が忘れかけている大事なことで、今も使って生きたい考え方、行動様式です。
日本的なものを大事にしていきたいなぁと思っています。
ファシリテーションとコーチング、そして江戸しぐさ、あわせて伝えていきたいです。
せんせい~(^^;
しかし、実際はこの時期、観光や子供の教育にかかわる人たちは忙しい。
イントラ(インストラクター)が足りずに私にまで声がかかることしばし。
正直なところ、私は直接子供にかかわる活動を好んではいない。大人対象がいい。
特に子供にかかわる大人たちのコミュニケーションやチーム力アップに関心がある。
とはいえ、請けた仕事、イントラが足りなければ困るのはわかるので「誰もあいてなかったら声かけて。」と最後に声がかかることになっている。
子供のチームチャレンジ活動のファシリテートをするのは、ファシリテーターとしての自分の「ありかた」の部分を見つめる機会になるので、定期的に点検する意味がある。
子供の活動のファシリテーションを主に仕事にしている人たちはキャラがたち、子供たちにも人気。場合によってはそのカリスマ的なところで、子供たちのモチベーションをあげているのかもしれない。
ファシリテーションや教育系のバックグラウンドがないイントラもいる。
しかし、経験から「待つ」「任せる」ことができる人もいるし、いつまでたっても、指示型でまるで先生のような人も。それでも活動の力で、ある程度の成果はある。
一方で私は、最初に興味を持ってもらえるよう、活動にひきこめたなら、あとは、なるべく存在を消す。
子供たちだけでものごとが進むように。
話し合いをするように。
だけど、私が黙って見守っていると先生が口をだしちゃうのよね。
「あ、ルール違反。あ、失敗した。もう一回やりなおし!」と指摘する。
「もっと声だしなさいよ。」先生が指示をするとメンバーから「こうしよう」がでてこなくなる。
「がんばれー!がんばれー!!」先生が大きく声援を送ればおくるほど、メンバーからの応援の言葉がでない。
「先生、口チャックでお願いします。」理由を伝えても、我慢できない先生。
先生、察してください~(××)。
失敗したら「自己申告」を最初から言い続けているのはなんのためか?私が基本、ジャッジしないのは、なんのためか。
必要最小限しか声をかけないのはなんのためか。
失敗したらオニになるけど、オニの役が楽しいゲームであれば、自己申告が抵抗なくできる。
そんな場面であっても今の子供たちはジャッジを先生や周囲のリーダー的な存在に求め、自分で判断できないケースがある。
「自分で考えて。間違ったんだったら、自分で交代してね。」
すこしづつ、活動のハードルをあげ、その中でも自己申告を求める。
申告しないとメンバーの中から指摘がでるケースもある。
誰かの失敗を責めるメンバーが出ることもある。
そんな中でも、失敗をフォローする声がけがでたり、気持ちを切り替えてがんばる雰囲気になったりもする。緊張した場面でも、失敗したら「ごめん!失敗した!」と言える子がでてくる。
それらを待ちたい。
グループは変化する。
丁寧なふりかえりが必要なケースもあるし、アクティビティの力で、変化することもある。
ルールを無視して、ごまかして「成功!」とする子供たちがいる。
それで満足度を訊くと、満足な子もいれば、ごまかしてたからいやだという子もいる。
もっとちゃんとやりたいという子供もでてくる。
そういうことがちゃんと言えるグループは、その次の活動では、変化がおきる。
一方で、ずっと真剣に取り組んできて、自分たちで厳しくやっていたのに、最後の最後でがんばってたメンバーが、ルールすれすれの危ういことになったとき、どうするんだろうと思ってみていたら、「ごめん、だめだった?」と不安そうに告白するのを「それくらいいいよ!」と受け入れるグループもあったし、
「あー、ざんねーん!」といいながら「がんばった」「気にしなくていいよ」と声をかけ、ふりかえりでは満足度いっぱいのグループもあった。
何度もごまかして達成でも全員が満足!というグループもある。
失敗しちゃったけど、言えなかったひととか、言いづらかったひととかいるんじゃないの?
どう?と声をかけても、みんなで、ない!と言い張るメンバーたち。
本音がいえない雰囲気だから、そういいながらも浮かない顔をしているケースがあるのはわかるのだけど、みんながみんな一様に、そう言い張る姿は異様。
先生がうるさく監視してきたようなグループは、先生の目をごまかして、とりあえずやるっていうことをこれまで繰り返してきているのかなぁ・・とそんなことを想像してしまう。
誰かが失敗すると課題の難易度があがるような活動では、すぐにリセットしたがる子供たち。
先生までも「リセットしちゃえ!」と声をかけるのを耳にして悲しくなる。
あまり語りたくはないのだけど、こんなふりかえりの場面では、ついつい語ってしまう。
「ねぇみんな。ゲームはリセットできるけど、人生はリセットできないでしょ。
一回くらい失敗したって、成功できたよね?
これまでだって、絶対無理!って最初に思ってたこと、クリアしてきたよね?
あきらめないのが大事だって気がついたって言ってたよね。
みんなにはそれだけの力があるんだよ。」
ここに書いたような先生は、一部ではあるのだけど、私はこういう先生方にこそ、こういう体験をしてもらいたいんだけどなぁ。
そしてファシリテーションについて知ってほしいのだけどなぁ。
もんもんとするのである。
主張の裏側にあるもの
事務連絡、報告事項などのあとに、「会議が発言しづらい」→「これを改善していこう」というような提案で、小グループに分かれて、討議した。
会議だけじゃなくて、これからのこの集団のありかたに発展してもいいんじゃないか?というような投げかけも。
久しぶりの参加、メンバーの顔ぶれの違い。この場の提案。
なにやら、不穏なかんじなの?私の知らないところで何がおこっていたのかしら?
なんて若干思いながらも、なんだか新鮮で、ちょっとわくわく。
まずは現状認識・・・ということで、ひとりひとりが話し始める。
さて、この「会議」が本当に発言しづらい場だったのか?
どうもそうとも言い切れないようだ。
個人の役割や参画年数(慣れ)の違いからなのか、発言しづらいと思った人と、そうでない人がいる。発言しづらいと思ったのは一部の人だけ。
でも発言するような内容があった会議だったのか?果たして報告事項ばかりではなかったか?
そんな現状を確認、区別していくと、提案してくれた人の「早く馴染みたい」「参画したい」「なにか自分がメンバーとしてできることを。貢献したい。」という思いが見え隠れしてきた。
「発言しづらい」という思いを肯定的に捉えると
「参画しているという意識を早く持ちたい。→活発なやりとりをするような会議をしたい」
「建設的な議論やプロジェクトなどの場がほしい」
そんなメッセージのように思える。
また進行役(ファシリテーター)という役割から感じる個人的ななにか・・・・
「雰囲気が悪い。誰も承認もせず、感想も話さず、表情も硬い。怒っているのか?非協力的な感じがする。これじゃ、活発な意見なんかだせる雰囲気じゃない」
→「もっとにこやかに雰囲気よく、自由な発言がなされながら会議をすすめたい。そうするべきだ。そうならないのは、問題だ」
みたいな感じがあるのかしら?このあたりは、昔、ファシリテーションの師匠にしばしば言われた事だ。
でも、本当に雰囲気が悪かったのか?
メンバーに確認すると、そうは思わないという人も多数。
私自身も・・・特に役割を背負ったときに、自分の思い描くとおりにならないとどこかで「問題だ」と思って、なんとかしようというエネルギーが働いてしまうことがある。
ときどき、点検したいところ。
もう片方のグループがどんな話をしているのか、詳細はわからないし、時間が短かったので、結論や次のアクションには至らなかったけど、いい現状認識と、意見交換会だった。
それぞれが、どんな気持ちでここに参画しているのかが見えてくる、そんな場でもあった。
そもそも、こういう場を持ちたいと発言できて、しかも時間がもてることが、開かれた場であることのように思う。
提案してくれたAさんに感謝。
安心で安全な場について思うこと
参加型の活動のことを一般的に言うと思う。
クラフトを作ったりというような活動のこともそのようにいうと思うけど、
私がここで意味しているワークショップというのは
「なんでも話せる」「安心してそこにいられる」「グループの一員感がある」
そんな場で、特定のテーマで話し合ったり、「まちづくり」を考えたり
体験学習の場だったり・・・・
そんなグループ活動のことを意味している。
「なんでも話せる」「安心してそこにいられる」「グループの一員感がある」
そんな雰囲気を作り出すのは、ファシリテーターとよばれる、進行役の役割が大きいが、
もちろん参加者がそこに賛同して作り出していくものだ。
そういう場をつくることで、多様な考えを吸い上げたり、本当の合意に向けた話し合いをし、参加者が納得したアウトプットをめざしたり、学びを深めたりする。
で。
普段、そういう場って、「あるべき」なのに、意外にない。
会社での会議、趣味の場での会議、町の集会・・・・
一部の声の大きい人や、責任ある役割のある人が、発言して、流れができてしまう。
反対意見をいいたいと思っても、言える雰囲気じゃなかったり、疎外感を感じてしまったり、つまらないから、あるいは嫌われたくないから、だまっておこうになったり。
だからかな?
「なんでも話せる」「安心してそこにいられる」「グループの一員感がある」という場を経験したひとは、「ここに参加している人たちって特別!愛がある!」となって極端な参加の仕方になったり、ある意味「信者」のように振舞ってしまったり。
自分の悲しみや苦しみを共感して聞いてもらって感じたカタルシスに病み付きになって
ワークショップときくと参加し続ける、ワークショップフリークになってしまったり。
極端に走る人がいるなぁと思う。
それだけ、そういう場が求められている。
逆に言えば、いかに安心で安全じゃない場に、自分達が普段いるのかということを思う。
で、「なんでも話せる」「安心してそこにいられる」「グループの一員感がある」ワークショップというか、「場」に居合わせたときに、逆に「気持ち悪い」と感じてしまう人もいるみたい。
これって、なんか宗教?洗脳されている?なんてね。
実は、私も、そう感じてしまう場がときどきある。
ひとつ明らかなのは、音楽を活用する時。雰囲気をもりあげるような・・・ね。
あれはいただけない。私の中のアラームが鳴る。
音楽はないのに、「ちょっと気持ち悪いな・・・」と思う場・・・
どうしてそうなってしまうんだろう?
という問いがたった。
ひとつの仮説をたててみた。
「安心な場」を作るために、意図は違ったとしても、ファシリテーターのお願いしたグランドルールが、
「誰かの意見や考えを否定してはいけない」というようなルールとして、参加者に伝わってしまっていたとしたら。
自分が思っていることと反対の考えが誰かからだされたときに、これを口に出してはいけない・・・と、言いたいことがいえなくなってしまっているのではないか?
多くの人が肯定的なことばかりを口に出せば出すほど、気持ち悪いかんじがある。
本当は、違う考えや意見をどんどん出してほしいはず。
だけど、そのときに、自分とは違う相手を攻撃したり、非難したりするのではなく、なるほど、あなたはそう感じたのですね。と受け止めた上で、
実は私には、あなたとは逆の考えもあるんです。別の経験をしました。というスタンスで、あってほしいということだと私は思っているし、そう関わっているつもりだ。
ネガティブな発言、ちょっと異質な発言でさえ、あたたかく受け入れられる。
そうであってほしいし、そうである自分でいたいし、さらにいえば、その真意がどこにあるのかを明らかに出来る自分(ファシリテーター)でありたい。
気に留めておきたいことだと思った。