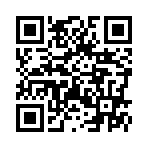味噌作りファシリテーション??
14名で十一斗(11樽)の味噌作り。私のファシリテーションの師匠の毎年のイベントに参加した。
味噌作り当日から参加することも出来るけど、1斗あたり、2.5升の大豆を使うから、その11倍だから結構なもの。前日にマメを洗い、水につけておくとこから味噌作りは始まるが、その大量の豆を洗う大変さを想像できるか否か、そのあたりから、人間関係は始まる気がする。
薪に火をつけるところから始まって、大豆が茹で上がるには2時間かかるということ。
お昼を食べてかたづけて解散するためには、9時には茹で上がっている必要があると企画者である師匠から前の晩に情報提供がある。
誰かが、これやって、あれやってと指示するわけではない。
朝早く起きた人が、薪に火をつけて、大釜で大豆をゆでる。
薪の番をする。かきまぜる。あくをとる。
その間、目が覚めた者、到着した者は、「久しぶり!」「始めまして!」とコミュニケーションを楽しみつつ、思い思いに、自分のできる仕事を探す。朝食の準備を手伝う者、道具をだしてくる者、味噌作りをする会場となる部屋のかたづけをする者。
ここは、コミュニケーションに積極的なひとじゃなくても、年齢も性別も職業もバックグラウンドも様々な人があつまるけど、無理にコミュニケーションをとらなくても、それぞれの居場所があって、どうやら居心地がいいらしい。
朝食が出来たら、手の空いている人から食事をし、あとかたづけをする。
その後、米麹、麦麹、塩の分量をはかり、11に分けるひとたち。
「アメ」と呼ばれる大豆のゆで汁をさますひとたち。
大豆と麹を混ぜる場所をセッティングする人たち。
大豆をミンサーで
(家庭用電動式豆ひき機)
ミンチにする人たち。
誰も指示していないのが面白い。
もちろん、お互いにリーダーシップを発揮して、あーでもないこーでもないとやってはいるけど。
企画者である師匠は、道具を出して、材料の配分などが一覧表になっているだけ。
参加者と近況を話したり、味噌作り談義をしたりしている。
準備が整ったら、誰が最初に作り始めるか?一度に作れるのは2斗分、ふたり。
「誰もやらないんなら、先にやっちゃおうかなー」と師匠が作り始めると、それを見習って誰かが始める。
見よう見まねでやったり、質問したり。
有料の講習会ではない。師匠は会場と、材料の手配と企画をしてくれて費用は実費だけ。
教える人、教えられる人という関係がない。
もちろん、経験者は、請われれば教えるし、おかしなことをやっている人がいれば、それを伝える人もいる。先にやった人が先生となり、初めての人にやりかたを教えたり。
経験者が多いというのもあるけど、このような場を作るのもファシリテーターの師匠ならではだなと、そんな視点でも、味噌作りを楽しみました。
中山間地のまちおこしイベントが、こんなかんじだと、それこそ第二のふるさとのようになるんじゃないかしら?自然に人間関係ができて・・・
私は・・・というと、2回目ということもあり、全体を見渡しながら、全工程を覚えるべく、ひとつの作業をしたらそれだけをずっとやるのではなく、誰かが入ったら、その場を譲り渡し、別の工程を見学し、おしゃべりをし、理由のわからないところは、質問したりして、あちこち渡り歩いて人との交流と味噌作りを楽しみました。
そうだ・・
今度、専門学校の生徒も連れて行こうかな。
ああいう場作りもきっと勉強になるはず~。
【会議運営ファシリテーター養成セミナー】5月16日・17日
http://coachkaneshige.cocolog-nifty.com/_kaneshigenews/2010/03/post-b2f9.html
【日和カフェDEコーチング~コーチング・クライアント体験会~5月11日(火)】http://facilitation.naganoblog.jp/e425857.html
味噌作り当日から参加することも出来るけど、1斗あたり、2.5升の大豆を使うから、その11倍だから結構なもの。前日にマメを洗い、水につけておくとこから味噌作りは始まるが、その大量の豆を洗う大変さを想像できるか否か、そのあたりから、人間関係は始まる気がする。
薪に火をつけるところから始まって、大豆が茹で上がるには2時間かかるということ。
お昼を食べてかたづけて解散するためには、9時には茹で上がっている必要があると企画者である師匠から前の晩に情報提供がある。
誰かが、これやって、あれやってと指示するわけではない。
朝早く起きた人が、薪に火をつけて、大釜で大豆をゆでる。
薪の番をする。かきまぜる。あくをとる。
その間、目が覚めた者、到着した者は、「久しぶり!」「始めまして!」とコミュニケーションを楽しみつつ、思い思いに、自分のできる仕事を探す。朝食の準備を手伝う者、道具をだしてくる者、味噌作りをする会場となる部屋のかたづけをする者。
ここは、コミュニケーションに積極的なひとじゃなくても、年齢も性別も職業もバックグラウンドも様々な人があつまるけど、無理にコミュニケーションをとらなくても、それぞれの居場所があって、どうやら居心地がいいらしい。
朝食が出来たら、手の空いている人から食事をし、あとかたづけをする。
その後、米麹、麦麹、塩の分量をはかり、11に分けるひとたち。
「アメ」と呼ばれる大豆のゆで汁をさますひとたち。
大豆と麹を混ぜる場所をセッティングする人たち。
大豆をミンサーで

(家庭用電動式豆ひき機)
ミンチにする人たち。
誰も指示していないのが面白い。
もちろん、お互いにリーダーシップを発揮して、あーでもないこーでもないとやってはいるけど。
企画者である師匠は、道具を出して、材料の配分などが一覧表になっているだけ。
参加者と近況を話したり、味噌作り談義をしたりしている。
準備が整ったら、誰が最初に作り始めるか?一度に作れるのは2斗分、ふたり。
「誰もやらないんなら、先にやっちゃおうかなー」と師匠が作り始めると、それを見習って誰かが始める。
見よう見まねでやったり、質問したり。
有料の講習会ではない。師匠は会場と、材料の手配と企画をしてくれて費用は実費だけ。
教える人、教えられる人という関係がない。
もちろん、経験者は、請われれば教えるし、おかしなことをやっている人がいれば、それを伝える人もいる。先にやった人が先生となり、初めての人にやりかたを教えたり。
経験者が多いというのもあるけど、このような場を作るのもファシリテーターの師匠ならではだなと、そんな視点でも、味噌作りを楽しみました。
中山間地のまちおこしイベントが、こんなかんじだと、それこそ第二のふるさとのようになるんじゃないかしら?自然に人間関係ができて・・・
私は・・・というと、2回目ということもあり、全体を見渡しながら、全工程を覚えるべく、ひとつの作業をしたらそれだけをずっとやるのではなく、誰かが入ったら、その場を譲り渡し、別の工程を見学し、おしゃべりをし、理由のわからないところは、質問したりして、あちこち渡り歩いて人との交流と味噌作りを楽しみました。
そうだ・・
今度、専門学校の生徒も連れて行こうかな。
ああいう場作りもきっと勉強になるはず~。
【会議運営ファシリテーター養成セミナー】5月16日・17日
http://coachkaneshige.cocolog-nifty.com/_kaneshigenews/2010/03/post-b2f9.html
【日和カフェDEコーチング~コーチング・クライアント体験会~5月11日(火)】http://facilitation.naganoblog.jp/e425857.html
奈良ワールドカフェのお知らせ
ファシリテーションつながりの友人の企画のお知らせです。
たくさんの方にお知らせしたいので、転送など、大歓迎です。
1010(遷都)のワクワクが生まれる他花受粉な対話 その(1)
~ワールドカフェという出会い&対話の場作り~
1010(遷都)のワクワクが生まれる他花受粉な対話 その(1)
~多数決を超えた市民の対話によるまちづくりの可能性~
他花受粉な対話とは、みつばちが蜜を求めて色々な花の間を飛び回ることで、異なる花どうしが受粉して新種の花が生まれるように、参加者がテーブルからテーブルへ移動しながら対話し、各テーブルでの多様な洞察を結びつけることで、思いがけない創造的なアイデアやワクワク感が生まれる対話です。
私たちは、この対話の力を使って、人々がかかわり、そしてむすびつき、今よりもっとワクワクすることが出来たらいいなと考え、継続的にこの奈良のまちでワールドカフェ※を行っていきたいと考えています。
今回は、その第1回目。ゲストに地元奈良のNPO活動の草分けであり、奈良町の保存に尽力し、いま奈良で市民主権の自治体経営をおしすすめる活動をされている木原勝彬さん(ローカル・ガバナンス研究所・所長)をお迎えします。多様な市民が参加し、地域の日常的な課題を市民が対話によって解決をはかる。そのような対話が持つ力と対話の場作りについて、これまでの活動をベースにしながらオープンに語っていただきます。
その後に、ワールドカフェでテーブルごとに参加者+ゲストの対話を行います。
※ワールドカフェとは
カフェの会話を会議室や話し合いに持ち込んだら?ということで生まれた、オープンで創造的な話し合いを生み出す対話のプログラムです。
カフェのような小さなテーブルを会場中にたくさん置いて、参加者がテーブルを移動することでメンバー変更を繰り返しながらグループで対話します。終わった後は、まるで会場の全員と話したような一体感とワクワク感が生まれる、楽しさと創造性にあふれる対話の場です。
プログラム
第一部
ゲストのトーク
ゲストトーク60分&ディスカッション30分
第二部
ワールドカフェ
30分×3ラウンド
第三部
ボディーパーカッションを
使ったドラムサークル
からだを使った手軽な
ドラムサークルのセッション15分
途中、おいしい大和茶とお菓子で、奇麗なお庭を見ながらゆっくりしていただく時間も用意しております。
ゲスト紹介
木原勝彬(きはら かつあきら)
1945年、奈良市生まれ。関西学院大学法学部卒業後、民間会社を経て、奈良町の歴史的町並み保存運動を興し、NPOの世界に入って30年。(社)奈良まちづくりセンター理事長、(特活)NPO政策研究所理事長を経て、2005年4月から現職。政策研究ネットワーク「なら・未来」代表、大阪市立大学大学院非常勤講師ほかを兼務。この間、「住民自治とは何か」、「市民・NPOと行政の協働はどうあるべきか」、「話し合いのプロセスを尊重する討議民主主義の定着化は」などについて思いをめぐらせる。現在、その数々の思いの、また自身のNPO人生の集大成の活動として、「市民による、市民のための、市民の自治体」としての「市民主権型自治体」の構築を奈良で実現することを夢みる。著書に『NPOと
行政の協働の手引き』(共著)『新しい自治のしくみづくり』(共著)がある。
開催日時
2009年7月18日(土) 13:30~18:00(13:00開場・受付開始)
場所
国際奈良学セミナーハウス
(近鉄奈良駅より東へ徒歩10分 奈良県庁過ぎてすぐ)
奈良県奈良市登大路町63番地
TEL: 0742-23-5821
http: //nara-manabi.com/
申込方法
以下の受付メールアドレスまたはFAX番号まで、
7月17日までに必要情報をお送りください。
● 受付メールアドレス
takajnara@yahoo.co.jp
● 受付FAX番号
0742-27-7113
● 必要情報
1.お名前 2.お仕事 3.住所 4.メールアドレス 5.ご年代(例:30歳代) 6.何を期待しますか 7.当日の緊急連絡先(携帯電話番号など)
定員
50名(定員に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます)
参加費・振込先
1,500円
(ユカタ割引あり:ユカタで参加の方は当日100円返金します)
参加費は指定の銀行口座にお振込下さい。銀行口座は申込された方に別途メール等でお知らせします。
その他
会場は古い建物を移築した奈良公園すぐの情緒豊かな風情のある施設です。初夏の暑い中ですが、エアコンがありませんのでお庭の緑と風を涼としております。お出かけの際は、団扇などお持ちになって涼しい服装でおいで下さい。
企画事務局
タカジュフン@奈良
代表: 山岸 裕(やまぎし ゆたか)
〒630-8113 奈良市法蓮町933番地
TEL : 090-7107-7088
e-mail : takajnara@yahoo.co.jp
*申込の際にいただいた個人情報は、タカジュフン@奈良の主催するイベントの企画・案内に使用する以外には一切使用しません。また、個人情報は厳重に管理致します。
*このイベントは、いかなる宗教団体の活動とも一切関係ありません。
たくさんの方にお知らせしたいので、転送など、大歓迎です。
1010(遷都)のワクワクが生まれる他花受粉な対話 その(1)
~ワールドカフェという出会い&対話の場作り~
1010(遷都)のワクワクが生まれる他花受粉な対話 その(1)
~多数決を超えた市民の対話によるまちづくりの可能性~
他花受粉な対話とは、みつばちが蜜を求めて色々な花の間を飛び回ることで、異なる花どうしが受粉して新種の花が生まれるように、参加者がテーブルからテーブルへ移動しながら対話し、各テーブルでの多様な洞察を結びつけることで、思いがけない創造的なアイデアやワクワク感が生まれる対話です。
私たちは、この対話の力を使って、人々がかかわり、そしてむすびつき、今よりもっとワクワクすることが出来たらいいなと考え、継続的にこの奈良のまちでワールドカフェ※を行っていきたいと考えています。
今回は、その第1回目。ゲストに地元奈良のNPO活動の草分けであり、奈良町の保存に尽力し、いま奈良で市民主権の自治体経営をおしすすめる活動をされている木原勝彬さん(ローカル・ガバナンス研究所・所長)をお迎えします。多様な市民が参加し、地域の日常的な課題を市民が対話によって解決をはかる。そのような対話が持つ力と対話の場作りについて、これまでの活動をベースにしながらオープンに語っていただきます。
その後に、ワールドカフェでテーブルごとに参加者+ゲストの対話を行います。
※ワールドカフェとは
カフェの会話を会議室や話し合いに持ち込んだら?ということで生まれた、オープンで創造的な話し合いを生み出す対話のプログラムです。
カフェのような小さなテーブルを会場中にたくさん置いて、参加者がテーブルを移動することでメンバー変更を繰り返しながらグループで対話します。終わった後は、まるで会場の全員と話したような一体感とワクワク感が生まれる、楽しさと創造性にあふれる対話の場です。
プログラム
第一部
ゲストのトーク
ゲストトーク60分&ディスカッション30分
第二部
ワールドカフェ
30分×3ラウンド
第三部
ボディーパーカッションを
使ったドラムサークル
からだを使った手軽な
ドラムサークルのセッション15分
途中、おいしい大和茶とお菓子で、奇麗なお庭を見ながらゆっくりしていただく時間も用意しております。
ゲスト紹介
木原勝彬(きはら かつあきら)
1945年、奈良市生まれ。関西学院大学法学部卒業後、民間会社を経て、奈良町の歴史的町並み保存運動を興し、NPOの世界に入って30年。(社)奈良まちづくりセンター理事長、(特活)NPO政策研究所理事長を経て、2005年4月から現職。政策研究ネットワーク「なら・未来」代表、大阪市立大学大学院非常勤講師ほかを兼務。この間、「住民自治とは何か」、「市民・NPOと行政の協働はどうあるべきか」、「話し合いのプロセスを尊重する討議民主主義の定着化は」などについて思いをめぐらせる。現在、その数々の思いの、また自身のNPO人生の集大成の活動として、「市民による、市民のための、市民の自治体」としての「市民主権型自治体」の構築を奈良で実現することを夢みる。著書に『NPOと
行政の協働の手引き』(共著)『新しい自治のしくみづくり』(共著)がある。
開催日時
2009年7月18日(土) 13:30~18:00(13:00開場・受付開始)
場所
国際奈良学セミナーハウス
(近鉄奈良駅より東へ徒歩10分 奈良県庁過ぎてすぐ)
奈良県奈良市登大路町63番地
TEL: 0742-23-5821
http: //nara-manabi.com/
申込方法
以下の受付メールアドレスまたはFAX番号まで、
7月17日までに必要情報をお送りください。
● 受付メールアドレス
takajnara@yahoo.co.jp
● 受付FAX番号
0742-27-7113
● 必要情報
1.お名前 2.お仕事 3.住所 4.メールアドレス 5.ご年代(例:30歳代) 6.何を期待しますか 7.当日の緊急連絡先(携帯電話番号など)
定員
50名(定員に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます)
参加費・振込先
1,500円
(ユカタ割引あり:ユカタで参加の方は当日100円返金します)
参加費は指定の銀行口座にお振込下さい。銀行口座は申込された方に別途メール等でお知らせします。
その他
会場は古い建物を移築した奈良公園すぐの情緒豊かな風情のある施設です。初夏の暑い中ですが、エアコンがありませんのでお庭の緑と風を涼としております。お出かけの際は、団扇などお持ちになって涼しい服装でおいで下さい。
企画事務局
タカジュフン@奈良
代表: 山岸 裕(やまぎし ゆたか)
〒630-8113 奈良市法蓮町933番地
TEL : 090-7107-7088
e-mail : takajnara@yahoo.co.jp
*申込の際にいただいた個人情報は、タカジュフン@奈良の主催するイベントの企画・案内に使用する以外には一切使用しません。また、個人情報は厳重に管理致します。
*このイベントは、いかなる宗教団体の活動とも一切関係ありません。
待つこと、観ること、感じ取ること、そして瞬時に反応すること
某任意団体での定期総会のこと。
議事に沿って、しゃんしゃんと終わるのが、楽でいいけど、やっぱり会員としては、折角きているのだし、質問もしたいだろうし、参画したい気持ちがあるはず。
今回の総会の山場は、組織変更の提案。
運営委員会が、グループの意見を吸い上げ、検討したうえでの提案ではあったけれど、総会数日前に、一部ひっくりかえった部分もあったりして、この部分は、波乱含み。
いずれにしても、提案に固執するものではなかったので、会員の意見で、変更があることはやぶさかではなかったのだけど・・・
議長「質問、意見はないですか?」
「・・・・」(1、2、3秒)
議長「では、ないようなので採決に移ります」
えー!
早いよ。ちょっと待ってよ。まだみんな議事録から目があがらないし、隣と話始めた人もいる、ちょっとがやつきはじめたような・・・
あたふたしているうちに、挙手がはじまってしまった。
一応可決したのだけど、まだ、会員は、なんとなくがやついている。
私は三役で、脇の席にいて、このタイミングで発言するのはどうだったんだろうと思うけど、思わず口をついて出てしまった。
「あの!後ろのほうで、なにやら話したそうな雰囲気を感じていたんですけど、本当に質問も、ご意見もないのでしょうか?このまま次に進んでよいのでしょうか?」
案の定、次から次へ質問やら意見がでてきて、30分近く意見交換が行われた。
おかげで、終了時刻が遅れてしまったし、議長さんには間が悪くて申し訳なかったけど、結果的には良かったのではないかと思っている。
そうでなくても、各人がそれぞれ、いろんな思いをもって関わっている会で、それぞれが歯がゆい思いを抱えながらの組織。
発言の機会もなく進んでしまったら、不満につながったかもしれない。
それは、みんなが、より良い組織、活動にしたいと思っているからこそのこと。
個人的には、「あっ」と思ったときに、瞬時に反応できるようになりたいなぁ。「可決しました」の声が出る前に言えたらよかったなぁ。
精進します。
議事に沿って、しゃんしゃんと終わるのが、楽でいいけど、やっぱり会員としては、折角きているのだし、質問もしたいだろうし、参画したい気持ちがあるはず。
今回の総会の山場は、組織変更の提案。
運営委員会が、グループの意見を吸い上げ、検討したうえでの提案ではあったけれど、総会数日前に、一部ひっくりかえった部分もあったりして、この部分は、波乱含み。
いずれにしても、提案に固執するものではなかったので、会員の意見で、変更があることはやぶさかではなかったのだけど・・・
議長「質問、意見はないですか?」
「・・・・」(1、2、3秒)
議長「では、ないようなので採決に移ります」
えー!
早いよ。ちょっと待ってよ。まだみんな議事録から目があがらないし、隣と話始めた人もいる、ちょっとがやつきはじめたような・・・
あたふたしているうちに、挙手がはじまってしまった。
一応可決したのだけど、まだ、会員は、なんとなくがやついている。
私は三役で、脇の席にいて、このタイミングで発言するのはどうだったんだろうと思うけど、思わず口をついて出てしまった。
「あの!後ろのほうで、なにやら話したそうな雰囲気を感じていたんですけど、本当に質問も、ご意見もないのでしょうか?このまま次に進んでよいのでしょうか?」
案の定、次から次へ質問やら意見がでてきて、30分近く意見交換が行われた。
おかげで、終了時刻が遅れてしまったし、議長さんには間が悪くて申し訳なかったけど、結果的には良かったのではないかと思っている。
そうでなくても、各人がそれぞれ、いろんな思いをもって関わっている会で、それぞれが歯がゆい思いを抱えながらの組織。
発言の機会もなく進んでしまったら、不満につながったかもしれない。
それは、みんなが、より良い組織、活動にしたいと思っているからこそのこと。
個人的には、「あっ」と思ったときに、瞬時に反応できるようになりたいなぁ。「可決しました」の声が出る前に言えたらよかったなぁ。
精進します。
ブランド事業とワールドカフェ2
前の記事でワールドカフェに触れたけど、ヨコハマ経済新聞4月25日によると
ここから引用・・
「知識や知恵は、管理されがちな会議室で生まれるのではなく、人々がオープンに会話を行い、自由にネットワークを築くことのできる"カフェのような空間"でこそ創発される」という基本的な考え方に基づいている。
この手法は、リラックスした雰囲気のなかで、一人ひとりの力を最大限に引き出し、そこからグループ全体の意見へとつなげていく点に特徴がある。結論を出すことでなく、あくまでもアイデアを出すことが目的。そのために話し合い、話し合いを記録することに集中する。そして、そこから新たな方向性が自然に生まれるのを待つ、というプロセスを重視する。
引用ここまで。
長野でも、ワールドカフェやりませんか?
長野市でも、長野県でも。
私は信濃町在住なので、信濃町ブランドのためにワールドカフェもいいと思うなぁ。
ほかに、OSTっていう手法も有ります。オープンスペーステクノロジー。
今回の記事詳細はこちらをどうぞ。
ここから引用・・
「知識や知恵は、管理されがちな会議室で生まれるのではなく、人々がオープンに会話を行い、自由にネットワークを築くことのできる"カフェのような空間"でこそ創発される」という基本的な考え方に基づいている。
この手法は、リラックスした雰囲気のなかで、一人ひとりの力を最大限に引き出し、そこからグループ全体の意見へとつなげていく点に特徴がある。結論を出すことでなく、あくまでもアイデアを出すことが目的。そのために話し合い、話し合いを記録することに集中する。そして、そこから新たな方向性が自然に生まれるのを待つ、というプロセスを重視する。
引用ここまで。
長野でも、ワールドカフェやりませんか?
長野市でも、長野県でも。
私は信濃町在住なので、信濃町ブランドのためにワールドカフェもいいと思うなぁ。
ほかに、OSTっていう手法も有ります。オープンスペーステクノロジー。
今回の記事詳細はこちらをどうぞ。
ブランド事業にワールドカフェ1
まちづくりに関心のある方へ
ヨコハマ経済新聞(2008年12月10日)より
横浜市は12月10日の市長定例記者会見で、都市ブランド共創プロジェクト「イマジン・ヨコハマ」の実施を発表。同日、横浜メディア・ビジネスセンター1階「ヨコハマNEWSハーバー」(横浜市中区太田町2)内に事務局を設置し、市民ボランティア1,000人の募集を開始した。
同プロジェクトは、2009年の開港150周年の機会に「都市ブランド」の構築に取り組むもの。市民の横浜への誇りや愛着心を高めることで、地域活動への参加促進やコミュニティ形成を図り、都市の魅力や独自性の発信により、地域を活性化することが狙い。
市民参加を重視し、「開国博Y150」会場などで市民の意見を集めるほか、インタビューを人から人へ連鎖的に広げて数万人の意見を集める「市民つながりインタビュー」などの新しい手法を実践。5月9日には、参加者全員がお互いの意見を共有しながら議論を発展させていく手法「ワールドカフェ」を日本最大規模の1,000人の参加者を集め実施する。
有識者による公開型の「都市ブランド研究会」や、意見を集約するワークショップなどによりブランドを特定。キャッチコピーやシンボルマークなどに表現し、2010年2月に発表する予定。その後、都市ブランドを観光誘客や企業誘致などのシティセールス、都市デザイン、まちづくりなどの活動に生かしていく。
横浜市は今年度、「都市ブランド戦略構築事業」として1,000万円の予算を計上。8月から9月にかけて事業者を公募し、応募があった8社に対し書類選考とヒヤリングを行い、事業者を広告代理店の「博報堂」(東京都港区)に決定している。
募集するボランティアは、活動全体の中心となるコアメンバー200人と、主に「ワールドカフェ」と「つながりインタビュー」に参加するレギュラーメンバー800人。対象は2009年4月時点で15歳以上の方。締切はコアメンバーが2009年1月31日、レギュラーメンバーが3月31日。
同プロジェクトの事務局担当者は「都市ブランドとは、都市名そのものをブランド化するもの。地名と商品を結びつけた地域ブランドとは違い、住民や企業からも支持される総合的な都市の評価を意味する。ゼロからスタートするこの新しい試みにぜひ参加して欲しい」と話している。
ヨコハマ経済新聞(2008年12月10日)より
横浜市は12月10日の市長定例記者会見で、都市ブランド共創プロジェクト「イマジン・ヨコハマ」の実施を発表。同日、横浜メディア・ビジネスセンター1階「ヨコハマNEWSハーバー」(横浜市中区太田町2)内に事務局を設置し、市民ボランティア1,000人の募集を開始した。
同プロジェクトは、2009年の開港150周年の機会に「都市ブランド」の構築に取り組むもの。市民の横浜への誇りや愛着心を高めることで、地域活動への参加促進やコミュニティ形成を図り、都市の魅力や独自性の発信により、地域を活性化することが狙い。
市民参加を重視し、「開国博Y150」会場などで市民の意見を集めるほか、インタビューを人から人へ連鎖的に広げて数万人の意見を集める「市民つながりインタビュー」などの新しい手法を実践。5月9日には、参加者全員がお互いの意見を共有しながら議論を発展させていく手法「ワールドカフェ」を日本最大規模の1,000人の参加者を集め実施する。
有識者による公開型の「都市ブランド研究会」や、意見を集約するワークショップなどによりブランドを特定。キャッチコピーやシンボルマークなどに表現し、2010年2月に発表する予定。その後、都市ブランドを観光誘客や企業誘致などのシティセールス、都市デザイン、まちづくりなどの活動に生かしていく。
横浜市は今年度、「都市ブランド戦略構築事業」として1,000万円の予算を計上。8月から9月にかけて事業者を公募し、応募があった8社に対し書類選考とヒヤリングを行い、事業者を広告代理店の「博報堂」(東京都港区)に決定している。
募集するボランティアは、活動全体の中心となるコアメンバー200人と、主に「ワールドカフェ」と「つながりインタビュー」に参加するレギュラーメンバー800人。対象は2009年4月時点で15歳以上の方。締切はコアメンバーが2009年1月31日、レギュラーメンバーが3月31日。
同プロジェクトの事務局担当者は「都市ブランドとは、都市名そのものをブランド化するもの。地名と商品を結びつけた地域ブランドとは違い、住民や企業からも支持される総合的な都市の評価を意味する。ゼロからスタートするこの新しい試みにぜひ参加して欲しい」と話している。
まちづくりとゆるやかな関係作り
まちづくりファシリテーターが実施する大学生対象のファシリテーター養成講座でのこと。
私はプログラムのひとつを依頼されていたのだが、早く到着したので、前の活動の様子を見学していた。
それはファシリテーター養成講座のスターティングプログラム。
ゆるやかな関係作りとしてペンキ塗りをしていた。
顔見知りではない人もいる、そんな状況から、ゆるやかな関係を作る。その体験だ。
たしかに、共同作業をするというのは、一種の連帯感が生まれる。
だけど、その様子を見て、私ったら、別の時間にこれを私にやらせてくれれば、ひとつの課題達成プログラムとして、その中から人間関係を学ぶ、ペンキ塗りワークショップができたのになぁと、ひとりごちていた。
実際の作業中何が起こっていたかというと・・・
一部の人だけがペンキをぬっていて、そのほかの人は、下準備のさび落としだけ・・・
本当は自分もペンキ塗りをやりたいと思っていたり、はしごを使っている姿に危ないと思いながら手を貸さなかったり。
手袋がほしいなぁとおもっていたり。
すれ違うときに、ぶつかって、あやうくペンキが服につきそうになったり。
いろんなことが個人の内側に、誰かと誰かの間に、グループの中で起こっている。
たしかに人間関係を学ぶための材料にはなるけど、この場で求められていたのは「ゆるやかな関係作り」という体験とその効果を実感すること。
そして、その経験を、そういう場を作っていくということに活かす事。
まちづくりにおいては、わざわざ、アイスブレークと称して、ゲームをしたり、自己紹介をしたりというのも、もちろんありだけど、必然として起こってくる共同作業を、うまく活用しながら、ゆるやかに関係を作っていくっていうことは、現実的なアプローチだなぁと私も学んだのであった。
私はプログラムのひとつを依頼されていたのだが、早く到着したので、前の活動の様子を見学していた。
それはファシリテーター養成講座のスターティングプログラム。
ゆるやかな関係作りとしてペンキ塗りをしていた。
顔見知りではない人もいる、そんな状況から、ゆるやかな関係を作る。その体験だ。
たしかに、共同作業をするというのは、一種の連帯感が生まれる。
だけど、その様子を見て、私ったら、別の時間にこれを私にやらせてくれれば、ひとつの課題達成プログラムとして、その中から人間関係を学ぶ、ペンキ塗りワークショップができたのになぁと、ひとりごちていた。
実際の作業中何が起こっていたかというと・・・
一部の人だけがペンキをぬっていて、そのほかの人は、下準備のさび落としだけ・・・
本当は自分もペンキ塗りをやりたいと思っていたり、はしごを使っている姿に危ないと思いながら手を貸さなかったり。
手袋がほしいなぁとおもっていたり。
すれ違うときに、ぶつかって、あやうくペンキが服につきそうになったり。
いろんなことが個人の内側に、誰かと誰かの間に、グループの中で起こっている。
たしかに人間関係を学ぶための材料にはなるけど、この場で求められていたのは「ゆるやかな関係作り」という体験とその効果を実感すること。
そして、その経験を、そういう場を作っていくということに活かす事。
まちづくりにおいては、わざわざ、アイスブレークと称して、ゲームをしたり、自己紹介をしたりというのも、もちろんありだけど、必然として起こってくる共同作業を、うまく活用しながら、ゆるやかに関係を作っていくっていうことは、現実的なアプローチだなぁと私も学んだのであった。
新潟まちづくりファシリテーション 映画「降りていく生き方」
ご存知ですか?
新潟が舞台で、地域ぐるみのオーディションを経て、2000人のエキストラが出演したそうです。
****************公式ホームページより***********
脚本と映画制作に影響を与えた「地域参加型のオーディション」
まちづくりを中心に「自然/共生/希望」が重要なテーマとなる本作において、私たちは、映画出演募集を一種の「祭り」と捉え、日本映画史上初の試みとなる前代未聞のオーディションを実施しました。
オーディション自体の企画/運営/実施を、本作に賛同頂いたボランティア・スタッフを中心に行い、行政、各種団体などの協力も得て、新潟県内7ヶ所で開催しました。
オーディション受験者は、生後8ヶ月から92才まで、老若男女、そして国籍を問わず、約2000名もの応募がありました。
このオーディションは、その情熱に満ち溢れ、数々のエピソードやドラマを生み出し、遂には本作の脚本開発や映画制作の方向性に対して大きな影響を与えたのでした。
***************************************************************
この映画に大きな影響を与えているのが、新潟で、まちづくりの仕掛け人として、ファシリテーターとして活躍されている清水義晴氏。
氏の著書
変革は、弱いところ、小さいところ、遠いところから
を読むと氏の考え方や活動がわかる。
まさにファシリテーターとして生きている方であり、カウンセラーの方、コーチの方、もちろん各種ファシリテーション、まちづくり、組織作りに関わる人にお勧め。
そして、生き方を考える本として、多くの方に手にとってもらいたい。
既存の一般的な「良い」と思われる生き方以外にも、いろんな選択肢があるよねと、ほっとするひともいるんじゃないかな。生き方指南の本とも言えるかも。
映画「降りていく生き方」は、通常のように映画館では見られないようです。
詳細は公式ページからどうぞ。
新潟が舞台で、地域ぐるみのオーディションを経て、2000人のエキストラが出演したそうです。
****************公式ホームページより***********
脚本と映画制作に影響を与えた「地域参加型のオーディション」
まちづくりを中心に「自然/共生/希望」が重要なテーマとなる本作において、私たちは、映画出演募集を一種の「祭り」と捉え、日本映画史上初の試みとなる前代未聞のオーディションを実施しました。
オーディション自体の企画/運営/実施を、本作に賛同頂いたボランティア・スタッフを中心に行い、行政、各種団体などの協力も得て、新潟県内7ヶ所で開催しました。
オーディション受験者は、生後8ヶ月から92才まで、老若男女、そして国籍を問わず、約2000名もの応募がありました。
このオーディションは、その情熱に満ち溢れ、数々のエピソードやドラマを生み出し、遂には本作の脚本開発や映画制作の方向性に対して大きな影響を与えたのでした。
***************************************************************
この映画に大きな影響を与えているのが、新潟で、まちづくりの仕掛け人として、ファシリテーターとして活躍されている清水義晴氏。
氏の著書

変革は、弱いところ、小さいところ、遠いところから
を読むと氏の考え方や活動がわかる。
まさにファシリテーターとして生きている方であり、カウンセラーの方、コーチの方、もちろん各種ファシリテーション、まちづくり、組織作りに関わる人にお勧め。
そして、生き方を考える本として、多くの方に手にとってもらいたい。
既存の一般的な「良い」と思われる生き方以外にも、いろんな選択肢があるよねと、ほっとするひともいるんじゃないかな。生き方指南の本とも言えるかも。
映画「降りていく生き方」は、通常のように映画館では見られないようです。
詳細は公式ページからどうぞ。