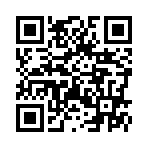あなたのファンを増やす(接客応対)
タイトルのようなねらいの、接客応対プログラムを実施していますが。
まさに、この日、私は「ファン」になってしまいました。
研修で時々訪れる「スペースアルファ神戸」でのことです。
今回はここで1泊2日の研修予定でした。
私はこの朝、トラブルがあり、出先でスカートを汚されてしまったのです。
しかしながら、荷物を少なくしたかったので、着替えが最小限しかなく、しかも、その汚れ成分には油が入っていたこともあり、どうしてもスカートをクリーニングにだしたいと思っていました。
スペースアルファに到着するなり、受付でクリーニングサービスについて問い合わせたところ、残念ながら当日は祝日で、出入りのクリーニング業者さんはお休みとのこと。
困ったなと事情を話したところ、「近くで即日仕上げのところを問い合わせてみます」との心強い言葉。
この言葉だけでも本当にありがたいことです。
その後、車で5分ほどの距離の駅のそばのクリーニング屋で、即日仕上げ可能との情報を入手してくれました。しかしながら、午前中に預けないとだめとのこと。
余裕を持って会場入りしたけど、すでに研修開始予定は迫っており、休み時間に移動するにしてもタクシーを呼ばないと間に合いそうもない。
仕方なく、感謝を伝えて、明日の朝一番のクリーニングで妥協した。
ところが。
再度連絡が入り、出入りの業者さんが、休日にもかかわらず対応してくれるとのことで、受付にスカートを預けることで、私の願いはかなえられたのです!
すごい!
ここまでしてくれるなんて。
本当に感動してしまいました。
ありがとうSさん。
私は、Sさんのファンになりました。
私はスペースアルファ神戸の話が出たら、きっとこの話も伝えるし、気合を入れて、この施設をお勧めするでしょう。
Sさんに感謝。
まさに、この日、私は「ファン」になってしまいました。
研修で時々訪れる「スペースアルファ神戸」でのことです。
今回はここで1泊2日の研修予定でした。
私はこの朝、トラブルがあり、出先でスカートを汚されてしまったのです。
しかしながら、荷物を少なくしたかったので、着替えが最小限しかなく、しかも、その汚れ成分には油が入っていたこともあり、どうしてもスカートをクリーニングにだしたいと思っていました。
スペースアルファに到着するなり、受付でクリーニングサービスについて問い合わせたところ、残念ながら当日は祝日で、出入りのクリーニング業者さんはお休みとのこと。
困ったなと事情を話したところ、「近くで即日仕上げのところを問い合わせてみます」との心強い言葉。
この言葉だけでも本当にありがたいことです。
その後、車で5分ほどの距離の駅のそばのクリーニング屋で、即日仕上げ可能との情報を入手してくれました。しかしながら、午前中に預けないとだめとのこと。
余裕を持って会場入りしたけど、すでに研修開始予定は迫っており、休み時間に移動するにしてもタクシーを呼ばないと間に合いそうもない。
仕方なく、感謝を伝えて、明日の朝一番のクリーニングで妥協した。
ところが。
再度連絡が入り、出入りの業者さんが、休日にもかかわらず対応してくれるとのことで、受付にスカートを預けることで、私の願いはかなえられたのです!
すごい!
ここまでしてくれるなんて。
本当に感動してしまいました。
ありがとうSさん。
私は、Sさんのファンになりました。
私はスペースアルファ神戸の話が出たら、きっとこの話も伝えるし、気合を入れて、この施設をお勧めするでしょう。
Sさんに感謝。
接客応対を体験学習する
「接客応対」というと、通常、マナー研修みたいな・・・・どんな風に挨拶して、言葉遣いはこうで、おじぎはこんなかんじ・・・
名刺の渡し方は・・・
っていう、「正しい作法」みたいな「答え」のあるものを「教え」て、「練習」する研修だと思う。
この時期、新入社員さんたちはそういう、研修を受けてるのではないかな?
私は・・・実は外資系企業にいたせいか、そういうのが、とてもゆるく・・・
いまだ、よくわかっていない・・・っていうか、覚える気がないのね。
たぶん、学生時代には学んだはずで、新人のころは一生懸命やっていたとは思うのですが。
人事・労務部門にいたせいもあり、社員が私のお客様。
となると、とおりいっぺんのお作法や言葉遣いは、逆に関係作りに阻害になったりするのです。
私の場合は、最初に配属されたのが、工場や技術センターのある事業所だったこともあり、地元の気のいいおじさんとか、理系バリバリのひととかでね、極端で。
学校で勉強したとおりに、丁寧に応対すればするほど、「すましてる」「きつい」みたいなうわさが聞こえてくるの。
よく見たら、まわりの先輩方は、近所の方々とおしゃべりするような対応だったり、ですます調だけど、フレンドリー。
相手を尊重しつつ、親しみのこもった対応なわけです。
それで、そっちに切り替えたら、その事業所中のほとんどの人(1000人近くいる)と知り合いになれて、向こうも親しみをもってくれた。顔と名前が一致しない・・電話だけのやりとりだったヒトもたくさんいたけどね。
だけど、本社に移動になったら、営業さんとか企画のひととかがいて、外部のお客さんとやり取りをしている方々がたくさんいると、そういうかたがたは、またちょっと違うニュアンスなのよね。
もちろん、知り合って仲良くなったらまた変わってくるけど。
そんなことを、相手とのやりとりを通じて、体感しながら、学んでいったかんじがある。
この人とは最初はこんな距離感、しばらくたったら、このぐらい・・・顔なじみになったらこんなかんじ・・・
まさに体験学習。
とはいえ、やたら丁寧な言葉遣いや、やたら腰の低い、マナーばっちりですっていうような営業マンさんに会うと、私はとっても居心地悪くて、相手に合わせられないのです。
そういう人も、こちらに合わせてくれるといいのになぁ。
てなわけで、私は接客応対を「教える」ことは出来ないんですが、そういうことをみんなで「考え」たり「体験」したことから、学んだりする場を作るのは大好きです。
一通りのマナーはわかっているけど、さらに一歩進んだ、お客様との対応を学びたい、あるいは学んで欲しいと思っている研修担当や上司の方々、ご検討くださいませ。
リピーターを増やす、あなたのファンを増やす研修です。
名刺の渡し方は・・・
っていう、「正しい作法」みたいな「答え」のあるものを「教え」て、「練習」する研修だと思う。
この時期、新入社員さんたちはそういう、研修を受けてるのではないかな?
私は・・・実は外資系企業にいたせいか、そういうのが、とてもゆるく・・・
いまだ、よくわかっていない・・・っていうか、覚える気がないのね。
たぶん、学生時代には学んだはずで、新人のころは一生懸命やっていたとは思うのですが。
人事・労務部門にいたせいもあり、社員が私のお客様。
となると、とおりいっぺんのお作法や言葉遣いは、逆に関係作りに阻害になったりするのです。
私の場合は、最初に配属されたのが、工場や技術センターのある事業所だったこともあり、地元の気のいいおじさんとか、理系バリバリのひととかでね、極端で。
学校で勉強したとおりに、丁寧に応対すればするほど、「すましてる」「きつい」みたいなうわさが聞こえてくるの。
よく見たら、まわりの先輩方は、近所の方々とおしゃべりするような対応だったり、ですます調だけど、フレンドリー。
相手を尊重しつつ、親しみのこもった対応なわけです。
それで、そっちに切り替えたら、その事業所中のほとんどの人(1000人近くいる)と知り合いになれて、向こうも親しみをもってくれた。顔と名前が一致しない・・電話だけのやりとりだったヒトもたくさんいたけどね。
だけど、本社に移動になったら、営業さんとか企画のひととかがいて、外部のお客さんとやり取りをしている方々がたくさんいると、そういうかたがたは、またちょっと違うニュアンスなのよね。
もちろん、知り合って仲良くなったらまた変わってくるけど。
そんなことを、相手とのやりとりを通じて、体感しながら、学んでいったかんじがある。
この人とは最初はこんな距離感、しばらくたったら、このぐらい・・・顔なじみになったらこんなかんじ・・・
まさに体験学習。
とはいえ、やたら丁寧な言葉遣いや、やたら腰の低い、マナーばっちりですっていうような営業マンさんに会うと、私はとっても居心地悪くて、相手に合わせられないのです。
そういう人も、こちらに合わせてくれるといいのになぁ。
てなわけで、私は接客応対を「教える」ことは出来ないんですが、そういうことをみんなで「考え」たり「体験」したことから、学んだりする場を作るのは大好きです。
一通りのマナーはわかっているけど、さらに一歩進んだ、お客様との対応を学びたい、あるいは学んで欲しいと思っている研修担当や上司の方々、ご検討くださいませ。
リピーターを増やす、あなたのファンを増やす研修です。
お体のほうは大丈夫ですか?
自動車保険は、安いのでA社を使っている。
今回、被害者ではあるが、先方が保険を使わない可能性があったので、念のため、保険会社に
一報をいれておいた。
保険会社が先方と交渉するようなサービスをつけているわけではないので、本当は関係ないはずだけど、「ご連絡ありがとうございます」と詳細を聞いてくれ、注意事項を教えてくれた。
休みがあけて、今日は、担当となる保険会社の方が電話をくれ、なにかあったら、こちらに電話してくださいと番号を伝えてきた。
自分の自動車保険に車両保険をつけているので、たとえ被害者であっても、自分の車をその車両保険でなおすことができる。たぶん、相手が逃げちゃったような場合とか。
だから、そのへんのことも考えて、関わってくれているらしい。
そうか、そういう仕事か・・・と少々思いつつも、こうやって電話をくれるのは、「気に掛けて」くれている「ほおっておかれていない」という安心感がある。
また電話口に出る人が必ず体のことを尋ねてくれるのは、少々マニュアル的なニュアンスもかんじるけど、悪い気はしない。
だって、場合によってはムチウチのように、あとからでてくることもあるものね。
電話対応には各社、気をつけて、研修などしているんだろうなぁ・・・・と、違う視点で考えてる私・・・
私のやっている人間関係や、コミュニケーションに関する研修では、マニュアルのように
「こういうときは、こういうことに気をつけてこんな言葉がけを」というようなことはやらない。
だから、私自身も言葉の選び方が完璧なわけではなく、むしろ苦手なほうだったりする。
だけど、体験学習を通じて、自らの体をとおして、経験を通して感じ取ったニュアンスから出てくる言葉や「あり方」なので、応用が効く。
言葉がまずかったとしてもその「ありかた」が伝われば、カバーできる事もある。
そういう点から考えたら、このA保険会社。マニュアルにないようなことに対する応対は、
もしかしたら苦手かもしれないなぁ。
へんなところに興味がわいてきた(^^;
今回、被害者ではあるが、先方が保険を使わない可能性があったので、念のため、保険会社に
一報をいれておいた。
保険会社が先方と交渉するようなサービスをつけているわけではないので、本当は関係ないはずだけど、「ご連絡ありがとうございます」と詳細を聞いてくれ、注意事項を教えてくれた。
休みがあけて、今日は、担当となる保険会社の方が電話をくれ、なにかあったら、こちらに電話してくださいと番号を伝えてきた。
自分の自動車保険に車両保険をつけているので、たとえ被害者であっても、自分の車をその車両保険でなおすことができる。たぶん、相手が逃げちゃったような場合とか。
だから、そのへんのことも考えて、関わってくれているらしい。
そうか、そういう仕事か・・・と少々思いつつも、こうやって電話をくれるのは、「気に掛けて」くれている「ほおっておかれていない」という安心感がある。
また電話口に出る人が必ず体のことを尋ねてくれるのは、少々マニュアル的なニュアンスもかんじるけど、悪い気はしない。
だって、場合によってはムチウチのように、あとからでてくることもあるものね。
電話対応には各社、気をつけて、研修などしているんだろうなぁ・・・・と、違う視点で考えてる私・・・
私のやっている人間関係や、コミュニケーションに関する研修では、マニュアルのように
「こういうときは、こういうことに気をつけてこんな言葉がけを」というようなことはやらない。
だから、私自身も言葉の選び方が完璧なわけではなく、むしろ苦手なほうだったりする。
だけど、体験学習を通じて、自らの体をとおして、経験を通して感じ取ったニュアンスから出てくる言葉や「あり方」なので、応用が効く。
言葉がまずかったとしてもその「ありかた」が伝われば、カバーできる事もある。
そういう点から考えたら、このA保険会社。マニュアルにないようなことに対する応対は、
もしかしたら苦手かもしれないなぁ。
へんなところに興味がわいてきた(^^;
タグ :接客応対
スキルじゃなくて、まずは根っこの確認を
某NPOのスタッフ向けの研修。
このNPOの活動には共感しているので、もう少しなにかできないかなぁと思う。
そういや、理事をしているNPOやまもりてんこもりでも、共通することだなぁと・・・
一方で某企業の経営者が「パートさんに会社がお金をだすといっても研修を好まない・・」という話が頭に浮かぶ。
それは、環境や、自分の興味範囲や、研修の中身や・・・いろんな要因が絡むと思う。
そして、あるボランティア団体のメンバーや、参画しているNPOのことも想像してみる・・・
プロフェッショナル意識をもってやっているのか、自分の出来る範囲で出来る事をと思っているのか、ボランティアだからこのくらいでいいと思っているのか・・・
それとも、ここからステップアップしていこうとしているか?
この活動でなにを実現していきたいと思っているのか?
それぞれのスタンスは違う。
でも、何を大事にしているのか?
この活動のどこの共感して、どんな役割をになっていこうとしているのか?
それがどのような状態を生み出す事を期待しているのか?
この活動を通じて、社会にどんな影響を生み出していこうとしているのか?
目先の・・・・スキル的なことじゃなくて、
そういう、根本的な・・・個人の根っこと、組織の目指す方向を確認する事が、まずは大事なんじゃないのかな?
それを、伝えていこう。そのための場作りをしよう。
そして、そういう組織やグループを活性化するためのお手伝いがしたいなぁと思う。
このNPOの活動には共感しているので、もう少しなにかできないかなぁと思う。
そういや、理事をしているNPOやまもりてんこもりでも、共通することだなぁと・・・
一方で某企業の経営者が「パートさんに会社がお金をだすといっても研修を好まない・・」という話が頭に浮かぶ。
それは、環境や、自分の興味範囲や、研修の中身や・・・いろんな要因が絡むと思う。
そして、あるボランティア団体のメンバーや、参画しているNPOのことも想像してみる・・・
プロフェッショナル意識をもってやっているのか、自分の出来る範囲で出来る事をと思っているのか、ボランティアだからこのくらいでいいと思っているのか・・・
それとも、ここからステップアップしていこうとしているか?
この活動でなにを実現していきたいと思っているのか?
それぞれのスタンスは違う。
でも、何を大事にしているのか?
この活動のどこの共感して、どんな役割をになっていこうとしているのか?
それがどのような状態を生み出す事を期待しているのか?
この活動を通じて、社会にどんな影響を生み出していこうとしているのか?
目先の・・・・スキル的なことじゃなくて、
そういう、根本的な・・・個人の根っこと、組織の目指す方向を確認する事が、まずは大事なんじゃないのかな?
それを、伝えていこう。そのための場作りをしよう。
そして、そういう組織やグループを活性化するためのお手伝いがしたいなぁと思う。
経営者とファシリテーション
昨年の山梨ファシリテーション研究会でのことである。
ファシリテーション導入事例を話してくれた若月社長のお話は興味深かった。
それまでは、自分の思いが強すぎて何でもかんでも押し付けていたのかもしれないと、若月社長は言う。
しかし、ファシリテーションを知り、相手から「引きだす」ことが大切と知ったが、一年間は試行錯誤だった様子。社長としては苦しい1年でもあったようだ。
そんななか、会議にファシリテーターとオブザーバー(観察記録者)をおくようにした。
誰でもオブザーバーのとった記録を見られるようにすることで、会議中には表面化しなかったけれども、その場で確かに起こっていたことを、参加者もファシリテーターも知ることが出来るようにした。
たとえば、ファシリテーターが何かを発言したときに、メンバーのほとんどが「ハッとした」表情をしたが、そのままファシリテーターは進行していった・・・とか、具体的な記録が残されている。
ファシリテーターはそれを見て自分の進行ぶりをふりかえる。
若月社長は、時々、状況をフィードバック(メンバーよりもファシリテーターが話しているほうが多いねとか)しながら、しかし、自分が話しすぎてしまうような場面もありながら・・・・と、反省したりという状況だったらしい。
いずれにせよ、継続するうちに少し筒持ち回りで行っているファシリテーターも、少しづつ成長し、ざっくばらんに、メンバーが考えを話せる環境が整っていったということだ。
そのうち、パートを含む社員=スタッフから、いろんな提案があがるようになり、今では携帯電話でその日の出来事や失敗などの報告がメールであがるようになり、携帯の配信システムで、その話題が全員で共有できるようになったそうだ。
そのシステムの提案もスタッフからでてきたそう。
会社の理念も、名刺サイズでパウチしたものが配布され、いつでもどこでも見るようにとスタッフから言われたそうだ。
社長の一方的な提案だったら、携帯電話システムも活用されなかっただろうし、会社の理念だって、見るスタッフなんていないだろう。
スタッフたちが自分たちで考え決めて実行する。そんなカルチャーが育っているようだ。
会社運営にファシリテーションの考えを取り入れるというのは、日常的に、社長や管理職が社員たちからの考えを引き出すことであったり、相手のノンバーバルに気がついて、かかわって、プロセスを明らかにしていくことだったり、自己開示やフィードバックをしていくことだったり、会議にファシリテーターをおく・・・というのはイメージできていたが、会社の会議にオブザーバーを置いて、観察記録をオープンにしておくというアイデアは考えていなかったので、なるほど、いい考えだと思った。
通常の会議では、議題に夢中になっていると、会話の内容は、把握できていたとしても、そこにはでてきていない、参加者の心の動きなどは、そのままおきざりになってしまう。
すると、会議終了し会議の結果あがってきたことをいざ実行しようとしたときに、なかなか実行されないというようなことがおこる可能性がある。
活発に意見がかわされたように見えた会議でも実は一部の人たちだけで進めていて、ほかのひとは、合意していなかった・・・なんてことはよくある話だ。
観察記録のメリットは表面にはでていないことを知る手がかりになる。
ファシリテーターもメンバーもその記録を見ることで、次の会議で何に気をつけて、何を見ていけばいいのかのヒントも得るだろう。
おのずと、お互いに関わりあう関係が生まれてくる。
ファシリテータートレーニングでは一般的なオブザーバーの存在ではあるが、実際の会議での活用も、今後活用させてもらおう。
若月社長の会社はこちら
http://www.plan-do-wakatsuki.jp/corp.html
オブザーバーの記録の取り方を学びたい方はお問い合わせを coach-kaneshige@nifty.com
ファシリテーション導入事例を話してくれた若月社長のお話は興味深かった。
それまでは、自分の思いが強すぎて何でもかんでも押し付けていたのかもしれないと、若月社長は言う。
しかし、ファシリテーションを知り、相手から「引きだす」ことが大切と知ったが、一年間は試行錯誤だった様子。社長としては苦しい1年でもあったようだ。
そんななか、会議にファシリテーターとオブザーバー(観察記録者)をおくようにした。
誰でもオブザーバーのとった記録を見られるようにすることで、会議中には表面化しなかったけれども、その場で確かに起こっていたことを、参加者もファシリテーターも知ることが出来るようにした。
たとえば、ファシリテーターが何かを発言したときに、メンバーのほとんどが「ハッとした」表情をしたが、そのままファシリテーターは進行していった・・・とか、具体的な記録が残されている。
ファシリテーターはそれを見て自分の進行ぶりをふりかえる。
若月社長は、時々、状況をフィードバック(メンバーよりもファシリテーターが話しているほうが多いねとか)しながら、しかし、自分が話しすぎてしまうような場面もありながら・・・・と、反省したりという状況だったらしい。
いずれにせよ、継続するうちに少し筒持ち回りで行っているファシリテーターも、少しづつ成長し、ざっくばらんに、メンバーが考えを話せる環境が整っていったということだ。
そのうち、パートを含む社員=スタッフから、いろんな提案があがるようになり、今では携帯電話でその日の出来事や失敗などの報告がメールであがるようになり、携帯の配信システムで、その話題が全員で共有できるようになったそうだ。
そのシステムの提案もスタッフからでてきたそう。
会社の理念も、名刺サイズでパウチしたものが配布され、いつでもどこでも見るようにとスタッフから言われたそうだ。
社長の一方的な提案だったら、携帯電話システムも活用されなかっただろうし、会社の理念だって、見るスタッフなんていないだろう。
スタッフたちが自分たちで考え決めて実行する。そんなカルチャーが育っているようだ。
会社運営にファシリテーションの考えを取り入れるというのは、日常的に、社長や管理職が社員たちからの考えを引き出すことであったり、相手のノンバーバルに気がついて、かかわって、プロセスを明らかにしていくことだったり、自己開示やフィードバックをしていくことだったり、会議にファシリテーターをおく・・・というのはイメージできていたが、会社の会議にオブザーバーを置いて、観察記録をオープンにしておくというアイデアは考えていなかったので、なるほど、いい考えだと思った。
通常の会議では、議題に夢中になっていると、会話の内容は、把握できていたとしても、そこにはでてきていない、参加者の心の動きなどは、そのままおきざりになってしまう。
すると、会議終了し会議の結果あがってきたことをいざ実行しようとしたときに、なかなか実行されないというようなことがおこる可能性がある。
活発に意見がかわされたように見えた会議でも実は一部の人たちだけで進めていて、ほかのひとは、合意していなかった・・・なんてことはよくある話だ。
観察記録のメリットは表面にはでていないことを知る手がかりになる。
ファシリテーターもメンバーもその記録を見ることで、次の会議で何に気をつけて、何を見ていけばいいのかのヒントも得るだろう。
おのずと、お互いに関わりあう関係が生まれてくる。
ファシリテータートレーニングでは一般的なオブザーバーの存在ではあるが、実際の会議での活用も、今後活用させてもらおう。
若月社長の会社はこちら
http://www.plan-do-wakatsuki.jp/corp.html
オブザーバーの記録の取り方を学びたい方はお問い合わせを coach-kaneshige@nifty.com
企業研修~チームベースづくり
2年ほどかかわらせていただいている農業法人さんの全体ミーティングで時間を持たせていただいた。普段は一部の方だけの接触だったので、私としても、この機会はとても嬉しかった。
せっかく、関わるのなら、先方のことをもっと知りたいという思いがあったし、ときどき見かける外部のひとという位置ではなく、社員さんとも、もっとお話できるといいなぁと思っていた。
朝の農場見学からご一緒させていただく。
農場スタッフの説明、それを聞いているスタッフの好奇心、誰に指示されたわけでないのに、私に説明してくれる態度などに、この仕事への愛情が感じられる。
午後の私の担当時間は、スタッフ間の【交流】【情報交換】がねらい。
規模が大きくなってくると、昔とは違うことがおきてくる。そんななかでの、試み。
自分の担当部署と違う人たちとチームになり、普段話さないようなことを話してもらう。
最初は相手の意外な一面を見て笑顔と驚きに。
次は、照れくささもあるような場面。
そして最後は、普段きけなかったこと、知らなかったことを、お互いに聞きあったり、こんな風にしてもらえたらいいんだけど・・・と情報交換。
この場面では、みんな真剣な顔に。
いつも見ている顔でも、知らなかった一面を見て嬉しくなった。身近になった。
相手が自分をそんな風に見てくれていたのかと知って、嬉しかった。
知らなかった相手の仕事内容がわかって協力してやっていけそう。
そんな感想が。
そして、私に、いい時間でしたと、こういう時間を持ててよかったですと感想をわざわざ伝えてくれるかたも。
感想をシェアするときも私をねぎらってくれるようなそんなニュアンスが伝わってきていた。
今日も、随所にみられたが、普段から社長や役員のかたたちが、こまめに感想を伝えたり、ねぎらいをかかさないから、スタッフも知らずにそういう振る舞いをされるのだろう。
普段からお互い知っているけど、もう一歩踏み込んで話し合える関係作り。
そんな場作りは、チームのベース作り。
こういう企業との関わりをもっと進めていきたい。
せっかく、関わるのなら、先方のことをもっと知りたいという思いがあったし、ときどき見かける外部のひとという位置ではなく、社員さんとも、もっとお話できるといいなぁと思っていた。
朝の農場見学からご一緒させていただく。
農場スタッフの説明、それを聞いているスタッフの好奇心、誰に指示されたわけでないのに、私に説明してくれる態度などに、この仕事への愛情が感じられる。
午後の私の担当時間は、スタッフ間の【交流】【情報交換】がねらい。
規模が大きくなってくると、昔とは違うことがおきてくる。そんななかでの、試み。
自分の担当部署と違う人たちとチームになり、普段話さないようなことを話してもらう。
最初は相手の意外な一面を見て笑顔と驚きに。
次は、照れくささもあるような場面。
そして最後は、普段きけなかったこと、知らなかったことを、お互いに聞きあったり、こんな風にしてもらえたらいいんだけど・・・と情報交換。
この場面では、みんな真剣な顔に。
いつも見ている顔でも、知らなかった一面を見て嬉しくなった。身近になった。
相手が自分をそんな風に見てくれていたのかと知って、嬉しかった。
知らなかった相手の仕事内容がわかって協力してやっていけそう。
そんな感想が。
そして、私に、いい時間でしたと、こういう時間を持ててよかったですと感想をわざわざ伝えてくれるかたも。
感想をシェアするときも私をねぎらってくれるようなそんなニュアンスが伝わってきていた。
今日も、随所にみられたが、普段から社長や役員のかたたちが、こまめに感想を伝えたり、ねぎらいをかかさないから、スタッフも知らずにそういう振る舞いをされるのだろう。
普段からお互い知っているけど、もう一歩踏み込んで話し合える関係作り。
そんな場作りは、チームのベース作り。
こういう企業との関わりをもっと進めていきたい。