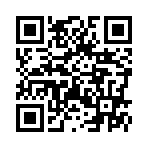こんな会議でいいの?
まちづくりとか非営利組織、異業種交流会に絡んだ会議に参加してびっくりしたこと。
★時間通りに終わらない。
★話がどんどん横にそれる。「今何の話をしているのですか?」と訊くとだれもわからない。
★いきなり「意見をどうぞ」といわれたが、何について意見を言えばいいのか、この時間のテーマが具体的にわからないところから始まった
★「総会」なのに式次第もなく、議長も選出されなかった。進行役もだれだかわからなかった。
★参加者はおおければ多いほどいろんな意見が聞けてよいということで、会の決定機関なのに、20人近くの会議参加メンバーがいる。結果、ものごとは決まらないし、出席率は下がる。
★時間がないからと言って、一部のメンバーで既に方向性を決め動き出しておきながら、会議で「どうですか?」と訊く。
★20人近くの会議参加メンバーの顔と名前も一致しない中で、進行役の指名で、わかってるひとだけで話して、決をとるわけでもなく、なんとなくの流れで進行役が、ではこの方向で行きましょうと物事が決定していく。
★最近会議が開かれないなぁと思ったら、一部のコアメンバーだけで物事が進んでいき、年に1、2度、報告のための会議だけが行われる。
★一部の人だけがもりあがって、どんどん話が先に進んでいくので、その方向で合意が取れているのかどうかもわからず、自分も含めどんどんほかのメンバーが取り残されていくのを見かねて、「今は何について話しているのか?どんどん先に進んでいくのでついていけないかんじがするのですが、私だけでしょうか?ほかの人はどうか?」と発言したら、ほかのひとは、さぁ?と首をかしげる。
もりあがっていたメンバーの一人は「ついてこれないやつが悪い。話したい人だけが話せばいいのだ」
これらは、複数の別の会議で起こったことを寄せ集め。
訊いた話だと
★時間通りにおわらないどころか、夜の会議が日付をまたいでもまだ収集がつかないという事態があったとか。
★トップがやりたいことをやらせるための会議で、メンバーの話を聴かないだけじゃなく、意見や要望を力でねじふせる・・・ということもあるとか。
★最後の事例の「話したい人だけが話せばいいのだ」と言った人は教育機関の運営に関わっているとか。
みなさんの会議はどうですか?
★時間通りに終わらない。
★話がどんどん横にそれる。「今何の話をしているのですか?」と訊くとだれもわからない。
★いきなり「意見をどうぞ」といわれたが、何について意見を言えばいいのか、この時間のテーマが具体的にわからないところから始まった
★「総会」なのに式次第もなく、議長も選出されなかった。進行役もだれだかわからなかった。
★参加者はおおければ多いほどいろんな意見が聞けてよいということで、会の決定機関なのに、20人近くの会議参加メンバーがいる。結果、ものごとは決まらないし、出席率は下がる。
★時間がないからと言って、一部のメンバーで既に方向性を決め動き出しておきながら、会議で「どうですか?」と訊く。
★20人近くの会議参加メンバーの顔と名前も一致しない中で、進行役の指名で、わかってるひとだけで話して、決をとるわけでもなく、なんとなくの流れで進行役が、ではこの方向で行きましょうと物事が決定していく。
★最近会議が開かれないなぁと思ったら、一部のコアメンバーだけで物事が進んでいき、年に1、2度、報告のための会議だけが行われる。
★一部の人だけがもりあがって、どんどん話が先に進んでいくので、その方向で合意が取れているのかどうかもわからず、自分も含めどんどんほかのメンバーが取り残されていくのを見かねて、「今は何について話しているのか?どんどん先に進んでいくのでついていけないかんじがするのですが、私だけでしょうか?ほかの人はどうか?」と発言したら、ほかのひとは、さぁ?と首をかしげる。
もりあがっていたメンバーの一人は「ついてこれないやつが悪い。話したい人だけが話せばいいのだ」
これらは、複数の別の会議で起こったことを寄せ集め。
訊いた話だと
★時間通りにおわらないどころか、夜の会議が日付をまたいでもまだ収集がつかないという事態があったとか。
★トップがやりたいことをやらせるための会議で、メンバーの話を聴かないだけじゃなく、意見や要望を力でねじふせる・・・ということもあるとか。
★最後の事例の「話したい人だけが話せばいいのだ」と言った人は教育機関の運営に関わっているとか。
みなさんの会議はどうですか?
会議運営ファシリテーションセミナー参加者募集中
久しぶりに公開講座を実施します。
日曜と月曜の二日間の実施なので、どうかなとも思いつつ。
会議の進行で、悩んでいる方、もっとうまくいく方法があるんじゃないかと思っている方、あなたの進行する会議のデザインを行いながら、ファシリテーター役とメンバー役を交互に体験しながら学ぶセミナーです。
【会議運営ファシリテーション・5月16日(日)17日(月)長野市内】
1)長時間の会議だったのに、何が決まったのかわからない
2)いつも特定のひとばかり発言している
3)何もしゃべらない会議参加者がいて、それに対しても誰も何も言わない
4)本来議論すべきところから論点がずれて別の話になってしまう。
5)会議の席では本音を言わず、あとで別のところでそれを言ってくる。
6)ボスが結局結論をひっくりかえす
7)声の大きい人の意見が結論になる
ほか
そんな不満を持っている方、会議改革、チーム改革への一歩を踏み出してみませんか?
日時)2010年5月16日(日) 10:00-18:30
5月17日(月) 9:30-18:30 (2日間の通い)
会場)長野市生涯学習センター トイーゴウエスト 3階
長野市鶴賀問御所町1271-3 電話026-223-8080
参加費) 38,000円(税込み) テキスト代、ノートブック代含む
講師) 兼重コーチング事務所 兼重 尚子
申し込みはこちらのフォームからお申し込みください。
ちらしはこちらのページから、ダウンロードページへどうぞ。
お問い合わせは coach-kaneshige@nifty.com へ。
日曜と月曜の二日間の実施なので、どうかなとも思いつつ。
会議の進行で、悩んでいる方、もっとうまくいく方法があるんじゃないかと思っている方、あなたの進行する会議のデザインを行いながら、ファシリテーター役とメンバー役を交互に体験しながら学ぶセミナーです。
【会議運営ファシリテーション・5月16日(日)17日(月)長野市内】
1)長時間の会議だったのに、何が決まったのかわからない
2)いつも特定のひとばかり発言している
3)何もしゃべらない会議参加者がいて、それに対しても誰も何も言わない
4)本来議論すべきところから論点がずれて別の話になってしまう。
5)会議の席では本音を言わず、あとで別のところでそれを言ってくる。
6)ボスが結局結論をひっくりかえす
7)声の大きい人の意見が結論になる
ほか
そんな不満を持っている方、会議改革、チーム改革への一歩を踏み出してみませんか?
日時)2010年5月16日(日) 10:00-18:30
5月17日(月) 9:30-18:30 (2日間の通い)
会場)長野市生涯学習センター トイーゴウエスト 3階
長野市鶴賀問御所町1271-3 電話026-223-8080
参加費) 38,000円(税込み) テキスト代、ノートブック代含む
講師) 兼重コーチング事務所 兼重 尚子
申し込みはこちらのフォームからお申し込みください。
ちらしはこちらのページから、ダウンロードページへどうぞ。
お問い合わせは coach-kaneshige@nifty.com へ。
記録係をするということの効用と、メンバーとの関係性について
会議などで、議事録をとるための記録ではなく、
議題から話し合いが離れず、有効な話し合いとなるための整理ツールとして、
板書したり、ホワイトボードを活用されたり、されているだろうか?
先日の会議ファシリテーションのセミナーでも、参加者の中で、記録経験のあるのは、わずかだったし、いつも活用しているわけではないという。
私自身がこれまで、参加してきた、異業種交流会や、町の会議でも、活用されているのを見たことがない。(私が勝手に書き出すことはあっても)
セミナーでは模造紙の利用をお勧めしている。
私の模造紙活用との出会いは、新潟でまちづくり活動を実施しているファシリテーターの活動で「ファシリテーショングラフィック」の存在を知ってから。
しかし企業や、一般の活動で、「グラフィック」を使わなかったとしても、模造紙の活用は、有効だ。
今回セミナーを実施して、参加者もその効用や利便性にめからうろこのようだった。
* 議論が、離れていっても、テーマを記載してある事で、戻しやすい
* 発言を記録する事で、同じところをぐるぐるしづらい
* 話し合いの軌跡を見ることが出来るので、これまでに出ていた発言を活用しやすい
* 次回の会議の際に、前回の模造紙を見ることで、経過や結論を思い出し、すぐに議題に入りやすい
などなど。
早速、模造紙を活用すること、ペンはマッキーではなく
にじみ・裏うつりなし!基本の8色セット三菱鉛筆 水性顔料マーカー プロッキー8色セット 太字+細字プロッキーねと、メモする人も。
以上は「記録の有効性」についてなんだけど、今回は「記録係をすることの有効性」について。
会議ファシリテーションのセミナーでは「ファシリテーター兼グラフィカ」として、進行役と記録係を兼ねて体験していただくのだが、昨日は、専門学校の授業(人間関係ファシリテーションの切り口)で、記録係と進行役を別れて別々の方が担当した。
今回「記録係=グラフィカ」の役割については「決まったことをまとめて記録するのではなく、議論を有効に進めるためのツールとして記録するんだよ」「テーマと日付だけは最初に書いておいてね」とだけ伝えて、模造紙とプロッキーを渡した。
グラフィカを担当したのは、普段、他者の発言や議題について促進するようなかかわりというのはほとんどみられなかった人なのだけど、グラフィカをしながらの自然なかかわりにびっくり。
記録をする為に、確認をしたり質問をしたり。記録に集中してしまって聞き漏らしたからもう一度言って~とお願いしたり。
それが、その場にとても貢献していた。
記録に対しても、色を変えたり、線で囲ったり、見やすい工夫が。
慣れないせいもあって、他者の発言を自分なりの解釈で自分の言葉で記録してしまうことは時にあったとしても、それが、上手く機能していたり、「それはちょっと違うかも」
と記録を見たメンバーが訂正の発言をしたりして、相互のかかわりが生まれていた。
グラフィカをするというその役割を負ったことで、彼から自然な、彼らしいファシリテーションが発揮されて、私は彼の新しい一面を見た気がする。
もちろん、ファシリテーター役も、参加者であり、ファシリテーターでありという役割であったにもかかわらず、自分の意見も言いながら、議論をまとめたり、方向性を確認したりして、その場に貢献。気負いなくできたと本人も言う。
メンバーそれぞれも、自分の意見をだしながら、それぞれのスタンスでファシリテーター的な動きもあり、「素敵なチームになったなぁ」と半年担当して、生徒さん達の成長ぶりに感動。
これまで自分が内側で考えている事や感じている事を出すのは苦手だったり、あえてださなかったひとが、自然にそれを出す事が出来ているのは、このメンバーだからだと言っていたけど、なぜ、そういうことが出来るようになったのか。
そんなことももっともっと是非分析して、他の場面でもいかしてほしいなぁ。
グラフィカをする役割から、必然的にファシリテーター的な動きがでてくる効能もある程度あるとは思うけど、いつもとは言えない・・・・
だけど、今回そういうことが起こったのはなぜか?
メンバー同士が信頼し、安心して発言したり、振舞う事が出来る。そういう関係性があるからこそ、役割を負ったときも、「こうしたほうがいいのかな?」と思ったことを試す事が出来るのではないか。うまく出来なくても、誰かがフォローしてくれる・・そんな無意識の安心感からかもしれない。
「役割が人を育てる」というようなことなんだろうか?とうっすら思いながらこの記事を書き始めた。
だけど、「安心してそこにいられる、発言できる、行動できる、信頼感のある関係性」がある、そのなかでだからこそ、「役割」に対しても「こうでなければならない」に縛られてしまうのではなく、役割に必要な事を自分なりに試すことができるのでははないか、と思うにいたった。
そして役割を負うことで新たな自分を発見したり、成長したりすることが出来るのではないだろうか?
下記は私の「記録」という一面をどこで取り入れるのかから、考えた仮説だけど。
★会議ファシリテーションセミナーのように、技術的なことを体験するセミナーでは、たとえば「記録する」ということの実用的な効用を感じながら、話し合いの結果を出す事が出来る。
そして繰り返すうちに、役割の技能があがり、人間関係もすこしづつよくなっていく・・というイメージ。
★人間関係ファシリテーションセミナーからスタートすると
「安心感のある関係作り」から人間関係を先に作るので、話し合いの結果というのは、なかなかでづらい。
しかし、人間関係ができてから「記録」などの技術的なことを導入すると、効果は比較的早く現れて、会議の成果がでやすい・・・
のかなと。
技術が先か、人間関係が先かっていう、鶏と卵の関係かな。
そんなことを考えた日でした。
議題から話し合いが離れず、有効な話し合いとなるための整理ツールとして、
板書したり、ホワイトボードを活用されたり、されているだろうか?
先日の会議ファシリテーションのセミナーでも、参加者の中で、記録経験のあるのは、わずかだったし、いつも活用しているわけではないという。
私自身がこれまで、参加してきた、異業種交流会や、町の会議でも、活用されているのを見たことがない。(私が勝手に書き出すことはあっても)
セミナーでは模造紙の利用をお勧めしている。
私の模造紙活用との出会いは、新潟でまちづくり活動を実施しているファシリテーターの活動で「ファシリテーショングラフィック」の存在を知ってから。
しかし企業や、一般の活動で、「グラフィック」を使わなかったとしても、模造紙の活用は、有効だ。
今回セミナーを実施して、参加者もその効用や利便性にめからうろこのようだった。
* 議論が、離れていっても、テーマを記載してある事で、戻しやすい
* 発言を記録する事で、同じところをぐるぐるしづらい
* 話し合いの軌跡を見ることが出来るので、これまでに出ていた発言を活用しやすい
* 次回の会議の際に、前回の模造紙を見ることで、経過や結論を思い出し、すぐに議題に入りやすい
などなど。
早速、模造紙を活用すること、ペンはマッキーではなく

にじみ・裏うつりなし!基本の8色セット三菱鉛筆 水性顔料マーカー プロッキー8色セット 太字+細字プロッキーねと、メモする人も。
以上は「記録の有効性」についてなんだけど、今回は「記録係をすることの有効性」について。
会議ファシリテーションのセミナーでは「ファシリテーター兼グラフィカ」として、進行役と記録係を兼ねて体験していただくのだが、昨日は、専門学校の授業(人間関係ファシリテーションの切り口)で、記録係と進行役を別れて別々の方が担当した。
今回「記録係=グラフィカ」の役割については「決まったことをまとめて記録するのではなく、議論を有効に進めるためのツールとして記録するんだよ」「テーマと日付だけは最初に書いておいてね」とだけ伝えて、模造紙とプロッキーを渡した。
グラフィカを担当したのは、普段、他者の発言や議題について促進するようなかかわりというのはほとんどみられなかった人なのだけど、グラフィカをしながらの自然なかかわりにびっくり。
記録をする為に、確認をしたり質問をしたり。記録に集中してしまって聞き漏らしたからもう一度言って~とお願いしたり。
それが、その場にとても貢献していた。
記録に対しても、色を変えたり、線で囲ったり、見やすい工夫が。
慣れないせいもあって、他者の発言を自分なりの解釈で自分の言葉で記録してしまうことは時にあったとしても、それが、上手く機能していたり、「それはちょっと違うかも」
と記録を見たメンバーが訂正の発言をしたりして、相互のかかわりが生まれていた。
グラフィカをするというその役割を負ったことで、彼から自然な、彼らしいファシリテーションが発揮されて、私は彼の新しい一面を見た気がする。
もちろん、ファシリテーター役も、参加者であり、ファシリテーターでありという役割であったにもかかわらず、自分の意見も言いながら、議論をまとめたり、方向性を確認したりして、その場に貢献。気負いなくできたと本人も言う。
メンバーそれぞれも、自分の意見をだしながら、それぞれのスタンスでファシリテーター的な動きもあり、「素敵なチームになったなぁ」と半年担当して、生徒さん達の成長ぶりに感動。
これまで自分が内側で考えている事や感じている事を出すのは苦手だったり、あえてださなかったひとが、自然にそれを出す事が出来ているのは、このメンバーだからだと言っていたけど、なぜ、そういうことが出来るようになったのか。
そんなことももっともっと是非分析して、他の場面でもいかしてほしいなぁ。
グラフィカをする役割から、必然的にファシリテーター的な動きがでてくる効能もある程度あるとは思うけど、いつもとは言えない・・・・
だけど、今回そういうことが起こったのはなぜか?
メンバー同士が信頼し、安心して発言したり、振舞う事が出来る。そういう関係性があるからこそ、役割を負ったときも、「こうしたほうがいいのかな?」と思ったことを試す事が出来るのではないか。うまく出来なくても、誰かがフォローしてくれる・・そんな無意識の安心感からかもしれない。
「役割が人を育てる」というようなことなんだろうか?とうっすら思いながらこの記事を書き始めた。
だけど、「安心してそこにいられる、発言できる、行動できる、信頼感のある関係性」がある、そのなかでだからこそ、「役割」に対しても「こうでなければならない」に縛られてしまうのではなく、役割に必要な事を自分なりに試すことができるのでははないか、と思うにいたった。
そして役割を負うことで新たな自分を発見したり、成長したりすることが出来るのではないだろうか?
下記は私の「記録」という一面をどこで取り入れるのかから、考えた仮説だけど。
★会議ファシリテーションセミナーのように、技術的なことを体験するセミナーでは、たとえば「記録する」ということの実用的な効用を感じながら、話し合いの結果を出す事が出来る。
そして繰り返すうちに、役割の技能があがり、人間関係もすこしづつよくなっていく・・というイメージ。
★人間関係ファシリテーションセミナーからスタートすると
「安心感のある関係作り」から人間関係を先に作るので、話し合いの結果というのは、なかなかでづらい。
しかし、人間関係ができてから「記録」などの技術的なことを導入すると、効果は比較的早く現れて、会議の成果がでやすい・・・
のかなと。
技術が先か、人間関係が先かっていう、鶏と卵の関係かな。
そんなことを考えた日でした。
臨時総会と議長
臨時総会って、もめるって本当? ちょっと前の出来事ですが。
いわゆる「総会」っていうのは、「1号議案」拍手~「2号議案」拍手~って、しゃんしゃんって終わる形だけなものしか、参加したことがなかったから、あんまり考えてなかった。
(ファシリやってるのに、それってどうよと自己突っ込み)
総会の議長は、シナリオどおりに、議事をすすめて、おしまいという役割だと、なんとなく思っていた自分に気がつく。
かといって、この人数をファシリテートしながら、満足する総会にするイメージが、すぐにはわかない。私の中で、「総会」の議長は、まじめくさって、決まったことしか話せないような、これまでの経験からの固定イメージがあった。
で、実際。
M議長。ほれぼれ。
「総会」なのに場を和ませる。「総会」なのに、笑わせる。「誰も意見を言わないと、指しますよ♪」だって。
そういうキャラクターだった?
そんな「総会」でたことない。
丁寧に議事をすすめ、どう、質問していいのか、どう意見を言ったらいいのか、わからないような人もいたように思うけど、そんな人たちの声をちゃんと吸い上げる。
話したそうな人に声をかける。
ここで回答すること、持ち帰って検討することを、区別する。
ああ、ファシリテーターだ。
議長も。
最初に時間を決め、協力を促し、場を和ませ、話しやすい雰囲気を作る。
議案を整理し、自分の言葉で簡潔に聞く。その時間をフルに使って意見をだしてもらう。
話したそうな人に声をかけ、難しい顔をしたひとに、声をかける。
相手の言いたいことを整理し、適切な方にふっていく。
結果、荒れることはなく、ある程度活発な意見交換がなされ、無事可決。
これが、誰も発言もしない会だったら、不満も残っただろう。
参加者の思いも受け取った。
自分が三役で「回答側」に座るなんて、始まるまでわかっていなかったおおぼけだった私だけど、適切な人が適切なわかりやすい回答をしてくれ「ああ、なんてこの会は役者がそろっているんだろう」。勝手に感動。
(昔、60人くらい出席してるのに、議長もいない、レジュメもない総会をやってた組織だったってことは、すっかり忘却のかなた(^^;) ちなみに、その際に私は、ぺーぺーなのに、思わず黒板だしてきて、進行やってました(^^;)
M議長のふるまいに、私もリラックスして、質問者の意図を明確にすることができて、私の役割も果たせたかなぁ。
「総会」ってつまらないものだと思っていたけど、見方がかわりました。
誰も彼も、ひとりひとりが、大切な役割を果たし、参加していた総会でした。
M議長。ありがとう。
新鮮な体験でした。
いわゆる「総会」っていうのは、「1号議案」拍手~「2号議案」拍手~って、しゃんしゃんって終わる形だけなものしか、参加したことがなかったから、あんまり考えてなかった。
(ファシリやってるのに、それってどうよと自己突っ込み)
総会の議長は、シナリオどおりに、議事をすすめて、おしまいという役割だと、なんとなく思っていた自分に気がつく。
かといって、この人数をファシリテートしながら、満足する総会にするイメージが、すぐにはわかない。私の中で、「総会」の議長は、まじめくさって、決まったことしか話せないような、これまでの経験からの固定イメージがあった。
で、実際。
M議長。ほれぼれ。
「総会」なのに場を和ませる。「総会」なのに、笑わせる。「誰も意見を言わないと、指しますよ♪」だって。
そういうキャラクターだった?
そんな「総会」でたことない。
丁寧に議事をすすめ、どう、質問していいのか、どう意見を言ったらいいのか、わからないような人もいたように思うけど、そんな人たちの声をちゃんと吸い上げる。
話したそうな人に声をかける。
ここで回答すること、持ち帰って検討することを、区別する。
ああ、ファシリテーターだ。
議長も。
最初に時間を決め、協力を促し、場を和ませ、話しやすい雰囲気を作る。
議案を整理し、自分の言葉で簡潔に聞く。その時間をフルに使って意見をだしてもらう。
話したそうな人に声をかけ、難しい顔をしたひとに、声をかける。
相手の言いたいことを整理し、適切な方にふっていく。
結果、荒れることはなく、ある程度活発な意見交換がなされ、無事可決。
これが、誰も発言もしない会だったら、不満も残っただろう。
参加者の思いも受け取った。
自分が三役で「回答側」に座るなんて、始まるまでわかっていなかったおおぼけだった私だけど、適切な人が適切なわかりやすい回答をしてくれ「ああ、なんてこの会は役者がそろっているんだろう」。勝手に感動。
(昔、60人くらい出席してるのに、議長もいない、レジュメもない総会をやってた組織だったってことは、すっかり忘却のかなた(^^;) ちなみに、その際に私は、ぺーぺーなのに、思わず黒板だしてきて、進行やってました(^^;)
M議長のふるまいに、私もリラックスして、質問者の意図を明確にすることができて、私の役割も果たせたかなぁ。
「総会」ってつまらないものだと思っていたけど、見方がかわりました。
誰も彼も、ひとりひとりが、大切な役割を果たし、参加していた総会でした。
M議長。ありがとう。
新鮮な体験でした。
できる人の会議に出る技術
現在、群馬県で実施する問題解決会議ファシリテーター一日セミナーの準備をしてるのです。
これは、ファシリテーターを養成するためのもの。
会議企画者、進行者用のセミナーなわけなんですが、ふと思うことが。

できる人の会議に出る技術
上記書籍の執筆者は、ビジネス系ファシリテーションの師匠なのです。
人間関係のファシリテーションを学んで、私は会議のメンバーとしてのファシリテーションを活用し、だんだんファシリテーターをやるようになってきたのを思い出す。
そうだ。
人間関係ファシリテーションの学びの場をベースに、会議参加者のためのセミナーをやったらどうかしら?
副読本として上記師匠の本を使って。
むふふ♪
いいねぇ♪
提案してみようっと。
興味あります?
これは、ファシリテーターを養成するためのもの。
会議企画者、進行者用のセミナーなわけなんですが、ふと思うことが。

できる人の会議に出る技術
上記書籍の執筆者は、ビジネス系ファシリテーションの師匠なのです。
人間関係のファシリテーションを学んで、私は会議のメンバーとしてのファシリテーションを活用し、だんだんファシリテーターをやるようになってきたのを思い出す。
そうだ。
人間関係ファシリテーションの学びの場をベースに、会議参加者のためのセミナーをやったらどうかしら?
副読本として上記師匠の本を使って。
むふふ♪
いいねぇ♪
提案してみようっと。
興味あります?
問題解決型会議ファシリテーション1日講座参加者募集
★ 問題解決型の会議を進行するファシリテーターのための講座です。
最短2時間で、行動まで落とし込みます。
チームの力を最大限に引き出したいチームリーダー、コンサルタント、人事担当者のかたがた、
お客様チームのニーズを引き出したい専門職の方、会社を変革させたい2代目社長、ご参加お待ちしています。
詳細はこちらのHPをご覧ください。
開催日時 2009年4月18日(土) 9時半~18時半
開催場所 (株)ビズクリエイト2階セミナールーム
群馬県富岡市富岡1441-1(上州富岡駅前)
定員 20名
参加費 15000円
申し込み・問い合わせはこちらのHPから
最短2時間で、行動まで落とし込みます。
チームの力を最大限に引き出したいチームリーダー、コンサルタント、人事担当者のかたがた、
お客様チームのニーズを引き出したい専門職の方、会社を変革させたい2代目社長、ご参加お待ちしています。
詳細はこちらのHPをご覧ください。
開催日時 2009年4月18日(土) 9時半~18時半
開催場所 (株)ビズクリエイト2階セミナールーム
群馬県富岡市富岡1441-1(上州富岡駅前)
定員 20名
参加費 15000円
申し込み・問い合わせはこちらのHPから
会議の実情とファシリテーション
非営利目的の有志による活動の中での会議。年齢も、地位も、その会での経験も知識もみんなバラバラの有志の集り。
個人個人が自分の興味のあることについて思いついたことを発言し、質問していく。どんどん、どんどん、話が広がっていく。
今、何の話をしてるの?
何を決めようとしてるの?何を話のテーブルにのせてるの?
よくわからないまま、個人個人が思いつくことを、言いたいことを言っている。
そして毎回何も決まらないまま、次回へ。
そして次回、また同じことがぐるぐる回っている・・・進展しない・・・
あるときは経営者の集り、あるときは町の集り。
経営者でも、主婦や自営業でも、会議のプロセスは同じという状況を目の前にして目が白黒。
経営者の集まりでは、さすがにみなさんお忙しいので、何も決まらなくても時間になればおしまい。
なんとなく声の大きな人や、リーダーが自分の言葉でまとめて、合意形成もなく、なんとなく方向性を示して結論付けて次へ。
町の集まりでは、だらだらと時間だけが過ぎていく。
私は経験したことはないけれど、夜7時に集って翌日になるまで、会議なんてこともあるそうだ(^^;
集りに参加して日が浅いが、勇気をふりしぼって言ってみた。
「あのぉ、今何の話しているんですか?」「今やろうとしていることの目的はなんですか?」
ある経営者の集まりでは、強制参加ではなく、自主参加なのだから、発言したい人だけが発言すればいい、合意形成?そんなもの関係ない・・。
話についてこれないものは、それだけの興味なのだから参加しなくてもいい。
・・・・そうなのかな?
「今話してることの目的は?」
「今ざっくばらんに話すところから、自由に思い付きを話すことからいいアイデアや思いもしなかったことがでてくるかもしれないだろう?そんないちいち合意形成して、この話をしましょうなんてやってたらアイデアでてこないよ」
自主参加の会議だからそうしてるというのですか?本当に?
町の会議では・・・
「今何の話してるんですか?」という問いに誰もわからなかった・・・
「今日の会議の目的は?」・・・・・ようやくスタート地点に立った。
別の集まりでの会議。
リーダーの声がけで、どんどん、いろんなことが決まっていく。でも、なにか取り残されているかんじ。
メンバーの温度差。どうして、それが決まったのか、よくわからない。
わかってないのは私だけ?他の皆さんはどう思っているんですか?
問いかけても自主的に話してくれないのは、ここは安全な場じゃないっていうことだなぁ。
話し手の目を見て聴いていると、それがいつのまにか私に対して話しかけるようになっている。周りを見回すと、目をあわさないようにしている人もいる。
目が合うと、役目が指名されるんだ。だから目を合わせないようにしてるんだ。なるほど・・・
理屈で指摘しても、伝わらない。やっぱりプロセス(自分の中で起こっていること)を出していくことが、キーを握るとかんじた。
たとえ会議であっても。
「指名されて、戸惑っている。役割を決める前に、何をするのかを話しあってからでないと納得して引き受けられる感じがしない」「私にはここがよくわからない。みなさんはどう理解されているんですか?納得されてますか?」
結局何も決まらなかったけど、振り出しに戻って、みんなが同じテーブルに乗れたような気がする。それぞれが思っていることを言う場が生まれた。
私のできること、役割はやはり、ファシリテーターでありコーチ。
課題達成したいのはヤマヤマだし、性分的にもそうしたいけど、そのためにもプロセスを大事にしないと成功しないと思う。第一、私がその課題達成に向けて納得してなきゃ、ベストをつくせない。
参加者としてのファシリテーション、磨いていこう。
(2005年6月の日記より)
個人個人が自分の興味のあることについて思いついたことを発言し、質問していく。どんどん、どんどん、話が広がっていく。
今、何の話をしてるの?
何を決めようとしてるの?何を話のテーブルにのせてるの?
よくわからないまま、個人個人が思いつくことを、言いたいことを言っている。
そして毎回何も決まらないまま、次回へ。
そして次回、また同じことがぐるぐる回っている・・・進展しない・・・
あるときは経営者の集り、あるときは町の集り。
経営者でも、主婦や自営業でも、会議のプロセスは同じという状況を目の前にして目が白黒。
経営者の集まりでは、さすがにみなさんお忙しいので、何も決まらなくても時間になればおしまい。
なんとなく声の大きな人や、リーダーが自分の言葉でまとめて、合意形成もなく、なんとなく方向性を示して結論付けて次へ。
町の集まりでは、だらだらと時間だけが過ぎていく。
私は経験したことはないけれど、夜7時に集って翌日になるまで、会議なんてこともあるそうだ(^^;
集りに参加して日が浅いが、勇気をふりしぼって言ってみた。
「あのぉ、今何の話しているんですか?」「今やろうとしていることの目的はなんですか?」
ある経営者の集まりでは、強制参加ではなく、自主参加なのだから、発言したい人だけが発言すればいい、合意形成?そんなもの関係ない・・。
話についてこれないものは、それだけの興味なのだから参加しなくてもいい。
・・・・そうなのかな?
「今話してることの目的は?」
「今ざっくばらんに話すところから、自由に思い付きを話すことからいいアイデアや思いもしなかったことがでてくるかもしれないだろう?そんないちいち合意形成して、この話をしましょうなんてやってたらアイデアでてこないよ」
自主参加の会議だからそうしてるというのですか?本当に?
町の会議では・・・
「今何の話してるんですか?」という問いに誰もわからなかった・・・
「今日の会議の目的は?」・・・・・ようやくスタート地点に立った。
別の集まりでの会議。
リーダーの声がけで、どんどん、いろんなことが決まっていく。でも、なにか取り残されているかんじ。
メンバーの温度差。どうして、それが決まったのか、よくわからない。
わかってないのは私だけ?他の皆さんはどう思っているんですか?
問いかけても自主的に話してくれないのは、ここは安全な場じゃないっていうことだなぁ。
話し手の目を見て聴いていると、それがいつのまにか私に対して話しかけるようになっている。周りを見回すと、目をあわさないようにしている人もいる。
目が合うと、役目が指名されるんだ。だから目を合わせないようにしてるんだ。なるほど・・・
理屈で指摘しても、伝わらない。やっぱりプロセス(自分の中で起こっていること)を出していくことが、キーを握るとかんじた。
たとえ会議であっても。
「指名されて、戸惑っている。役割を決める前に、何をするのかを話しあってからでないと納得して引き受けられる感じがしない」「私にはここがよくわからない。みなさんはどう理解されているんですか?納得されてますか?」
結局何も決まらなかったけど、振り出しに戻って、みんなが同じテーブルに乗れたような気がする。それぞれが思っていることを言う場が生まれた。
私のできること、役割はやはり、ファシリテーターでありコーチ。
課題達成したいのはヤマヤマだし、性分的にもそうしたいけど、そのためにもプロセスを大事にしないと成功しないと思う。第一、私がその課題達成に向けて納得してなきゃ、ベストをつくせない。
参加者としてのファシリテーション、磨いていこう。
(2005年6月の日記より)