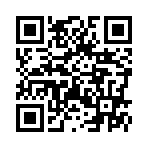医療関係者のコミュニケーション
最近病院通いが続く。
結果、なんでもないのだけど、そこでのやりとりには、考えさせられます。
ここでは一つ目の話を。
まずは、健康診断で乳房健診・・いわゆるマンモグラフィーというやつです。
撮影して、外来外科へ。そして触診。
「んー、ちょっと硬いところがあるので、念のため超音波やっておきましょう。」
あくまでも「念のため」とのこと。
微妙に思いつつ・・それでも気軽な気持ちで、超音波の予約をして帰りました。
同じ病院で一週間後超音波健診。
技師さんが、今やっていることの説明をしながら、撮影をする。
「怪しいところを撮影してるんですか?」とたずねると「それもあるけど、ま、記念撮影みたいなもんだね。」
わかったような、わからないような。
その後、画面を見せながら、ここが表皮、ここが脂肪、乳腺、筋肉・・と説明してくれた。
「で、どうだったんですか?」とたずねると
「カルテ記入しますから、外で待っていてください。詳細は外科の先生のところで。」
んー、技師さんは医者じゃないから診断はできませんっていうことなんだろうなぁと思いつつ、ちょっとなぁ・・・少々不安にさせる対応だなぁ・・・と、お医者様の診断を待つ。
名前が呼ばれ先生の元に行くと、
「問題ありません。」とひとこと。
え?と次の言葉を待っていたら、
「定期的に診断を受けてくださいね。それでは・・・」
と終了。
看護師さんも退室を促し「定期的に診断をうけてくださいね」と。
・・・・・・
なんじゃそりゃ??
不安にさせて、結果、なんの説明もなく「問題ない」「定期的に」って。
硬いところがあったんだよね?
で、「定期的に」って言われたら、気にしやすい人はとっても気になるぞ!
私は、こういう医者の対応の思考パターンには慣れてきたので、そんなに気にはしません。
でも、知りたいので受付に行くまでの間に自分でカルテを見た。
「○○部硬結」というのが2箇所。そのほかに「豹紋柄様」という文字が。
そして「悪性腫瘍(-)」
ああ、この硬結ってのが、「硬いところ」があったってことね。超音波でなにか柄が見えたけど、両方とも悪性じゃないよっていうことで、「問題ない」なわけか。
で、わからないけど、もしかしたら「豹紋柄様」ってのが何かに変化するかもしれないし、しないかもしれないけど、「なんにもおこっていない」わけではないから「定期的に」診断を受けたほうがいいよっていうことか。
でもわからないひとは「悪性腫瘍」っていう言葉がある時点でパニックになるだろうなぁ・・
それにしても・・・
この対応はクレームや不信の元だと思う。
医者と患者という図式では、どうしても患者の立場は弱いし、わからないことが多い。
もう少し患者の身になって、丁寧な説明ができるのでは?このくらいの説明にたいした時間はかからないはず。
医者は絶対コミュニケーションを学ぶ必要があるだろう。
医者不足で仕方ないというのなら、説明のためだけのインターンとか看護師とかを配置したらどうなんでしょう?
医者は「問題ありません」と判断し、詳細は説明担当員が担当する。質問に答える。医師でないと応えられない質問については、医師に戻す。
まぁ、そういうことがこれまでされていないというのは、何か理由があるのかもしれないけど。
結局、医者と患者の間に十分なコミュニケーションがないから、当然信頼関係も築けず、なにかあったときに、医療ミスとして訴えられるということがあるように思うなぁ。
十分にコミュニケーションがあり、必要な情報や、患者が知りたいことについての情報も提供され、医師への信頼があったなら、リスクも患者は承知しているし、医師への訴訟だって減るんじゃないだろうか。
医療関係者が患者とのコミュニケーションを大事にしていったなら、訴訟も減り、医療関係者のストレスも減り、医療関係者への尊敬の念も高まり、自らも医療従事者になりたいと思う人も増え、いい循環が始まるのでは?
ことは、そう単純なことではないとは思いますが、時間はかかるけど、可能性のある解決策のひとつになるように思うのは、私だけかしら・・・
結果、なんでもないのだけど、そこでのやりとりには、考えさせられます。
ここでは一つ目の話を。
まずは、健康診断で乳房健診・・いわゆるマンモグラフィーというやつです。
撮影して、外来外科へ。そして触診。
「んー、ちょっと硬いところがあるので、念のため超音波やっておきましょう。」
あくまでも「念のため」とのこと。
微妙に思いつつ・・それでも気軽な気持ちで、超音波の予約をして帰りました。
同じ病院で一週間後超音波健診。
技師さんが、今やっていることの説明をしながら、撮影をする。
「怪しいところを撮影してるんですか?」とたずねると「それもあるけど、ま、記念撮影みたいなもんだね。」
わかったような、わからないような。
その後、画面を見せながら、ここが表皮、ここが脂肪、乳腺、筋肉・・と説明してくれた。
「で、どうだったんですか?」とたずねると
「カルテ記入しますから、外で待っていてください。詳細は外科の先生のところで。」
んー、技師さんは医者じゃないから診断はできませんっていうことなんだろうなぁと思いつつ、ちょっとなぁ・・・少々不安にさせる対応だなぁ・・・と、お医者様の診断を待つ。
名前が呼ばれ先生の元に行くと、
「問題ありません。」とひとこと。
え?と次の言葉を待っていたら、
「定期的に診断を受けてくださいね。それでは・・・」
と終了。
看護師さんも退室を促し「定期的に診断をうけてくださいね」と。
・・・・・・
なんじゃそりゃ??
不安にさせて、結果、なんの説明もなく「問題ない」「定期的に」って。
硬いところがあったんだよね?
で、「定期的に」って言われたら、気にしやすい人はとっても気になるぞ!
私は、こういう医者の対応の思考パターンには慣れてきたので、そんなに気にはしません。
でも、知りたいので受付に行くまでの間に自分でカルテを見た。
「○○部硬結」というのが2箇所。そのほかに「豹紋柄様」という文字が。
そして「悪性腫瘍(-)」
ああ、この硬結ってのが、「硬いところ」があったってことね。超音波でなにか柄が見えたけど、両方とも悪性じゃないよっていうことで、「問題ない」なわけか。
で、わからないけど、もしかしたら「豹紋柄様」ってのが何かに変化するかもしれないし、しないかもしれないけど、「なんにもおこっていない」わけではないから「定期的に」診断を受けたほうがいいよっていうことか。
でもわからないひとは「悪性腫瘍」っていう言葉がある時点でパニックになるだろうなぁ・・
それにしても・・・
この対応はクレームや不信の元だと思う。
医者と患者という図式では、どうしても患者の立場は弱いし、わからないことが多い。
もう少し患者の身になって、丁寧な説明ができるのでは?このくらいの説明にたいした時間はかからないはず。
医者は絶対コミュニケーションを学ぶ必要があるだろう。
医者不足で仕方ないというのなら、説明のためだけのインターンとか看護師とかを配置したらどうなんでしょう?
医者は「問題ありません」と判断し、詳細は説明担当員が担当する。質問に答える。医師でないと応えられない質問については、医師に戻す。
まぁ、そういうことがこれまでされていないというのは、何か理由があるのかもしれないけど。
結局、医者と患者の間に十分なコミュニケーションがないから、当然信頼関係も築けず、なにかあったときに、医療ミスとして訴えられるということがあるように思うなぁ。
十分にコミュニケーションがあり、必要な情報や、患者が知りたいことについての情報も提供され、医師への信頼があったなら、リスクも患者は承知しているし、医師への訴訟だって減るんじゃないだろうか。
医療関係者が患者とのコミュニケーションを大事にしていったなら、訴訟も減り、医療関係者のストレスも減り、医療関係者への尊敬の念も高まり、自らも医療従事者になりたいと思う人も増え、いい循環が始まるのでは?
ことは、そう単純なことではないとは思いますが、時間はかかるけど、可能性のある解決策のひとつになるように思うのは、私だけかしら・・・
研修のウラテーマ
研修のお仕事というと、コーチングやらコミュニケーション、指導力等の名目が先には来ているけど、「参加者同士のむすびつきを強める」とか「相談しあえる関係に」とか「雑談ではなく、もう少し深い対話を」といった「隠れテーマ」のニーズのほうの強さを感じます。
実施すると、お互いを知らないから、挨拶さえしづらいという状況が、一変したり。
普段から顔を合わせ、挨拶や雑談はするけど、あまり会話とか対話という類のものをしたことがない関係から、そんな話をする場を作っただけど、今までとちょっと関係が変わったり。
「聞き方」をちょっと変えてみてもらっただけで、いつもより深い話になって、相手のことを知ることが出来たり。
研修後「近所の人や、職場で、今回のような話をしたり、聴いたりしたいけど、(なにいってるの?このひと?)と、冷めた目で見られそうだし、ちゃんと聴いてもらえる気がしない。」とか「こういう話を普段したことがないけど、みんな似たようなことを感じたり、考えたりしているんだなぁと知って安心した」
という感想を聞く。
私は、対話の場、聞いてもらえる場を作りたいと思っていますが、何も新たに場を設定しなくても、私の今の仕事は結果的にそのような場になっているようです。
この仕事をしていて感じるのは、誰もが自分のことを知って欲しい、聞いてほしいと思っているということ。
深い対話に、本当は飢えているのではということ。
大人たちが、十分に気持ちや考えを話し、聞いてもらえる関係性を作っていたら。
大人たちに余裕が生まれ、自然に子どもたちの話も聴けるようになるのではないでしょうか。
あるいは
大人たちが、好きなことをしっかりとやり、自分を大切にし、充実した人生を送っていたら・・・
子どもの人生にも、もっと肝要でいられるんじゃないだろうか・・・
私の思いです。
実施すると、お互いを知らないから、挨拶さえしづらいという状況が、一変したり。
普段から顔を合わせ、挨拶や雑談はするけど、あまり会話とか対話という類のものをしたことがない関係から、そんな話をする場を作っただけど、今までとちょっと関係が変わったり。
「聞き方」をちょっと変えてみてもらっただけで、いつもより深い話になって、相手のことを知ることが出来たり。
研修後「近所の人や、職場で、今回のような話をしたり、聴いたりしたいけど、(なにいってるの?このひと?)と、冷めた目で見られそうだし、ちゃんと聴いてもらえる気がしない。」とか「こういう話を普段したことがないけど、みんな似たようなことを感じたり、考えたりしているんだなぁと知って安心した」
という感想を聞く。
私は、対話の場、聞いてもらえる場を作りたいと思っていますが、何も新たに場を設定しなくても、私の今の仕事は結果的にそのような場になっているようです。
この仕事をしていて感じるのは、誰もが自分のことを知って欲しい、聞いてほしいと思っているということ。
深い対話に、本当は飢えているのではということ。
大人たちが、十分に気持ちや考えを話し、聞いてもらえる関係性を作っていたら。
大人たちに余裕が生まれ、自然に子どもたちの話も聴けるようになるのではないでしょうか。
あるいは
大人たちが、好きなことをしっかりとやり、自分を大切にし、充実した人生を送っていたら・・・
子どもの人生にも、もっと肝要でいられるんじゃないだろうか・・・
私の思いです。