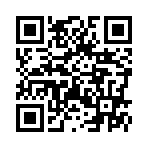待つこと、観ること、感じ取ること、そして瞬時に反応すること
某任意団体での定期総会のこと。
議事に沿って、しゃんしゃんと終わるのが、楽でいいけど、やっぱり会員としては、折角きているのだし、質問もしたいだろうし、参画したい気持ちがあるはず。
今回の総会の山場は、組織変更の提案。
運営委員会が、グループの意見を吸い上げ、検討したうえでの提案ではあったけれど、総会数日前に、一部ひっくりかえった部分もあったりして、この部分は、波乱含み。
いずれにしても、提案に固執するものではなかったので、会員の意見で、変更があることはやぶさかではなかったのだけど・・・
議長「質問、意見はないですか?」
「・・・・」(1、2、3秒)
議長「では、ないようなので採決に移ります」
えー!
早いよ。ちょっと待ってよ。まだみんな議事録から目があがらないし、隣と話始めた人もいる、ちょっとがやつきはじめたような・・・
あたふたしているうちに、挙手がはじまってしまった。
一応可決したのだけど、まだ、会員は、なんとなくがやついている。
私は三役で、脇の席にいて、このタイミングで発言するのはどうだったんだろうと思うけど、思わず口をついて出てしまった。
「あの!後ろのほうで、なにやら話したそうな雰囲気を感じていたんですけど、本当に質問も、ご意見もないのでしょうか?このまま次に進んでよいのでしょうか?」
案の定、次から次へ質問やら意見がでてきて、30分近く意見交換が行われた。
おかげで、終了時刻が遅れてしまったし、議長さんには間が悪くて申し訳なかったけど、結果的には良かったのではないかと思っている。
そうでなくても、各人がそれぞれ、いろんな思いをもって関わっている会で、それぞれが歯がゆい思いを抱えながらの組織。
発言の機会もなく進んでしまったら、不満につながったかもしれない。
それは、みんなが、より良い組織、活動にしたいと思っているからこそのこと。
個人的には、「あっ」と思ったときに、瞬時に反応できるようになりたいなぁ。「可決しました」の声が出る前に言えたらよかったなぁ。
精進します。
議事に沿って、しゃんしゃんと終わるのが、楽でいいけど、やっぱり会員としては、折角きているのだし、質問もしたいだろうし、参画したい気持ちがあるはず。
今回の総会の山場は、組織変更の提案。
運営委員会が、グループの意見を吸い上げ、検討したうえでの提案ではあったけれど、総会数日前に、一部ひっくりかえった部分もあったりして、この部分は、波乱含み。
いずれにしても、提案に固執するものではなかったので、会員の意見で、変更があることはやぶさかではなかったのだけど・・・
議長「質問、意見はないですか?」
「・・・・」(1、2、3秒)
議長「では、ないようなので採決に移ります」
えー!
早いよ。ちょっと待ってよ。まだみんな議事録から目があがらないし、隣と話始めた人もいる、ちょっとがやつきはじめたような・・・
あたふたしているうちに、挙手がはじまってしまった。
一応可決したのだけど、まだ、会員は、なんとなくがやついている。
私は三役で、脇の席にいて、このタイミングで発言するのはどうだったんだろうと思うけど、思わず口をついて出てしまった。
「あの!後ろのほうで、なにやら話したそうな雰囲気を感じていたんですけど、本当に質問も、ご意見もないのでしょうか?このまま次に進んでよいのでしょうか?」
案の定、次から次へ質問やら意見がでてきて、30分近く意見交換が行われた。
おかげで、終了時刻が遅れてしまったし、議長さんには間が悪くて申し訳なかったけど、結果的には良かったのではないかと思っている。
そうでなくても、各人がそれぞれ、いろんな思いをもって関わっている会で、それぞれが歯がゆい思いを抱えながらの組織。
発言の機会もなく進んでしまったら、不満につながったかもしれない。
それは、みんなが、より良い組織、活動にしたいと思っているからこそのこと。
個人的には、「あっ」と思ったときに、瞬時に反応できるようになりたいなぁ。「可決しました」の声が出る前に言えたらよかったなぁ。
精進します。
ファシリテーションフォーラムに行こう
週末に東京で行われるファシリテーションフォーラムに24日のみですが、行ってこようと思います。
ワールドカフェとオープンスペーステクノロジーを日本での第一人者のオーガナイズで体験してみたいということ、テーマが「教育を変える」ということであることも関心のひとつです。
そして、以前ここでもご紹介した「降りてゆく生き方」という映画に関連した分科会「映画「降りてゆく生き方」でのファシリテーションの実践について語り合おう」もあり、そちらにも参加したいと・・・よくばりな私なのです。(二つしか参加できないのに)
「降りてゆく生き方」は、劇場で一般公開はされず、自主上映という形をとります。
私は是非信濃町で上映したいなぁと思っているのですが、上映方法がわかりません。
思ってはいるけど、実は、内容も本当にはわかっていないのです(^^;
でも、映画をつかったまちづくりであったり、監督の森田さんは弁護士でありながら、まちづくりに関心があり、この映画を使ってまちづくりにつながることも期待されているようです。
また、この映画には私の知っているファシリテーターも何人か関わっており、興味のあるところです。
このあたりも、ファシリテーションフォーラムの分科会ではご紹介いただけるのではと期待しています。
誰か、一緒に自主上映しませんか?
ワールドカフェとオープンスペーステクノロジーを日本での第一人者のオーガナイズで体験してみたいということ、テーマが「教育を変える」ということであることも関心のひとつです。
そして、以前ここでもご紹介した「降りてゆく生き方」という映画に関連した分科会「映画「降りてゆく生き方」でのファシリテーションの実践について語り合おう」もあり、そちらにも参加したいと・・・よくばりな私なのです。(二つしか参加できないのに)
「降りてゆく生き方」は、劇場で一般公開はされず、自主上映という形をとります。
私は是非信濃町で上映したいなぁと思っているのですが、上映方法がわかりません。
思ってはいるけど、実は、内容も本当にはわかっていないのです(^^;
でも、映画をつかったまちづくりであったり、監督の森田さんは弁護士でありながら、まちづくりに関心があり、この映画を使ってまちづくりにつながることも期待されているようです。
また、この映画には私の知っているファシリテーターも何人か関わっており、興味のあるところです。
このあたりも、ファシリテーションフォーラムの分科会ではご紹介いただけるのではと期待しています。
誰か、一緒に自主上映しませんか?
多くの人が求めている
しばしば耳にします。
「楽しいが表面的な会話」をするのが苦痛で、それがゆえにコミュニケーションがとれない。苦手だと思っている。
とか、
昔はもっとお互いの心のうちを話せたのに最近はそうではないのは、友達の質なのか、それとも・・・?とか。
それって、もっと、お互いの本当に考えていることや気持ちを伝え合えたり、聴きあえたりできることを望んでいるっていうことですよね。
しばしば目にします。
普段の会議の場では、なかなか意見がでないのに、ちょっと仕掛けをしただけで、ひとりひとりがちゃんと自分の意見を話している。
がやがやと、今までの静けさはなんだったのかというくらい。
ワークショップなんかすると、こんなに自分が話せることに驚いたり、目を輝かせて話していたり、この場の存在自体に感動していたり。
時間が終わっても、話し続ける。
わかちあいのときに、一人で多くの時間をとって話してしまうひとや、質問と称して、自分の話を延々とするひとも・・・・
本当は「話したい」人がたくさんいる。
「聴いてもらいたい」人がたくさんいる。
行政窓口やら何やら、関係ないところで身の上相談を延々とするひとがいる・・・
しばしば耳にします。
「認めてもらいたいんだ」って。
子どもだけじゃない、大人が、口々にそう言葉にする。
自分の存在確認をしたくて、人からほめてもらいたくて、動いている。
そういう時もあるでしょう、そういう場面もあるでしょう、認めて欲しい特別な人がいる場合もあるでしょう。
だけど、価値観よりもそこにスポットがあたっているケースを多々耳にするんです。
私の中ではこれらは全部つながっているような気がしています。
「楽しいが表面的な会話」をするのが苦痛で、それがゆえにコミュニケーションがとれない。苦手だと思っている。
とか、
昔はもっとお互いの心のうちを話せたのに最近はそうではないのは、友達の質なのか、それとも・・・?とか。
それって、もっと、お互いの本当に考えていることや気持ちを伝え合えたり、聴きあえたりできることを望んでいるっていうことですよね。
しばしば目にします。
普段の会議の場では、なかなか意見がでないのに、ちょっと仕掛けをしただけで、ひとりひとりがちゃんと自分の意見を話している。
がやがやと、今までの静けさはなんだったのかというくらい。
ワークショップなんかすると、こんなに自分が話せることに驚いたり、目を輝かせて話していたり、この場の存在自体に感動していたり。
時間が終わっても、話し続ける。
わかちあいのときに、一人で多くの時間をとって話してしまうひとや、質問と称して、自分の話を延々とするひとも・・・・
本当は「話したい」人がたくさんいる。
「聴いてもらいたい」人がたくさんいる。
行政窓口やら何やら、関係ないところで身の上相談を延々とするひとがいる・・・
しばしば耳にします。
「認めてもらいたいんだ」って。
子どもだけじゃない、大人が、口々にそう言葉にする。
自分の存在確認をしたくて、人からほめてもらいたくて、動いている。
そういう時もあるでしょう、そういう場面もあるでしょう、認めて欲しい特別な人がいる場合もあるでしょう。
だけど、価値観よりもそこにスポットがあたっているケースを多々耳にするんです。
私の中ではこれらは全部つながっているような気がしています。
医療をとりまく諸問題をテーマに、自由な対話から学びあう対話会
同じ時期に同じチームの仲間として学びあった、友人のコーチ高木光恵さんからのお知らせがありました。
彼女は、ナースであり、コーチであり、そのほかにもいろんな面を持った心豊かな女性です。
このたび、彼女と思いを同じくするコーチがともにタッグを組んで、医療関係者と一般のかたが同じ場で対話する会を開催するとのことです。
記事の後方にご案内分を転記しましたので、ご覧ください。
ここからは、そのおしらせを受けて感じた私の感想です。
医療関係者と患者さんの間には、目には見えない関係や、壁があって、コミュニケーション不足による、さまざまな弊害がおこっているんじゃないかなと。仕組みに関しても同様です。
医療者のなかにも、そこをなんとかしたいと思っている方もたくさんいるでしょう。
妊婦たらいまわしなど、今日も医療に関係するニュースが流れています。
この対話の会がきっかけとなり、何が生まれてくるのか、わかりませんが、私は期待せずにはいられません。
ファシリテーターのお二人は、経験豊かで、細やかな感情を感じ取り、いろんな思いを受容してくれるひとたちです。
この案内を読んで、こころがゆれた人は是非、足を運んでみてください。
*****************************
オープン・ダイアログ≪対話の会≫
☆日 時 : 2009年5月17日(日)13:30~17:00(13:15受付開始)
☆場 所 : 東京都港区生涯学習センター(205号室)
JR新橋駅 烏森口 徒歩3分
http://www.kissport.or.jp/sisetu/syougai/index.html
☆参 加 費 : 3,000円
☆お申し込み : 下記アドレスに以下の項目を添えてご連絡ください。
E-mail : opened_dialogue@yahoo.co.jp
○ お名前 ○ メールアドレス ○ その他ご自由に何でもどうぞ
問い合わせ先 :opened_dialogue@yahoo.co.jp
*****************************
≪オープン・ダイアログとは?≫
少人数のグループでファシリテーターの元、今起きている問題について様々な立場のあらゆる声を尊重しながら進められる対話手法の1つです。
安全な場で行われるこの対話は、意見交換や議論とは異なり、対立や葛藤を超え、問題の奥にある共通の想いや願いに気付き、違う立場の人を深いレベルで理解できるプロセスを提供します。そのプロセスによって参加者は、立場を超えた共感やつながりを体験し、新たな智慧や勇気を得ることができます。
≪なぜ医療について対話するの?≫
日本の医療は危機の時代を迎えています。地方/都市部に関係なく、医師・看護師不足によって経営が破綻する病院の数は、増加の一途をたどっています。 また医療事故を含め様々な情報が流れる中、社会全体が医療者へ疑問や不信を抱いたり、モンスターペイシェントと呼ばれる人が現れたり、様々なことが起きています。
近い将来、私たちや大切な人が病気になったとき、近くに診てもらう病院がない。という状況が来るかもしれません。これに対して、医療者や政府は懸命に策を講じていますが、それは医療の世界の内側で一部の専門家たちだけが話し合っているようで、当事者である医療の現場の人、そしてその医療の受け手の多くは、問題意識や不安があっても表現する機会は殆どないという環境にあります。
今回案内するオープン・ダイアログでは、どの人の人生にも必要不可欠な医療について、様々な立場の人が対話を深めることを通して、今までの不安感や不満感に気付いて癒されたり、立場を超えて分かり合ったりすることを望んでいます。またそこからどのような可能性が開かれるのかを、皆様と一緒に探求したいと願っています。
≪誰が参加すればいいの?≫
上のような医療を取り巻く状況に問題意識を持っていて、対話から新たな気づきや可能性を望んでいる全ての方(医療者・介護者・医療の受け手になる人やなったことのある人)
*******************************
☆日 時 : 2009年5月17日(日)13:30~17:00(13:15受付開始)
☆場 所 : 東京都港区生涯学習センター(205号室)※≪対話の会≫で予約
JR新橋駅 烏森口 徒歩3分
http://www.kissport.or.jp/sisetu/syougai/index.html
☆参加いただきたい方:医療に直接関わっているかどうかに関係なく、色々な立場や経験を持つ方に参加いただきたいと思っています。特に、医療に対する疑問や不信、不安や懸念も持ったことがあり、もっとよくなったらいいなぁ。と思っている方、大歓迎です。
☆参 加 費 : 3,000円
☆お申し込み : 下記アドレスに以下の項目を添えてご連絡ください。
E-mail : opened_dialogue@yahoo.co.jp
○ お名前 ○ メールアドレス ○ その他ご自由に何でもどうぞ
問い合わせ先 :opened_dialogue@yahoo.co.jp
*****************************
<ファシリテーター プロフィール>
○津村 英作
組織心理学博士/グループ・ファシリテーター/国際コーチ連盟認定プロコーチ
個と組織の成長プロセスを促進するために「協働関係の構築」、「リーダーシップ発揮」、
「コーチング的コミュニケーション」を通して多数の個人と団体を支援。
温かい安心な対話の場を提供しつつ、新たな気づきを生みだす関わりに定評がある。
CTIジャパン(コーチ養成機関)、慶応大学(社会人教育)、明星大学などで講師。
また家族の絆を高めるためのNPO法人ファミリーツリーの理事としても活動中。
○高木 光恵
看護師/保健師/NLPトレーナーアソシエイト/米国CTI認定コーアクティブコーチ
ケアの場に起きる深い交流に魅かれ、患者様やご家族と関わり続けている現役ナース。
自身も胸椎の病変や、介護を要する家族を持つ。
微細なセンスで事象を捉える深い洞察力と、豊かな表現力が持ち味。
医療法人医仁会武田総合病院副師長。院内カウンセラー・コーチ兼任。
プロコーチ、研修講師として院外でも活動を展開している。
彼女は、ナースであり、コーチであり、そのほかにもいろんな面を持った心豊かな女性です。
このたび、彼女と思いを同じくするコーチがともにタッグを組んで、医療関係者と一般のかたが同じ場で対話する会を開催するとのことです。
記事の後方にご案内分を転記しましたので、ご覧ください。
ここからは、そのおしらせを受けて感じた私の感想です。
医療関係者と患者さんの間には、目には見えない関係や、壁があって、コミュニケーション不足による、さまざまな弊害がおこっているんじゃないかなと。仕組みに関しても同様です。
医療者のなかにも、そこをなんとかしたいと思っている方もたくさんいるでしょう。
妊婦たらいまわしなど、今日も医療に関係するニュースが流れています。
この対話の会がきっかけとなり、何が生まれてくるのか、わかりませんが、私は期待せずにはいられません。
ファシリテーターのお二人は、経験豊かで、細やかな感情を感じ取り、いろんな思いを受容してくれるひとたちです。
この案内を読んで、こころがゆれた人は是非、足を運んでみてください。
*****************************
オープン・ダイアログ≪対話の会≫
☆日 時 : 2009年5月17日(日)13:30~17:00(13:15受付開始)
☆場 所 : 東京都港区生涯学習センター(205号室)
JR新橋駅 烏森口 徒歩3分
http://www.kissport.or.jp/sisetu/syougai/index.html
☆参 加 費 : 3,000円
☆お申し込み : 下記アドレスに以下の項目を添えてご連絡ください。
E-mail : opened_dialogue@yahoo.co.jp
○ お名前 ○ メールアドレス ○ その他ご自由に何でもどうぞ
問い合わせ先 :opened_dialogue@yahoo.co.jp
*****************************
≪オープン・ダイアログとは?≫
少人数のグループでファシリテーターの元、今起きている問題について様々な立場のあらゆる声を尊重しながら進められる対話手法の1つです。
安全な場で行われるこの対話は、意見交換や議論とは異なり、対立や葛藤を超え、問題の奥にある共通の想いや願いに気付き、違う立場の人を深いレベルで理解できるプロセスを提供します。そのプロセスによって参加者は、立場を超えた共感やつながりを体験し、新たな智慧や勇気を得ることができます。
≪なぜ医療について対話するの?≫
日本の医療は危機の時代を迎えています。地方/都市部に関係なく、医師・看護師不足によって経営が破綻する病院の数は、増加の一途をたどっています。 また医療事故を含め様々な情報が流れる中、社会全体が医療者へ疑問や不信を抱いたり、モンスターペイシェントと呼ばれる人が現れたり、様々なことが起きています。
近い将来、私たちや大切な人が病気になったとき、近くに診てもらう病院がない。という状況が来るかもしれません。これに対して、医療者や政府は懸命に策を講じていますが、それは医療の世界の内側で一部の専門家たちだけが話し合っているようで、当事者である医療の現場の人、そしてその医療の受け手の多くは、問題意識や不安があっても表現する機会は殆どないという環境にあります。
今回案内するオープン・ダイアログでは、どの人の人生にも必要不可欠な医療について、様々な立場の人が対話を深めることを通して、今までの不安感や不満感に気付いて癒されたり、立場を超えて分かり合ったりすることを望んでいます。またそこからどのような可能性が開かれるのかを、皆様と一緒に探求したいと願っています。
≪誰が参加すればいいの?≫
上のような医療を取り巻く状況に問題意識を持っていて、対話から新たな気づきや可能性を望んでいる全ての方(医療者・介護者・医療の受け手になる人やなったことのある人)
*******************************
☆日 時 : 2009年5月17日(日)13:30~17:00(13:15受付開始)
☆場 所 : 東京都港区生涯学習センター(205号室)※≪対話の会≫で予約
JR新橋駅 烏森口 徒歩3分
http://www.kissport.or.jp/sisetu/syougai/index.html
☆参加いただきたい方:医療に直接関わっているかどうかに関係なく、色々な立場や経験を持つ方に参加いただきたいと思っています。特に、医療に対する疑問や不信、不安や懸念も持ったことがあり、もっとよくなったらいいなぁ。と思っている方、大歓迎です。
☆参 加 費 : 3,000円
☆お申し込み : 下記アドレスに以下の項目を添えてご連絡ください。
E-mail : opened_dialogue@yahoo.co.jp
○ お名前 ○ メールアドレス ○ その他ご自由に何でもどうぞ
問い合わせ先 :opened_dialogue@yahoo.co.jp
*****************************
<ファシリテーター プロフィール>
○津村 英作
組織心理学博士/グループ・ファシリテーター/国際コーチ連盟認定プロコーチ
個と組織の成長プロセスを促進するために「協働関係の構築」、「リーダーシップ発揮」、
「コーチング的コミュニケーション」を通して多数の個人と団体を支援。
温かい安心な対話の場を提供しつつ、新たな気づきを生みだす関わりに定評がある。
CTIジャパン(コーチ養成機関)、慶応大学(社会人教育)、明星大学などで講師。
また家族の絆を高めるためのNPO法人ファミリーツリーの理事としても活動中。
○高木 光恵
看護師/保健師/NLPトレーナーアソシエイト/米国CTI認定コーアクティブコーチ
ケアの場に起きる深い交流に魅かれ、患者様やご家族と関わり続けている現役ナース。
自身も胸椎の病変や、介護を要する家族を持つ。
微細なセンスで事象を捉える深い洞察力と、豊かな表現力が持ち味。
医療法人医仁会武田総合病院副師長。院内カウンセラー・コーチ兼任。
プロコーチ、研修講師として院外でも活動を展開している。
ファシリテーショングラフィック・記録のとり方
効果的な板書の仕方。
ここでは模造紙を使った記録のとり方のご紹介です。
とってもアナログではありますが、これが優れもの!
結構マニアックな世界かもしれません。
この本で紹介しているほど、凝らなくても、基本を抑えておくだけで、
発言がぶれない!
誰かが前に言ったことが思い出せる!
次回の会議に「どこまで話したんだっけ?」「何がきまったんだっけ?」にならず、経過も含めて思い出せます。
一度手にとって見てください。
ファシリテーションフォーラム
日本ファシリテーション協会によるファシリテーションフォーラムが5月23日、24日に行われます。
多様なテーマでファシリテーションについて、ファシリテーションの使い方について、ファシリテーションのさまざまな手法について、体験できます。
先日投稿した、ワールドカフェやOSTも体験できます。(24日)
各日の予定はこちら
多様なテーマでファシリテーションについて、ファシリテーションの使い方について、ファシリテーションのさまざまな手法について、体験できます。
先日投稿した、ワールドカフェやOSTも体験できます。(24日)
各日の予定はこちら
ブランド事業とワールドカフェ2
前の記事でワールドカフェに触れたけど、ヨコハマ経済新聞4月25日によると
ここから引用・・
「知識や知恵は、管理されがちな会議室で生まれるのではなく、人々がオープンに会話を行い、自由にネットワークを築くことのできる"カフェのような空間"でこそ創発される」という基本的な考え方に基づいている。
この手法は、リラックスした雰囲気のなかで、一人ひとりの力を最大限に引き出し、そこからグループ全体の意見へとつなげていく点に特徴がある。結論を出すことでなく、あくまでもアイデアを出すことが目的。そのために話し合い、話し合いを記録することに集中する。そして、そこから新たな方向性が自然に生まれるのを待つ、というプロセスを重視する。
引用ここまで。
長野でも、ワールドカフェやりませんか?
長野市でも、長野県でも。
私は信濃町在住なので、信濃町ブランドのためにワールドカフェもいいと思うなぁ。
ほかに、OSTっていう手法も有ります。オープンスペーステクノロジー。
今回の記事詳細はこちらをどうぞ。
ここから引用・・
「知識や知恵は、管理されがちな会議室で生まれるのではなく、人々がオープンに会話を行い、自由にネットワークを築くことのできる"カフェのような空間"でこそ創発される」という基本的な考え方に基づいている。
この手法は、リラックスした雰囲気のなかで、一人ひとりの力を最大限に引き出し、そこからグループ全体の意見へとつなげていく点に特徴がある。結論を出すことでなく、あくまでもアイデアを出すことが目的。そのために話し合い、話し合いを記録することに集中する。そして、そこから新たな方向性が自然に生まれるのを待つ、というプロセスを重視する。
引用ここまで。
長野でも、ワールドカフェやりませんか?
長野市でも、長野県でも。
私は信濃町在住なので、信濃町ブランドのためにワールドカフェもいいと思うなぁ。
ほかに、OSTっていう手法も有ります。オープンスペーステクノロジー。
今回の記事詳細はこちらをどうぞ。
ブランド事業にワールドカフェ1
まちづくりに関心のある方へ
ヨコハマ経済新聞(2008年12月10日)より
横浜市は12月10日の市長定例記者会見で、都市ブランド共創プロジェクト「イマジン・ヨコハマ」の実施を発表。同日、横浜メディア・ビジネスセンター1階「ヨコハマNEWSハーバー」(横浜市中区太田町2)内に事務局を設置し、市民ボランティア1,000人の募集を開始した。
同プロジェクトは、2009年の開港150周年の機会に「都市ブランド」の構築に取り組むもの。市民の横浜への誇りや愛着心を高めることで、地域活動への参加促進やコミュニティ形成を図り、都市の魅力や独自性の発信により、地域を活性化することが狙い。
市民参加を重視し、「開国博Y150」会場などで市民の意見を集めるほか、インタビューを人から人へ連鎖的に広げて数万人の意見を集める「市民つながりインタビュー」などの新しい手法を実践。5月9日には、参加者全員がお互いの意見を共有しながら議論を発展させていく手法「ワールドカフェ」を日本最大規模の1,000人の参加者を集め実施する。
有識者による公開型の「都市ブランド研究会」や、意見を集約するワークショップなどによりブランドを特定。キャッチコピーやシンボルマークなどに表現し、2010年2月に発表する予定。その後、都市ブランドを観光誘客や企業誘致などのシティセールス、都市デザイン、まちづくりなどの活動に生かしていく。
横浜市は今年度、「都市ブランド戦略構築事業」として1,000万円の予算を計上。8月から9月にかけて事業者を公募し、応募があった8社に対し書類選考とヒヤリングを行い、事業者を広告代理店の「博報堂」(東京都港区)に決定している。
募集するボランティアは、活動全体の中心となるコアメンバー200人と、主に「ワールドカフェ」と「つながりインタビュー」に参加するレギュラーメンバー800人。対象は2009年4月時点で15歳以上の方。締切はコアメンバーが2009年1月31日、レギュラーメンバーが3月31日。
同プロジェクトの事務局担当者は「都市ブランドとは、都市名そのものをブランド化するもの。地名と商品を結びつけた地域ブランドとは違い、住民や企業からも支持される総合的な都市の評価を意味する。ゼロからスタートするこの新しい試みにぜひ参加して欲しい」と話している。
ヨコハマ経済新聞(2008年12月10日)より
横浜市は12月10日の市長定例記者会見で、都市ブランド共創プロジェクト「イマジン・ヨコハマ」の実施を発表。同日、横浜メディア・ビジネスセンター1階「ヨコハマNEWSハーバー」(横浜市中区太田町2)内に事務局を設置し、市民ボランティア1,000人の募集を開始した。
同プロジェクトは、2009年の開港150周年の機会に「都市ブランド」の構築に取り組むもの。市民の横浜への誇りや愛着心を高めることで、地域活動への参加促進やコミュニティ形成を図り、都市の魅力や独自性の発信により、地域を活性化することが狙い。
市民参加を重視し、「開国博Y150」会場などで市民の意見を集めるほか、インタビューを人から人へ連鎖的に広げて数万人の意見を集める「市民つながりインタビュー」などの新しい手法を実践。5月9日には、参加者全員がお互いの意見を共有しながら議論を発展させていく手法「ワールドカフェ」を日本最大規模の1,000人の参加者を集め実施する。
有識者による公開型の「都市ブランド研究会」や、意見を集約するワークショップなどによりブランドを特定。キャッチコピーやシンボルマークなどに表現し、2010年2月に発表する予定。その後、都市ブランドを観光誘客や企業誘致などのシティセールス、都市デザイン、まちづくりなどの活動に生かしていく。
横浜市は今年度、「都市ブランド戦略構築事業」として1,000万円の予算を計上。8月から9月にかけて事業者を公募し、応募があった8社に対し書類選考とヒヤリングを行い、事業者を広告代理店の「博報堂」(東京都港区)に決定している。
募集するボランティアは、活動全体の中心となるコアメンバー200人と、主に「ワールドカフェ」と「つながりインタビュー」に参加するレギュラーメンバー800人。対象は2009年4月時点で15歳以上の方。締切はコアメンバーが2009年1月31日、レギュラーメンバーが3月31日。
同プロジェクトの事務局担当者は「都市ブランドとは、都市名そのものをブランド化するもの。地名と商品を結びつけた地域ブランドとは違い、住民や企業からも支持される総合的な都市の評価を意味する。ゼロからスタートするこの新しい試みにぜひ参加して欲しい」と話している。
あなたのファンを増やす(接客応対)
タイトルのようなねらいの、接客応対プログラムを実施していますが。
まさに、この日、私は「ファン」になってしまいました。
研修で時々訪れる「スペースアルファ神戸」でのことです。
今回はここで1泊2日の研修予定でした。
私はこの朝、トラブルがあり、出先でスカートを汚されてしまったのです。
しかしながら、荷物を少なくしたかったので、着替えが最小限しかなく、しかも、その汚れ成分には油が入っていたこともあり、どうしてもスカートをクリーニングにだしたいと思っていました。
スペースアルファに到着するなり、受付でクリーニングサービスについて問い合わせたところ、残念ながら当日は祝日で、出入りのクリーニング業者さんはお休みとのこと。
困ったなと事情を話したところ、「近くで即日仕上げのところを問い合わせてみます」との心強い言葉。
この言葉だけでも本当にありがたいことです。
その後、車で5分ほどの距離の駅のそばのクリーニング屋で、即日仕上げ可能との情報を入手してくれました。しかしながら、午前中に預けないとだめとのこと。
余裕を持って会場入りしたけど、すでに研修開始予定は迫っており、休み時間に移動するにしてもタクシーを呼ばないと間に合いそうもない。
仕方なく、感謝を伝えて、明日の朝一番のクリーニングで妥協した。
ところが。
再度連絡が入り、出入りの業者さんが、休日にもかかわらず対応してくれるとのことで、受付にスカートを預けることで、私の願いはかなえられたのです!
すごい!
ここまでしてくれるなんて。
本当に感動してしまいました。
ありがとうSさん。
私は、Sさんのファンになりました。
私はスペースアルファ神戸の話が出たら、きっとこの話も伝えるし、気合を入れて、この施設をお勧めするでしょう。
Sさんに感謝。
まさに、この日、私は「ファン」になってしまいました。
研修で時々訪れる「スペースアルファ神戸」でのことです。
今回はここで1泊2日の研修予定でした。
私はこの朝、トラブルがあり、出先でスカートを汚されてしまったのです。
しかしながら、荷物を少なくしたかったので、着替えが最小限しかなく、しかも、その汚れ成分には油が入っていたこともあり、どうしてもスカートをクリーニングにだしたいと思っていました。
スペースアルファに到着するなり、受付でクリーニングサービスについて問い合わせたところ、残念ながら当日は祝日で、出入りのクリーニング業者さんはお休みとのこと。
困ったなと事情を話したところ、「近くで即日仕上げのところを問い合わせてみます」との心強い言葉。
この言葉だけでも本当にありがたいことです。
その後、車で5分ほどの距離の駅のそばのクリーニング屋で、即日仕上げ可能との情報を入手してくれました。しかしながら、午前中に預けないとだめとのこと。
余裕を持って会場入りしたけど、すでに研修開始予定は迫っており、休み時間に移動するにしてもタクシーを呼ばないと間に合いそうもない。
仕方なく、感謝を伝えて、明日の朝一番のクリーニングで妥協した。
ところが。
再度連絡が入り、出入りの業者さんが、休日にもかかわらず対応してくれるとのことで、受付にスカートを預けることで、私の願いはかなえられたのです!
すごい!
ここまでしてくれるなんて。
本当に感動してしまいました。
ありがとうSさん。
私は、Sさんのファンになりました。
私はスペースアルファ神戸の話が出たら、きっとこの話も伝えるし、気合を入れて、この施設をお勧めするでしょう。
Sさんに感謝。