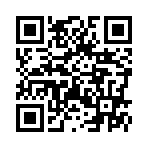医療関係者のコミュニケーション
最近病院通いが続く。
結果、なんでもないのだけど、そこでのやりとりには、考えさせられます。
ここでは一つ目の話を。
まずは、健康診断で乳房健診・・いわゆるマンモグラフィーというやつです。
撮影して、外来外科へ。そして触診。
「んー、ちょっと硬いところがあるので、念のため超音波やっておきましょう。」
あくまでも「念のため」とのこと。
微妙に思いつつ・・それでも気軽な気持ちで、超音波の予約をして帰りました。
同じ病院で一週間後超音波健診。
技師さんが、今やっていることの説明をしながら、撮影をする。
「怪しいところを撮影してるんですか?」とたずねると「それもあるけど、ま、記念撮影みたいなもんだね。」
わかったような、わからないような。
その後、画面を見せながら、ここが表皮、ここが脂肪、乳腺、筋肉・・と説明してくれた。
「で、どうだったんですか?」とたずねると
「カルテ記入しますから、外で待っていてください。詳細は外科の先生のところで。」
んー、技師さんは医者じゃないから診断はできませんっていうことなんだろうなぁと思いつつ、ちょっとなぁ・・・少々不安にさせる対応だなぁ・・・と、お医者様の診断を待つ。
名前が呼ばれ先生の元に行くと、
「問題ありません。」とひとこと。
え?と次の言葉を待っていたら、
「定期的に診断を受けてくださいね。それでは・・・」
と終了。
看護師さんも退室を促し「定期的に診断をうけてくださいね」と。
・・・・・・
なんじゃそりゃ??
不安にさせて、結果、なんの説明もなく「問題ない」「定期的に」って。
硬いところがあったんだよね?
で、「定期的に」って言われたら、気にしやすい人はとっても気になるぞ!
私は、こういう医者の対応の思考パターンには慣れてきたので、そんなに気にはしません。
でも、知りたいので受付に行くまでの間に自分でカルテを見た。
「○○部硬結」というのが2箇所。そのほかに「豹紋柄様」という文字が。
そして「悪性腫瘍(-)」
ああ、この硬結ってのが、「硬いところ」があったってことね。超音波でなにか柄が見えたけど、両方とも悪性じゃないよっていうことで、「問題ない」なわけか。
で、わからないけど、もしかしたら「豹紋柄様」ってのが何かに変化するかもしれないし、しないかもしれないけど、「なんにもおこっていない」わけではないから「定期的に」診断を受けたほうがいいよっていうことか。
でもわからないひとは「悪性腫瘍」っていう言葉がある時点でパニックになるだろうなぁ・・
それにしても・・・
この対応はクレームや不信の元だと思う。
医者と患者という図式では、どうしても患者の立場は弱いし、わからないことが多い。
もう少し患者の身になって、丁寧な説明ができるのでは?このくらいの説明にたいした時間はかからないはず。
医者は絶対コミュニケーションを学ぶ必要があるだろう。
医者不足で仕方ないというのなら、説明のためだけのインターンとか看護師とかを配置したらどうなんでしょう?
医者は「問題ありません」と判断し、詳細は説明担当員が担当する。質問に答える。医師でないと応えられない質問については、医師に戻す。
まぁ、そういうことがこれまでされていないというのは、何か理由があるのかもしれないけど。
結局、医者と患者の間に十分なコミュニケーションがないから、当然信頼関係も築けず、なにかあったときに、医療ミスとして訴えられるということがあるように思うなぁ。
十分にコミュニケーションがあり、必要な情報や、患者が知りたいことについての情報も提供され、医師への信頼があったなら、リスクも患者は承知しているし、医師への訴訟だって減るんじゃないだろうか。
医療関係者が患者とのコミュニケーションを大事にしていったなら、訴訟も減り、医療関係者のストレスも減り、医療関係者への尊敬の念も高まり、自らも医療従事者になりたいと思う人も増え、いい循環が始まるのでは?
ことは、そう単純なことではないとは思いますが、時間はかかるけど、可能性のある解決策のひとつになるように思うのは、私だけかしら・・・
結果、なんでもないのだけど、そこでのやりとりには、考えさせられます。
ここでは一つ目の話を。
まずは、健康診断で乳房健診・・いわゆるマンモグラフィーというやつです。
撮影して、外来外科へ。そして触診。
「んー、ちょっと硬いところがあるので、念のため超音波やっておきましょう。」
あくまでも「念のため」とのこと。
微妙に思いつつ・・それでも気軽な気持ちで、超音波の予約をして帰りました。
同じ病院で一週間後超音波健診。
技師さんが、今やっていることの説明をしながら、撮影をする。
「怪しいところを撮影してるんですか?」とたずねると「それもあるけど、ま、記念撮影みたいなもんだね。」
わかったような、わからないような。
その後、画面を見せながら、ここが表皮、ここが脂肪、乳腺、筋肉・・と説明してくれた。
「で、どうだったんですか?」とたずねると
「カルテ記入しますから、外で待っていてください。詳細は外科の先生のところで。」
んー、技師さんは医者じゃないから診断はできませんっていうことなんだろうなぁと思いつつ、ちょっとなぁ・・・少々不安にさせる対応だなぁ・・・と、お医者様の診断を待つ。
名前が呼ばれ先生の元に行くと、
「問題ありません。」とひとこと。
え?と次の言葉を待っていたら、
「定期的に診断を受けてくださいね。それでは・・・」
と終了。
看護師さんも退室を促し「定期的に診断をうけてくださいね」と。
・・・・・・
なんじゃそりゃ??
不安にさせて、結果、なんの説明もなく「問題ない」「定期的に」って。
硬いところがあったんだよね?
で、「定期的に」って言われたら、気にしやすい人はとっても気になるぞ!
私は、こういう医者の対応の思考パターンには慣れてきたので、そんなに気にはしません。
でも、知りたいので受付に行くまでの間に自分でカルテを見た。
「○○部硬結」というのが2箇所。そのほかに「豹紋柄様」という文字が。
そして「悪性腫瘍(-)」
ああ、この硬結ってのが、「硬いところ」があったってことね。超音波でなにか柄が見えたけど、両方とも悪性じゃないよっていうことで、「問題ない」なわけか。
で、わからないけど、もしかしたら「豹紋柄様」ってのが何かに変化するかもしれないし、しないかもしれないけど、「なんにもおこっていない」わけではないから「定期的に」診断を受けたほうがいいよっていうことか。
でもわからないひとは「悪性腫瘍」っていう言葉がある時点でパニックになるだろうなぁ・・
それにしても・・・
この対応はクレームや不信の元だと思う。
医者と患者という図式では、どうしても患者の立場は弱いし、わからないことが多い。
もう少し患者の身になって、丁寧な説明ができるのでは?このくらいの説明にたいした時間はかからないはず。
医者は絶対コミュニケーションを学ぶ必要があるだろう。
医者不足で仕方ないというのなら、説明のためだけのインターンとか看護師とかを配置したらどうなんでしょう?
医者は「問題ありません」と判断し、詳細は説明担当員が担当する。質問に答える。医師でないと応えられない質問については、医師に戻す。
まぁ、そういうことがこれまでされていないというのは、何か理由があるのかもしれないけど。
結局、医者と患者の間に十分なコミュニケーションがないから、当然信頼関係も築けず、なにかあったときに、医療ミスとして訴えられるということがあるように思うなぁ。
十分にコミュニケーションがあり、必要な情報や、患者が知りたいことについての情報も提供され、医師への信頼があったなら、リスクも患者は承知しているし、医師への訴訟だって減るんじゃないだろうか。
医療関係者が患者とのコミュニケーションを大事にしていったなら、訴訟も減り、医療関係者のストレスも減り、医療関係者への尊敬の念も高まり、自らも医療従事者になりたいと思う人も増え、いい循環が始まるのでは?
ことは、そう単純なことではないとは思いますが、時間はかかるけど、可能性のある解決策のひとつになるように思うのは、私だけかしら・・・
人間関係を学びたい人のためのサイトオープン!
5月1日にオープンしたばかりです。
今後コンテンツも充実していくと思いますが、まずは人間関係ファシリテーションに関わる人たちが登録されています。
各人のブログやHPにアクセスしてみてください。
なにかヒントがあるかも?
人間関係を学びたい人のためのサイト・のろまひと
職場、学校、家庭また地域社会などいろいろな場面で
人と人とのつながり、人と人との輪、人と人との絆、人と人との縁を
大切にしたいと思っている人のための人間関係応援サイトです。
誰でも、いつでもこのサイトからのろまひと(*人間関係ファシリテーター)
にどうぞつながってください。きっとよい手がかりが得られると思います。
のろまひとサイト運営委員会 代表 田崎哲夫
(のろまひと トップページより引用)
今後コンテンツも充実していくと思いますが、まずは人間関係ファシリテーションに関わる人たちが登録されています。
各人のブログやHPにアクセスしてみてください。
なにかヒントがあるかも?
人間関係を学びたい人のためのサイト・のろまひと
職場、学校、家庭また地域社会などいろいろな場面で
人と人とのつながり、人と人との輪、人と人との絆、人と人との縁を
大切にしたいと思っている人のための人間関係応援サイトです。
誰でも、いつでもこのサイトからのろまひと(*人間関係ファシリテーター)
にどうぞつながってください。きっとよい手がかりが得られると思います。
のろまひとサイト運営委員会 代表 田崎哲夫
(のろまひと トップページより引用)
人間関係を探求してみよう
グループプロセストレーニング in 黒姫 のご案内
自然豊かな長野県黒姫高原の地で、人と人との関係を探求してみませんか
■ ねらい
GPTは、一般的には「Tグループ 」と呼ばれている合宿型の研修です。
トレーニングといっても、何かを「教えてもらう」とか「訓練させられる」というような場ではありませんし、あらかじめテーマや課題などが決められたものでもありません。
基本的な流れは10名前後の小グループで、輪になり、1時間から1時間30分程度のセッションを繰り返していきます。そのなかで、他者と関わるうちに、自分のことや、コミュニケーションのありかたに気がついたり、人と人との関係やグループなどの理解を深めていくことになります。
■ ご参加いただきたい方々
・ 自分を大切にしたい人
・ 自分を成長させたい人
・ 他者の気持ちを受け止められるようになりたい人
・ 人間関係をよりよくしたい人
・ 聴く姿勢を磨きたい人
・ ファシリテーターとして、人を大切に関わりたいと思っている人
・ チームワークを大切にしたい人
出会いと関わりのなかで自分と向きあうこの5日間は、あなたにとって特別な時間となることでしょう。
ご参加をお待ちしています。
■ 日程・集合時間・参加費
日程:2009年11月21日(土)~25日(水)(4泊5日)
開始14:00 解散14:00 定員10名
集合場所: ペンション 森のシンフォニー
http://www3.ocn.ne.jp/~symphony/
〒389-1303 長野県上水内郡信濃町黒姫高原
TEL (026) 255-4418
参加費: 72,000円 (別途 宿泊費32,000円/4泊12食付)
詳細はこちらをご覧ください。
自然豊かな長野県黒姫高原の地で、人と人との関係を探求してみませんか
■ ねらい
GPTは、一般的には「Tグループ 」と呼ばれている合宿型の研修です。
トレーニングといっても、何かを「教えてもらう」とか「訓練させられる」というような場ではありませんし、あらかじめテーマや課題などが決められたものでもありません。
基本的な流れは10名前後の小グループで、輪になり、1時間から1時間30分程度のセッションを繰り返していきます。そのなかで、他者と関わるうちに、自分のことや、コミュニケーションのありかたに気がついたり、人と人との関係やグループなどの理解を深めていくことになります。
■ ご参加いただきたい方々
・ 自分を大切にしたい人
・ 自分を成長させたい人
・ 他者の気持ちを受け止められるようになりたい人
・ 人間関係をよりよくしたい人
・ 聴く姿勢を磨きたい人
・ ファシリテーターとして、人を大切に関わりたいと思っている人
・ チームワークを大切にしたい人
出会いと関わりのなかで自分と向きあうこの5日間は、あなたにとって特別な時間となることでしょう。
ご参加をお待ちしています。
■ 日程・集合時間・参加費
日程:2009年11月21日(土)~25日(水)(4泊5日)
開始14:00 解散14:00 定員10名
集合場所: ペンション 森のシンフォニー
http://www3.ocn.ne.jp/~symphony/
〒389-1303 長野県上水内郡信濃町黒姫高原
TEL (026) 255-4418
参加費: 72,000円 (別途 宿泊費32,000円/4泊12食付)
詳細はこちらをご覧ください。
そんなつもりじゃなかったのに
「そんなつもりじゃなかったのに」
「だって○○だったから」
人とのコミュニケーショントラブルが発覚したとき、私たちは上記のような言い訳をしたくなります。
でも、憤慨している相手にとって、そんな言い訳はどうでもいいんです。
「私は気分を害している」「怒っている」「なんだかもやもやする」
そういう事実があることを、黙っていることもできるのに、あえて口に出してくれたのです。
きっと勇気がいったことでしょう。
口に出してくれなかったら、それはずっとわからずに、表面的には進んでいくでしょう。
でも確実にふたりのあいだにしこりは残り、口に出してもらえなかった人は
「なんだか、最近あのひと、私に対して前と違う態度なんだよね・・・」と、またこちらももやもやが残ります。
そうやって、いつの間にか関係が悪くなっていくかもしれません。
自分側の事実と相手側の事実は違うことがあります。
言葉の意味や、使い方、感じ方や受け取り方はそれぞれ。
だけど、結果的に相手の気分を害した原因をつくったのは自分です。
なんらかの丁寧さが欠けていたり、配慮がなかったり、関係に甘えていたり、なんらかの原因はあるでしょう。
最近、そういうことがありました。
相手に言われて、ふりかえってみれば、こちらの意図はどうあれ、相手に対する配慮が足りなかったことに気がつきました。
情けないなぁと思います。
同じ言葉を発し同じことをしていても、もっと相手を尊重し、大事にする思いがあれば、相手に嫌な思いをさせずに済んだのに。
甘えがあったと思います。
それでも、言い訳しないで、相手に謝れる自分でほっとしました。
相手の気持ち、過去の経験を聞くことで、またそのひとを近く感じました。
口に出し難い思いを、誠実に伝え、言われたほうはそれを受け止めて、また関係をつくっていく。
いいときだけじゃなく、そういうこともできる関係でいたいなぁと思います。
伝えてくれてありがとう。
「だって○○だったから」
人とのコミュニケーショントラブルが発覚したとき、私たちは上記のような言い訳をしたくなります。
でも、憤慨している相手にとって、そんな言い訳はどうでもいいんです。
「私は気分を害している」「怒っている」「なんだかもやもやする」
そういう事実があることを、黙っていることもできるのに、あえて口に出してくれたのです。
きっと勇気がいったことでしょう。
口に出してくれなかったら、それはずっとわからずに、表面的には進んでいくでしょう。
でも確実にふたりのあいだにしこりは残り、口に出してもらえなかった人は
「なんだか、最近あのひと、私に対して前と違う態度なんだよね・・・」と、またこちらももやもやが残ります。
そうやって、いつの間にか関係が悪くなっていくかもしれません。
自分側の事実と相手側の事実は違うことがあります。
言葉の意味や、使い方、感じ方や受け取り方はそれぞれ。
だけど、結果的に相手の気分を害した原因をつくったのは自分です。
なんらかの丁寧さが欠けていたり、配慮がなかったり、関係に甘えていたり、なんらかの原因はあるでしょう。
最近、そういうことがありました。
相手に言われて、ふりかえってみれば、こちらの意図はどうあれ、相手に対する配慮が足りなかったことに気がつきました。
情けないなぁと思います。
同じ言葉を発し同じことをしていても、もっと相手を尊重し、大事にする思いがあれば、相手に嫌な思いをさせずに済んだのに。
甘えがあったと思います。
それでも、言い訳しないで、相手に謝れる自分でほっとしました。
相手の気持ち、過去の経験を聞くことで、またそのひとを近く感じました。
口に出し難い思いを、誠実に伝え、言われたほうはそれを受け止めて、また関係をつくっていく。
いいときだけじゃなく、そういうこともできる関係でいたいなぁと思います。
伝えてくれてありがとう。
チームビルディング
新任の小中学校の先生向けの研修
2泊3日のプログラムのなかで、私が担当したのは、野外で体を動かす活動。
それを通じて「つながり」をつくるのがねらい。
同期で入った新任教員として、悩みがあったときに、同じ仲間として相談しあえる仲間であってほしい・・そんな意図なのだと思う。どこの新人研修も一緒だ。
今回は3時間ほどのプログラム。
名前を覚えて、アイコンタクトをして。コミュニケーションについて考えて。
みなさんそれぞれ積極的で、発言者も多いし、感想も個別に自分の言葉で自主的に話してくれる。
コミュニケーションが制限されるようなシチュエーションでもそれぞれがそれぞれの場所で出来ることをやっていく。大きな声で取りまとめる人がいれば、耳を傾ける。
発言の少ない人や、発言をしたけど、とりあげられなかった人の様子を観察していたけれども、特に、こだわっている風でもなく、アイデアを取り込んで、次々に試していく。
次々に課題をこなしていく優秀さ。
こりゃ、もっと難しいものを設定しないとだめかな・・・と
3Mの壁のぼりを提案。
誰も怖いとかいやだという人がいない。
唯一体格のいい引率者が、ちょっと心配そうだったけど。
それぞれが、相手をいたわりながら、「こうしてほしい」「どうしたらいいの?」
わからないことは教えてといい、どうしてほしいのかを聞き、こうしてほしいという。
男女の能力の差も、上手にとりいれながらも、女性でもできることはやってみよう、やってもらおうという柔軟性もあり・・・・
どこかで男女共同参画事業の是非を語っていたひとがいたけれど、ここでも、そんなことは自然に行われていた。
全体をマネジメントするリーダーがあらわれるかと思ったら、ひとりひとりが役割のローテーションを理解し、ほかのひとに伝え、関わっていった。
もちろん、リーダーシップを発揮してくれる人は何人かいたけど、場面によって出たり引っ込んだり。
引率の先生がだいぶ口出しをしていたけど、その先生のことを良い加減で尊重しながらも、自分たちのアイデアでどんどん進めていく・・・・
とてもバランスのいい人たちだった。
きっとほかの先輩先生や保護者たちともうまくやっていけるひとたちだろう。
と心強く思う反面、なんだかちょっと物足りないような思いが、先日来あるのはなんなんだろう。
このあたりは、もう少し考えてみたい。
2泊3日のプログラムのなかで、私が担当したのは、野外で体を動かす活動。
それを通じて「つながり」をつくるのがねらい。
同期で入った新任教員として、悩みがあったときに、同じ仲間として相談しあえる仲間であってほしい・・そんな意図なのだと思う。どこの新人研修も一緒だ。
今回は3時間ほどのプログラム。
名前を覚えて、アイコンタクトをして。コミュニケーションについて考えて。
みなさんそれぞれ積極的で、発言者も多いし、感想も個別に自分の言葉で自主的に話してくれる。
コミュニケーションが制限されるようなシチュエーションでもそれぞれがそれぞれの場所で出来ることをやっていく。大きな声で取りまとめる人がいれば、耳を傾ける。
発言の少ない人や、発言をしたけど、とりあげられなかった人の様子を観察していたけれども、特に、こだわっている風でもなく、アイデアを取り込んで、次々に試していく。
次々に課題をこなしていく優秀さ。
こりゃ、もっと難しいものを設定しないとだめかな・・・と
3Mの壁のぼりを提案。
誰も怖いとかいやだという人がいない。
唯一体格のいい引率者が、ちょっと心配そうだったけど。
それぞれが、相手をいたわりながら、「こうしてほしい」「どうしたらいいの?」
わからないことは教えてといい、どうしてほしいのかを聞き、こうしてほしいという。
男女の能力の差も、上手にとりいれながらも、女性でもできることはやってみよう、やってもらおうという柔軟性もあり・・・・
どこかで男女共同参画事業の是非を語っていたひとがいたけれど、ここでも、そんなことは自然に行われていた。
全体をマネジメントするリーダーがあらわれるかと思ったら、ひとりひとりが役割のローテーションを理解し、ほかのひとに伝え、関わっていった。
もちろん、リーダーシップを発揮してくれる人は何人かいたけど、場面によって出たり引っ込んだり。
引率の先生がだいぶ口出しをしていたけど、その先生のことを良い加減で尊重しながらも、自分たちのアイデアでどんどん進めていく・・・・
とてもバランスのいい人たちだった。
きっとほかの先輩先生や保護者たちともうまくやっていけるひとたちだろう。
と心強く思う反面、なんだかちょっと物足りないような思いが、先日来あるのはなんなんだろう。
このあたりは、もう少し考えてみたい。
経営者・管理者のためのチーム力アップセミナー
というタイトルで、和歌山で実施してまいりました。
和歌山在住の仲間の企画で、会社経営者、管理者、士業事務所長、コーチが参加してくれました。
参加してくれたメンバーで作る即席のグループが、チームのように、心が少しづつ近くなっていくのを体感していただきました。
なぜ?こんなに近くなったのか?
経営者、管理者として、ここから何を学び、どう、メンバーと関わっていくのかを感じ取っていただきました。
また、午後は、仮想会議を実施。
なんだか、いつもと違ってうまくいっちゃいますねー♪
何が違うのかな?信頼感?何でもいえちゃうかんじ?なぜかしら?
そのうえで、役割を振っての新たな仮想会議。
人間関係について、人のことについて、いろんなことに思いがめぐった実習でした。
長野でもやりたいですね。
ぜひ呼んでください♪
和歌山在住の仲間の企画で、会社経営者、管理者、士業事務所長、コーチが参加してくれました。
参加してくれたメンバーで作る即席のグループが、チームのように、心が少しづつ近くなっていくのを体感していただきました。
なぜ?こんなに近くなったのか?
経営者、管理者として、ここから何を学び、どう、メンバーと関わっていくのかを感じ取っていただきました。
また、午後は、仮想会議を実施。
なんだか、いつもと違ってうまくいっちゃいますねー♪
何が違うのかな?信頼感?何でもいえちゃうかんじ?なぜかしら?
そのうえで、役割を振っての新たな仮想会議。
人間関係について、人のことについて、いろんなことに思いがめぐった実習でした。
長野でもやりたいですね。
ぜひ呼んでください♪
山岳ガイドとファシリテーション
夏山ツアーでの低体温症による死亡遭難事故の話を聞き、痛ましく思う。
メディアの情報では、ガイドの判断ミスの印象が強い。
想定外のことが次々に起こったのかもしれない。
詳細はわからないけど。
以下はネットでの読売新聞の記事から引用。
「公募で集まったメンバーは、ほとんどが初対面。コミュニケーション不足が危険を招きかねない」。こう語るのは、中高年のパーティーを国内外の高峰に案内してきた日本勤労者山岳連盟理事の石原裕一郎さん(46)。
何度か公募パーティーに参加した経験がある女性(70)も、「参加者の体力や技術に差があったため、隊列が長くなって、はぐれそうになったことがある」と証言する。悪天候に見舞われ、先に進むか引き返すかでパーティーの意見が真っ二つに割れるという事態も、この女性は経験したという。
今回のアミューズトラベルのツアーに参加した15人は、広島、中部、仙台の各空港から新千歳空港に到着する便を利用して集まった即席パーティーだった。
登山家の田部井淳子さん(69)は公募パーティーについて、「1人では難しい山にも気軽に登れるなど魅力がたくさんある」としながらも、「見知らぬ人ばかりのため『きつくて歩けない』と言い出しにくい雰囲気になる」と問題点を強調。
さらに「帰りの飛行機の時間が決まっており、天気が急変しても、日程を変更しにくい面がある」と話し、「予備日を設けているなど、余裕のある日程の組まれたツアーを選んだ方がよい」と参加者にアドバイスする。(後藤将洋)
(2009年7月18日02時55分 読売新聞)
周囲には学校登山のガイドをする人間が多くいる。
そんな関係で耳にする事から考えるに、現場のガイドと募集をかける会社との意見の違いもあるだろう。
本当は日程の組み方とか、パーティの人数とか、技術や経験の違いとか、考慮してパーティを組むとか、救助をよぶときの判断基準とか、ガイドの人数とか、ガイドのほうから要望がでていても、改善されないこともあるだろう。
だからガイドのことだけを言うのは、片手落ちのようにも思う。
だけど、このような公募ツアーをガイドする人は、個人登山者の集団としてのグループを案内し、状況を判断し決定する単なるガイドとしてではなく、最初から「チーム」づくりを意図しながらファシリテーターとして関わっていたらどうだろう?
参加者同士が話をし易い環境作りをしたり、自分の状況を遠慮せず素直に口に出せる雰囲気作りとか。少なくともガイドと参加者の間にはなんでも言える、相談できる関係を作り出す必要もあるのでは?
言えない人に気がついて、声をかけ状況を把握するとか。
どんな仕事においても、大勢の人たちに関わる人たちにファシリテーションは必要な考え方だと、あらためて思う。
今回の事について安易な事はいえないけれども、山岳ガイドに関わる人にも知ってほしいことだと思った。
亡くなった方のご冥福を祈ります。合掌。
メディアの情報では、ガイドの判断ミスの印象が強い。
想定外のことが次々に起こったのかもしれない。
詳細はわからないけど。
以下はネットでの読売新聞の記事から引用。
「公募で集まったメンバーは、ほとんどが初対面。コミュニケーション不足が危険を招きかねない」。こう語るのは、中高年のパーティーを国内外の高峰に案内してきた日本勤労者山岳連盟理事の石原裕一郎さん(46)。
何度か公募パーティーに参加した経験がある女性(70)も、「参加者の体力や技術に差があったため、隊列が長くなって、はぐれそうになったことがある」と証言する。悪天候に見舞われ、先に進むか引き返すかでパーティーの意見が真っ二つに割れるという事態も、この女性は経験したという。
今回のアミューズトラベルのツアーに参加した15人は、広島、中部、仙台の各空港から新千歳空港に到着する便を利用して集まった即席パーティーだった。
登山家の田部井淳子さん(69)は公募パーティーについて、「1人では難しい山にも気軽に登れるなど魅力がたくさんある」としながらも、「見知らぬ人ばかりのため『きつくて歩けない』と言い出しにくい雰囲気になる」と問題点を強調。
さらに「帰りの飛行機の時間が決まっており、天気が急変しても、日程を変更しにくい面がある」と話し、「予備日を設けているなど、余裕のある日程の組まれたツアーを選んだ方がよい」と参加者にアドバイスする。(後藤将洋)
(2009年7月18日02時55分 読売新聞)
周囲には学校登山のガイドをする人間が多くいる。
そんな関係で耳にする事から考えるに、現場のガイドと募集をかける会社との意見の違いもあるだろう。
本当は日程の組み方とか、パーティの人数とか、技術や経験の違いとか、考慮してパーティを組むとか、救助をよぶときの判断基準とか、ガイドの人数とか、ガイドのほうから要望がでていても、改善されないこともあるだろう。
だからガイドのことだけを言うのは、片手落ちのようにも思う。
だけど、このような公募ツアーをガイドする人は、個人登山者の集団としてのグループを案内し、状況を判断し決定する単なるガイドとしてではなく、最初から「チーム」づくりを意図しながらファシリテーターとして関わっていたらどうだろう?
参加者同士が話をし易い環境作りをしたり、自分の状況を遠慮せず素直に口に出せる雰囲気作りとか。少なくともガイドと参加者の間にはなんでも言える、相談できる関係を作り出す必要もあるのでは?
言えない人に気がついて、声をかけ状況を把握するとか。
どんな仕事においても、大勢の人たちに関わる人たちにファシリテーションは必要な考え方だと、あらためて思う。
今回の事について安易な事はいえないけれども、山岳ガイドに関わる人にも知ってほしいことだと思った。
亡くなった方のご冥福を祈ります。合掌。
渦中の人になったとき
会議やグループ活動をしているなかで、ファシリテーター的なスタンスがいつも、そばにある。
日々生活の中では、必要に応じて、スイッチが入る。
会議で・・私が進行役ではなく、一メンバーだったとしても、少数意見の声の背景をきちんと受け止めた上で決議したいところ。
そのためのかかわりはたとえメンバーだったとしても出来る。
だけど、ときどき・・・・自分がたったひとりの違う意見を持った立場になったときなど・・・
「参加者でありながらのファシリ」スタンスではなく「当事者」でしかいられないことがやってくる。
ある会議において、出席者10名のうち7対1(保留2)の1の意見が私だった。
多数意見の理由はそれぞれから聞いた。
そして、自分の意見やその理由は伝えた。そのほかにたくさんの思いや感情があったのだけど、それは訊ねてはもらえず、伝えきることもできず、汲み取ってももらえず。
対抗する意見の理由をあらためて、自分個人に対し、言われるってことは「説得」ニュアンスになるんだなぁとあらためて気づきもありながら・・・・
私の思いは受け止めてもらえず。
「やめたくなったよ・・・・」って言ったけど、だれも気に留めてはもらえず・・・
悲しくなった。
あのときこの、「悲しい」気持ちを言って、理由を尋ねられてもうまくいえなかっただろうけど、今気づいた。私の気持ちが、そこにいる人たちに伝わった感じがしなかったからだ。
「意見」に同意されなくても、そこにいたる「気持ち」や「背景」を受け止めてもらえていたらもう少しこのもやもや感は違っていただろう。
とはいえ、今も納得出来ていないのだけど。
みんながそれがいいというのなら・・と引き下がってしまったけど、「もっと主張する」という選択肢もあったのだろうか・・・
保留者に意見を聞いてみたのだけど、言葉にならなかったり、途中でさえぎられたり。
今思えば、保留者の思いをもっと聞いてみたらよかったかもしれないなぁ。
別のケース。
ある意見交換会において、今なにが行われているのかぜんぜんついていけない感じを持っていた。
そしてその場の進行役から、私にも発言がもとめられ、感想を言えというのでいやいや感想を話したが、それを聞いた後、その場とは関係のない質問が、進行役から尋問のようにあり、もうさらに嫌で嫌でたまらなくなった。
もう私に質問はいいから他の人の話を聞いてくれと、私はその嫌な気持ちと、理由も伝えているのにその進行役は離してくれず、しかも侮辱ともとれるような発言まであって辟易していた。
もう少し丁寧に、自分の気持ちと向き合って、それを言葉に乗せられたら良かったんだろうけど・・なんだか、めげてしまって。
だけど、私がここで踏ん張っていたら、この進行役に大勢の前で恥をかかすことになってしまうのでは?
それに私は、違う学びが欲しくてここに来ているのに・・・・
ほかの人だって・・・・そんな思いもあり、逃げてしまった(涙)
救いは、同じように感じていた参加者がほかにもいたこと。
私の気持ちを感じ取ってくれた人がいたこと。そしてそれを発言してくれたこと。
「あなたは○さん(私のこと)を尊重していない気がして不愉快です」
それさえも、その進行役は受け取ることは出来ず、私にパスを回してきた。
私が退場したあとも、そのやりとりはしばらく続いたらしいけど、私はあの場にはいられなかったな・・
結局、そのやりとりを経ても、場の運営は何も変わらなかったらしく、私がそのままあそこにいても、参加の目的を果たすことは出来そうになかったけど。
どうしたらよかったのかな。
自分が渦中になってしまうと、自分のプロセスをきちんと出しきれればいいのかもしれないけど、いつもいつもそうは出来ず。
だから伝わりづらいのかな。
ファシリテーターがほしいな。
日々生活の中では、必要に応じて、スイッチが入る。
会議で・・私が進行役ではなく、一メンバーだったとしても、少数意見の声の背景をきちんと受け止めた上で決議したいところ。
そのためのかかわりはたとえメンバーだったとしても出来る。
だけど、ときどき・・・・自分がたったひとりの違う意見を持った立場になったときなど・・・
「参加者でありながらのファシリ」スタンスではなく「当事者」でしかいられないことがやってくる。
ある会議において、出席者10名のうち7対1(保留2)の1の意見が私だった。
多数意見の理由はそれぞれから聞いた。
そして、自分の意見やその理由は伝えた。そのほかにたくさんの思いや感情があったのだけど、それは訊ねてはもらえず、伝えきることもできず、汲み取ってももらえず。
対抗する意見の理由をあらためて、自分個人に対し、言われるってことは「説得」ニュアンスになるんだなぁとあらためて気づきもありながら・・・・
私の思いは受け止めてもらえず。
「やめたくなったよ・・・・」って言ったけど、だれも気に留めてはもらえず・・・
悲しくなった。
あのときこの、「悲しい」気持ちを言って、理由を尋ねられてもうまくいえなかっただろうけど、今気づいた。私の気持ちが、そこにいる人たちに伝わった感じがしなかったからだ。
「意見」に同意されなくても、そこにいたる「気持ち」や「背景」を受け止めてもらえていたらもう少しこのもやもや感は違っていただろう。
とはいえ、今も納得出来ていないのだけど。
みんながそれがいいというのなら・・と引き下がってしまったけど、「もっと主張する」という選択肢もあったのだろうか・・・
保留者に意見を聞いてみたのだけど、言葉にならなかったり、途中でさえぎられたり。
今思えば、保留者の思いをもっと聞いてみたらよかったかもしれないなぁ。
別のケース。
ある意見交換会において、今なにが行われているのかぜんぜんついていけない感じを持っていた。
そしてその場の進行役から、私にも発言がもとめられ、感想を言えというのでいやいや感想を話したが、それを聞いた後、その場とは関係のない質問が、進行役から尋問のようにあり、もうさらに嫌で嫌でたまらなくなった。
もう私に質問はいいから他の人の話を聞いてくれと、私はその嫌な気持ちと、理由も伝えているのにその進行役は離してくれず、しかも侮辱ともとれるような発言まであって辟易していた。
もう少し丁寧に、自分の気持ちと向き合って、それを言葉に乗せられたら良かったんだろうけど・・なんだか、めげてしまって。
だけど、私がここで踏ん張っていたら、この進行役に大勢の前で恥をかかすことになってしまうのでは?
それに私は、違う学びが欲しくてここに来ているのに・・・・
ほかの人だって・・・・そんな思いもあり、逃げてしまった(涙)
救いは、同じように感じていた参加者がほかにもいたこと。
私の気持ちを感じ取ってくれた人がいたこと。そしてそれを発言してくれたこと。
「あなたは○さん(私のこと)を尊重していない気がして不愉快です」
それさえも、その進行役は受け取ることは出来ず、私にパスを回してきた。
私が退場したあとも、そのやりとりはしばらく続いたらしいけど、私はあの場にはいられなかったな・・
結局、そのやりとりを経ても、場の運営は何も変わらなかったらしく、私がそのままあそこにいても、参加の目的を果たすことは出来そうになかったけど。
どうしたらよかったのかな。
自分が渦中になってしまうと、自分のプロセスをきちんと出しきれればいいのかもしれないけど、いつもいつもそうは出来ず。
だから伝わりづらいのかな。
ファシリテーターがほしいな。
学生の成長と私の成長?
先日・・新潟、妙高にて専門学校の3年生前期のファシリテーション演習の最終授業。
事前に担当を決めて、最終日に適当と思われる実習を、進行、ふりかえりを学生に実施してもらう。
メンバー個人個人も自分の成長を、そしてメンバーの変化、成長を実感している様子。
「今の自分だったら、以前参加したグループでの登山実習でのハプニングのようなときに、もう少し違うかかわりができそうな気がする。」
それでも、
「ほかのグループでも、今のこの場のように、安心して意見を言うことができるんだろうか」
ちょうど良いタイミングで、そんな感想もでたので、「グループの成長」についての話をする。
自然と腑に落ちたようだ。
この場で出来た事は、ほかでも実現できるはず。この感覚を忘れずに、それぞれの道に生かして欲しい。
カリキュラムはあって、ないようなもの。
去年と今年、授業の回数は少し減り、シラバスの内容はほぼ同じではあったけど、メンバーが違うと起こることも変わり、ふりかえると全然違う授業をしたかのような感覚。
前の学年にはどちらかというと、スキル的なこととして伝わった気がするけど、この学年には、違う届き方をしたような気がする。
スキルというよりは、自分の内面に問いかけるような・・自分たちの成長を通じて、ファシリテーションを感覚的にとらえたような?
「先生」としては意図してそうしたのなら、かっこいいけど、そうでもない。
もう少し分析して、次につなげたい。
私もともに成長しよう。
3年目、慣れてきて慢心しないよう、初心で、秋からの新しい出会いに向き合おう。
事前に担当を決めて、最終日に適当と思われる実習を、進行、ふりかえりを学生に実施してもらう。
メンバー個人個人も自分の成長を、そしてメンバーの変化、成長を実感している様子。
「今の自分だったら、以前参加したグループでの登山実習でのハプニングのようなときに、もう少し違うかかわりができそうな気がする。」
それでも、
「ほかのグループでも、今のこの場のように、安心して意見を言うことができるんだろうか」
ちょうど良いタイミングで、そんな感想もでたので、「グループの成長」についての話をする。
自然と腑に落ちたようだ。
この場で出来た事は、ほかでも実現できるはず。この感覚を忘れずに、それぞれの道に生かして欲しい。
カリキュラムはあって、ないようなもの。
去年と今年、授業の回数は少し減り、シラバスの内容はほぼ同じではあったけど、メンバーが違うと起こることも変わり、ふりかえると全然違う授業をしたかのような感覚。
前の学年にはどちらかというと、スキル的なこととして伝わった気がするけど、この学年には、違う届き方をしたような気がする。
スキルというよりは、自分の内面に問いかけるような・・自分たちの成長を通じて、ファシリテーションを感覚的にとらえたような?
「先生」としては意図してそうしたのなら、かっこいいけど、そうでもない。
もう少し分析して、次につなげたい。
私もともに成長しよう。
3年目、慣れてきて慢心しないよう、初心で、秋からの新しい出会いに向き合おう。
裁判員制度とファシリテーター
裁判員に選ばれたら・・・「参加したいか」「参加したくないか」
というような街角アンケートをテレビでやっていた。
参加したいを1とすると、したくないが1.5くらいの結果だった。
そのなかで、理由を話しているなかで自信を持って「自分の意見を言えますよ。死刑も」ということを言っているひとがいたけど、危ういなぁと思う。
そういう人が怖いと思う。
自分の一方的なものの観方に固執して、他者の意見には耳を傾けず、声は大きく、他者を圧倒してしまいそうな気がして。
これは、自分の体験として思う。
実際私自身が上記のタイプの人間だったからだ。
だけど、人間関係、ファシリテーションを学んで自分自身が他者にどういう影響を与えているのかを知った。
そして、他者の真意に耳を傾けることで、多様な考え方を知り、自分がいかに偏ったものの見方をしていたのかにもきがついたし、そこから、最初の自分の考えが180度ひっくりかえる体験もした。
自分がいままで、どれだけおごった人間であったのかを知った。
だからこそ思う。
そういうひとも、他者の多様な物の見方考え方を聴くことで、変化していく可能性はあるのだけど、果たして、裁判員の議論の場で、公平に全ての裁判員の意見を明らかにしていけるのだろうか?
国会を見ていても、テレビで政治家の公開討論を見ていても、お互いの主張ばかりで、けなしあいばかりで、お互いの考えの真意を聴いていこうとか、歩み寄ろうという姿は見られない。
裁判員の議論の場において、ひとりひとり意見を聞くことがあったとしても、全員が全員、上手く伝えられるとは限らない。
そこを、ちゃんと真意をひきだしていくだけの場になるのだろうか?
ファシリテーターはいるのだろうか?
裁判官がその役目をするというのだろうか?
外国の裁判員制度が成り立つのは、子供の頃からディベートを学んだり、慣れているという背景があるような気がする。
主張するのに慣れているのでは?
何でも欧米の真似をしている日本だけど、その文化的背景や資質が違うのに、同じことを取り入れても上手くいかないのではないだろうか?
日本人にあったアレンジをしていかないと。
裁判員制度の議論の場に、第三者の中立な立場のファシリテーターという存在が必要なのでは?と思ったのでした。
というような街角アンケートをテレビでやっていた。
参加したいを1とすると、したくないが1.5くらいの結果だった。
そのなかで、理由を話しているなかで自信を持って「自分の意見を言えますよ。死刑も」ということを言っているひとがいたけど、危ういなぁと思う。
そういう人が怖いと思う。
自分の一方的なものの観方に固執して、他者の意見には耳を傾けず、声は大きく、他者を圧倒してしまいそうな気がして。
これは、自分の体験として思う。
実際私自身が上記のタイプの人間だったからだ。
だけど、人間関係、ファシリテーションを学んで自分自身が他者にどういう影響を与えているのかを知った。
そして、他者の真意に耳を傾けることで、多様な考え方を知り、自分がいかに偏ったものの見方をしていたのかにもきがついたし、そこから、最初の自分の考えが180度ひっくりかえる体験もした。
自分がいままで、どれだけおごった人間であったのかを知った。
だからこそ思う。
そういうひとも、他者の多様な物の見方考え方を聴くことで、変化していく可能性はあるのだけど、果たして、裁判員の議論の場で、公平に全ての裁判員の意見を明らかにしていけるのだろうか?
国会を見ていても、テレビで政治家の公開討論を見ていても、お互いの主張ばかりで、けなしあいばかりで、お互いの考えの真意を聴いていこうとか、歩み寄ろうという姿は見られない。
裁判員の議論の場において、ひとりひとり意見を聞くことがあったとしても、全員が全員、上手く伝えられるとは限らない。
そこを、ちゃんと真意をひきだしていくだけの場になるのだろうか?
ファシリテーターはいるのだろうか?
裁判官がその役目をするというのだろうか?
外国の裁判員制度が成り立つのは、子供の頃からディベートを学んだり、慣れているという背景があるような気がする。
主張するのに慣れているのでは?
何でも欧米の真似をしている日本だけど、その文化的背景や資質が違うのに、同じことを取り入れても上手くいかないのではないだろうか?
日本人にあったアレンジをしていかないと。
裁判員制度の議論の場に、第三者の中立な立場のファシリテーターという存在が必要なのでは?と思ったのでした。
Tグループにおけるグループの成長
数ヶ月前のTグループの5泊6日の記録写真を入手。
何人かで撮ったものをそのまま合体させただけのCDだったので、最初は気がつかなかったのだけど、撮影日順にソートして、もういちど見てみたら・・・
表情が変化していくのがとてもよくわかった。
初日。
最初の全体会の説明を受ける表情。
そこはかとなく漂う緊張感、不安感。一様にみんな無表情。
その後全体会がなんどかあるのだけど、後半になると似たように無表情に説明を聞いている風に見えるけど、そこに不安感はただよわない。
時に笑顔もあり。
初日、二日目の食事風景。
無表情で淡々と食べているように見えたり、話はしている様子だけど、なんとなくぎこちない。
笑顔が見えるのは、前から知っている人たちだけ?
ペアでのわかちあいに、微笑みはなく、まじめに語り合っているけど、そこにはぎこちなさや、遠慮が見える気がする。
3日目、個人で、野外に出てオブジェの材料を探す・・・
歩き方やたたずまいに個性あり。なにか、考え込んでいるような、味わっているような、静かな表情・・・
落ちているものや木の幹をたったまま、じーっと見つめる姿。
個人とグループの表現活動を経て・・・グループも一山越えて。
4日の朝の食事からは、表情に変化が。自然な笑顔が。
そのまんまのあなたが。私が・・写っている。
距離感にもなにか違うものが感じられるのはきのせい?
離れて写っているふたりだけど、その空間にはつながりがあるみたいな。
会話が見えるような。
午後、ペアでの野外活動。「無言の探検」
お互いをみつめるまなざしが優しく、あたたかい。
目隠しをされている人は、ペアを信頼し、この時間を楽しんでいるのがわかる。
リードしているほうも、前のようなぎこちなさや遠慮が少なくなっていたり、まったくないように見える人も。
5日目。
カメラを向けられると自然にカメラ目線になり笑顔を向ける参加者たち。
わざわざくっついてみたり、満面の笑顔。屈託がない。
会話中に気がつかないうちに撮られた写真の表情は、会話を楽しんでいる様子。
みんなの距離が近い。
6日目。
最後のわかちあい。
個人作業中のメンバー同士の距離感にも、不安オーラはなく、空気がやわらかい気がする。
ペアで、トリオで、お互いのむねのうちを語り合い、耳を傾けるひとたち。
おだやかに、やさしいまなざし、微笑み・・・・気持ちの動き・・・
いろんなことがあったなぁ。
データーでもグループが成長していくことが記録としてでていたけど、写真という記録でも、まさにそれが現れているなと感じた。
私は、どんな形式であれ、このような体験学習や人間関係トレーニング的な場や、実践には今後もつながっていくのだと思う。
すべてに感謝。
何人かで撮ったものをそのまま合体させただけのCDだったので、最初は気がつかなかったのだけど、撮影日順にソートして、もういちど見てみたら・・・
表情が変化していくのがとてもよくわかった。
初日。
最初の全体会の説明を受ける表情。
そこはかとなく漂う緊張感、不安感。一様にみんな無表情。
その後全体会がなんどかあるのだけど、後半になると似たように無表情に説明を聞いている風に見えるけど、そこに不安感はただよわない。
時に笑顔もあり。
初日、二日目の食事風景。
無表情で淡々と食べているように見えたり、話はしている様子だけど、なんとなくぎこちない。
笑顔が見えるのは、前から知っている人たちだけ?
ペアでのわかちあいに、微笑みはなく、まじめに語り合っているけど、そこにはぎこちなさや、遠慮が見える気がする。
3日目、個人で、野外に出てオブジェの材料を探す・・・
歩き方やたたずまいに個性あり。なにか、考え込んでいるような、味わっているような、静かな表情・・・
落ちているものや木の幹をたったまま、じーっと見つめる姿。
個人とグループの表現活動を経て・・・グループも一山越えて。
4日の朝の食事からは、表情に変化が。自然な笑顔が。
そのまんまのあなたが。私が・・写っている。
距離感にもなにか違うものが感じられるのはきのせい?
離れて写っているふたりだけど、その空間にはつながりがあるみたいな。
会話が見えるような。
午後、ペアでの野外活動。「無言の探検」
お互いをみつめるまなざしが優しく、あたたかい。
目隠しをされている人は、ペアを信頼し、この時間を楽しんでいるのがわかる。
リードしているほうも、前のようなぎこちなさや遠慮が少なくなっていたり、まったくないように見える人も。
5日目。
カメラを向けられると自然にカメラ目線になり笑顔を向ける参加者たち。
わざわざくっついてみたり、満面の笑顔。屈託がない。
会話中に気がつかないうちに撮られた写真の表情は、会話を楽しんでいる様子。
みんなの距離が近い。
6日目。
最後のわかちあい。
個人作業中のメンバー同士の距離感にも、不安オーラはなく、空気がやわらかい気がする。
ペアで、トリオで、お互いのむねのうちを語り合い、耳を傾けるひとたち。
おだやかに、やさしいまなざし、微笑み・・・・気持ちの動き・・・
いろんなことがあったなぁ。
データーでもグループが成長していくことが記録としてでていたけど、写真という記録でも、まさにそれが現れているなと感じた。
私は、どんな形式であれ、このような体験学習や人間関係トレーニング的な場や、実践には今後もつながっていくのだと思う。
すべてに感謝。
みんなの関心が自分に向くのが嫌になるとき
ファシリテータートレーニング。
自分のことに関心を向けてもらうことが嫌だという人がいた。
だけど、なぜか、みんなの関心が向いてしまう。
なぜだろう・・・・・
人には関わるのに、自分のことを言わないから?
人には問いかけるのに、それを問うてみたくなった背景や、気持ちが、伝わってこないから、なんとなく周囲に違和感を感じさせ、その人に注目が集まる?
そんな気がした。
そういえば、私も、ときどき、自分にメンバーの関心が集まることが嫌になる。
上記のケースとはちょっと違う。
私の場合は、特定のケース。明確にある。
そういうのは、たいてい、自分の課題が自分の中でも明確にあり、自分なりにどうにかしようとして取り組んでいるのに、周囲の人たちがなんやかんや言ったり、質問したりすることで、私に代わって問題解決をしてあげようとしているニュアンスを感じるとき。
自分の課題に自分で気がついていないときは、嫌にはならない。
関わってもらえることがありがたいと思う。
気がついた瞬間に・・・・それ以上問われるのはつらいな・・と思ったとき、師匠は「本人が気がついたのなら、そこまで」といって、ほかの人のかかわりをストップさせたっけ。
その経験があるからなのか。
あるいは自分が、嫌だからなのか?
一人の人に質問が集中するとき・・・しかもそれが、相手の問題を解決してあげようというニュアンスにあふれているとき・・・
私は苦しくなってくる。
いやだ・・・やめて・・・・
質問を受けている相手が平気であったとしても、私は居心地が悪くなる。
ついつい私は、自分の気持ちを出すことで、それをストップさせようとしてしまうのだけど・・・
この次は、質問を受けている相手に、尋ねてみよう。
「あなたに質問が集中していますが大丈夫ですか?私はそれを見ていて少しつらく感じますが」
自分のことに関心を向けてもらうことが嫌だという人がいた。
だけど、なぜか、みんなの関心が向いてしまう。
なぜだろう・・・・・
人には関わるのに、自分のことを言わないから?
人には問いかけるのに、それを問うてみたくなった背景や、気持ちが、伝わってこないから、なんとなく周囲に違和感を感じさせ、その人に注目が集まる?
そんな気がした。
そういえば、私も、ときどき、自分にメンバーの関心が集まることが嫌になる。
上記のケースとはちょっと違う。
私の場合は、特定のケース。明確にある。
そういうのは、たいてい、自分の課題が自分の中でも明確にあり、自分なりにどうにかしようとして取り組んでいるのに、周囲の人たちがなんやかんや言ったり、質問したりすることで、私に代わって問題解決をしてあげようとしているニュアンスを感じるとき。
自分の課題に自分で気がついていないときは、嫌にはならない。
関わってもらえることがありがたいと思う。
気がついた瞬間に・・・・それ以上問われるのはつらいな・・と思ったとき、師匠は「本人が気がついたのなら、そこまで」といって、ほかの人のかかわりをストップさせたっけ。
その経験があるからなのか。
あるいは自分が、嫌だからなのか?
一人の人に質問が集中するとき・・・しかもそれが、相手の問題を解決してあげようというニュアンスにあふれているとき・・・
私は苦しくなってくる。
いやだ・・・やめて・・・・
質問を受けている相手が平気であったとしても、私は居心地が悪くなる。
ついつい私は、自分の気持ちを出すことで、それをストップさせようとしてしまうのだけど・・・
この次は、質問を受けている相手に、尋ねてみよう。
「あなたに質問が集中していますが大丈夫ですか?私はそれを見ていて少しつらく感じますが」
タグ :ファシリテーター
言いたいことを言うことと、話を聞くということ
悪気は無いんだけど、人の話を聞けない人。
本人は「聞いてる」と思っている。
自分の考えを持っている人。
「こうするのが正しい」と信念を持っている。
だからちょっと自分と違う考えには、「そうじゃなくて」と言いたくなる。
ちゃんと聞いてるよ。でも、こっちが正しいでしょ、と言わずにはおれない。
そんなひと。
目上の人だし、悪気はないし、立場も上だし・・
なんて思うと、不満を抱えてしまう。
全然ひとのはなしを聞いてなくて、なんでも自分の考えにもっていってしまう・・・
それは正論かもしれないけど・・・・
それじゃ言いたいこと、言えなくなりますよ・・・・
こうやって、部下は自分の意見がいえなくなるんですね・・・・
と、実感する。
だけどこの方は、本当は、この場が活性化して、みんなが言いたいことが言える場になるといいと思っているのを知っている。
コミュニケーションのくせが、邪魔をするだけ。
「えー、もう~。ちゃんと話聴いてくれてますぅ?(^^;
今否定するのやめましょうよぉ?まだ、方向性や、具体的に何するかを決定するための話し合いじゃないし・・・
今はとりあえず、言いたいこと言わせてくださいな~」
たぶん、他者の意見をきいて、「否定」の意見をもったことを「あなた」が言うのは「言いたいことをいうこと」だと思っているんですよね。「聞いている」から意見が言えるのよと思っているんですね。
でも、意見を言うたびに、だれかが(あなたが)否定していたら、だれも、「言いたいこと」がいえなくなりませんか?
そして、あなたの意見を誰かが否定のニュアンスで違う意見を言ったら、引き下がらなくてその話だけで終わってしまうのを知っているから、誰も反論しないんですよ・・・・
「ここのひとたち、みんな強いから」
そうですよ。みんな頑張っています(笑)
でも、あなたの周囲の人は、そうじゃないから、自分の意見がいえなくなっているひとが、もしかしたらいませんか?
「最近の若い子は自分の意見が無くて」
本当にそうですか?
「とりあえず、それぞれの考えは、だすだけ出してから検討しましょうよ~」
伝わったかどうかはわからないけど、少なくとも私はすっきり。
相手への不満は抱えていない。
相手のほうも「そうお?だってぇー」
「まぁ、お互い言いたいこといいましょうね(^^)」
「なんだか言われちゃったわ~」というにやにやという雰囲気をかもしつつ、別にいやな雰囲気にはならない。
以前はこういう風には言えなかったな。
言えずに、不満を抱えるか、
言えたとしても不満爆発、否定とか批判モードになってしまったと思う。
だいたい、よくよく考えれば、私もこの方と同じ。
そういう発言をしてきたな。
実は似ているところがたくさんある。
そんなことも思うので、自戒の念もわきながら。
ときには、忘れて、私もこういう振る舞いをしているかもしれないんだよね。
そんなとき、責めるでもなく、きづかせてくれるひとがいることは、わたしにとってはありがたいこと。
だから、あなたもそう思ってくれていると信じている。
私はあなたが、好きだから。
コーチングやファシリテーションを学んで、本当に良かったなと思うのである。
本人は「聞いてる」と思っている。
自分の考えを持っている人。
「こうするのが正しい」と信念を持っている。
だからちょっと自分と違う考えには、「そうじゃなくて」と言いたくなる。
ちゃんと聞いてるよ。でも、こっちが正しいでしょ、と言わずにはおれない。
そんなひと。
目上の人だし、悪気はないし、立場も上だし・・
なんて思うと、不満を抱えてしまう。
全然ひとのはなしを聞いてなくて、なんでも自分の考えにもっていってしまう・・・
それは正論かもしれないけど・・・・
それじゃ言いたいこと、言えなくなりますよ・・・・
こうやって、部下は自分の意見がいえなくなるんですね・・・・
と、実感する。
だけどこの方は、本当は、この場が活性化して、みんなが言いたいことが言える場になるといいと思っているのを知っている。
コミュニケーションのくせが、邪魔をするだけ。
「えー、もう~。ちゃんと話聴いてくれてますぅ?(^^;
今否定するのやめましょうよぉ?まだ、方向性や、具体的に何するかを決定するための話し合いじゃないし・・・
今はとりあえず、言いたいこと言わせてくださいな~」
たぶん、他者の意見をきいて、「否定」の意見をもったことを「あなた」が言うのは「言いたいことをいうこと」だと思っているんですよね。「聞いている」から意見が言えるのよと思っているんですね。
でも、意見を言うたびに、だれかが(あなたが)否定していたら、だれも、「言いたいこと」がいえなくなりませんか?
そして、あなたの意見を誰かが否定のニュアンスで違う意見を言ったら、引き下がらなくてその話だけで終わってしまうのを知っているから、誰も反論しないんですよ・・・・
「ここのひとたち、みんな強いから」
そうですよ。みんな頑張っています(笑)
でも、あなたの周囲の人は、そうじゃないから、自分の意見がいえなくなっているひとが、もしかしたらいませんか?
「最近の若い子は自分の意見が無くて」
本当にそうですか?
「とりあえず、それぞれの考えは、だすだけ出してから検討しましょうよ~」
伝わったかどうかはわからないけど、少なくとも私はすっきり。
相手への不満は抱えていない。
相手のほうも「そうお?だってぇー」
「まぁ、お互い言いたいこといいましょうね(^^)」
「なんだか言われちゃったわ~」というにやにやという雰囲気をかもしつつ、別にいやな雰囲気にはならない。
以前はこういう風には言えなかったな。
言えずに、不満を抱えるか、
言えたとしても不満爆発、否定とか批判モードになってしまったと思う。
だいたい、よくよく考えれば、私もこの方と同じ。
そういう発言をしてきたな。
実は似ているところがたくさんある。
そんなことも思うので、自戒の念もわきながら。
ときには、忘れて、私もこういう振る舞いをしているかもしれないんだよね。
そんなとき、責めるでもなく、きづかせてくれるひとがいることは、わたしにとってはありがたいこと。
だから、あなたもそう思ってくれていると信じている。
私はあなたが、好きだから。
コーチングやファシリテーションを学んで、本当に良かったなと思うのである。
今どんな気持ち?
「今どんな気持ち?」って聞かれたら、どんな風に応えますか?
私は以前、そんなときは普通に、「今思っていること」や「今考え始めたこと」などを話していました。
たとえば、まさに今だとしたら、
「今パソコンに向かっていて、どんな記事を書こうかと思っている」という風に。
コーチングのセミナーや、体験学習の場において、
「今この体験をしてみて、何を感じましたか?どんな気持ちになりましたか?」と問うとき、
「こういうことって、日常生活でもよくあるなぁと思いました」とか
「一般的にこういうもんですよね」
なんて応えが返ってきたりする。気持ちや、感じたことをきちんと自分でも受け止めず、すっとばして、そこからの「考え」「思ってること」とか「連想したこと」とか、「一般的なこと」を応えたりする。
で、さらに突っ込まれて「で、まさに今の気持ちは?」なんて言われるとしどろもどろ・・・私の気持ちって??
なんてわからないことも。
言ってるじゃないの。「こう思う」って!みたいなイライラが出てきちゃったり。
で、ようやく「あ、わかってもらえなくてイライラしてます!」みたいな。
もちろん、みんながみんなそんなわけではないんですが、自分の「気持ち」がわからない人が多い気がする。
それって、学校教育や仕事生活の中で、「気持ち」を訊かれることなんかなくて、「正解」にたどりつけるような「考え」ばかり求められ続けてきたからかなぁ。
けんかをしても
大人「どうしてこんなことしたの?」
こども「だって、いやなんだもの」
大人「いやじゃ、理由にならないでしょ!」
「いや」という気持ちは受け止めてもらえず、「理由」を求められる。
気持ちがどこかに置き去りにされちゃって、気がつかなくなってしまう?
だけど、感情は、ちゃんと体の中で起こっていて、自分にさえ受け止めてもらえず、外にだすにもだしかたがわからず・・・・病気になったりする?
そんなことが起こっているような気がする。
人間関係(ファシリテーション)の第一歩は、まず自分の内側で起こっていること・・・気持ち・・・それはもやもやしていて、言葉では表現できないこともあるかもしれないけど・・・「考え」とは違う・・・その何か内側で起こっていることを自分でキャッチすること・・・・そこから始まると思っている。
自分の内側で起こっていることに意識を向けて、キャッチする・・・
そんな練習からはじめてみませんか?
6月20・21日(土日)にファシリテーション入門行います。ご関心のある方はお問い合わせを
coach-kaneshige@nifty.com
私は以前、そんなときは普通に、「今思っていること」や「今考え始めたこと」などを話していました。
たとえば、まさに今だとしたら、
「今パソコンに向かっていて、どんな記事を書こうかと思っている」という風に。
コーチングのセミナーや、体験学習の場において、
「今この体験をしてみて、何を感じましたか?どんな気持ちになりましたか?」と問うとき、
「こういうことって、日常生活でもよくあるなぁと思いました」とか
「一般的にこういうもんですよね」
なんて応えが返ってきたりする。気持ちや、感じたことをきちんと自分でも受け止めず、すっとばして、そこからの「考え」「思ってること」とか「連想したこと」とか、「一般的なこと」を応えたりする。
で、さらに突っ込まれて「で、まさに今の気持ちは?」なんて言われるとしどろもどろ・・・私の気持ちって??
なんてわからないことも。
言ってるじゃないの。「こう思う」って!みたいなイライラが出てきちゃったり。
で、ようやく「あ、わかってもらえなくてイライラしてます!」みたいな。
もちろん、みんながみんなそんなわけではないんですが、自分の「気持ち」がわからない人が多い気がする。
それって、学校教育や仕事生活の中で、「気持ち」を訊かれることなんかなくて、「正解」にたどりつけるような「考え」ばかり求められ続けてきたからかなぁ。
けんかをしても
大人「どうしてこんなことしたの?」
こども「だって、いやなんだもの」
大人「いやじゃ、理由にならないでしょ!」
「いや」という気持ちは受け止めてもらえず、「理由」を求められる。
気持ちがどこかに置き去りにされちゃって、気がつかなくなってしまう?
だけど、感情は、ちゃんと体の中で起こっていて、自分にさえ受け止めてもらえず、外にだすにもだしかたがわからず・・・・病気になったりする?
そんなことが起こっているような気がする。
人間関係(ファシリテーション)の第一歩は、まず自分の内側で起こっていること・・・気持ち・・・それはもやもやしていて、言葉では表現できないこともあるかもしれないけど・・・「考え」とは違う・・・その何か内側で起こっていることを自分でキャッチすること・・・・そこから始まると思っている。
自分の内側で起こっていることに意識を向けて、キャッチする・・・
そんな練習からはじめてみませんか?
6月20・21日(土日)にファシリテーション入門行います。ご関心のある方はお問い合わせを
coach-kaneshige@nifty.com
話を聞かない営業マン・・・体験学習から学ぶ
<話を聞かない営業マン>
久しぶりにむかついた。
広告を見て、出向いたその先にいたのは、客の話を全く聞かず、自分のペースで、自分の売りたいもの、自分の話したいことを弾丸のように、口を挟む間もなく話し、こちらの反応におかまいなしの営業マンだった。(体験)そして、こちらの質問は無視する。やっと聞き出してもいい加減な回答をする。自分の価値観を押し付け、客の興味のあることに対しても、自分の判断で、説明もせずに、それはダメという。
「ちょっと聞いてくださいよ」
「質問してるんですけど~」
「こういう理由なんですけど~」
背景を説明しようとしても、聴く耳を持たない。
この人と話しても時間が無駄。(仮説化)そして不快。
体験学習の循環サイクルを逆にまわしている。いかんいかん。
帰ってきてから、体験学習のサイクルに沿って振り返っている。
指摘)なんか、急いでいるっぽくてせわしなかったな。話もろくに聞いてくれないし。
分析)どうしてだろう?聞けない理由とか、あったんだろうか?アポなし訪問だったから、あのあとで用事があったのかもしれない?
仮説化)こんど同じような場面があったら、私はどうすればいいだろう?
「ねぇ、あなたは、どうして、そう、人の話聞かないんですか?いつもそうなんです?」
→(これはちょっと、直接的だなー。非難っぽいニュアンスかも?)
「なんか、すごくあわててるように見えますが、もしかしてこの後、予定かなんかあるんですか?」
「質問に答えてもらえなくて、困ってるんですけど、答えてくれないのはなにか理由があるんですか?」(指摘)と(分析)
って、あの営業マンに聞いてみたらどうなんだろう?
(聴いて見てその理由がわかったら、こちらの対応もかわってきますよね)
だけど、今の気持のまま、言ったら、戦線布告しているようなもんだな。
もっと、好意的に、「このひとかわってるなぁ」ぐらいなノリで面白がって訊けたら、面白い展開になるかもしれない。
いや、基本は「好奇心」だよな・・・と思いつつ、そこまで無邪気になれると人生楽だなぁ・・・と妙に客観的になっている私。
まぁ、こちらの気持ちを自己開示しつつ、相手に好奇心を向けてみる・・・っていうのが、きっといいんだろうな。
「好奇心」から、そして「無邪気に」
「ねぇねぇ、どうして?」
「急いでます?だって○○だから・・・」
「私の話も聞いてくださいよぅ~」
「うーん、対象になるかならないかの判断は私にさせてくださいよ(^^)」
って言えたら、何が起こったかな?(仮説化)
「体験学習の循環サイクル」をこんな風にまわして、気持のいいコミュニケーションをしませんか?
なにより自分がすっきりとできますよ。
そして、体験学習の循環サイクルは、とっても役に立つ考え方です。
この【体験学習】方法で、私はコーチングのセミナーを行っています。
また、さらに「人間関係ファシリテーション」をまさに体験学習方式で学ぶ場を実施しています。
お問い合わせくださいませ。
coach-kaneshige@nifty.com
久しぶりにむかついた。
広告を見て、出向いたその先にいたのは、客の話を全く聞かず、自分のペースで、自分の売りたいもの、自分の話したいことを弾丸のように、口を挟む間もなく話し、こちらの反応におかまいなしの営業マンだった。(体験)そして、こちらの質問は無視する。やっと聞き出してもいい加減な回答をする。自分の価値観を押し付け、客の興味のあることに対しても、自分の判断で、説明もせずに、それはダメという。
「ちょっと聞いてくださいよ」
「質問してるんですけど~」
「こういう理由なんですけど~」
背景を説明しようとしても、聴く耳を持たない。
この人と話しても時間が無駄。(仮説化)そして不快。
体験学習の循環サイクルを逆にまわしている。いかんいかん。
帰ってきてから、体験学習のサイクルに沿って振り返っている。
指摘)なんか、急いでいるっぽくてせわしなかったな。話もろくに聞いてくれないし。
分析)どうしてだろう?聞けない理由とか、あったんだろうか?アポなし訪問だったから、あのあとで用事があったのかもしれない?
仮説化)こんど同じような場面があったら、私はどうすればいいだろう?
「ねぇ、あなたは、どうして、そう、人の話聞かないんですか?いつもそうなんです?」
→(これはちょっと、直接的だなー。非難っぽいニュアンスかも?)
「なんか、すごくあわててるように見えますが、もしかしてこの後、予定かなんかあるんですか?」
「質問に答えてもらえなくて、困ってるんですけど、答えてくれないのはなにか理由があるんですか?」(指摘)と(分析)
って、あの営業マンに聞いてみたらどうなんだろう?
(聴いて見てその理由がわかったら、こちらの対応もかわってきますよね)
だけど、今の気持のまま、言ったら、戦線布告しているようなもんだな。
もっと、好意的に、「このひとかわってるなぁ」ぐらいなノリで面白がって訊けたら、面白い展開になるかもしれない。
いや、基本は「好奇心」だよな・・・と思いつつ、そこまで無邪気になれると人生楽だなぁ・・・と妙に客観的になっている私。
まぁ、こちらの気持ちを自己開示しつつ、相手に好奇心を向けてみる・・・っていうのが、きっといいんだろうな。
「好奇心」から、そして「無邪気に」
「ねぇねぇ、どうして?」
「急いでます?だって○○だから・・・」
「私の話も聞いてくださいよぅ~」
「うーん、対象になるかならないかの判断は私にさせてくださいよ(^^)」
って言えたら、何が起こったかな?(仮説化)
「体験学習の循環サイクル」をこんな風にまわして、気持のいいコミュニケーションをしませんか?
なにより自分がすっきりとできますよ。
そして、体験学習の循環サイクルは、とっても役に立つ考え方です。
この【体験学習】方法で、私はコーチングのセミナーを行っています。
また、さらに「人間関係ファシリテーション」をまさに体験学習方式で学ぶ場を実施しています。
お問い合わせくださいませ。
coach-kaneshige@nifty.com
体験学習の循環サイクルとファシリテーション
【体験をする】→
【何がそこで起こっていたのか指摘する】→
【その理由を分析する】→
【(学んだことを次に活かすべく)仮説化する】→
【(仮説化したことを検証・試してみる)体験する】→・・・また指摘・分析とつづいていく・・
上記が体験学習の循環過程(循環サイクルともいう)といいます。
図が書けなくてごめんなさい。
私たちは、何かを体験したとき、このサイクルを逆に回してしまう。
【体験をする】
(パートナーに話をきいてもらおうと一生懸命話すが、聴いてもらえていないとかんじた)
→【仮説化する】
(この人はいつも話を聴かない。この人に話しても無駄だ)
このような考え方でいると、いつまでたっても同じ繰り返しで、相手の新しい面に気がつかないばかりか、関係も固着してしまう。
このケースではいずれ、パートナーと話をすることをあきらめ、会話の無いふたりになってしまうかもしれない。
「体験学習の循環サイクル」
で考えるとこういう風になる。
【体験をする】
(パートナーに話をしたが、聞いてもらえないと感じた)
→【何が起こっていたのか指摘する】
(彼の視線は定まらず、キョロキョロしているかんじだった)
→【指摘した事象をなぜだろうと分析してみる・あるいは相手になぜ?とたずねてみる】
→(気になる事があったのかもしれない)
→【(次によりよい関係をつくるために)仮説化する】
→「今聞いてほしいことがあるんだけど、いい?」と許可をとる。落ち着かないようだったら、別の時に仕切り直しをする。
体験したことから学習をして、次の関係を作る一歩を手に入れることができる。
仮説にもとづいて行動しても上手くいかなかったら、また新たに洞察をして、別の行動選択ができるし、よく相手の様子を見て、直接関わる事も出来る。
「話を聞いてほしいんだけど・・・(キョロキョロしているようだったら)何か気になる事があるの?」
最初から決め付け(仮説化)しないで、そこで起こっていることをよく思い出して、分析し、新しい行動を選択する事ができます。
慣れてきたら、その場で、相手を良く見て関わる事でよりよい関係を作っていくことが出来ます。(ファシリテーション)
人間関係は体験学習で学び、そしてそれを、「今ここ」で活用できるようになる事・・・「いまここで」関わっていく事・・・
ファシリテーションの一歩です。
【何がそこで起こっていたのか指摘する】→
【その理由を分析する】→
【(学んだことを次に活かすべく)仮説化する】→
【(仮説化したことを検証・試してみる)体験する】→・・・また指摘・分析とつづいていく・・
上記が体験学習の循環過程(循環サイクルともいう)といいます。
図が書けなくてごめんなさい。
私たちは、何かを体験したとき、このサイクルを逆に回してしまう。
【体験をする】
(パートナーに話をきいてもらおうと一生懸命話すが、聴いてもらえていないとかんじた)
→【仮説化する】
(この人はいつも話を聴かない。この人に話しても無駄だ)
このような考え方でいると、いつまでたっても同じ繰り返しで、相手の新しい面に気がつかないばかりか、関係も固着してしまう。
このケースではいずれ、パートナーと話をすることをあきらめ、会話の無いふたりになってしまうかもしれない。
「体験学習の循環サイクル」
で考えるとこういう風になる。
【体験をする】
(パートナーに話をしたが、聞いてもらえないと感じた)
→【何が起こっていたのか指摘する】
(彼の視線は定まらず、キョロキョロしているかんじだった)
→【指摘した事象をなぜだろうと分析してみる・あるいは相手になぜ?とたずねてみる】
→(気になる事があったのかもしれない)
→【(次によりよい関係をつくるために)仮説化する】
→「今聞いてほしいことがあるんだけど、いい?」と許可をとる。落ち着かないようだったら、別の時に仕切り直しをする。
体験したことから学習をして、次の関係を作る一歩を手に入れることができる。
仮説にもとづいて行動しても上手くいかなかったら、また新たに洞察をして、別の行動選択ができるし、よく相手の様子を見て、直接関わる事も出来る。
「話を聞いてほしいんだけど・・・(キョロキョロしているようだったら)何か気になる事があるの?」
最初から決め付け(仮説化)しないで、そこで起こっていることをよく思い出して、分析し、新しい行動を選択する事ができます。
慣れてきたら、その場で、相手を良く見て関わる事でよりよい関係を作っていくことが出来ます。(ファシリテーション)
人間関係は体験学習で学び、そしてそれを、「今ここ」で活用できるようになる事・・・「いまここで」関わっていく事・・・
ファシリテーションの一歩です。