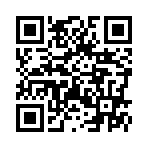経営者とファシリテーション
2009年04月09日
kaneshige at 15:00 | Comments(0) | 組織変革
昨年の山梨ファシリテーション研究会でのことである。
ファシリテーション導入事例を話してくれた若月社長のお話は興味深かった。
それまでは、自分の思いが強すぎて何でもかんでも押し付けていたのかもしれないと、若月社長は言う。
しかし、ファシリテーションを知り、相手から「引きだす」ことが大切と知ったが、一年間は試行錯誤だった様子。社長としては苦しい1年でもあったようだ。
そんななか、会議にファシリテーターとオブザーバー(観察記録者)をおくようにした。
誰でもオブザーバーのとった記録を見られるようにすることで、会議中には表面化しなかったけれども、その場で確かに起こっていたことを、参加者もファシリテーターも知ることが出来るようにした。
たとえば、ファシリテーターが何かを発言したときに、メンバーのほとんどが「ハッとした」表情をしたが、そのままファシリテーターは進行していった・・・とか、具体的な記録が残されている。
ファシリテーターはそれを見て自分の進行ぶりをふりかえる。
若月社長は、時々、状況をフィードバック(メンバーよりもファシリテーターが話しているほうが多いねとか)しながら、しかし、自分が話しすぎてしまうような場面もありながら・・・・と、反省したりという状況だったらしい。
いずれにせよ、継続するうちに少し筒持ち回りで行っているファシリテーターも、少しづつ成長し、ざっくばらんに、メンバーが考えを話せる環境が整っていったということだ。
そのうち、パートを含む社員=スタッフから、いろんな提案があがるようになり、今では携帯電話でその日の出来事や失敗などの報告がメールであがるようになり、携帯の配信システムで、その話題が全員で共有できるようになったそうだ。
そのシステムの提案もスタッフからでてきたそう。
会社の理念も、名刺サイズでパウチしたものが配布され、いつでもどこでも見るようにとスタッフから言われたそうだ。
社長の一方的な提案だったら、携帯電話システムも活用されなかっただろうし、会社の理念だって、見るスタッフなんていないだろう。
スタッフたちが自分たちで考え決めて実行する。そんなカルチャーが育っているようだ。
会社運営にファシリテーションの考えを取り入れるというのは、日常的に、社長や管理職が社員たちからの考えを引き出すことであったり、相手のノンバーバルに気がついて、かかわって、プロセスを明らかにしていくことだったり、自己開示やフィードバックをしていくことだったり、会議にファシリテーターをおく・・・というのはイメージできていたが、会社の会議にオブザーバーを置いて、観察記録をオープンにしておくというアイデアは考えていなかったので、なるほど、いい考えだと思った。
通常の会議では、議題に夢中になっていると、会話の内容は、把握できていたとしても、そこにはでてきていない、参加者の心の動きなどは、そのままおきざりになってしまう。
すると、会議終了し会議の結果あがってきたことをいざ実行しようとしたときに、なかなか実行されないというようなことがおこる可能性がある。
活発に意見がかわされたように見えた会議でも実は一部の人たちだけで進めていて、ほかのひとは、合意していなかった・・・なんてことはよくある話だ。
観察記録のメリットは表面にはでていないことを知る手がかりになる。
ファシリテーターもメンバーもその記録を見ることで、次の会議で何に気をつけて、何を見ていけばいいのかのヒントも得るだろう。
おのずと、お互いに関わりあう関係が生まれてくる。
ファシリテータートレーニングでは一般的なオブザーバーの存在ではあるが、実際の会議での活用も、今後活用させてもらおう。
若月社長の会社はこちら
http://www.plan-do-wakatsuki.jp/corp.html
オブザーバーの記録の取り方を学びたい方はお問い合わせを coach-kaneshige@nifty.com
ファシリテーション導入事例を話してくれた若月社長のお話は興味深かった。
それまでは、自分の思いが強すぎて何でもかんでも押し付けていたのかもしれないと、若月社長は言う。
しかし、ファシリテーションを知り、相手から「引きだす」ことが大切と知ったが、一年間は試行錯誤だった様子。社長としては苦しい1年でもあったようだ。
そんななか、会議にファシリテーターとオブザーバー(観察記録者)をおくようにした。
誰でもオブザーバーのとった記録を見られるようにすることで、会議中には表面化しなかったけれども、その場で確かに起こっていたことを、参加者もファシリテーターも知ることが出来るようにした。
たとえば、ファシリテーターが何かを発言したときに、メンバーのほとんどが「ハッとした」表情をしたが、そのままファシリテーターは進行していった・・・とか、具体的な記録が残されている。
ファシリテーターはそれを見て自分の進行ぶりをふりかえる。
若月社長は、時々、状況をフィードバック(メンバーよりもファシリテーターが話しているほうが多いねとか)しながら、しかし、自分が話しすぎてしまうような場面もありながら・・・・と、反省したりという状況だったらしい。
いずれにせよ、継続するうちに少し筒持ち回りで行っているファシリテーターも、少しづつ成長し、ざっくばらんに、メンバーが考えを話せる環境が整っていったということだ。
そのうち、パートを含む社員=スタッフから、いろんな提案があがるようになり、今では携帯電話でその日の出来事や失敗などの報告がメールであがるようになり、携帯の配信システムで、その話題が全員で共有できるようになったそうだ。
そのシステムの提案もスタッフからでてきたそう。
会社の理念も、名刺サイズでパウチしたものが配布され、いつでもどこでも見るようにとスタッフから言われたそうだ。
社長の一方的な提案だったら、携帯電話システムも活用されなかっただろうし、会社の理念だって、見るスタッフなんていないだろう。
スタッフたちが自分たちで考え決めて実行する。そんなカルチャーが育っているようだ。
会社運営にファシリテーションの考えを取り入れるというのは、日常的に、社長や管理職が社員たちからの考えを引き出すことであったり、相手のノンバーバルに気がついて、かかわって、プロセスを明らかにしていくことだったり、自己開示やフィードバックをしていくことだったり、会議にファシリテーターをおく・・・というのはイメージできていたが、会社の会議にオブザーバーを置いて、観察記録をオープンにしておくというアイデアは考えていなかったので、なるほど、いい考えだと思った。
通常の会議では、議題に夢中になっていると、会話の内容は、把握できていたとしても、そこにはでてきていない、参加者の心の動きなどは、そのままおきざりになってしまう。
すると、会議終了し会議の結果あがってきたことをいざ実行しようとしたときに、なかなか実行されないというようなことがおこる可能性がある。
活発に意見がかわされたように見えた会議でも実は一部の人たちだけで進めていて、ほかのひとは、合意していなかった・・・なんてことはよくある話だ。
観察記録のメリットは表面にはでていないことを知る手がかりになる。
ファシリテーターもメンバーもその記録を見ることで、次の会議で何に気をつけて、何を見ていけばいいのかのヒントも得るだろう。
おのずと、お互いに関わりあう関係が生まれてくる。
ファシリテータートレーニングでは一般的なオブザーバーの存在ではあるが、実際の会議での活用も、今後活用させてもらおう。
若月社長の会社はこちら
http://www.plan-do-wakatsuki.jp/corp.html
オブザーバーの記録の取り方を学びたい方はお問い合わせを coach-kaneshige@nifty.com