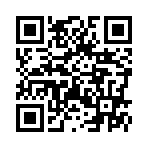記録係をするということの効用と、メンバーとの関係性について
2009年04月24日
kaneshige at 14:02 | Comments(0) | 会議ファシリテーション
会議などで、議事録をとるための記録ではなく、
議題から話し合いが離れず、有効な話し合いとなるための整理ツールとして、
板書したり、ホワイトボードを活用されたり、されているだろうか?
先日の会議ファシリテーションのセミナーでも、参加者の中で、記録経験のあるのは、わずかだったし、いつも活用しているわけではないという。
私自身がこれまで、参加してきた、異業種交流会や、町の会議でも、活用されているのを見たことがない。(私が勝手に書き出すことはあっても)
セミナーでは模造紙の利用をお勧めしている。
私の模造紙活用との出会いは、新潟でまちづくり活動を実施しているファシリテーターの活動で「ファシリテーショングラフィック」の存在を知ってから。
しかし企業や、一般の活動で、「グラフィック」を使わなかったとしても、模造紙の活用は、有効だ。
今回セミナーを実施して、参加者もその効用や利便性にめからうろこのようだった。
* 議論が、離れていっても、テーマを記載してある事で、戻しやすい
* 発言を記録する事で、同じところをぐるぐるしづらい
* 話し合いの軌跡を見ることが出来るので、これまでに出ていた発言を活用しやすい
* 次回の会議の際に、前回の模造紙を見ることで、経過や結論を思い出し、すぐに議題に入りやすい
などなど。
早速、模造紙を活用すること、ペンはマッキーではなく
にじみ・裏うつりなし!基本の8色セット三菱鉛筆 水性顔料マーカー プロッキー8色セット 太字+細字プロッキーねと、メモする人も。
以上は「記録の有効性」についてなんだけど、今回は「記録係をすることの有効性」について。
会議ファシリテーションのセミナーでは「ファシリテーター兼グラフィカ」として、進行役と記録係を兼ねて体験していただくのだが、昨日は、専門学校の授業(人間関係ファシリテーションの切り口)で、記録係と進行役を別れて別々の方が担当した。
今回「記録係=グラフィカ」の役割については「決まったことをまとめて記録するのではなく、議論を有効に進めるためのツールとして記録するんだよ」「テーマと日付だけは最初に書いておいてね」とだけ伝えて、模造紙とプロッキーを渡した。
グラフィカを担当したのは、普段、他者の発言や議題について促進するようなかかわりというのはほとんどみられなかった人なのだけど、グラフィカをしながらの自然なかかわりにびっくり。
記録をする為に、確認をしたり質問をしたり。記録に集中してしまって聞き漏らしたからもう一度言って~とお願いしたり。
それが、その場にとても貢献していた。
記録に対しても、色を変えたり、線で囲ったり、見やすい工夫が。
慣れないせいもあって、他者の発言を自分なりの解釈で自分の言葉で記録してしまうことは時にあったとしても、それが、上手く機能していたり、「それはちょっと違うかも」
と記録を見たメンバーが訂正の発言をしたりして、相互のかかわりが生まれていた。
グラフィカをするというその役割を負ったことで、彼から自然な、彼らしいファシリテーションが発揮されて、私は彼の新しい一面を見た気がする。
もちろん、ファシリテーター役も、参加者であり、ファシリテーターでありという役割であったにもかかわらず、自分の意見も言いながら、議論をまとめたり、方向性を確認したりして、その場に貢献。気負いなくできたと本人も言う。
メンバーそれぞれも、自分の意見をだしながら、それぞれのスタンスでファシリテーター的な動きもあり、「素敵なチームになったなぁ」と半年担当して、生徒さん達の成長ぶりに感動。
これまで自分が内側で考えている事や感じている事を出すのは苦手だったり、あえてださなかったひとが、自然にそれを出す事が出来ているのは、このメンバーだからだと言っていたけど、なぜ、そういうことが出来るようになったのか。
そんなことももっともっと是非分析して、他の場面でもいかしてほしいなぁ。
グラフィカをする役割から、必然的にファシリテーター的な動きがでてくる効能もある程度あるとは思うけど、いつもとは言えない・・・・
だけど、今回そういうことが起こったのはなぜか?
メンバー同士が信頼し、安心して発言したり、振舞う事が出来る。そういう関係性があるからこそ、役割を負ったときも、「こうしたほうがいいのかな?」と思ったことを試す事が出来るのではないか。うまく出来なくても、誰かがフォローしてくれる・・そんな無意識の安心感からかもしれない。
「役割が人を育てる」というようなことなんだろうか?とうっすら思いながらこの記事を書き始めた。
だけど、「安心してそこにいられる、発言できる、行動できる、信頼感のある関係性」がある、そのなかでだからこそ、「役割」に対しても「こうでなければならない」に縛られてしまうのではなく、役割に必要な事を自分なりに試すことができるのでははないか、と思うにいたった。
そして役割を負うことで新たな自分を発見したり、成長したりすることが出来るのではないだろうか?
下記は私の「記録」という一面をどこで取り入れるのかから、考えた仮説だけど。
★会議ファシリテーションセミナーのように、技術的なことを体験するセミナーでは、たとえば「記録する」ということの実用的な効用を感じながら、話し合いの結果を出す事が出来る。
そして繰り返すうちに、役割の技能があがり、人間関係もすこしづつよくなっていく・・というイメージ。
★人間関係ファシリテーションセミナーからスタートすると
「安心感のある関係作り」から人間関係を先に作るので、話し合いの結果というのは、なかなかでづらい。
しかし、人間関係ができてから「記録」などの技術的なことを導入すると、効果は比較的早く現れて、会議の成果がでやすい・・・
のかなと。
技術が先か、人間関係が先かっていう、鶏と卵の関係かな。
そんなことを考えた日でした。
議題から話し合いが離れず、有効な話し合いとなるための整理ツールとして、
板書したり、ホワイトボードを活用されたり、されているだろうか?
先日の会議ファシリテーションのセミナーでも、参加者の中で、記録経験のあるのは、わずかだったし、いつも活用しているわけではないという。
私自身がこれまで、参加してきた、異業種交流会や、町の会議でも、活用されているのを見たことがない。(私が勝手に書き出すことはあっても)
セミナーでは模造紙の利用をお勧めしている。
私の模造紙活用との出会いは、新潟でまちづくり活動を実施しているファシリテーターの活動で「ファシリテーショングラフィック」の存在を知ってから。
しかし企業や、一般の活動で、「グラフィック」を使わなかったとしても、模造紙の活用は、有効だ。
今回セミナーを実施して、参加者もその効用や利便性にめからうろこのようだった。
* 議論が、離れていっても、テーマを記載してある事で、戻しやすい
* 発言を記録する事で、同じところをぐるぐるしづらい
* 話し合いの軌跡を見ることが出来るので、これまでに出ていた発言を活用しやすい
* 次回の会議の際に、前回の模造紙を見ることで、経過や結論を思い出し、すぐに議題に入りやすい
などなど。
早速、模造紙を活用すること、ペンはマッキーではなく

にじみ・裏うつりなし!基本の8色セット三菱鉛筆 水性顔料マーカー プロッキー8色セット 太字+細字プロッキーねと、メモする人も。
以上は「記録の有効性」についてなんだけど、今回は「記録係をすることの有効性」について。
会議ファシリテーションのセミナーでは「ファシリテーター兼グラフィカ」として、進行役と記録係を兼ねて体験していただくのだが、昨日は、専門学校の授業(人間関係ファシリテーションの切り口)で、記録係と進行役を別れて別々の方が担当した。
今回「記録係=グラフィカ」の役割については「決まったことをまとめて記録するのではなく、議論を有効に進めるためのツールとして記録するんだよ」「テーマと日付だけは最初に書いておいてね」とだけ伝えて、模造紙とプロッキーを渡した。
グラフィカを担当したのは、普段、他者の発言や議題について促進するようなかかわりというのはほとんどみられなかった人なのだけど、グラフィカをしながらの自然なかかわりにびっくり。
記録をする為に、確認をしたり質問をしたり。記録に集中してしまって聞き漏らしたからもう一度言って~とお願いしたり。
それが、その場にとても貢献していた。
記録に対しても、色を変えたり、線で囲ったり、見やすい工夫が。
慣れないせいもあって、他者の発言を自分なりの解釈で自分の言葉で記録してしまうことは時にあったとしても、それが、上手く機能していたり、「それはちょっと違うかも」
と記録を見たメンバーが訂正の発言をしたりして、相互のかかわりが生まれていた。
グラフィカをするというその役割を負ったことで、彼から自然な、彼らしいファシリテーションが発揮されて、私は彼の新しい一面を見た気がする。
もちろん、ファシリテーター役も、参加者であり、ファシリテーターでありという役割であったにもかかわらず、自分の意見も言いながら、議論をまとめたり、方向性を確認したりして、その場に貢献。気負いなくできたと本人も言う。
メンバーそれぞれも、自分の意見をだしながら、それぞれのスタンスでファシリテーター的な動きもあり、「素敵なチームになったなぁ」と半年担当して、生徒さん達の成長ぶりに感動。
これまで自分が内側で考えている事や感じている事を出すのは苦手だったり、あえてださなかったひとが、自然にそれを出す事が出来ているのは、このメンバーだからだと言っていたけど、なぜ、そういうことが出来るようになったのか。
そんなことももっともっと是非分析して、他の場面でもいかしてほしいなぁ。
グラフィカをする役割から、必然的にファシリテーター的な動きがでてくる効能もある程度あるとは思うけど、いつもとは言えない・・・・
だけど、今回そういうことが起こったのはなぜか?
メンバー同士が信頼し、安心して発言したり、振舞う事が出来る。そういう関係性があるからこそ、役割を負ったときも、「こうしたほうがいいのかな?」と思ったことを試す事が出来るのではないか。うまく出来なくても、誰かがフォローしてくれる・・そんな無意識の安心感からかもしれない。
「役割が人を育てる」というようなことなんだろうか?とうっすら思いながらこの記事を書き始めた。
だけど、「安心してそこにいられる、発言できる、行動できる、信頼感のある関係性」がある、そのなかでだからこそ、「役割」に対しても「こうでなければならない」に縛られてしまうのではなく、役割に必要な事を自分なりに試すことができるのでははないか、と思うにいたった。
そして役割を負うことで新たな自分を発見したり、成長したりすることが出来るのではないだろうか?
下記は私の「記録」という一面をどこで取り入れるのかから、考えた仮説だけど。
★会議ファシリテーションセミナーのように、技術的なことを体験するセミナーでは、たとえば「記録する」ということの実用的な効用を感じながら、話し合いの結果を出す事が出来る。
そして繰り返すうちに、役割の技能があがり、人間関係もすこしづつよくなっていく・・というイメージ。
★人間関係ファシリテーションセミナーからスタートすると
「安心感のある関係作り」から人間関係を先に作るので、話し合いの結果というのは、なかなかでづらい。
しかし、人間関係ができてから「記録」などの技術的なことを導入すると、効果は比較的早く現れて、会議の成果がでやすい・・・
のかなと。
技術が先か、人間関係が先かっていう、鶏と卵の関係かな。
そんなことを考えた日でした。