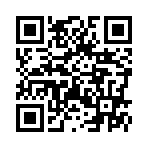一番学んだのは私
ファシリテーター仲間の勉強会。
進行役が、これまで実践し効果のあがった実習事例を報告し、メンバーに体験してもらうもの。
2グループに別れ、テーマを決めた。
同じ実習をテーマを変えて二回行う。
一回目はやりかたを理解するために、取り組みやすそうな楽しそうなテーマを、与えられた中から選ぶ。
メンバーそれぞれ、ばらばらな意見だったけど、まぁいいかとほぼ全員がなんとなく妥協したテーマで取り組んだ。
結果・・・・
一回目の体験では、思った以上に楽しく、メンバーのことを知ることができて、関係が近くなったきがした。いまひとつなテーマだと思ったのに!
これは意外。
二回目は、本番・・ということで、一回目で実習の構造(やりかた)を知ったので、もう少し実践的なテーマに取り組む。
しかしながら、今回はほかのメンバー全員が乗り気だけど、私だけ、乗れないテーマ。
でもま、時間もないしここで合意形成するまでの時間をかけるよりも、勉強会の本題である実習体験のほうが大事かと、納得の上で妥協。
研修であたえられたテーマだとしたら、参加者の中にいまひとつ乗り切れない人がいることもある。
そんな参加者ロールで、この実習を体験したらどうなるのかなー?という好奇心でそのまま参加してみた。
結果・・・
私は、乗り切れないままで終わった。
途中なんどか、乗れそうな場面があったんだけど、不完全燃焼というか、あれれ?とメンバーとの温度差は埋まらない。
「なんでなんで?」私にはたくさん聞いてみたいことがあるのだけど、この実習を限られた時間の中で完成させたいと思う、私以外のメンバーは、困った顔。
なんでかなー?
私だけ何が違ってるのかなー?私の反応はみんなと違うの?
前の日飲みすぎて、調子も確かに今ひとつだったけど。
そのせいかな?
テーマが、ぴんときてないからかな・・
途中から内側に入ってしまい、参加できなくなった。
きづいたひとりのメンバーが声をかけてくれたけど、「二日酔いだからかなー?」とやり過ごす。
入れない寂しい気持ちがあるけど、なんだかよくわからないのよ、どうしてなのか。
前に進めたいみんなと私の間には気持ちのずれがあって、邪魔をしてはいけないような気がしていたみたいだ。
結局、私ひとりだけ「チームビルディングに効果的」という体験はできず。
逆に疎外感。
終了後、なんでかなぁと、ふりかえる。
まったく入れなかったわけじゃない。
テーマには共感できなかったけど、メンバーの話を聞きながら沸いてきた思いがあった。
訊いてみたいことがあったし、そこにかかわっていったこともあった。
だけど、1回目と違って、2回目は私以外のメンバーのなかに、実習を最後まで体験したい。アウトプットを出したいという欲求がおこり、課題達成に向かう力が強くなっていた。
実習の意図した構造を省略するような動きになっていて、先に進めようというエネルギーが場にあったため、私のかかわり(構造上もとめられていること)はほかのメンバーにとって阻害要因に感じられていた様子。
(これは終了後にふりかえって、気がついたこと)
そこで自分なりにわかったこと。
A)この実習をチームビルディングに使うには、メンバーが興味の持てるテーマであることが望ましいこと。
B)興味のもてない人がいたとしても、実習の構造上、メンバーの思いや価値観や、表面にはすぐにでてこないものが明らかになっていく過程で、共感や、好奇心が生まれ、参画しやすくなり、チームビルディングにつながるであろうこと。
C)課題達成に意識が向きすぎて、実習の構造がいかされず、表面的なアイデアのみの共有でアウトプットにいたった場合、テーマに興味のもてない人は、参画できないで終わる可能性があること。
D)メンバー全員が興味をもって取り組めるテーマであれば、課題達成に意識が向きすぎて、多少実習の構造が生かされず、アイデアのみの共有で、その裏の思いや価値観が明らかにならなくても、効果がありそうであること。(ほかのメンバーの満足度は高かったので)
よってファシリテーターとして、この実習を活用する際の注意点は、
アウトプット(成果物)が目的にならないよう、実習の構造が生かされるよう、必要に応じて介入する。
そのためには、すべてのグループに目が届くような人数であることが望ましい。
上記が原則ではあるけれども、参加メンバーが共通の目的を持って、テーマに取り組む土壌があるケース(スポーツチームが優勝にむかってチーム力をあげるために活用する場合など)には、多少目が届かないような人数(グループ数)であっても、効果的であるようだ。(これは勉強会担当者の実践事例より)。
当初の私の目的の「チームビルディングに役立つ」という実感は体験できなかった。
が、この実習を実施するうえでの、ファシリテーターの留意点が明確になり、これをしっかり実施していれば、効果的であろうという感触を持つことができた。
今回、メンバーとして満足感を得られなかったことで、私自身はこの実習を活用する上で、大いに学びになったというのが、なんだかとても興味深い。
案外、今回参加者の中で一番学んだのは私かもしれない(^^)
進行役が、これまで実践し効果のあがった実習事例を報告し、メンバーに体験してもらうもの。
2グループに別れ、テーマを決めた。
同じ実習をテーマを変えて二回行う。
一回目はやりかたを理解するために、取り組みやすそうな楽しそうなテーマを、与えられた中から選ぶ。
メンバーそれぞれ、ばらばらな意見だったけど、まぁいいかとほぼ全員がなんとなく妥協したテーマで取り組んだ。
結果・・・・
一回目の体験では、思った以上に楽しく、メンバーのことを知ることができて、関係が近くなったきがした。いまひとつなテーマだと思ったのに!
これは意外。
二回目は、本番・・ということで、一回目で実習の構造(やりかた)を知ったので、もう少し実践的なテーマに取り組む。
しかしながら、今回はほかのメンバー全員が乗り気だけど、私だけ、乗れないテーマ。
でもま、時間もないしここで合意形成するまでの時間をかけるよりも、勉強会の本題である実習体験のほうが大事かと、納得の上で妥協。
研修であたえられたテーマだとしたら、参加者の中にいまひとつ乗り切れない人がいることもある。
そんな参加者ロールで、この実習を体験したらどうなるのかなー?という好奇心でそのまま参加してみた。
結果・・・
私は、乗り切れないままで終わった。
途中なんどか、乗れそうな場面があったんだけど、不完全燃焼というか、あれれ?とメンバーとの温度差は埋まらない。
「なんでなんで?」私にはたくさん聞いてみたいことがあるのだけど、この実習を限られた時間の中で完成させたいと思う、私以外のメンバーは、困った顔。
なんでかなー?
私だけ何が違ってるのかなー?私の反応はみんなと違うの?
前の日飲みすぎて、調子も確かに今ひとつだったけど。
そのせいかな?
テーマが、ぴんときてないからかな・・
途中から内側に入ってしまい、参加できなくなった。
きづいたひとりのメンバーが声をかけてくれたけど、「二日酔いだからかなー?」とやり過ごす。
入れない寂しい気持ちがあるけど、なんだかよくわからないのよ、どうしてなのか。
前に進めたいみんなと私の間には気持ちのずれがあって、邪魔をしてはいけないような気がしていたみたいだ。
結局、私ひとりだけ「チームビルディングに効果的」という体験はできず。
逆に疎外感。
終了後、なんでかなぁと、ふりかえる。
まったく入れなかったわけじゃない。
テーマには共感できなかったけど、メンバーの話を聞きながら沸いてきた思いがあった。
訊いてみたいことがあったし、そこにかかわっていったこともあった。
だけど、1回目と違って、2回目は私以外のメンバーのなかに、実習を最後まで体験したい。アウトプットを出したいという欲求がおこり、課題達成に向かう力が強くなっていた。
実習の意図した構造を省略するような動きになっていて、先に進めようというエネルギーが場にあったため、私のかかわり(構造上もとめられていること)はほかのメンバーにとって阻害要因に感じられていた様子。
(これは終了後にふりかえって、気がついたこと)
そこで自分なりにわかったこと。
A)この実習をチームビルディングに使うには、メンバーが興味の持てるテーマであることが望ましいこと。
B)興味のもてない人がいたとしても、実習の構造上、メンバーの思いや価値観や、表面にはすぐにでてこないものが明らかになっていく過程で、共感や、好奇心が生まれ、参画しやすくなり、チームビルディングにつながるであろうこと。
C)課題達成に意識が向きすぎて、実習の構造がいかされず、表面的なアイデアのみの共有でアウトプットにいたった場合、テーマに興味のもてない人は、参画できないで終わる可能性があること。
D)メンバー全員が興味をもって取り組めるテーマであれば、課題達成に意識が向きすぎて、多少実習の構造が生かされず、アイデアのみの共有で、その裏の思いや価値観が明らかにならなくても、効果がありそうであること。(ほかのメンバーの満足度は高かったので)
よってファシリテーターとして、この実習を活用する際の注意点は、
アウトプット(成果物)が目的にならないよう、実習の構造が生かされるよう、必要に応じて介入する。
そのためには、すべてのグループに目が届くような人数であることが望ましい。
上記が原則ではあるけれども、参加メンバーが共通の目的を持って、テーマに取り組む土壌があるケース(スポーツチームが優勝にむかってチーム力をあげるために活用する場合など)には、多少目が届かないような人数(グループ数)であっても、効果的であるようだ。(これは勉強会担当者の実践事例より)。
当初の私の目的の「チームビルディングに役立つ」という実感は体験できなかった。
が、この実習を実施するうえでの、ファシリテーターの留意点が明確になり、これをしっかり実施していれば、効果的であろうという感触を持つことができた。
今回、メンバーとして満足感を得られなかったことで、私自身はこの実習を活用する上で、大いに学びになったというのが、なんだかとても興味深い。
案外、今回参加者の中で一番学んだのは私かもしれない(^^)