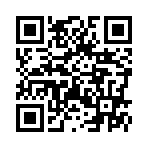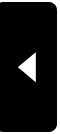議事録のとりかた。記録のとりかた。板書のしかた。
へたくそです。嫌いです。コンプレックスがあります・・・
子供の頃から授業のノートはぐちゃぐちゃで、活用できた事ない。
でも東大入学者のノートのとりかたが、書籍化されて出ているのを読んだりすると、
やはり、ノートのとり方というのは大事だというのがよくわかる。
とはいえ、私はそれ(ノートの記録)をなんのためにノートするのか、がわかってなかったように思うのだ。ノートの記録=試験対策=「暗記」って思っていた。
で、暗記のために活用と思うと、もうとたんにダメ。意欲もなくなるし、だいたい、作ったノートで暗記なんか出来ない。
そのまえに「美しく、みやすく記録する」というところに意識の欠如があった気がするけど。
と、そんな背景を持った私は、「記録」「議事録」「板書」ちょー苦手です。
なのだけど。
5,6年前にファシリテーショングラフィックというのに出会いまして。
議論の見える化って大事なんだなって言うことを、体感。
その後、へたくそなくせに、っていうか、文字だけしか書けないけど、率先して板書をする。
ファシリテーショングラフィックっていうのは、グラフィック」っていうくらいですから、絵とか記号とかを使って「模造紙」にカラフルに話し合いの記録をとっていくんです。
大事と思われるところは大きく書いたり、盛り上がった所には、そういうことがわかるような印をつけたりね。
絵の得意な人が、工夫しながら書き上げていくのはもう芸術であり、
またそれを観ながら、話が活性化することもあり、次回の話し合いに、この模造紙の記録を張り出すことで、これまでの議論がすぐに思い出されたり・・
また縮小コピーして、議事録としても活用できる。
有益だなぁと思っているわけです。
でも私には出来ないんですね。絵がかけないから(涙) 字が下手だから。空間をうまく使えないから。
私の周囲にも優秀なファシリテーショングラフィッカーが出てきてくれないかなとひそかに思っているわけです。
↓これは一日習っただけの学生さんが書いたもの。


こちらは、指導者が書いたもの。
絵も苦手、空間把握して、予測して美しく仕上げるなんてのはチョー苦手なんだけどね、
記録する事で、議論がぶれなかったり、話が戻しやすかったり、誰かの発言が置いてきぼりになるのが避けられたり・・・いいことがたくさんあるんです。
また、どんな話し合いだったか?っていうのが思い出されるような記録ってのはいいなぁと思うんですよ。欠席者にも伝わるような。
それで、ときどき、チャレンジします。
臨場感がでる記録づくりに。
板書しながら、模造紙書きながら、途中で入ったチャチャを口語体でそのまんま記録したり、もりあがったところは、わかるように印をつけたり、あえて発言者の発言そのまんま、方言いれて書いたり。
最近は携帯で写真を撮って印刷し、そのまんま議事録として配布しちゃったりすることも。
先日はカフェでのうちあわせだったので、ホワイトボードもなく、手元用紙に「議事録」をとる役目だったのですが・・・
結局発言をほとんど記録する形になり。
だけどあとで読み返してみたら、話の流れがわかって面白かった。
「議事録」としての体裁を整える為、日付場所、時間、参加者名、テーマ書いて、この日の結論を書いて。
あとは、だらっと発言の要点を記録しておきました。
少なくとも参加した人にしたら、あの場でおこっていたことを思い出すきっかけになるだろうし、欠席したひとは、どういう背景でこういう結論になったのかっていうことがわかるのは有益じゃないだろうかと。
「記録」系は苦手という意識が強かったんですが、ファシリテーショングラフィックと出会ってから、「活用」に意識が行くようになったきがします。
絵はかけなくても、この「記録」がどんな風に役に立つのか、なんのための記録なのか?を意識する事によって、「記録」そのものが、ファシリテート・・・いろんなことを促進する役目を果たしてくれるんだなぁということに気がつきました。
というわけで、苦手意識はあっても、目的を遂行する為に出来る事として、チャレンジしていこうと思っています。
子供の頃から授業のノートはぐちゃぐちゃで、活用できた事ない。
でも東大入学者のノートのとりかたが、書籍化されて出ているのを読んだりすると、
やはり、ノートのとり方というのは大事だというのがよくわかる。
とはいえ、私はそれ(ノートの記録)をなんのためにノートするのか、がわかってなかったように思うのだ。ノートの記録=試験対策=「暗記」って思っていた。
で、暗記のために活用と思うと、もうとたんにダメ。意欲もなくなるし、だいたい、作ったノートで暗記なんか出来ない。
そのまえに「美しく、みやすく記録する」というところに意識の欠如があった気がするけど。
と、そんな背景を持った私は、「記録」「議事録」「板書」ちょー苦手です。
なのだけど。
5,6年前にファシリテーショングラフィックというのに出会いまして。
議論の見える化って大事なんだなって言うことを、体感。
その後、へたくそなくせに、っていうか、文字だけしか書けないけど、率先して板書をする。
ファシリテーショングラフィックっていうのは、グラフィック」っていうくらいですから、絵とか記号とかを使って「模造紙」にカラフルに話し合いの記録をとっていくんです。
大事と思われるところは大きく書いたり、盛り上がった所には、そういうことがわかるような印をつけたりね。
絵の得意な人が、工夫しながら書き上げていくのはもう芸術であり、
またそれを観ながら、話が活性化することもあり、次回の話し合いに、この模造紙の記録を張り出すことで、これまでの議論がすぐに思い出されたり・・
また縮小コピーして、議事録としても活用できる。
有益だなぁと思っているわけです。
でも私には出来ないんですね。絵がかけないから(涙) 字が下手だから。空間をうまく使えないから。
私の周囲にも優秀なファシリテーショングラフィッカーが出てきてくれないかなとひそかに思っているわけです。
↓これは一日習っただけの学生さんが書いたもの。
こちらは、指導者が書いたもの。
絵も苦手、空間把握して、予測して美しく仕上げるなんてのはチョー苦手なんだけどね、
記録する事で、議論がぶれなかったり、話が戻しやすかったり、誰かの発言が置いてきぼりになるのが避けられたり・・・いいことがたくさんあるんです。
また、どんな話し合いだったか?っていうのが思い出されるような記録ってのはいいなぁと思うんですよ。欠席者にも伝わるような。
それで、ときどき、チャレンジします。
臨場感がでる記録づくりに。
板書しながら、模造紙書きながら、途中で入ったチャチャを口語体でそのまんま記録したり、もりあがったところは、わかるように印をつけたり、あえて発言者の発言そのまんま、方言いれて書いたり。
最近は携帯で写真を撮って印刷し、そのまんま議事録として配布しちゃったりすることも。
先日はカフェでのうちあわせだったので、ホワイトボードもなく、手元用紙に「議事録」をとる役目だったのですが・・・
結局発言をほとんど記録する形になり。
だけどあとで読み返してみたら、話の流れがわかって面白かった。
「議事録」としての体裁を整える為、日付場所、時間、参加者名、テーマ書いて、この日の結論を書いて。
あとは、だらっと発言の要点を記録しておきました。
少なくとも参加した人にしたら、あの場でおこっていたことを思い出すきっかけになるだろうし、欠席したひとは、どういう背景でこういう結論になったのかっていうことがわかるのは有益じゃないだろうかと。
「記録」系は苦手という意識が強かったんですが、ファシリテーショングラフィックと出会ってから、「活用」に意識が行くようになったきがします。
絵はかけなくても、この「記録」がどんな風に役に立つのか、なんのための記録なのか?を意識する事によって、「記録」そのものが、ファシリテート・・・いろんなことを促進する役目を果たしてくれるんだなぁということに気がつきました。
というわけで、苦手意識はあっても、目的を遂行する為に出来る事として、チャレンジしていこうと思っています。
ファシリテーション授業の感想
ファシリテーションについて、専門学校での授業。
「一方通行のコミュニケーション」「聴くこと、話すこと」などをテーマにした実習を行い、一部の学生さんにファシリテーター役も経験してもらいました。
以下は、「気づいたこと、学んだこと」「次に活かしたいこと」「感想」などの一部です。
学生さんたちからは了解をいただいています。
*****
相手の気持ちを汲み取って確認するように聞き返すと、仮に誤解があっても相手をあまり嫌な気持ちにさせずにコミュニケーションを修復することができる。
円滑なコミュニケーションを行なうためには、話し手と聞き手がお互いに努力しあわなければならない。
自分の解釈や決めつけで相手の言葉の真意を判断するのではなく、相手の心の奥にある感情を読み取れるよう努力したい。
一方的なコミュニケーションによって起こる弊害などは常に日頃ありうることなので、コニュニケーションの方法を見直すという意味で非常に勉強になった。話し手も聞き手も、お互いのことを考えながらコミュニケーションをとっていくことが必要になるのだ思った。
発信者の思う気持ちは、受信者の受け取り方や感じ方で変わってしまうということ。受信者が想像して相手の事を理解してしまう事があるということ。
相手が伝えたいことと自分が摘み取った話の内容がお互いに合っているかを確認することで間違いが少なくなると思いました。
同じ事を聞いて、絵を描くだけなのに、それぞれ、出来上がった絵が違った事が面白かったです。受け取る側によって、変わるということはとても興味深いことだと思いました。
今回ファシリテーターをやってみて、ファシリテーターに限らず話し合いに参加しているメンバーであるときも、他の人のプロセスを汲み取り、話し合いの方向付けを行うことの難しさと重要性を再認識した。
今回は、話を広げていけるような材料があったにもかかわらずそれを生かせなかった。あせりもあったと思う。次回は、もう少し落ち着いて話し合いに臨みたい。
聞き手の思い込みなど、コミュニケーションには発信者・受信者とその間におけるさまざまな段階で、ミスコミュニケーションが起きる可能性がある。
発信者・受信者ともにミスコミュニケーションが起きないよう気をつける必要があるが、一方でミスコミュニケーションは起こるものだという認識も必要である。
伝わるだろうという気持ちではなく、伝わらないこともあると言う認識で伝える努力が必要。
「伝わっているよ~」の確認の意味も含めて、確認をすること。
少しでも理解できていないと感じたら、恥ずかしがらすに確認すること。(自分は、コミュニケーションで聞くことを遠慮する傾向があるので)"
「一方通行のコミュニケーション」「聴くこと、話すこと」などをテーマにした実習を行い、一部の学生さんにファシリテーター役も経験してもらいました。
以下は、「気づいたこと、学んだこと」「次に活かしたいこと」「感想」などの一部です。
学生さんたちからは了解をいただいています。
*****
相手の気持ちを汲み取って確認するように聞き返すと、仮に誤解があっても相手をあまり嫌な気持ちにさせずにコミュニケーションを修復することができる。
円滑なコミュニケーションを行なうためには、話し手と聞き手がお互いに努力しあわなければならない。
自分の解釈や決めつけで相手の言葉の真意を判断するのではなく、相手の心の奥にある感情を読み取れるよう努力したい。
一方的なコミュニケーションによって起こる弊害などは常に日頃ありうることなので、コニュニケーションの方法を見直すという意味で非常に勉強になった。話し手も聞き手も、お互いのことを考えながらコミュニケーションをとっていくことが必要になるのだ思った。
発信者の思う気持ちは、受信者の受け取り方や感じ方で変わってしまうということ。受信者が想像して相手の事を理解してしまう事があるということ。
相手が伝えたいことと自分が摘み取った話の内容がお互いに合っているかを確認することで間違いが少なくなると思いました。
同じ事を聞いて、絵を描くだけなのに、それぞれ、出来上がった絵が違った事が面白かったです。受け取る側によって、変わるということはとても興味深いことだと思いました。
今回ファシリテーターをやってみて、ファシリテーターに限らず話し合いに参加しているメンバーであるときも、他の人のプロセスを汲み取り、話し合いの方向付けを行うことの難しさと重要性を再認識した。
今回は、話を広げていけるような材料があったにもかかわらずそれを生かせなかった。あせりもあったと思う。次回は、もう少し落ち着いて話し合いに臨みたい。
聞き手の思い込みなど、コミュニケーションには発信者・受信者とその間におけるさまざまな段階で、ミスコミュニケーションが起きる可能性がある。
発信者・受信者ともにミスコミュニケーションが起きないよう気をつける必要があるが、一方でミスコミュニケーションは起こるものだという認識も必要である。
伝わるだろうという気持ちではなく、伝わらないこともあると言う認識で伝える努力が必要。
「伝わっているよ~」の確認の意味も含めて、確認をすること。
少しでも理解できていないと感じたら、恥ずかしがらすに確認すること。(自分は、コミュニケーションで聞くことを遠慮する傾向があるので)"
経営者とファシリテーション
昨年の山梨ファシリテーション研究会でのことである。
ファシリテーション導入事例を話してくれた若月社長のお話は興味深かった。
それまでは、自分の思いが強すぎて何でもかんでも押し付けていたのかもしれないと、若月社長は言う。
しかし、ファシリテーションを知り、相手から「引きだす」ことが大切と知ったが、一年間は試行錯誤だった様子。社長としては苦しい1年でもあったようだ。
そんななか、会議にファシリテーターとオブザーバー(観察記録者)をおくようにした。
誰でもオブザーバーのとった記録を見られるようにすることで、会議中には表面化しなかったけれども、その場で確かに起こっていたことを、参加者もファシリテーターも知ることが出来るようにした。
たとえば、ファシリテーターが何かを発言したときに、メンバーのほとんどが「ハッとした」表情をしたが、そのままファシリテーターは進行していった・・・とか、具体的な記録が残されている。
ファシリテーターはそれを見て自分の進行ぶりをふりかえる。
若月社長は、時々、状況をフィードバック(メンバーよりもファシリテーターが話しているほうが多いねとか)しながら、しかし、自分が話しすぎてしまうような場面もありながら・・・・と、反省したりという状況だったらしい。
いずれにせよ、継続するうちに少し筒持ち回りで行っているファシリテーターも、少しづつ成長し、ざっくばらんに、メンバーが考えを話せる環境が整っていったということだ。
そのうち、パートを含む社員=スタッフから、いろんな提案があがるようになり、今では携帯電話でその日の出来事や失敗などの報告がメールであがるようになり、携帯の配信システムで、その話題が全員で共有できるようになったそうだ。
そのシステムの提案もスタッフからでてきたそう。
会社の理念も、名刺サイズでパウチしたものが配布され、いつでもどこでも見るようにとスタッフから言われたそうだ。
社長の一方的な提案だったら、携帯電話システムも活用されなかっただろうし、会社の理念だって、見るスタッフなんていないだろう。
スタッフたちが自分たちで考え決めて実行する。そんなカルチャーが育っているようだ。
会社運営にファシリテーションの考えを取り入れるというのは、日常的に、社長や管理職が社員たちからの考えを引き出すことであったり、相手のノンバーバルに気がついて、かかわって、プロセスを明らかにしていくことだったり、自己開示やフィードバックをしていくことだったり、会議にファシリテーターをおく・・・というのはイメージできていたが、会社の会議にオブザーバーを置いて、観察記録をオープンにしておくというアイデアは考えていなかったので、なるほど、いい考えだと思った。
通常の会議では、議題に夢中になっていると、会話の内容は、把握できていたとしても、そこにはでてきていない、参加者の心の動きなどは、そのままおきざりになってしまう。
すると、会議終了し会議の結果あがってきたことをいざ実行しようとしたときに、なかなか実行されないというようなことがおこる可能性がある。
活発に意見がかわされたように見えた会議でも実は一部の人たちだけで進めていて、ほかのひとは、合意していなかった・・・なんてことはよくある話だ。
観察記録のメリットは表面にはでていないことを知る手がかりになる。
ファシリテーターもメンバーもその記録を見ることで、次の会議で何に気をつけて、何を見ていけばいいのかのヒントも得るだろう。
おのずと、お互いに関わりあう関係が生まれてくる。
ファシリテータートレーニングでは一般的なオブザーバーの存在ではあるが、実際の会議での活用も、今後活用させてもらおう。
若月社長の会社はこちら
http://www.plan-do-wakatsuki.jp/corp.html
オブザーバーの記録の取り方を学びたい方はお問い合わせを coach-kaneshige@nifty.com
ファシリテーション導入事例を話してくれた若月社長のお話は興味深かった。
それまでは、自分の思いが強すぎて何でもかんでも押し付けていたのかもしれないと、若月社長は言う。
しかし、ファシリテーションを知り、相手から「引きだす」ことが大切と知ったが、一年間は試行錯誤だった様子。社長としては苦しい1年でもあったようだ。
そんななか、会議にファシリテーターとオブザーバー(観察記録者)をおくようにした。
誰でもオブザーバーのとった記録を見られるようにすることで、会議中には表面化しなかったけれども、その場で確かに起こっていたことを、参加者もファシリテーターも知ることが出来るようにした。
たとえば、ファシリテーターが何かを発言したときに、メンバーのほとんどが「ハッとした」表情をしたが、そのままファシリテーターは進行していった・・・とか、具体的な記録が残されている。
ファシリテーターはそれを見て自分の進行ぶりをふりかえる。
若月社長は、時々、状況をフィードバック(メンバーよりもファシリテーターが話しているほうが多いねとか)しながら、しかし、自分が話しすぎてしまうような場面もありながら・・・・と、反省したりという状況だったらしい。
いずれにせよ、継続するうちに少し筒持ち回りで行っているファシリテーターも、少しづつ成長し、ざっくばらんに、メンバーが考えを話せる環境が整っていったということだ。
そのうち、パートを含む社員=スタッフから、いろんな提案があがるようになり、今では携帯電話でその日の出来事や失敗などの報告がメールであがるようになり、携帯の配信システムで、その話題が全員で共有できるようになったそうだ。
そのシステムの提案もスタッフからでてきたそう。
会社の理念も、名刺サイズでパウチしたものが配布され、いつでもどこでも見るようにとスタッフから言われたそうだ。
社長の一方的な提案だったら、携帯電話システムも活用されなかっただろうし、会社の理念だって、見るスタッフなんていないだろう。
スタッフたちが自分たちで考え決めて実行する。そんなカルチャーが育っているようだ。
会社運営にファシリテーションの考えを取り入れるというのは、日常的に、社長や管理職が社員たちからの考えを引き出すことであったり、相手のノンバーバルに気がついて、かかわって、プロセスを明らかにしていくことだったり、自己開示やフィードバックをしていくことだったり、会議にファシリテーターをおく・・・というのはイメージできていたが、会社の会議にオブザーバーを置いて、観察記録をオープンにしておくというアイデアは考えていなかったので、なるほど、いい考えだと思った。
通常の会議では、議題に夢中になっていると、会話の内容は、把握できていたとしても、そこにはでてきていない、参加者の心の動きなどは、そのままおきざりになってしまう。
すると、会議終了し会議の結果あがってきたことをいざ実行しようとしたときに、なかなか実行されないというようなことがおこる可能性がある。
活発に意見がかわされたように見えた会議でも実は一部の人たちだけで進めていて、ほかのひとは、合意していなかった・・・なんてことはよくある話だ。
観察記録のメリットは表面にはでていないことを知る手がかりになる。
ファシリテーターもメンバーもその記録を見ることで、次の会議で何に気をつけて、何を見ていけばいいのかのヒントも得るだろう。
おのずと、お互いに関わりあう関係が生まれてくる。
ファシリテータートレーニングでは一般的なオブザーバーの存在ではあるが、実際の会議での活用も、今後活用させてもらおう。
若月社長の会社はこちら
http://www.plan-do-wakatsuki.jp/corp.html
オブザーバーの記録の取り方を学びたい方はお問い合わせを coach-kaneshige@nifty.com
コーチングをどこで学ぶかではなく、どう学び続けるか
私がコーチングを学んだのは、
コーチ21(CTP)、CTIジャパン(コーアクティブコーチング)のという二つのプロコーチ養成スクール。
この二つの養成スクールは、ともに米国に本拠を置く世界屈指のコーチ養成機関 から正式にライセンスを受けており国際コーチ連盟(ICF;International Coach Federation)に認定されているプログラムです。
私はコーチ21でスキル(Doing なにをするか)を学び、次にCTIジャパンで、コーチとしての自分の内側・・ありかた・・・(Being どんな自分でいるか)を学んだと思う。
もちろん、コーチ21のプログラムを学び実践する中でも、スキルだけじゃ上手く行かない体験から、自分自身が本当にコーチとして、相手の中の答えを信じて関わっているのか、
自分の答えを手放していたかどうか・・そんなことと向き合い、自分のBeingにも学びがあった。
どっちが良いとか、そういうことではなくて、目指す所はどこのコーチングも同じ。
どちらが自分にとって学びやすいかとか、自分の置かれている環境とか、自分でそのときに良いと思うほうを選べばいい。
コーチ21・・・電話会議方式で学ぶ
CTIジャパン・・・ワークショップ形式で体験を通じてその場で学ぶ
私自身は、どちらかというと「答えがほしい」と思うタイプだったし、既に遠方に住んでいた事もあり、コーチ21は学びやすかった。
プロコーチとしての、数年の経験を経て、いったんこれまでの学びを手放して、先入観なしに、今度はCTIジャパンで学ぼうとした。
それはなかなか難しい事でもあった。これまでのやりかたが出てしまったり、CTIの「やりかた」が頭ではよくわからなかった。「やりかた」じゃないんだよね・・・と思いながら・・なにかが響いている。
その感覚を信じて、CTIジャパンで上級コースでも学び、資格をとった。
体験を通じ、仲間とわかちあい、コーチングしあいながら切磋琢磨し、自分のありかたを見つめ続ける。ときに、厳しいことと向き合うことも。
そんな仲間には、隠し事は出来ないし、今もまだ連絡を取り続け、刺激を与え合っている。
ふたつの学校で学び、それぞれの良さを知り、私には引き出しが増えた。
コーチングを学ぼうと思う人は、「相手のために」というところからスタートするかもしれないけど、結果として、学びながら自分と向き合い、自分が成長する事によって、相手も変わってくる・・・
自分が自分と向き合い、自分の人生を本当に生きようとする事、そこが、本当のスタートのように思う。
最近はこの大手のふたつの学校以外にもコーチングを学べる場が増えている。
どこで学んでもいい。
だけど目指す所は同じ。
関わる相手が、自分らしい選択をし、行動し、人生を切り開いていくことに立ち会いサポートしていく事。
表現方法はいろいろあるだろうけど、結局一緒だと思う。
折角、コーチングに関心を持たれて学ばれた方が、さまざまな事情で、それを役立てられないでいたり、誤解を生んでしまったりするのは、コーチングに関わる者として悲しいです。
だから、コーチングをどこで学んだとしても、お互いのバックグラウンドも尊重しながら、先入観は捨てて「いまここ」で起こっていることから、「事実」を見て感じて学びあう場を作りたい。
体験を通じて、感じ取り学び取っていく場を作る。
それはプロ養成スクールで学んだ人だけでなく、企業研修で学んだ人に対しても。
実践の場、練習の場がほしいと思う人にむけて、誰かが教える場でなく、学びあう場。
私自身、企業様や各種団体様に声をかけていただいて数時間の研修を提供するけれども、伝えきれないもどかしさがある。
折角コーチングに触れた方が、短時間で一部しか取り扱えなかったばっかりに、あるいはさまざまな環境要因で、間違ったとらえ方をしたり、発信の仕方をされて、誤解をうけたり・・・
それは悲しい。
なかなか使えない、あるいはもっと学びたいと思う人へ。
そんな場を、作っています。
ともに学び、成長していきましょう。そして、それぞれの現場、持ち場に帰って、より良い人間関係、そして社会に貢献していけたらいいなぁ・・・
そんな思いも持っています。
次回は
【コーチング道場】~コーチングの練習会です。
日時 : 5月10日(日)午後1:30-4:30
場所 : 会場:長野市三輪1-5-19電弘第一ビル2階(長野中央警察署前)
進行担当: 兼重尚子(兼重コーチング事務所)
参加費: 2000円
主催: Team100
興味のある方は必要事項を明記し、こちらにお問い合わせ下さい。⇒coach-kaneshige@nifty.com
お名前:
どこで学んだか、誰から学んだか:
どのくらいの期間か:
お住まい:
(携帯)電話:
E-mail:
*企業研修で学んだ方は、分かる範囲内でお答え下さい。 二日間とか3時間とか、社内講師から、あるいは外部県内の講師など。
*本を読んだだけだけど、実践してるよ!という方も大歓迎です。
お待ちしています。
コーチ21(CTP)、CTIジャパン(コーアクティブコーチング)のという二つのプロコーチ養成スクール。
この二つの養成スクールは、ともに米国に本拠を置く世界屈指のコーチ養成機関 から正式にライセンスを受けており国際コーチ連盟(ICF;International Coach Federation)に認定されているプログラムです。
私はコーチ21でスキル(Doing なにをするか)を学び、次にCTIジャパンで、コーチとしての自分の内側・・ありかた・・・(Being どんな自分でいるか)を学んだと思う。
もちろん、コーチ21のプログラムを学び実践する中でも、スキルだけじゃ上手く行かない体験から、自分自身が本当にコーチとして、相手の中の答えを信じて関わっているのか、
自分の答えを手放していたかどうか・・そんなことと向き合い、自分のBeingにも学びがあった。
どっちが良いとか、そういうことではなくて、目指す所はどこのコーチングも同じ。
どちらが自分にとって学びやすいかとか、自分の置かれている環境とか、自分でそのときに良いと思うほうを選べばいい。
コーチ21・・・電話会議方式で学ぶ
CTIジャパン・・・ワークショップ形式で体験を通じてその場で学ぶ
私自身は、どちらかというと「答えがほしい」と思うタイプだったし、既に遠方に住んでいた事もあり、コーチ21は学びやすかった。
プロコーチとしての、数年の経験を経て、いったんこれまでの学びを手放して、先入観なしに、今度はCTIジャパンで学ぼうとした。
それはなかなか難しい事でもあった。これまでのやりかたが出てしまったり、CTIの「やりかた」が頭ではよくわからなかった。「やりかた」じゃないんだよね・・・と思いながら・・なにかが響いている。
その感覚を信じて、CTIジャパンで上級コースでも学び、資格をとった。
体験を通じ、仲間とわかちあい、コーチングしあいながら切磋琢磨し、自分のありかたを見つめ続ける。ときに、厳しいことと向き合うことも。
そんな仲間には、隠し事は出来ないし、今もまだ連絡を取り続け、刺激を与え合っている。
ふたつの学校で学び、それぞれの良さを知り、私には引き出しが増えた。
コーチングを学ぼうと思う人は、「相手のために」というところからスタートするかもしれないけど、結果として、学びながら自分と向き合い、自分が成長する事によって、相手も変わってくる・・・
自分が自分と向き合い、自分の人生を本当に生きようとする事、そこが、本当のスタートのように思う。
最近はこの大手のふたつの学校以外にもコーチングを学べる場が増えている。
どこで学んでもいい。
だけど目指す所は同じ。
関わる相手が、自分らしい選択をし、行動し、人生を切り開いていくことに立ち会いサポートしていく事。
表現方法はいろいろあるだろうけど、結局一緒だと思う。
折角、コーチングに関心を持たれて学ばれた方が、さまざまな事情で、それを役立てられないでいたり、誤解を生んでしまったりするのは、コーチングに関わる者として悲しいです。
だから、コーチングをどこで学んだとしても、お互いのバックグラウンドも尊重しながら、先入観は捨てて「いまここ」で起こっていることから、「事実」を見て感じて学びあう場を作りたい。
体験を通じて、感じ取り学び取っていく場を作る。
それはプロ養成スクールで学んだ人だけでなく、企業研修で学んだ人に対しても。
実践の場、練習の場がほしいと思う人にむけて、誰かが教える場でなく、学びあう場。
私自身、企業様や各種団体様に声をかけていただいて数時間の研修を提供するけれども、伝えきれないもどかしさがある。
折角コーチングに触れた方が、短時間で一部しか取り扱えなかったばっかりに、あるいはさまざまな環境要因で、間違ったとらえ方をしたり、発信の仕方をされて、誤解をうけたり・・・
それは悲しい。
なかなか使えない、あるいはもっと学びたいと思う人へ。
そんな場を、作っています。
ともに学び、成長していきましょう。そして、それぞれの現場、持ち場に帰って、より良い人間関係、そして社会に貢献していけたらいいなぁ・・・
そんな思いも持っています。
次回は
【コーチング道場】~コーチングの練習会です。
日時 : 5月10日(日)午後1:30-4:30
場所 : 会場:長野市三輪1-5-19電弘第一ビル2階(長野中央警察署前)
進行担当: 兼重尚子(兼重コーチング事務所)
参加費: 2000円
主催: Team100
興味のある方は必要事項を明記し、こちらにお問い合わせ下さい。⇒coach-kaneshige@nifty.com
お名前:
どこで学んだか、誰から学んだか:
どのくらいの期間か:
お住まい:
(携帯)電話:
E-mail:
*企業研修で学んだ方は、分かる範囲内でお答え下さい。 二日間とか3時間とか、社内講師から、あるいは外部県内の講師など。
*本を読んだだけだけど、実践してるよ!という方も大歓迎です。
お待ちしています。
企業研修~チームベースづくり
2年ほどかかわらせていただいている農業法人さんの全体ミーティングで時間を持たせていただいた。普段は一部の方だけの接触だったので、私としても、この機会はとても嬉しかった。
せっかく、関わるのなら、先方のことをもっと知りたいという思いがあったし、ときどき見かける外部のひとという位置ではなく、社員さんとも、もっとお話できるといいなぁと思っていた。
朝の農場見学からご一緒させていただく。
農場スタッフの説明、それを聞いているスタッフの好奇心、誰に指示されたわけでないのに、私に説明してくれる態度などに、この仕事への愛情が感じられる。
午後の私の担当時間は、スタッフ間の【交流】【情報交換】がねらい。
規模が大きくなってくると、昔とは違うことがおきてくる。そんななかでの、試み。
自分の担当部署と違う人たちとチームになり、普段話さないようなことを話してもらう。
最初は相手の意外な一面を見て笑顔と驚きに。
次は、照れくささもあるような場面。
そして最後は、普段きけなかったこと、知らなかったことを、お互いに聞きあったり、こんな風にしてもらえたらいいんだけど・・・と情報交換。
この場面では、みんな真剣な顔に。
いつも見ている顔でも、知らなかった一面を見て嬉しくなった。身近になった。
相手が自分をそんな風に見てくれていたのかと知って、嬉しかった。
知らなかった相手の仕事内容がわかって協力してやっていけそう。
そんな感想が。
そして、私に、いい時間でしたと、こういう時間を持ててよかったですと感想をわざわざ伝えてくれるかたも。
感想をシェアするときも私をねぎらってくれるようなそんなニュアンスが伝わってきていた。
今日も、随所にみられたが、普段から社長や役員のかたたちが、こまめに感想を伝えたり、ねぎらいをかかさないから、スタッフも知らずにそういう振る舞いをされるのだろう。
普段からお互い知っているけど、もう一歩踏み込んで話し合える関係作り。
そんな場作りは、チームのベース作り。
こういう企業との関わりをもっと進めていきたい。
せっかく、関わるのなら、先方のことをもっと知りたいという思いがあったし、ときどき見かける外部のひとという位置ではなく、社員さんとも、もっとお話できるといいなぁと思っていた。
朝の農場見学からご一緒させていただく。
農場スタッフの説明、それを聞いているスタッフの好奇心、誰に指示されたわけでないのに、私に説明してくれる態度などに、この仕事への愛情が感じられる。
午後の私の担当時間は、スタッフ間の【交流】【情報交換】がねらい。
規模が大きくなってくると、昔とは違うことがおきてくる。そんななかでの、試み。
自分の担当部署と違う人たちとチームになり、普段話さないようなことを話してもらう。
最初は相手の意外な一面を見て笑顔と驚きに。
次は、照れくささもあるような場面。
そして最後は、普段きけなかったこと、知らなかったことを、お互いに聞きあったり、こんな風にしてもらえたらいいんだけど・・・と情報交換。
この場面では、みんな真剣な顔に。
いつも見ている顔でも、知らなかった一面を見て嬉しくなった。身近になった。
相手が自分をそんな風に見てくれていたのかと知って、嬉しかった。
知らなかった相手の仕事内容がわかって協力してやっていけそう。
そんな感想が。
そして、私に、いい時間でしたと、こういう時間を持ててよかったですと感想をわざわざ伝えてくれるかたも。
感想をシェアするときも私をねぎらってくれるようなそんなニュアンスが伝わってきていた。
今日も、随所にみられたが、普段から社長や役員のかたたちが、こまめに感想を伝えたり、ねぎらいをかかさないから、スタッフも知らずにそういう振る舞いをされるのだろう。
普段からお互い知っているけど、もう一歩踏み込んで話し合える関係作り。
そんな場作りは、チームのベース作り。
こういう企業との関わりをもっと進めていきたい。
安心で安全な場について思うこと
ワークショップとは・・・
参加型の活動のことを一般的に言うと思う。
クラフトを作ったりというような活動のこともそのようにいうと思うけど、
私がここで意味しているワークショップというのは
「なんでも話せる」「安心してそこにいられる」「グループの一員感がある」
そんな場で、特定のテーマで話し合ったり、「まちづくり」を考えたり
体験学習の場だったり・・・・
そんなグループ活動のことを意味している。
「なんでも話せる」「安心してそこにいられる」「グループの一員感がある」
そんな雰囲気を作り出すのは、ファシリテーターとよばれる、進行役の役割が大きいが、
もちろん参加者がそこに賛同して作り出していくものだ。
そういう場をつくることで、多様な考えを吸い上げたり、本当の合意に向けた話し合いをし、参加者が納得したアウトプットをめざしたり、学びを深めたりする。
で。
普段、そういう場って、「あるべき」なのに、意外にない。
会社での会議、趣味の場での会議、町の集会・・・・
一部の声の大きい人や、責任ある役割のある人が、発言して、流れができてしまう。
反対意見をいいたいと思っても、言える雰囲気じゃなかったり、疎外感を感じてしまったり、つまらないから、あるいは嫌われたくないから、だまっておこうになったり。
だからかな?
「なんでも話せる」「安心してそこにいられる」「グループの一員感がある」という場を経験したひとは、「ここに参加している人たちって特別!愛がある!」となって極端な参加の仕方になったり、ある意味「信者」のように振舞ってしまったり。
自分の悲しみや苦しみを共感して聞いてもらって感じたカタルシスに病み付きになって
ワークショップときくと参加し続ける、ワークショップフリークになってしまったり。
極端に走る人がいるなぁと思う。
それだけ、そういう場が求められている。
逆に言えば、いかに安心で安全じゃない場に、自分達が普段いるのかということを思う。
で、「なんでも話せる」「安心してそこにいられる」「グループの一員感がある」ワークショップというか、「場」に居合わせたときに、逆に「気持ち悪い」と感じてしまう人もいるみたい。
これって、なんか宗教?洗脳されている?なんてね。
実は、私も、そう感じてしまう場がときどきある。
ひとつ明らかなのは、音楽を活用する時。雰囲気をもりあげるような・・・ね。
あれはいただけない。私の中のアラームが鳴る。
音楽はないのに、「ちょっと気持ち悪いな・・・」と思う場・・・
どうしてそうなってしまうんだろう?
という問いがたった。
ひとつの仮説をたててみた。
「安心な場」を作るために、意図は違ったとしても、ファシリテーターのお願いしたグランドルールが、
「誰かの意見や考えを否定してはいけない」というようなルールとして、参加者に伝わってしまっていたとしたら。
自分が思っていることと反対の考えが誰かからだされたときに、これを口に出してはいけない・・・と、言いたいことがいえなくなってしまっているのではないか?
多くの人が肯定的なことばかりを口に出せば出すほど、気持ち悪いかんじがある。
本当は、違う考えや意見をどんどん出してほしいはず。
だけど、そのときに、自分とは違う相手を攻撃したり、非難したりするのではなく、なるほど、あなたはそう感じたのですね。と受け止めた上で、
実は私には、あなたとは逆の考えもあるんです。別の経験をしました。というスタンスで、あってほしいということだと私は思っているし、そう関わっているつもりだ。
ネガティブな発言、ちょっと異質な発言でさえ、あたたかく受け入れられる。
そうであってほしいし、そうである自分でいたいし、さらにいえば、その真意がどこにあるのかを明らかに出来る自分(ファシリテーター)でありたい。
気に留めておきたいことだと思った。
参加型の活動のことを一般的に言うと思う。
クラフトを作ったりというような活動のこともそのようにいうと思うけど、
私がここで意味しているワークショップというのは
「なんでも話せる」「安心してそこにいられる」「グループの一員感がある」
そんな場で、特定のテーマで話し合ったり、「まちづくり」を考えたり
体験学習の場だったり・・・・
そんなグループ活動のことを意味している。
「なんでも話せる」「安心してそこにいられる」「グループの一員感がある」
そんな雰囲気を作り出すのは、ファシリテーターとよばれる、進行役の役割が大きいが、
もちろん参加者がそこに賛同して作り出していくものだ。
そういう場をつくることで、多様な考えを吸い上げたり、本当の合意に向けた話し合いをし、参加者が納得したアウトプットをめざしたり、学びを深めたりする。
で。
普段、そういう場って、「あるべき」なのに、意外にない。
会社での会議、趣味の場での会議、町の集会・・・・
一部の声の大きい人や、責任ある役割のある人が、発言して、流れができてしまう。
反対意見をいいたいと思っても、言える雰囲気じゃなかったり、疎外感を感じてしまったり、つまらないから、あるいは嫌われたくないから、だまっておこうになったり。
だからかな?
「なんでも話せる」「安心してそこにいられる」「グループの一員感がある」という場を経験したひとは、「ここに参加している人たちって特別!愛がある!」となって極端な参加の仕方になったり、ある意味「信者」のように振舞ってしまったり。
自分の悲しみや苦しみを共感して聞いてもらって感じたカタルシスに病み付きになって
ワークショップときくと参加し続ける、ワークショップフリークになってしまったり。
極端に走る人がいるなぁと思う。
それだけ、そういう場が求められている。
逆に言えば、いかに安心で安全じゃない場に、自分達が普段いるのかということを思う。
で、「なんでも話せる」「安心してそこにいられる」「グループの一員感がある」ワークショップというか、「場」に居合わせたときに、逆に「気持ち悪い」と感じてしまう人もいるみたい。
これって、なんか宗教?洗脳されている?なんてね。
実は、私も、そう感じてしまう場がときどきある。
ひとつ明らかなのは、音楽を活用する時。雰囲気をもりあげるような・・・ね。
あれはいただけない。私の中のアラームが鳴る。
音楽はないのに、「ちょっと気持ち悪いな・・・」と思う場・・・
どうしてそうなってしまうんだろう?
という問いがたった。
ひとつの仮説をたててみた。
「安心な場」を作るために、意図は違ったとしても、ファシリテーターのお願いしたグランドルールが、
「誰かの意見や考えを否定してはいけない」というようなルールとして、参加者に伝わってしまっていたとしたら。
自分が思っていることと反対の考えが誰かからだされたときに、これを口に出してはいけない・・・と、言いたいことがいえなくなってしまっているのではないか?
多くの人が肯定的なことばかりを口に出せば出すほど、気持ち悪いかんじがある。
本当は、違う考えや意見をどんどん出してほしいはず。
だけど、そのときに、自分とは違う相手を攻撃したり、非難したりするのではなく、なるほど、あなたはそう感じたのですね。と受け止めた上で、
実は私には、あなたとは逆の考えもあるんです。別の経験をしました。というスタンスで、あってほしいということだと私は思っているし、そう関わっているつもりだ。
ネガティブな発言、ちょっと異質な発言でさえ、あたたかく受け入れられる。
そうであってほしいし、そうである自分でいたいし、さらにいえば、その真意がどこにあるのかを明らかに出来る自分(ファシリテーター)でありたい。
気に留めておきたいことだと思った。
非構成的エンカウンターグループGW開催のご案内
~非構成的エンカウンターグループ 2009年ゴールデンウィーク ご案内~
昨年いっしょにグループを囲んだ かとうあきこさんから 上田女神山での非構成的エンカウンターグループのおしらせが届きました。会場も素晴らしい環境のようです。
私の体験や思いは前の記事を御覧下さい。
この機会に是非体験してみて下さい。お勧めです。
《非構成的エンカウンターグループって何?》
その場に集まった参加者とファシリテーターが、車座に座って始まり、過ごす時間。
具体的に書くことができるのは、これだけです。
何が起きるかは分かりません。何も起きないかもしれません。
話してもいいし、話さなくてもいい。
あなたが発したことばに、反応があるかもしれないし、ないかもしれない。
こんなふうに過ごす5日間。
説明するのは難しく、具体的にこのワークショップでは何かを得られると
いうことを示すことはできません。なぜなら、どんな場になるかは、その時、
その参加者から起こってくるものだからです。それが非構成です。
しかし、この濃密な時間は、日常とは違う時間として、参加した方の奥深くに
何かを残していきます。
《世話人からのことば》
私が初めて非構成的エンカウンターグループに参加したのは、2年前の
2007年6月のことです。実は、何をするのかもまったく分からないまま、
ただ、届いた案内にファシリテーションのことが書いてあり、その当時、
ファシリテーションに興味をもっていたことと、その案内文がとても強い
印象として残り、「なんだか分からないけど、とにかく行かねば」という
思いから参加を決めたのでした。
(「怪しかったらすぐ帰ろう」と思って、わざわざ車で出掛けたのでした。
杞憂でしたが。)
そして参加をして、その体験は、他の参加者とともに、大きな川を渉った
ような、大陸を旅して横断したかのような感じが今でもあります。
何が目に見えて起こったのかというと、ことばにするのは難しいです。
ただ、このエンカウンターグループの時間のなかで、自分の存在を、普段
できないほど感じていたということが言えます。エンカウンターグループの
開始から終了までの間、自分のなかに湧き起こることを感じ、自分に丁寧
に付き合うことをしていたのだと思います。
自分に丁寧に付き合う。
これは日常では、実はなかなか難しいのではと私は仮説を立てています。
特に、組織に居る人には。
組織のなかで働くということは、自分の意思ももちろんあり、場面、場面で
その意思を表明したり、行動の源泉とします。それと同時に、目まぐるしく
変化する周りとの関係や、凄まじいスピードで入ってくる外からの情報に、
次々と対応しているうちに、自分が置き去りになっていることも、あるので
はないでしょうか。
そんな日常から、一歩横に出て、そしてまるでステージから一段下りるよう
に自分を眺め、ゆっくりと時間をかけて丁寧に自分に付き合う、そんな時間
が組織で働く人にとって、もしかすると組織で働く人にこそ、とても大切なも
のではないかという思いがあります。
私自身が企業人であり、普段は大きな組織のなかで働いています。
ゴールデンウィークという、日常から離れられるチャンスに、思いっきり離れ、
そしてまた戻っていく力を得られる場になるのでしたら、これほど嬉しいこ
とはありません。
皆様のお申込みを、心よりお待ちしております。
世話人 かとうあきこ
《ワークショップ要項》
非構成的エンカウンターグループ 2009年ゴールデンウィーク
日程: 2009年5月2日(土)~5月6日(水)4泊5日
3時間×11セッションを行なう予定です。
ファシリテーター:
橋本 久仁彦
(ファシリテーター、カウンセラー、PTプロデュース代表、
シアター・ザ・フェンス代表、
国際プレイバックシアター“IPTN”プラクティショナー)
<プロフィール>
高校教師時代には、パーソン・センタード・アプローチに基づく、
「教えない授業」を実施。その後、龍谷大学で学生相談室カウンセラーや
講師を務める。フリーになった後は、カウンセラートレーニングやプレイ
バックシアター、コンステレーションワーク、ダンサートレーニング等、
多岐にわたるファシリテーションを全国各地で行なっている。大阪府在住。
橋本さんのブログ http://kunis.blog50.fc2.com/
場所: 女神山ライフセンター 長野県上田市
交通: 列車の場合)長野新幹線上田駅から上田交通別所線で約30分
終点別所温泉駅から車で約15分
別所温泉駅で待ち合わせをして送迎していただく予定です。
車の場合)上信越自動車道/上田菅平ICから約45分
http://www.megamiyama.jp/contact.html
料金: 45,000円 (含まれるもの:ワークショップ費用)
*別途、宿泊費・食事代を、現地で直接施設にお支払いください。
1泊3食付き9,450円(税込)、4泊で37,800円。5月2日の夕食から
5月6日の昼食までが含まれます。
気候によっては、1日当り数百円から千円程度の、暖房費の
ご負担をお願いする可能性があります。
**開催が確定次第、振込先をご連絡いたします。連絡後3日以内に
お振込ください。
定員: 14名(先着順・定員になり次第締め切ります。お早目にお申込ください。)
申込方法:
次の内容を添えて、eg_200905@owl.nifty.jpへe-Mailでお申込みください。
++++++++++
・お名前(ふりかな):
・年齢:
・住所:
・E-mail Address:
・当日連絡可能な電話番号:
・普段は何をなされていますか?ご職業など:
+++++++++++
お問い合わせ先:
かとうあきこ
E-mail: eg_200905@owl.nifty.jp
Tel: 090-6199-9832
以上
昨年いっしょにグループを囲んだ かとうあきこさんから 上田女神山での非構成的エンカウンターグループのおしらせが届きました。会場も素晴らしい環境のようです。
私の体験や思いは前の記事を御覧下さい。
この機会に是非体験してみて下さい。お勧めです。
《非構成的エンカウンターグループって何?》
その場に集まった参加者とファシリテーターが、車座に座って始まり、過ごす時間。
具体的に書くことができるのは、これだけです。
何が起きるかは分かりません。何も起きないかもしれません。
話してもいいし、話さなくてもいい。
あなたが発したことばに、反応があるかもしれないし、ないかもしれない。
こんなふうに過ごす5日間。
説明するのは難しく、具体的にこのワークショップでは何かを得られると
いうことを示すことはできません。なぜなら、どんな場になるかは、その時、
その参加者から起こってくるものだからです。それが非構成です。
しかし、この濃密な時間は、日常とは違う時間として、参加した方の奥深くに
何かを残していきます。
《世話人からのことば》
私が初めて非構成的エンカウンターグループに参加したのは、2年前の
2007年6月のことです。実は、何をするのかもまったく分からないまま、
ただ、届いた案内にファシリテーションのことが書いてあり、その当時、
ファシリテーションに興味をもっていたことと、その案内文がとても強い
印象として残り、「なんだか分からないけど、とにかく行かねば」という
思いから参加を決めたのでした。
(「怪しかったらすぐ帰ろう」と思って、わざわざ車で出掛けたのでした。
杞憂でしたが。)
そして参加をして、その体験は、他の参加者とともに、大きな川を渉った
ような、大陸を旅して横断したかのような感じが今でもあります。
何が目に見えて起こったのかというと、ことばにするのは難しいです。
ただ、このエンカウンターグループの時間のなかで、自分の存在を、普段
できないほど感じていたということが言えます。エンカウンターグループの
開始から終了までの間、自分のなかに湧き起こることを感じ、自分に丁寧
に付き合うことをしていたのだと思います。
自分に丁寧に付き合う。
これは日常では、実はなかなか難しいのではと私は仮説を立てています。
特に、組織に居る人には。
組織のなかで働くということは、自分の意思ももちろんあり、場面、場面で
その意思を表明したり、行動の源泉とします。それと同時に、目まぐるしく
変化する周りとの関係や、凄まじいスピードで入ってくる外からの情報に、
次々と対応しているうちに、自分が置き去りになっていることも、あるので
はないでしょうか。
そんな日常から、一歩横に出て、そしてまるでステージから一段下りるよう
に自分を眺め、ゆっくりと時間をかけて丁寧に自分に付き合う、そんな時間
が組織で働く人にとって、もしかすると組織で働く人にこそ、とても大切なも
のではないかという思いがあります。
私自身が企業人であり、普段は大きな組織のなかで働いています。
ゴールデンウィークという、日常から離れられるチャンスに、思いっきり離れ、
そしてまた戻っていく力を得られる場になるのでしたら、これほど嬉しいこ
とはありません。
皆様のお申込みを、心よりお待ちしております。
世話人 かとうあきこ
《ワークショップ要項》
非構成的エンカウンターグループ 2009年ゴールデンウィーク
日程: 2009年5月2日(土)~5月6日(水)4泊5日
3時間×11セッションを行なう予定です。
ファシリテーター:
橋本 久仁彦
(ファシリテーター、カウンセラー、PTプロデュース代表、
シアター・ザ・フェンス代表、
国際プレイバックシアター“IPTN”プラクティショナー)
<プロフィール>
高校教師時代には、パーソン・センタード・アプローチに基づく、
「教えない授業」を実施。その後、龍谷大学で学生相談室カウンセラーや
講師を務める。フリーになった後は、カウンセラートレーニングやプレイ
バックシアター、コンステレーションワーク、ダンサートレーニング等、
多岐にわたるファシリテーションを全国各地で行なっている。大阪府在住。
橋本さんのブログ http://kunis.blog50.fc2.com/
場所: 女神山ライフセンター 長野県上田市
交通: 列車の場合)長野新幹線上田駅から上田交通別所線で約30分
終点別所温泉駅から車で約15分
別所温泉駅で待ち合わせをして送迎していただく予定です。
車の場合)上信越自動車道/上田菅平ICから約45分
http://www.megamiyama.jp/contact.html
料金: 45,000円 (含まれるもの:ワークショップ費用)
*別途、宿泊費・食事代を、現地で直接施設にお支払いください。
1泊3食付き9,450円(税込)、4泊で37,800円。5月2日の夕食から
5月6日の昼食までが含まれます。
気候によっては、1日当り数百円から千円程度の、暖房費の
ご負担をお願いする可能性があります。
**開催が確定次第、振込先をご連絡いたします。連絡後3日以内に
お振込ください。
定員: 14名(先着順・定員になり次第締め切ります。お早目にお申込ください。)
申込方法:
次の内容を添えて、eg_200905@owl.nifty.jpへe-Mailでお申込みください。
++++++++++
・お名前(ふりかな):
・年齢:
・住所:
・E-mail Address:
・当日連絡可能な電話番号:
・普段は何をなされていますか?ご職業など:
+++++++++++
お問い合わせ先:
かとうあきこ
E-mail: eg_200905@owl.nifty.jp
Tel: 090-6199-9832
以上
非構成エンカウンターグループのすすめ
昨年のGW。橋本久仁彦さんがファシリテーターの非構成的エンカウンターグループ(ベーシックエンカウンターグループ)に参加しました。
橋本さんとは5年くらい前に赤城で行われた「教育系ワークショップフォーラム」で、名刺交換させていただき、以来ご案内をいただいていた。
名刺交換のきっかけとしては、橋本さんがプレイバックシアターという心理劇というか、興味深い活動をされていることに関心をもってのことだった。
昨年のGWのご案内は、私の住む信濃町、野尻湖での開催という事もあり、また、橋本さん自身に興味があったこともあり、これは呼ばれてる(^^)って思って何も考えず参加。
事前知識としては「用意された内容はない」っていうことだけ。
で、そこで何が起こるんだろう、何が体験できるんだろう。っていう好奇心。
コーチングやファシリテーションという今までの経験をいったんゼロにして、ただその場を味わい、そこにいることから始めてみよう。そんなところから私自身はスタートしました。
で、どうだったかというと・・・・
去年のブログを見てみたのだけど、いろんな思いが交錯して書けなかったんですね。
一部そのことについて記録がありました→ここ
「GW前半他者の存在に・・」ってところです。
今あらためて、言葉にするとすれば。
誰かの思いに触れ、次々に触発されて語りだす人たち。
最初は、それってちゃんと聞いてるの?っていう、そんなかんじもあったのだけど。
時間が経つにつれ、あいづちを打たなくても、相手の目を見なくても、そこにいるだけで、聴いてくれている、思いをうけとめてくれている、共感している・・・・そんなことが起こっていることが感じられ・・・・
頭の理解ではなく、心の奥のほうで、何かが響いてる・・そんな体験をしていました。
みんながそこにいてくれるっていうこと、自分も同じようにそこにいて、語っている人の存在を感じ思いを感じ、心震える体験をしました。
私自身は、この文脈では、語ることは何もないって思っていたんだけど・・・・
思いもかけないところで、人の思いに触れ・・忘れようとしていた事を思い出し、語ることになったのでした。
いつもいつも同じような場になるわけではありません。私の体験は、あの時だけのものかもしれない。参加する人が変われば、違う場になるでしょう。
私は「傾聴」ということに対する理解に、大きな変化がありました。
本当に聴くって言う事はいったいどういうことなのかを、本当に聴いてもらうっていうことはいったいどういうことなのかを、体感したと思います。
心の扉が開いて、日常に帰ってきてからも、深い対話ができました。
数日でもとにもどってしまいましたが、あの感覚は思い出せます。
コーチやファシリテーターや、カウンセラー。
キャリアカウンセラーなど、人の話を聴くお仕事の方、人と関わる人たちにお勧めします。
それから、最近自分の感情が良く分からないという人にも。
日々の忙しさの中、自分と向き合う時間がほしいなと思う方にもお勧めです。
橋本さんとは5年くらい前に赤城で行われた「教育系ワークショップフォーラム」で、名刺交換させていただき、以来ご案内をいただいていた。
名刺交換のきっかけとしては、橋本さんがプレイバックシアターという心理劇というか、興味深い活動をされていることに関心をもってのことだった。
昨年のGWのご案内は、私の住む信濃町、野尻湖での開催という事もあり、また、橋本さん自身に興味があったこともあり、これは呼ばれてる(^^)って思って何も考えず参加。
事前知識としては「用意された内容はない」っていうことだけ。
で、そこで何が起こるんだろう、何が体験できるんだろう。っていう好奇心。
コーチングやファシリテーションという今までの経験をいったんゼロにして、ただその場を味わい、そこにいることから始めてみよう。そんなところから私自身はスタートしました。
で、どうだったかというと・・・・
去年のブログを見てみたのだけど、いろんな思いが交錯して書けなかったんですね。
一部そのことについて記録がありました→ここ
「GW前半他者の存在に・・」ってところです。
今あらためて、言葉にするとすれば。
誰かの思いに触れ、次々に触発されて語りだす人たち。
最初は、それってちゃんと聞いてるの?っていう、そんなかんじもあったのだけど。
時間が経つにつれ、あいづちを打たなくても、相手の目を見なくても、そこにいるだけで、聴いてくれている、思いをうけとめてくれている、共感している・・・・そんなことが起こっていることが感じられ・・・・
頭の理解ではなく、心の奥のほうで、何かが響いてる・・そんな体験をしていました。
みんながそこにいてくれるっていうこと、自分も同じようにそこにいて、語っている人の存在を感じ思いを感じ、心震える体験をしました。
私自身は、この文脈では、語ることは何もないって思っていたんだけど・・・・
思いもかけないところで、人の思いに触れ・・忘れようとしていた事を思い出し、語ることになったのでした。
いつもいつも同じような場になるわけではありません。私の体験は、あの時だけのものかもしれない。参加する人が変われば、違う場になるでしょう。
私は「傾聴」ということに対する理解に、大きな変化がありました。
本当に聴くって言う事はいったいどういうことなのかを、本当に聴いてもらうっていうことはいったいどういうことなのかを、体感したと思います。
心の扉が開いて、日常に帰ってきてからも、深い対話ができました。
数日でもとにもどってしまいましたが、あの感覚は思い出せます。
コーチやファシリテーターや、カウンセラー。
キャリアカウンセラーなど、人の話を聴くお仕事の方、人と関わる人たちにお勧めします。
それから、最近自分の感情が良く分からないという人にも。
日々の忙しさの中、自分と向き合う時間がほしいなと思う方にもお勧めです。
今どんな気持ち?
「今どんな気持ち?」って聞かれたら、どんな風に応えますか?
私は以前、そんなときは普通に、「今思っていること」や「今考え始めたこと」などを話していました。
たとえば、まさに今だとしたら、
「今パソコンに向かっていて、どんな記事を書こうかと思っている」という風に。
コーチングのセミナーや、体験学習の場において、
「今この体験をしてみて、何を感じましたか?どんな気持ちになりましたか?」と問うとき、
「こういうことって、日常生活でもよくあるなぁと思いました」とか
「一般的にこういうもんですよね」
なんて応えが返ってきたりする。気持ちや、感じたことをきちんと自分でも受け止めず、すっとばして、そこからの「考え」「思ってること」とか「連想したこと」とか、「一般的なこと」を応えたりする。
で、さらに突っ込まれて「で、まさに今の気持ちは?」なんて言われるとしどろもどろ・・・私の気持ちって??
なんてわからないことも。
言ってるじゃないの。「こう思う」って!みたいなイライラが出てきちゃったり。
で、ようやく「あ、わかってもらえなくてイライラしてます!」みたいな。
もちろん、みんながみんなそんなわけではないんですが、自分の「気持ち」がわからない人が多い気がする。
それって、学校教育や仕事生活の中で、「気持ち」を訊かれることなんかなくて、「正解」にたどりつけるような「考え」ばかり求められ続けてきたからかなぁ。
けんかをしても
大人「どうしてこんなことしたの?」
こども「だって、いやなんだもの」
大人「いやじゃ、理由にならないでしょ!」
「いや」という気持ちは受け止めてもらえず、「理由」を求められる。
気持ちがどこかに置き去りにされちゃって、気がつかなくなってしまう?
だけど、感情は、ちゃんと体の中で起こっていて、自分にさえ受け止めてもらえず、外にだすにもだしかたがわからず・・・・病気になったりする?
そんなことが起こっているような気がする。
人間関係(ファシリテーション)の第一歩は、まず自分の内側で起こっていること・・・気持ち・・・それはもやもやしていて、言葉では表現できないこともあるかもしれないけど・・・「考え」とは違う・・・その何か内側で起こっていることを自分でキャッチすること・・・・そこから始まると思っている。
自分の内側で起こっていることに意識を向けて、キャッチする・・・
そんな練習からはじめてみませんか?
6月20・21日(土日)にファシリテーション入門行います。ご関心のある方はお問い合わせを
coach-kaneshige@nifty.com
私は以前、そんなときは普通に、「今思っていること」や「今考え始めたこと」などを話していました。
たとえば、まさに今だとしたら、
「今パソコンに向かっていて、どんな記事を書こうかと思っている」という風に。
コーチングのセミナーや、体験学習の場において、
「今この体験をしてみて、何を感じましたか?どんな気持ちになりましたか?」と問うとき、
「こういうことって、日常生活でもよくあるなぁと思いました」とか
「一般的にこういうもんですよね」
なんて応えが返ってきたりする。気持ちや、感じたことをきちんと自分でも受け止めず、すっとばして、そこからの「考え」「思ってること」とか「連想したこと」とか、「一般的なこと」を応えたりする。
で、さらに突っ込まれて「で、まさに今の気持ちは?」なんて言われるとしどろもどろ・・・私の気持ちって??
なんてわからないことも。
言ってるじゃないの。「こう思う」って!みたいなイライラが出てきちゃったり。
で、ようやく「あ、わかってもらえなくてイライラしてます!」みたいな。
もちろん、みんながみんなそんなわけではないんですが、自分の「気持ち」がわからない人が多い気がする。
それって、学校教育や仕事生活の中で、「気持ち」を訊かれることなんかなくて、「正解」にたどりつけるような「考え」ばかり求められ続けてきたからかなぁ。
けんかをしても
大人「どうしてこんなことしたの?」
こども「だって、いやなんだもの」
大人「いやじゃ、理由にならないでしょ!」
「いや」という気持ちは受け止めてもらえず、「理由」を求められる。
気持ちがどこかに置き去りにされちゃって、気がつかなくなってしまう?
だけど、感情は、ちゃんと体の中で起こっていて、自分にさえ受け止めてもらえず、外にだすにもだしかたがわからず・・・・病気になったりする?
そんなことが起こっているような気がする。
人間関係(ファシリテーション)の第一歩は、まず自分の内側で起こっていること・・・気持ち・・・それはもやもやしていて、言葉では表現できないこともあるかもしれないけど・・・「考え」とは違う・・・その何か内側で起こっていることを自分でキャッチすること・・・・そこから始まると思っている。
自分の内側で起こっていることに意識を向けて、キャッチする・・・
そんな練習からはじめてみませんか?
6月20・21日(土日)にファシリテーション入門行います。ご関心のある方はお問い合わせを
coach-kaneshige@nifty.com
新潟まちづくりファシリテーション 映画「降りていく生き方」
ご存知ですか?
新潟が舞台で、地域ぐるみのオーディションを経て、2000人のエキストラが出演したそうです。
****************公式ホームページより***********
脚本と映画制作に影響を与えた「地域参加型のオーディション」
まちづくりを中心に「自然/共生/希望」が重要なテーマとなる本作において、私たちは、映画出演募集を一種の「祭り」と捉え、日本映画史上初の試みとなる前代未聞のオーディションを実施しました。
オーディション自体の企画/運営/実施を、本作に賛同頂いたボランティア・スタッフを中心に行い、行政、各種団体などの協力も得て、新潟県内7ヶ所で開催しました。
オーディション受験者は、生後8ヶ月から92才まで、老若男女、そして国籍を問わず、約2000名もの応募がありました。
このオーディションは、その情熱に満ち溢れ、数々のエピソードやドラマを生み出し、遂には本作の脚本開発や映画制作の方向性に対して大きな影響を与えたのでした。
***************************************************************
この映画に大きな影響を与えているのが、新潟で、まちづくりの仕掛け人として、ファシリテーターとして活躍されている清水義晴氏。
氏の著書
変革は、弱いところ、小さいところ、遠いところから
を読むと氏の考え方や活動がわかる。
まさにファシリテーターとして生きている方であり、カウンセラーの方、コーチの方、もちろん各種ファシリテーション、まちづくり、組織作りに関わる人にお勧め。
そして、生き方を考える本として、多くの方に手にとってもらいたい。
既存の一般的な「良い」と思われる生き方以外にも、いろんな選択肢があるよねと、ほっとするひともいるんじゃないかな。生き方指南の本とも言えるかも。
映画「降りていく生き方」は、通常のように映画館では見られないようです。
詳細は公式ページからどうぞ。
新潟が舞台で、地域ぐるみのオーディションを経て、2000人のエキストラが出演したそうです。
****************公式ホームページより***********
脚本と映画制作に影響を与えた「地域参加型のオーディション」
まちづくりを中心に「自然/共生/希望」が重要なテーマとなる本作において、私たちは、映画出演募集を一種の「祭り」と捉え、日本映画史上初の試みとなる前代未聞のオーディションを実施しました。
オーディション自体の企画/運営/実施を、本作に賛同頂いたボランティア・スタッフを中心に行い、行政、各種団体などの協力も得て、新潟県内7ヶ所で開催しました。
オーディション受験者は、生後8ヶ月から92才まで、老若男女、そして国籍を問わず、約2000名もの応募がありました。
このオーディションは、その情熱に満ち溢れ、数々のエピソードやドラマを生み出し、遂には本作の脚本開発や映画制作の方向性に対して大きな影響を与えたのでした。
***************************************************************
この映画に大きな影響を与えているのが、新潟で、まちづくりの仕掛け人として、ファシリテーターとして活躍されている清水義晴氏。
氏の著書

変革は、弱いところ、小さいところ、遠いところから
を読むと氏の考え方や活動がわかる。
まさにファシリテーターとして生きている方であり、カウンセラーの方、コーチの方、もちろん各種ファシリテーション、まちづくり、組織作りに関わる人にお勧め。
そして、生き方を考える本として、多くの方に手にとってもらいたい。
既存の一般的な「良い」と思われる生き方以外にも、いろんな選択肢があるよねと、ほっとするひともいるんじゃないかな。生き方指南の本とも言えるかも。
映画「降りていく生き方」は、通常のように映画館では見られないようです。
詳細は公式ページからどうぞ。
話を聞かない営業マン・・・体験学習から学ぶ
<話を聞かない営業マン>
久しぶりにむかついた。
広告を見て、出向いたその先にいたのは、客の話を全く聞かず、自分のペースで、自分の売りたいもの、自分の話したいことを弾丸のように、口を挟む間もなく話し、こちらの反応におかまいなしの営業マンだった。(体験)そして、こちらの質問は無視する。やっと聞き出してもいい加減な回答をする。自分の価値観を押し付け、客の興味のあることに対しても、自分の判断で、説明もせずに、それはダメという。
「ちょっと聞いてくださいよ」
「質問してるんですけど~」
「こういう理由なんですけど~」
背景を説明しようとしても、聴く耳を持たない。
この人と話しても時間が無駄。(仮説化)そして不快。
体験学習の循環サイクルを逆にまわしている。いかんいかん。
帰ってきてから、体験学習のサイクルに沿って振り返っている。
指摘)なんか、急いでいるっぽくてせわしなかったな。話もろくに聞いてくれないし。
分析)どうしてだろう?聞けない理由とか、あったんだろうか?アポなし訪問だったから、あのあとで用事があったのかもしれない?
仮説化)こんど同じような場面があったら、私はどうすればいいだろう?
「ねぇ、あなたは、どうして、そう、人の話聞かないんですか?いつもそうなんです?」
→(これはちょっと、直接的だなー。非難っぽいニュアンスかも?)
「なんか、すごくあわててるように見えますが、もしかしてこの後、予定かなんかあるんですか?」
「質問に答えてもらえなくて、困ってるんですけど、答えてくれないのはなにか理由があるんですか?」(指摘)と(分析)
って、あの営業マンに聞いてみたらどうなんだろう?
(聴いて見てその理由がわかったら、こちらの対応もかわってきますよね)
だけど、今の気持のまま、言ったら、戦線布告しているようなもんだな。
もっと、好意的に、「このひとかわってるなぁ」ぐらいなノリで面白がって訊けたら、面白い展開になるかもしれない。
いや、基本は「好奇心」だよな・・・と思いつつ、そこまで無邪気になれると人生楽だなぁ・・・と妙に客観的になっている私。
まぁ、こちらの気持ちを自己開示しつつ、相手に好奇心を向けてみる・・・っていうのが、きっといいんだろうな。
「好奇心」から、そして「無邪気に」
「ねぇねぇ、どうして?」
「急いでます?だって○○だから・・・」
「私の話も聞いてくださいよぅ~」
「うーん、対象になるかならないかの判断は私にさせてくださいよ(^^)」
って言えたら、何が起こったかな?(仮説化)
「体験学習の循環サイクル」をこんな風にまわして、気持のいいコミュニケーションをしませんか?
なにより自分がすっきりとできますよ。
そして、体験学習の循環サイクルは、とっても役に立つ考え方です。
この【体験学習】方法で、私はコーチングのセミナーを行っています。
また、さらに「人間関係ファシリテーション」をまさに体験学習方式で学ぶ場を実施しています。
お問い合わせくださいませ。
coach-kaneshige@nifty.com
久しぶりにむかついた。
広告を見て、出向いたその先にいたのは、客の話を全く聞かず、自分のペースで、自分の売りたいもの、自分の話したいことを弾丸のように、口を挟む間もなく話し、こちらの反応におかまいなしの営業マンだった。(体験)そして、こちらの質問は無視する。やっと聞き出してもいい加減な回答をする。自分の価値観を押し付け、客の興味のあることに対しても、自分の判断で、説明もせずに、それはダメという。
「ちょっと聞いてくださいよ」
「質問してるんですけど~」
「こういう理由なんですけど~」
背景を説明しようとしても、聴く耳を持たない。
この人と話しても時間が無駄。(仮説化)そして不快。
体験学習の循環サイクルを逆にまわしている。いかんいかん。
帰ってきてから、体験学習のサイクルに沿って振り返っている。
指摘)なんか、急いでいるっぽくてせわしなかったな。話もろくに聞いてくれないし。
分析)どうしてだろう?聞けない理由とか、あったんだろうか?アポなし訪問だったから、あのあとで用事があったのかもしれない?
仮説化)こんど同じような場面があったら、私はどうすればいいだろう?
「ねぇ、あなたは、どうして、そう、人の話聞かないんですか?いつもそうなんです?」
→(これはちょっと、直接的だなー。非難っぽいニュアンスかも?)
「なんか、すごくあわててるように見えますが、もしかしてこの後、予定かなんかあるんですか?」
「質問に答えてもらえなくて、困ってるんですけど、答えてくれないのはなにか理由があるんですか?」(指摘)と(分析)
って、あの営業マンに聞いてみたらどうなんだろう?
(聴いて見てその理由がわかったら、こちらの対応もかわってきますよね)
だけど、今の気持のまま、言ったら、戦線布告しているようなもんだな。
もっと、好意的に、「このひとかわってるなぁ」ぐらいなノリで面白がって訊けたら、面白い展開になるかもしれない。
いや、基本は「好奇心」だよな・・・と思いつつ、そこまで無邪気になれると人生楽だなぁ・・・と妙に客観的になっている私。
まぁ、こちらの気持ちを自己開示しつつ、相手に好奇心を向けてみる・・・っていうのが、きっといいんだろうな。
「好奇心」から、そして「無邪気に」
「ねぇねぇ、どうして?」
「急いでます?だって○○だから・・・」
「私の話も聞いてくださいよぅ~」
「うーん、対象になるかならないかの判断は私にさせてくださいよ(^^)」
って言えたら、何が起こったかな?(仮説化)
「体験学習の循環サイクル」をこんな風にまわして、気持のいいコミュニケーションをしませんか?
なにより自分がすっきりとできますよ。
そして、体験学習の循環サイクルは、とっても役に立つ考え方です。
この【体験学習】方法で、私はコーチングのセミナーを行っています。
また、さらに「人間関係ファシリテーション」をまさに体験学習方式で学ぶ場を実施しています。
お問い合わせくださいませ。
coach-kaneshige@nifty.com
会議の実情とファシリテーション
非営利目的の有志による活動の中での会議。年齢も、地位も、その会での経験も知識もみんなバラバラの有志の集り。
個人個人が自分の興味のあることについて思いついたことを発言し、質問していく。どんどん、どんどん、話が広がっていく。
今、何の話をしてるの?
何を決めようとしてるの?何を話のテーブルにのせてるの?
よくわからないまま、個人個人が思いつくことを、言いたいことを言っている。
そして毎回何も決まらないまま、次回へ。
そして次回、また同じことがぐるぐる回っている・・・進展しない・・・
あるときは経営者の集り、あるときは町の集り。
経営者でも、主婦や自営業でも、会議のプロセスは同じという状況を目の前にして目が白黒。
経営者の集まりでは、さすがにみなさんお忙しいので、何も決まらなくても時間になればおしまい。
なんとなく声の大きな人や、リーダーが自分の言葉でまとめて、合意形成もなく、なんとなく方向性を示して結論付けて次へ。
町の集まりでは、だらだらと時間だけが過ぎていく。
私は経験したことはないけれど、夜7時に集って翌日になるまで、会議なんてこともあるそうだ(^^;
集りに参加して日が浅いが、勇気をふりしぼって言ってみた。
「あのぉ、今何の話しているんですか?」「今やろうとしていることの目的はなんですか?」
ある経営者の集まりでは、強制参加ではなく、自主参加なのだから、発言したい人だけが発言すればいい、合意形成?そんなもの関係ない・・。
話についてこれないものは、それだけの興味なのだから参加しなくてもいい。
・・・・そうなのかな?
「今話してることの目的は?」
「今ざっくばらんに話すところから、自由に思い付きを話すことからいいアイデアや思いもしなかったことがでてくるかもしれないだろう?そんないちいち合意形成して、この話をしましょうなんてやってたらアイデアでてこないよ」
自主参加の会議だからそうしてるというのですか?本当に?
町の会議では・・・
「今何の話してるんですか?」という問いに誰もわからなかった・・・
「今日の会議の目的は?」・・・・・ようやくスタート地点に立った。
別の集まりでの会議。
リーダーの声がけで、どんどん、いろんなことが決まっていく。でも、なにか取り残されているかんじ。
メンバーの温度差。どうして、それが決まったのか、よくわからない。
わかってないのは私だけ?他の皆さんはどう思っているんですか?
問いかけても自主的に話してくれないのは、ここは安全な場じゃないっていうことだなぁ。
話し手の目を見て聴いていると、それがいつのまにか私に対して話しかけるようになっている。周りを見回すと、目をあわさないようにしている人もいる。
目が合うと、役目が指名されるんだ。だから目を合わせないようにしてるんだ。なるほど・・・
理屈で指摘しても、伝わらない。やっぱりプロセス(自分の中で起こっていること)を出していくことが、キーを握るとかんじた。
たとえ会議であっても。
「指名されて、戸惑っている。役割を決める前に、何をするのかを話しあってからでないと納得して引き受けられる感じがしない」「私にはここがよくわからない。みなさんはどう理解されているんですか?納得されてますか?」
結局何も決まらなかったけど、振り出しに戻って、みんなが同じテーブルに乗れたような気がする。それぞれが思っていることを言う場が生まれた。
私のできること、役割はやはり、ファシリテーターでありコーチ。
課題達成したいのはヤマヤマだし、性分的にもそうしたいけど、そのためにもプロセスを大事にしないと成功しないと思う。第一、私がその課題達成に向けて納得してなきゃ、ベストをつくせない。
参加者としてのファシリテーション、磨いていこう。
(2005年6月の日記より)
個人個人が自分の興味のあることについて思いついたことを発言し、質問していく。どんどん、どんどん、話が広がっていく。
今、何の話をしてるの?
何を決めようとしてるの?何を話のテーブルにのせてるの?
よくわからないまま、個人個人が思いつくことを、言いたいことを言っている。
そして毎回何も決まらないまま、次回へ。
そして次回、また同じことがぐるぐる回っている・・・進展しない・・・
あるときは経営者の集り、あるときは町の集り。
経営者でも、主婦や自営業でも、会議のプロセスは同じという状況を目の前にして目が白黒。
経営者の集まりでは、さすがにみなさんお忙しいので、何も決まらなくても時間になればおしまい。
なんとなく声の大きな人や、リーダーが自分の言葉でまとめて、合意形成もなく、なんとなく方向性を示して結論付けて次へ。
町の集まりでは、だらだらと時間だけが過ぎていく。
私は経験したことはないけれど、夜7時に集って翌日になるまで、会議なんてこともあるそうだ(^^;
集りに参加して日が浅いが、勇気をふりしぼって言ってみた。
「あのぉ、今何の話しているんですか?」「今やろうとしていることの目的はなんですか?」
ある経営者の集まりでは、強制参加ではなく、自主参加なのだから、発言したい人だけが発言すればいい、合意形成?そんなもの関係ない・・。
話についてこれないものは、それだけの興味なのだから参加しなくてもいい。
・・・・そうなのかな?
「今話してることの目的は?」
「今ざっくばらんに話すところから、自由に思い付きを話すことからいいアイデアや思いもしなかったことがでてくるかもしれないだろう?そんないちいち合意形成して、この話をしましょうなんてやってたらアイデアでてこないよ」
自主参加の会議だからそうしてるというのですか?本当に?
町の会議では・・・
「今何の話してるんですか?」という問いに誰もわからなかった・・・
「今日の会議の目的は?」・・・・・ようやくスタート地点に立った。
別の集まりでの会議。
リーダーの声がけで、どんどん、いろんなことが決まっていく。でも、なにか取り残されているかんじ。
メンバーの温度差。どうして、それが決まったのか、よくわからない。
わかってないのは私だけ?他の皆さんはどう思っているんですか?
問いかけても自主的に話してくれないのは、ここは安全な場じゃないっていうことだなぁ。
話し手の目を見て聴いていると、それがいつのまにか私に対して話しかけるようになっている。周りを見回すと、目をあわさないようにしている人もいる。
目が合うと、役目が指名されるんだ。だから目を合わせないようにしてるんだ。なるほど・・・
理屈で指摘しても、伝わらない。やっぱりプロセス(自分の中で起こっていること)を出していくことが、キーを握るとかんじた。
たとえ会議であっても。
「指名されて、戸惑っている。役割を決める前に、何をするのかを話しあってからでないと納得して引き受けられる感じがしない」「私にはここがよくわからない。みなさんはどう理解されているんですか?納得されてますか?」
結局何も決まらなかったけど、振り出しに戻って、みんなが同じテーブルに乗れたような気がする。それぞれが思っていることを言う場が生まれた。
私のできること、役割はやはり、ファシリテーターでありコーチ。
課題達成したいのはヤマヤマだし、性分的にもそうしたいけど、そのためにもプロセスを大事にしないと成功しないと思う。第一、私がその課題達成に向けて納得してなきゃ、ベストをつくせない。
参加者としてのファシリテーション、磨いていこう。
(2005年6月の日記より)
体験学習の循環サイクルとファシリテーション
【体験をする】→
【何がそこで起こっていたのか指摘する】→
【その理由を分析する】→
【(学んだことを次に活かすべく)仮説化する】→
【(仮説化したことを検証・試してみる)体験する】→・・・また指摘・分析とつづいていく・・
上記が体験学習の循環過程(循環サイクルともいう)といいます。
図が書けなくてごめんなさい。
私たちは、何かを体験したとき、このサイクルを逆に回してしまう。
【体験をする】
(パートナーに話をきいてもらおうと一生懸命話すが、聴いてもらえていないとかんじた)
→【仮説化する】
(この人はいつも話を聴かない。この人に話しても無駄だ)
このような考え方でいると、いつまでたっても同じ繰り返しで、相手の新しい面に気がつかないばかりか、関係も固着してしまう。
このケースではいずれ、パートナーと話をすることをあきらめ、会話の無いふたりになってしまうかもしれない。
「体験学習の循環サイクル」
で考えるとこういう風になる。
【体験をする】
(パートナーに話をしたが、聞いてもらえないと感じた)
→【何が起こっていたのか指摘する】
(彼の視線は定まらず、キョロキョロしているかんじだった)
→【指摘した事象をなぜだろうと分析してみる・あるいは相手になぜ?とたずねてみる】
→(気になる事があったのかもしれない)
→【(次によりよい関係をつくるために)仮説化する】
→「今聞いてほしいことがあるんだけど、いい?」と許可をとる。落ち着かないようだったら、別の時に仕切り直しをする。
体験したことから学習をして、次の関係を作る一歩を手に入れることができる。
仮説にもとづいて行動しても上手くいかなかったら、また新たに洞察をして、別の行動選択ができるし、よく相手の様子を見て、直接関わる事も出来る。
「話を聞いてほしいんだけど・・・(キョロキョロしているようだったら)何か気になる事があるの?」
最初から決め付け(仮説化)しないで、そこで起こっていることをよく思い出して、分析し、新しい行動を選択する事ができます。
慣れてきたら、その場で、相手を良く見て関わる事でよりよい関係を作っていくことが出来ます。(ファシリテーション)
人間関係は体験学習で学び、そしてそれを、「今ここ」で活用できるようになる事・・・「いまここで」関わっていく事・・・
ファシリテーションの一歩です。
【何がそこで起こっていたのか指摘する】→
【その理由を分析する】→
【(学んだことを次に活かすべく)仮説化する】→
【(仮説化したことを検証・試してみる)体験する】→・・・また指摘・分析とつづいていく・・
上記が体験学習の循環過程(循環サイクルともいう)といいます。
図が書けなくてごめんなさい。
私たちは、何かを体験したとき、このサイクルを逆に回してしまう。
【体験をする】
(パートナーに話をきいてもらおうと一生懸命話すが、聴いてもらえていないとかんじた)
→【仮説化する】
(この人はいつも話を聴かない。この人に話しても無駄だ)
このような考え方でいると、いつまでたっても同じ繰り返しで、相手の新しい面に気がつかないばかりか、関係も固着してしまう。
このケースではいずれ、パートナーと話をすることをあきらめ、会話の無いふたりになってしまうかもしれない。
「体験学習の循環サイクル」
で考えるとこういう風になる。
【体験をする】
(パートナーに話をしたが、聞いてもらえないと感じた)
→【何が起こっていたのか指摘する】
(彼の視線は定まらず、キョロキョロしているかんじだった)
→【指摘した事象をなぜだろうと分析してみる・あるいは相手になぜ?とたずねてみる】
→(気になる事があったのかもしれない)
→【(次によりよい関係をつくるために)仮説化する】
→「今聞いてほしいことがあるんだけど、いい?」と許可をとる。落ち着かないようだったら、別の時に仕切り直しをする。
体験したことから学習をして、次の関係を作る一歩を手に入れることができる。
仮説にもとづいて行動しても上手くいかなかったら、また新たに洞察をして、別の行動選択ができるし、よく相手の様子を見て、直接関わる事も出来る。
「話を聞いてほしいんだけど・・・(キョロキョロしているようだったら)何か気になる事があるの?」
最初から決め付け(仮説化)しないで、そこで起こっていることをよく思い出して、分析し、新しい行動を選択する事ができます。
慣れてきたら、その場で、相手を良く見て関わる事でよりよい関係を作っていくことが出来ます。(ファシリテーション)
人間関係は体験学習で学び、そしてそれを、「今ここ」で活用できるようになる事・・・「いまここで」関わっていく事・・・
ファシリテーションの一歩です。
「似てる」「違う」を手放す(2)
相手の話を聞きながら、「私も同じ」「似てる」って思うことってありませんか?
そうすると、相手の話が終わったとみるやいなや、
「私の場合は、こんなかんじ」という、いかに自分たちが似ているかという証明をしたくなって、余分な言葉や説明を付け加えてしまいがちです。
「似てる」話をされた相手は、おそらく、微妙なニュアンスの違いに戸惑い、その微妙なニュアンスの違いを伝えたくなって・・・
結局、相手が本当に伝えたかった事は聞けなくなってしまうかもしれない。
もちろん「一緒だ~♪」と盛り上がることもあるでしょう。
でも、「似てるな」と感じながらもそれを脇において、よくよく聞いていると、本当はぜんぜん「違う」部分が見えてきたり、相手の一番言いたいことが聴こえてきたりします。
傾聴のコツは、「自分のことに意識」がいってしまったら、それをちょっと脇において、目の前の相手に興味関心を向け続けること、これがまず、第一歩。
(私と似てる)も(私と違う)も手放すことです。
それをわかっているのに、「この人私と似てる」と一部の話のことだけのことじゃなくて「方向性、大事にしているもの、感覚的なもの」の一致感を持ってしまった相手とは、甘えがでちゃうんですね。そこからの気づきはこちらです。
そうすると、相手の話が終わったとみるやいなや、
「私の場合は、こんなかんじ」という、いかに自分たちが似ているかという証明をしたくなって、余分な言葉や説明を付け加えてしまいがちです。
「似てる」話をされた相手は、おそらく、微妙なニュアンスの違いに戸惑い、その微妙なニュアンスの違いを伝えたくなって・・・
結局、相手が本当に伝えたかった事は聞けなくなってしまうかもしれない。
もちろん「一緒だ~♪」と盛り上がることもあるでしょう。
でも、「似てるな」と感じながらもそれを脇において、よくよく聞いていると、本当はぜんぜん「違う」部分が見えてきたり、相手の一番言いたいことが聴こえてきたりします。
傾聴のコツは、「自分のことに意識」がいってしまったら、それをちょっと脇において、目の前の相手に興味関心を向け続けること、これがまず、第一歩。
(私と似てる)も(私と違う)も手放すことです。
それをわかっているのに、「この人私と似てる」と一部の話のことだけのことじゃなくて「方向性、大事にしているもの、感覚的なもの」の一致感を持ってしまった相手とは、甘えがでちゃうんですね。そこからの気づきはこちらです。
タグ :傾聴
ファシリテーション授業の感想
専門学校での2008年度最後の授業での感想をアップします。
最後の授業。
授業の最初に立てた目標を見ながら、お互いを認め合っていましたね。
そして、みなさんが、それぞれ、自分の成長を実感されている様子がわかって、とても嬉しいです。
みなさんありがとう。来年度もよろしく!
*****きづいた事学んだ事、感想など*******
後期の授業を通して、自分で立てた目標(内なる想いを言葉にする)を少しでも達成できたと思えたこと、また他のメンバーがそれを認めてくれたことがうれしかった。
心にわだかまりを持ったまま議論を進めていっても、グループにも良くないし、最終的に良い結果が得られないと思う。今日は自分にそれが起こったことではあるが良い経験になったと思う。また、グループに悩んでいる人がいれば、察知し、介入していくことも大切だと思った。ファシリテーション演習は来年度もあるようなので、全体のふりかえりをして、しっかりと自分の中に落とし込んでおきたいと思います。また、日常生活でもどんどん活用していきたいです。
・今回ファシリテーターを体験して、改めてそこで何が起きているのか様子をしっかりみる大切さがわかりました。見ることによって中で起きていることにも気付くことができると思いました。
・話が盛り上がっている時は、みんなが納得のいくように見守り待ってみることのも大事だと思いました。そのこともその時の状況を見て判断する。
授業のはじめに、人前で話す、緊張しない、場の雰囲気を読むなどの目標を決めて、今思うと達成できたと思うので、この成果をほかの場面でも生かせるようになりたいです。
ファシリテーション演習の授業を受けて、今まで気にしていなかったことに目を向け、関わるうちに、違う視点を持てるようになったと思います。
今後は出来る限り、まずは議論の内容の核心となる部分は何なのかをはっきりさせてから話し合いを開始したい。以前も、何かの話し合いで似たような感想を持った気がするのだが、どうもしっかり覚えていなかったらしい。また来年度もよろしくお願いいたします。
・授業のはじめに書いた目標に、近づけていると自分で実感できたのがうれしかったです。
・自分が最後にファシリテーターをやったときに、ふりかえりでメンバーに「自然に話を進められていた」と指摘されて、少しはうまくできていたのかとうれしかったです。
・授業で身につけたこと・学んだことを、今度は日常や仕事の場で実践できるようになることです。
・兼重さん、半年間ありがとうございました。みんなにもありがとう。途中、ファシリテーターがうまくできてなくて悩んだり、ファシリテーションを勉強する意味が見えなかったりしましたが、半年勉強して、納得もできたし自分の成長も実感できたので、よかったと思います。
自分を含め全員に、この授業の成果が確実に現れている。とくに僕の場合は、「他人の気持ちを尊重する」、「よく考えて効果的な発言をする」、「わからないことやあまり関心のないことでも流さず確認する」、「意見を集約しまとめる」といった、今までわりと苦手だった部分で顕著な成果が現れているように思う。
前述したこの授業での成果は、現在おこなっている仕事の中で即活かせると思う。
もともと感覚的に動くタイプの人間なので、今までは、会議とか、議論を展開したり、アイデアを出したり、といった行為がわずらわしくあまり好きではなかったが、この授業のおかげか、そういった行為もあまり苦にならなくなった。むしろ、現在はそれを重要なこととしてとらえることができるようになった。それもこれからの仕事の中で必ず活きてくると思う。
自分が最初にあげた目標である、「理論や実践力の習得」ということよりも、むしろ他者との関わり方、コミュニケーション、自分自身の考え方の変化など、違った部分での成長が大きかったように思う。
最後の授業。
授業の最初に立てた目標を見ながら、お互いを認め合っていましたね。
そして、みなさんが、それぞれ、自分の成長を実感されている様子がわかって、とても嬉しいです。
みなさんありがとう。来年度もよろしく!
*****きづいた事学んだ事、感想など*******
後期の授業を通して、自分で立てた目標(内なる想いを言葉にする)を少しでも達成できたと思えたこと、また他のメンバーがそれを認めてくれたことがうれしかった。
心にわだかまりを持ったまま議論を進めていっても、グループにも良くないし、最終的に良い結果が得られないと思う。今日は自分にそれが起こったことではあるが良い経験になったと思う。また、グループに悩んでいる人がいれば、察知し、介入していくことも大切だと思った。ファシリテーション演習は来年度もあるようなので、全体のふりかえりをして、しっかりと自分の中に落とし込んでおきたいと思います。また、日常生活でもどんどん活用していきたいです。
・今回ファシリテーターを体験して、改めてそこで何が起きているのか様子をしっかりみる大切さがわかりました。見ることによって中で起きていることにも気付くことができると思いました。
・話が盛り上がっている時は、みんなが納得のいくように見守り待ってみることのも大事だと思いました。そのこともその時の状況を見て判断する。
授業のはじめに、人前で話す、緊張しない、場の雰囲気を読むなどの目標を決めて、今思うと達成できたと思うので、この成果をほかの場面でも生かせるようになりたいです。
ファシリテーション演習の授業を受けて、今まで気にしていなかったことに目を向け、関わるうちに、違う視点を持てるようになったと思います。
今後は出来る限り、まずは議論の内容の核心となる部分は何なのかをはっきりさせてから話し合いを開始したい。以前も、何かの話し合いで似たような感想を持った気がするのだが、どうもしっかり覚えていなかったらしい。また来年度もよろしくお願いいたします。
・授業のはじめに書いた目標に、近づけていると自分で実感できたのがうれしかったです。
・自分が最後にファシリテーターをやったときに、ふりかえりでメンバーに「自然に話を進められていた」と指摘されて、少しはうまくできていたのかとうれしかったです。
・授業で身につけたこと・学んだことを、今度は日常や仕事の場で実践できるようになることです。
・兼重さん、半年間ありがとうございました。みんなにもありがとう。途中、ファシリテーターがうまくできてなくて悩んだり、ファシリテーションを勉強する意味が見えなかったりしましたが、半年勉強して、納得もできたし自分の成長も実感できたので、よかったと思います。
自分を含め全員に、この授業の成果が確実に現れている。とくに僕の場合は、「他人の気持ちを尊重する」、「よく考えて効果的な発言をする」、「わからないことやあまり関心のないことでも流さず確認する」、「意見を集約しまとめる」といった、今までわりと苦手だった部分で顕著な成果が現れているように思う。
前述したこの授業での成果は、現在おこなっている仕事の中で即活かせると思う。
もともと感覚的に動くタイプの人間なので、今までは、会議とか、議論を展開したり、アイデアを出したり、といった行為がわずらわしくあまり好きではなかったが、この授業のおかげか、そういった行為もあまり苦にならなくなった。むしろ、現在はそれを重要なこととしてとらえることができるようになった。それもこれからの仕事の中で必ず活きてくると思う。
自分が最初にあげた目標である、「理論や実践力の習得」ということよりも、むしろ他者との関わり方、コミュニケーション、自分自身の考え方の変化など、違った部分での成長が大きかったように思う。
「似てる」「違う」を手放す(1)
都会から知人がやってきた。
数年前の勉強会で出会い、その後同じ勉強会で2、3回会って、そのあとの懇親会で少しお話したぐらいの仲。
良い意味で、「自分とは違う人だなぁ」というかんじが最初の印象で、なぜかちょっと気になる人だった。
私は、戸隠や黒姫などの素敵な場所を案内するのが大好き。
そんな場所で、お互いの話をしていると、より、相手が身近に感じたり、相手の思いや、ひととなりを聴いたり感じたりできる。そんな気がする。
そして、どんな人といても、いつの間にかその場と自分たちが溶け合っている瞬間がある。
たとえば都会でバリバリの会社員。
「次は何する?」
先を考えてしまって、「いまここ」を十分味わうことなく次に意識がいってしまうひとも、ふと気がつく瞬間がある。
そんなきづきに立ち会うのも大好き。
今回の知人は、こちらがナビゲートする必要もなく、自分から味わいにいく人だったなので、私はおもてなし側として、相手のペースにあわせていれば良かったのだけど、そのペースは、私にとっても心地よいものだった。
もしかしたら、知らないうちに相手が私に合わせていたのかもしれないけど。
何度も訪れる場所も、そのときそのときで違う表情を見せてくれるのだけど、
それに加え、彼の好奇心は、私に新しい体験を与えてくれた。
そして、食事しながら、お茶しながら・・・たくさんたくさん、おしゃべりしたなぁ。よく話がつきないよね。ふたりとも。

十輪 冬の珈琲(グラスの中で雪が降ってます)

 胡桃割り
胡桃割り
「私とは違う」って、何を見て感じたのかな。
違うけど、同じものを大事にしているんだなって思う発見があった。
「似てる」「違う」
それにとらわれると、真実が見えなくなる。
そういうものもすべて手放して、いまここを見ていこう。
そんなことをあらためて思う。
知人と友人の境目ってなんだろう。
もうこのひとは単なる知り合いじゃなくて、かなり近しいお友達だな。
きてくれてありがとう。
たくさんのギフトをいただきました。
数年前の勉強会で出会い、その後同じ勉強会で2、3回会って、そのあとの懇親会で少しお話したぐらいの仲。
良い意味で、「自分とは違う人だなぁ」というかんじが最初の印象で、なぜかちょっと気になる人だった。
私は、戸隠や黒姫などの素敵な場所を案内するのが大好き。
そんな場所で、お互いの話をしていると、より、相手が身近に感じたり、相手の思いや、ひととなりを聴いたり感じたりできる。そんな気がする。
そして、どんな人といても、いつの間にかその場と自分たちが溶け合っている瞬間がある。
たとえば都会でバリバリの会社員。
「次は何する?」
先を考えてしまって、「いまここ」を十分味わうことなく次に意識がいってしまうひとも、ふと気がつく瞬間がある。
そんなきづきに立ち会うのも大好き。
今回の知人は、こちらがナビゲートする必要もなく、自分から味わいにいく人だったなので、私はおもてなし側として、相手のペースにあわせていれば良かったのだけど、そのペースは、私にとっても心地よいものだった。
もしかしたら、知らないうちに相手が私に合わせていたのかもしれないけど。
何度も訪れる場所も、そのときそのときで違う表情を見せてくれるのだけど、
それに加え、彼の好奇心は、私に新しい体験を与えてくれた。
そして、食事しながら、お茶しながら・・・たくさんたくさん、おしゃべりしたなぁ。よく話がつきないよね。ふたりとも。

十輪 冬の珈琲(グラスの中で雪が降ってます)

 胡桃割り
胡桃割り「私とは違う」って、何を見て感じたのかな。
違うけど、同じものを大事にしているんだなって思う発見があった。
「似てる」「違う」
それにとらわれると、真実が見えなくなる。
そういうものもすべて手放して、いまここを見ていこう。
そんなことをあらためて思う。
知人と友人の境目ってなんだろう。
もうこのひとは単なる知り合いじゃなくて、かなり近しいお友達だな。
きてくれてありがとう。
たくさんのギフトをいただきました。
意図的に「ほおっておく」ことを選択する
「身の回りに起こっていること」について
あなたはどんな風に解釈していますか?
何にも考えない?
これはなんのメッセージ?と意味づけしようとする?
「自分の課題」について
あなたはどんな風に取り組んでいますか?
何も考えない?
学びを行動に変え、成長しようとする?
しっくりくる感覚がないとき。
次にどうしたら良いのか、どうしてもわからないとき。
いつまでもそれを握り締めて、「いま」がおろそかになるくらいだったら、
熟成が必要っていうことかもしれません。
いつまでもきにかけているよりも、
きちんと意志を持って、「ほおっておく(考えない)」と決める。
そうすると、きがかりがひとつ減ってすっきりしますよ。
意図的に選択して放置する
あなたはどんな風に解釈していますか?
何にも考えない?
これはなんのメッセージ?と意味づけしようとする?
「自分の課題」について
あなたはどんな風に取り組んでいますか?
何も考えない?
学びを行動に変え、成長しようとする?
しっくりくる感覚がないとき。
次にどうしたら良いのか、どうしてもわからないとき。
いつまでもそれを握り締めて、「いま」がおろそかになるくらいだったら、
熟成が必要っていうことかもしれません。
いつまでもきにかけているよりも、
きちんと意志を持って、「ほおっておく(考えない)」と決める。
そうすると、きがかりがひとつ減ってすっきりしますよ。
意図的に選択して放置する
タグ :未完了
はじめました
新しくブログを開設しました。
東京から長野に来て、コーチングや、souceやファシリテーションを通じて活動しています。
活動場所は黒姫・戸隠で、緑あふれる自然環境豊かなこの場所で、伝えていきたい、体験してほしい、感じてほしいことがあります。
自分らしく、イキイキ生きるには
1)大好きなことは優先順位をつけたり、あきらめたりせずにすべて継続していく事。
2)自分の生きる方向性を知ること(目標ではなくて)。
3)自分も相手も大事にしたコミュニケーションをとること。
と思っています。
人と人と関係しながら、ノウハウではなくて、体験を通じて感じ取る・・そんな場の提供をしています。
それは「学び方を学ぶ」場でもあります。
このブログでは、そんな活動の中から身につけた学び方を使い、私自身が自分を使って実験している・・・そんな学びや、きづきをつづっていきます。
赤裸々に綴っていきます。
読者のかたがたとは違う考え方もあるかもしれませんが、こんな考え方もあるんだなぁと、ひとつの選択肢となれば嬉しいです。
また、ファシリテーションやコーチング、自分らしい生き方にまつわる情報もお伝えしていきます。
東京から長野に来て、コーチングや、souceやファシリテーションを通じて活動しています。
活動場所は黒姫・戸隠で、緑あふれる自然環境豊かなこの場所で、伝えていきたい、体験してほしい、感じてほしいことがあります。
自分らしく、イキイキ生きるには
1)大好きなことは優先順位をつけたり、あきらめたりせずにすべて継続していく事。
2)自分の生きる方向性を知ること(目標ではなくて)。
3)自分も相手も大事にしたコミュニケーションをとること。
と思っています。
人と人と関係しながら、ノウハウではなくて、体験を通じて感じ取る・・そんな場の提供をしています。
それは「学び方を学ぶ」場でもあります。
このブログでは、そんな活動の中から身につけた学び方を使い、私自身が自分を使って実験している・・・そんな学びや、きづきをつづっていきます。
赤裸々に綴っていきます。
読者のかたがたとは違う考え方もあるかもしれませんが、こんな考え方もあるんだなぁと、ひとつの選択肢となれば嬉しいです。
また、ファシリテーションやコーチング、自分らしい生き方にまつわる情報もお伝えしていきます。