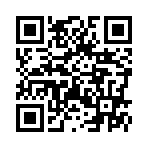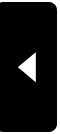あなたのファンを増やす(接客応対)
タイトルのようなねらいの、接客応対プログラムを実施していますが。
まさに、この日、私は「ファン」になってしまいました。
研修で時々訪れる「スペースアルファ神戸」でのことです。
今回はここで1泊2日の研修予定でした。
私はこの朝、トラブルがあり、出先でスカートを汚されてしまったのです。
しかしながら、荷物を少なくしたかったので、着替えが最小限しかなく、しかも、その汚れ成分には油が入っていたこともあり、どうしてもスカートをクリーニングにだしたいと思っていました。
スペースアルファに到着するなり、受付でクリーニングサービスについて問い合わせたところ、残念ながら当日は祝日で、出入りのクリーニング業者さんはお休みとのこと。
困ったなと事情を話したところ、「近くで即日仕上げのところを問い合わせてみます」との心強い言葉。
この言葉だけでも本当にありがたいことです。
その後、車で5分ほどの距離の駅のそばのクリーニング屋で、即日仕上げ可能との情報を入手してくれました。しかしながら、午前中に預けないとだめとのこと。
余裕を持って会場入りしたけど、すでに研修開始予定は迫っており、休み時間に移動するにしてもタクシーを呼ばないと間に合いそうもない。
仕方なく、感謝を伝えて、明日の朝一番のクリーニングで妥協した。
ところが。
再度連絡が入り、出入りの業者さんが、休日にもかかわらず対応してくれるとのことで、受付にスカートを預けることで、私の願いはかなえられたのです!
すごい!
ここまでしてくれるなんて。
本当に感動してしまいました。
ありがとうSさん。
私は、Sさんのファンになりました。
私はスペースアルファ神戸の話が出たら、きっとこの話も伝えるし、気合を入れて、この施設をお勧めするでしょう。
Sさんに感謝。
まさに、この日、私は「ファン」になってしまいました。
研修で時々訪れる「スペースアルファ神戸」でのことです。
今回はここで1泊2日の研修予定でした。
私はこの朝、トラブルがあり、出先でスカートを汚されてしまったのです。
しかしながら、荷物を少なくしたかったので、着替えが最小限しかなく、しかも、その汚れ成分には油が入っていたこともあり、どうしてもスカートをクリーニングにだしたいと思っていました。
スペースアルファに到着するなり、受付でクリーニングサービスについて問い合わせたところ、残念ながら当日は祝日で、出入りのクリーニング業者さんはお休みとのこと。
困ったなと事情を話したところ、「近くで即日仕上げのところを問い合わせてみます」との心強い言葉。
この言葉だけでも本当にありがたいことです。
その後、車で5分ほどの距離の駅のそばのクリーニング屋で、即日仕上げ可能との情報を入手してくれました。しかしながら、午前中に預けないとだめとのこと。
余裕を持って会場入りしたけど、すでに研修開始予定は迫っており、休み時間に移動するにしてもタクシーを呼ばないと間に合いそうもない。
仕方なく、感謝を伝えて、明日の朝一番のクリーニングで妥協した。
ところが。
再度連絡が入り、出入りの業者さんが、休日にもかかわらず対応してくれるとのことで、受付にスカートを預けることで、私の願いはかなえられたのです!
すごい!
ここまでしてくれるなんて。
本当に感動してしまいました。
ありがとうSさん。
私は、Sさんのファンになりました。
私はスペースアルファ神戸の話が出たら、きっとこの話も伝えるし、気合を入れて、この施設をお勧めするでしょう。
Sさんに感謝。
接客応対を体験学習する
「接客応対」というと、通常、マナー研修みたいな・・・・どんな風に挨拶して、言葉遣いはこうで、おじぎはこんなかんじ・・・
名刺の渡し方は・・・
っていう、「正しい作法」みたいな「答え」のあるものを「教え」て、「練習」する研修だと思う。
この時期、新入社員さんたちはそういう、研修を受けてるのではないかな?
私は・・・実は外資系企業にいたせいか、そういうのが、とてもゆるく・・・
いまだ、よくわかっていない・・・っていうか、覚える気がないのね。
たぶん、学生時代には学んだはずで、新人のころは一生懸命やっていたとは思うのですが。
人事・労務部門にいたせいもあり、社員が私のお客様。
となると、とおりいっぺんのお作法や言葉遣いは、逆に関係作りに阻害になったりするのです。
私の場合は、最初に配属されたのが、工場や技術センターのある事業所だったこともあり、地元の気のいいおじさんとか、理系バリバリのひととかでね、極端で。
学校で勉強したとおりに、丁寧に応対すればするほど、「すましてる」「きつい」みたいなうわさが聞こえてくるの。
よく見たら、まわりの先輩方は、近所の方々とおしゃべりするような対応だったり、ですます調だけど、フレンドリー。
相手を尊重しつつ、親しみのこもった対応なわけです。
それで、そっちに切り替えたら、その事業所中のほとんどの人(1000人近くいる)と知り合いになれて、向こうも親しみをもってくれた。顔と名前が一致しない・・電話だけのやりとりだったヒトもたくさんいたけどね。
だけど、本社に移動になったら、営業さんとか企画のひととかがいて、外部のお客さんとやり取りをしている方々がたくさんいると、そういうかたがたは、またちょっと違うニュアンスなのよね。
もちろん、知り合って仲良くなったらまた変わってくるけど。
そんなことを、相手とのやりとりを通じて、体感しながら、学んでいったかんじがある。
この人とは最初はこんな距離感、しばらくたったら、このぐらい・・・顔なじみになったらこんなかんじ・・・
まさに体験学習。
とはいえ、やたら丁寧な言葉遣いや、やたら腰の低い、マナーばっちりですっていうような営業マンさんに会うと、私はとっても居心地悪くて、相手に合わせられないのです。
そういう人も、こちらに合わせてくれるといいのになぁ。
てなわけで、私は接客応対を「教える」ことは出来ないんですが、そういうことをみんなで「考え」たり「体験」したことから、学んだりする場を作るのは大好きです。
一通りのマナーはわかっているけど、さらに一歩進んだ、お客様との対応を学びたい、あるいは学んで欲しいと思っている研修担当や上司の方々、ご検討くださいませ。
リピーターを増やす、あなたのファンを増やす研修です。
名刺の渡し方は・・・
っていう、「正しい作法」みたいな「答え」のあるものを「教え」て、「練習」する研修だと思う。
この時期、新入社員さんたちはそういう、研修を受けてるのではないかな?
私は・・・実は外資系企業にいたせいか、そういうのが、とてもゆるく・・・
いまだ、よくわかっていない・・・っていうか、覚える気がないのね。
たぶん、学生時代には学んだはずで、新人のころは一生懸命やっていたとは思うのですが。
人事・労務部門にいたせいもあり、社員が私のお客様。
となると、とおりいっぺんのお作法や言葉遣いは、逆に関係作りに阻害になったりするのです。
私の場合は、最初に配属されたのが、工場や技術センターのある事業所だったこともあり、地元の気のいいおじさんとか、理系バリバリのひととかでね、極端で。
学校で勉強したとおりに、丁寧に応対すればするほど、「すましてる」「きつい」みたいなうわさが聞こえてくるの。
よく見たら、まわりの先輩方は、近所の方々とおしゃべりするような対応だったり、ですます調だけど、フレンドリー。
相手を尊重しつつ、親しみのこもった対応なわけです。
それで、そっちに切り替えたら、その事業所中のほとんどの人(1000人近くいる)と知り合いになれて、向こうも親しみをもってくれた。顔と名前が一致しない・・電話だけのやりとりだったヒトもたくさんいたけどね。
だけど、本社に移動になったら、営業さんとか企画のひととかがいて、外部のお客さんとやり取りをしている方々がたくさんいると、そういうかたがたは、またちょっと違うニュアンスなのよね。
もちろん、知り合って仲良くなったらまた変わってくるけど。
そんなことを、相手とのやりとりを通じて、体感しながら、学んでいったかんじがある。
この人とは最初はこんな距離感、しばらくたったら、このぐらい・・・顔なじみになったらこんなかんじ・・・
まさに体験学習。
とはいえ、やたら丁寧な言葉遣いや、やたら腰の低い、マナーばっちりですっていうような営業マンさんに会うと、私はとっても居心地悪くて、相手に合わせられないのです。
そういう人も、こちらに合わせてくれるといいのになぁ。
てなわけで、私は接客応対を「教える」ことは出来ないんですが、そういうことをみんなで「考え」たり「体験」したことから、学んだりする場を作るのは大好きです。
一通りのマナーはわかっているけど、さらに一歩進んだ、お客様との対応を学びたい、あるいは学んで欲しいと思っている研修担当や上司の方々、ご検討くださいませ。
リピーターを増やす、あなたのファンを増やす研修です。
穂高養生園で10日間の非構成的エンカウンターグループ
穂高養生園で10日間の非構成的エンカウンターグループのご案内です。
私もお世話になった橋本久仁彦さんの今後あるかどうか?という長期間のエンカウンターグループのご案内が届きましたので、皆さんにもお知らせです。
どんな場になるんでしょうね?
もしも、この記事を見て参加された方がいらしたら、是非、感想をシェアしていただきたいな♪
主催のリビングワールドの西村さんもワークショップをされている方。
ファシリテーションやワークショップに関心のある方はきっと、そそられる人たちが参加するんじゃないかしら。
出会いも楽しみですね。
****以下、ご案内をそのままコピペしました***************
橋本久仁彦さんと12名で、はじめての“9泊10日”
年に一度、橋本久仁彦さんをファシリテータにむかえ、安曇野の森の快適な建物を丸ごと借りておこなっている、
非構成的エンカウンターグループ。
例年・4泊5日でやってきましたが、今年は9泊10日間のロングステイで開催します。
非構成でかつ10日間というワークショップは、橋本さんも、主催者のわたしたちも初めての体験。
養生園の美味しい食事と温泉と、山の紅葉を楽しみながら、10日間の流れを味わいたいと思います。
ぜひお越しください。
日時 :2009年11月4日(水)?13日(金)
集合 11/4(水)15:00 現地集合
解散 11/13(金)13:00頃
ファシリテータ:橋本久仁彦
主催 :リビングワールド(西村佳哲・西村たりほ)
場所 :穂高養生園・森の家/長野県 穂高
参加費:70,000円
宿泊費:10,000円×9泊(食費含む)
定員 :12ー15名
なぜ10日間?
理由はいくつかあります。ひとつには、滞在地の穂高養生園がとても気持ちの良い場所で、
食事も美味しいので、もっと長く滞在してみたくなった。
ここのマクロビ・メニューの質には、毎年満たされる思いがします。
養生園ではヨガやマッサージや針灸などのプログラムをうけることも出来るのですが、
5日間の日程では、その時間がとれなかった。
今年は期間中、半日ほどのフリータイムを入れようと思います。
カール・ロジャース(非構成的エンカウンターグループの創始者)等は1970年代、
当初2週間ほどの長期セッションを開いていたようです。
日本でも以前は一週間ほどのセッションが盛んだったようですが、次第に短くなり、
現在、私たちが開催してきた4泊5日は長い方です(2泊3日ほどのものが多い)。
そこで2週間はありませんが、10日間(昨年までの2倍)のセッションを一度体験してみたくなりました。
橋本さんも、これほど長いグループセッションは初めてとのこと。
ファシリテーターも初めて…という場には、いきいきとした良さが生じやすいと思っています。
非構成的エンカウンターグループとは
非構成的エンカウンターグループは、カール・ロジャース(心理学者/1902ー1987)が切り拓いたグループセッションのスタイル。
あらかじめ用意されている内容は、何もありません。集まった人々が、言葉や存在を交わして進みます。
10日間を通じて生まれるのは、再現性のない一度かぎりの場です。
「こういう体験が出来ます」とか「学べます」といった話は書けません。すべてがその場であらわれ、形づくられてゆくからです。
ワークショップが、工場(ファクトリー)でも教室でもなく文字通り「工房」であり、
お互いを活かし合ってなにかをつくり出す試みの場であるなら、非構成的エンカウンターグループは
その貴重な一例だと思います。?
◎お申込み方法:
以下の事項を、2009/9/11(金)までにお送りください。
・お名前:?
・連絡用メールアドレス:(複数可)?
・連絡用電話番号:
・ご住所:
・ご年齢:
・性別:
・お仕事・専攻など:(差し支えのない範囲で結構です)
・お申込みの動機:(必ずご記入願います)
送付先:hodaka0911@livingworld.net
*お申込み多数の場合は原則抽選となりますが、早い時期にお申込みくださった方については、出来る限り優先的に扱います
◎申込完了までの流れ:
・お申込が定員を超えた場合は、抽選ないし先着順で選考させていただきます。
・申込者には、9/17(木)までに結果をご連絡します。その後一週間以内に参加費をお振り込みいただき、
その確認をもって参加申し込みの完了となります。
* 全日程の参加が前提です。
* このワークショップは治療を目的としたグループセッションではありません。
現在なんらかの治療を受けられている方は、必ず担当医またはカウンセラー/セラピストらとご相談の上、
参加をご検討ください。また、お申込み時にはその旨お伝えください。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◎非構成的エンカウンターグループについて
自分たち(リビングワールドの西村佳哲・たりほ)は、2006年秋にはじめてこのワークショップを体験し、感銘を受けました。
このワークショップに感銘を受けた、という言い方はちょっと違うかな。
このワークショップの方法によって生まれた場に感銘を受けた、という方が正しい。
やっていたのは、五日間、車座になって語り合った。
ただそれだけです。
ただそれだけのことなのですが、振り返ってみるとそれは、大陸を歩いて横断するような五日間でした。
話が横道にそれるようですが、僕らは1999年から仲間達と「サウンドバム」という旅を開催しています。
音を聴きに出かける旅のプロジェクトです。
この旅には、カメラの代わりにレコーダー(録音機)を持って出かけます。
宿の窓辺や、街の市場、朝の森で音を録っていると、それまで聞こえていたはずなのに聴いていなかった、
様々な音が、耳に飛び込んでくるようになります。
風が木のこずえを鳴らしてゆく音、遠くから近づいてくる雨、枝にとまる鳥、子どもを呼ぶ母親の声、車のクラクション、
ある時は自分の呼吸の音も。
最初その旅から帰った時は、一年ぐらい音楽を聴く気になれなかった。
世界はすでに音に溢れていて、その音でもう十分に嬉しい自分に気づいてしまったからです。
抽象的な説明で恐縮ですが、僕にとって非構成的エンカウンターグループでの体験はこれに似ています。
なにがどうなるかはその時々の話だと思うので、これ以上の説明はひかえますね。
いずれにせよ現在の日本には、あまり体験できる機会がありません。
このワークショップの特徴のひとつは、時間を要すること。
当初ロジャースとその仲間たちは、1週間ないし2週間ほどの日程で行っていたとか。
手法が一般化してゆく過程で次第に短くなり、10年以上前に橋本さんが学んでいた頃は、三泊四日が多かったそうです。
では思い切って、四泊五日の贅沢なエンカウンターグループを実施してみよう!と開催してみたのが、2006年の秋。
きわめて好評であり、かつ私たちにとっても掛け替えのない体験となったので、
年に一回のペースでつづけているわけですが、9泊10日間のロングステイは今年が初めてです。
安曇野の渓谷ぞいの森の中に、穂高養生園という自然療法の施設が建てた「森の家」という快適な施設を借り切って開催します。
自然も食事も素晴らしく、スタッフも気持ちいい。近くにいい温泉があり、養生園のお風呂も温泉。
旅も学びも、基本は一人だと思います。
でも一人ではいけない、体験できない旅もあるなあと思うんです。
西村佳哲
2009-1-3(昨年の文章を改訂して)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
詳細と西村氏についてはリビングワールドHPをご覧ください。
http://www.livingworld.net/schedule/
私もお世話になった橋本久仁彦さんの今後あるかどうか?という長期間のエンカウンターグループのご案内が届きましたので、皆さんにもお知らせです。
どんな場になるんでしょうね?
もしも、この記事を見て参加された方がいらしたら、是非、感想をシェアしていただきたいな♪
主催のリビングワールドの西村さんもワークショップをされている方。
ファシリテーションやワークショップに関心のある方はきっと、そそられる人たちが参加するんじゃないかしら。
出会いも楽しみですね。
****以下、ご案内をそのままコピペしました***************
橋本久仁彦さんと12名で、はじめての“9泊10日”
年に一度、橋本久仁彦さんをファシリテータにむかえ、安曇野の森の快適な建物を丸ごと借りておこなっている、
非構成的エンカウンターグループ。
例年・4泊5日でやってきましたが、今年は9泊10日間のロングステイで開催します。
非構成でかつ10日間というワークショップは、橋本さんも、主催者のわたしたちも初めての体験。
養生園の美味しい食事と温泉と、山の紅葉を楽しみながら、10日間の流れを味わいたいと思います。
ぜひお越しください。
日時 :2009年11月4日(水)?13日(金)
集合 11/4(水)15:00 現地集合
解散 11/13(金)13:00頃
ファシリテータ:橋本久仁彦
主催 :リビングワールド(西村佳哲・西村たりほ)
場所 :穂高養生園・森の家/長野県 穂高
参加費:70,000円
宿泊費:10,000円×9泊(食費含む)
定員 :12ー15名
なぜ10日間?
理由はいくつかあります。ひとつには、滞在地の穂高養生園がとても気持ちの良い場所で、
食事も美味しいので、もっと長く滞在してみたくなった。
ここのマクロビ・メニューの質には、毎年満たされる思いがします。
養生園ではヨガやマッサージや針灸などのプログラムをうけることも出来るのですが、
5日間の日程では、その時間がとれなかった。
今年は期間中、半日ほどのフリータイムを入れようと思います。
カール・ロジャース(非構成的エンカウンターグループの創始者)等は1970年代、
当初2週間ほどの長期セッションを開いていたようです。
日本でも以前は一週間ほどのセッションが盛んだったようですが、次第に短くなり、
現在、私たちが開催してきた4泊5日は長い方です(2泊3日ほどのものが多い)。
そこで2週間はありませんが、10日間(昨年までの2倍)のセッションを一度体験してみたくなりました。
橋本さんも、これほど長いグループセッションは初めてとのこと。
ファシリテーターも初めて…という場には、いきいきとした良さが生じやすいと思っています。
非構成的エンカウンターグループとは
非構成的エンカウンターグループは、カール・ロジャース(心理学者/1902ー1987)が切り拓いたグループセッションのスタイル。
あらかじめ用意されている内容は、何もありません。集まった人々が、言葉や存在を交わして進みます。
10日間を通じて生まれるのは、再現性のない一度かぎりの場です。
「こういう体験が出来ます」とか「学べます」といった話は書けません。すべてがその場であらわれ、形づくられてゆくからです。
ワークショップが、工場(ファクトリー)でも教室でもなく文字通り「工房」であり、
お互いを活かし合ってなにかをつくり出す試みの場であるなら、非構成的エンカウンターグループは
その貴重な一例だと思います。?
◎お申込み方法:
以下の事項を、2009/9/11(金)までにお送りください。
・お名前:?
・連絡用メールアドレス:(複数可)?
・連絡用電話番号:
・ご住所:
・ご年齢:
・性別:
・お仕事・専攻など:(差し支えのない範囲で結構です)
・お申込みの動機:(必ずご記入願います)
送付先:hodaka0911@livingworld.net
*お申込み多数の場合は原則抽選となりますが、早い時期にお申込みくださった方については、出来る限り優先的に扱います
◎申込完了までの流れ:
・お申込が定員を超えた場合は、抽選ないし先着順で選考させていただきます。
・申込者には、9/17(木)までに結果をご連絡します。その後一週間以内に参加費をお振り込みいただき、
その確認をもって参加申し込みの完了となります。
* 全日程の参加が前提です。
* このワークショップは治療を目的としたグループセッションではありません。
現在なんらかの治療を受けられている方は、必ず担当医またはカウンセラー/セラピストらとご相談の上、
参加をご検討ください。また、お申込み時にはその旨お伝えください。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◎非構成的エンカウンターグループについて
自分たち(リビングワールドの西村佳哲・たりほ)は、2006年秋にはじめてこのワークショップを体験し、感銘を受けました。
このワークショップに感銘を受けた、という言い方はちょっと違うかな。
このワークショップの方法によって生まれた場に感銘を受けた、という方が正しい。
やっていたのは、五日間、車座になって語り合った。
ただそれだけです。
ただそれだけのことなのですが、振り返ってみるとそれは、大陸を歩いて横断するような五日間でした。
話が横道にそれるようですが、僕らは1999年から仲間達と「サウンドバム」という旅を開催しています。
音を聴きに出かける旅のプロジェクトです。
この旅には、カメラの代わりにレコーダー(録音機)を持って出かけます。
宿の窓辺や、街の市場、朝の森で音を録っていると、それまで聞こえていたはずなのに聴いていなかった、
様々な音が、耳に飛び込んでくるようになります。
風が木のこずえを鳴らしてゆく音、遠くから近づいてくる雨、枝にとまる鳥、子どもを呼ぶ母親の声、車のクラクション、
ある時は自分の呼吸の音も。
最初その旅から帰った時は、一年ぐらい音楽を聴く気になれなかった。
世界はすでに音に溢れていて、その音でもう十分に嬉しい自分に気づいてしまったからです。
抽象的な説明で恐縮ですが、僕にとって非構成的エンカウンターグループでの体験はこれに似ています。
なにがどうなるかはその時々の話だと思うので、これ以上の説明はひかえますね。
いずれにせよ現在の日本には、あまり体験できる機会がありません。
このワークショップの特徴のひとつは、時間を要すること。
当初ロジャースとその仲間たちは、1週間ないし2週間ほどの日程で行っていたとか。
手法が一般化してゆく過程で次第に短くなり、10年以上前に橋本さんが学んでいた頃は、三泊四日が多かったそうです。
では思い切って、四泊五日の贅沢なエンカウンターグループを実施してみよう!と開催してみたのが、2006年の秋。
きわめて好評であり、かつ私たちにとっても掛け替えのない体験となったので、
年に一回のペースでつづけているわけですが、9泊10日間のロングステイは今年が初めてです。
安曇野の渓谷ぞいの森の中に、穂高養生園という自然療法の施設が建てた「森の家」という快適な施設を借り切って開催します。
自然も食事も素晴らしく、スタッフも気持ちいい。近くにいい温泉があり、養生園のお風呂も温泉。
旅も学びも、基本は一人だと思います。
でも一人ではいけない、体験できない旅もあるなあと思うんです。
西村佳哲
2009-1-3(昨年の文章を改訂して)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
詳細と西村氏についてはリビングワールドHPをご覧ください。
http://www.livingworld.net/schedule/
記録係をするということの効用と、メンバーとの関係性について
会議などで、議事録をとるための記録ではなく、
議題から話し合いが離れず、有効な話し合いとなるための整理ツールとして、
板書したり、ホワイトボードを活用されたり、されているだろうか?
先日の会議ファシリテーションのセミナーでも、参加者の中で、記録経験のあるのは、わずかだったし、いつも活用しているわけではないという。
私自身がこれまで、参加してきた、異業種交流会や、町の会議でも、活用されているのを見たことがない。(私が勝手に書き出すことはあっても)
セミナーでは模造紙の利用をお勧めしている。
私の模造紙活用との出会いは、新潟でまちづくり活動を実施しているファシリテーターの活動で「ファシリテーショングラフィック」の存在を知ってから。
しかし企業や、一般の活動で、「グラフィック」を使わなかったとしても、模造紙の活用は、有効だ。
今回セミナーを実施して、参加者もその効用や利便性にめからうろこのようだった。
* 議論が、離れていっても、テーマを記載してある事で、戻しやすい
* 発言を記録する事で、同じところをぐるぐるしづらい
* 話し合いの軌跡を見ることが出来るので、これまでに出ていた発言を活用しやすい
* 次回の会議の際に、前回の模造紙を見ることで、経過や結論を思い出し、すぐに議題に入りやすい
などなど。
早速、模造紙を活用すること、ペンはマッキーではなく
にじみ・裏うつりなし!基本の8色セット三菱鉛筆 水性顔料マーカー プロッキー8色セット 太字+細字プロッキーねと、メモする人も。
以上は「記録の有効性」についてなんだけど、今回は「記録係をすることの有効性」について。
会議ファシリテーションのセミナーでは「ファシリテーター兼グラフィカ」として、進行役と記録係を兼ねて体験していただくのだが、昨日は、専門学校の授業(人間関係ファシリテーションの切り口)で、記録係と進行役を別れて別々の方が担当した。
今回「記録係=グラフィカ」の役割については「決まったことをまとめて記録するのではなく、議論を有効に進めるためのツールとして記録するんだよ」「テーマと日付だけは最初に書いておいてね」とだけ伝えて、模造紙とプロッキーを渡した。
グラフィカを担当したのは、普段、他者の発言や議題について促進するようなかかわりというのはほとんどみられなかった人なのだけど、グラフィカをしながらの自然なかかわりにびっくり。
記録をする為に、確認をしたり質問をしたり。記録に集中してしまって聞き漏らしたからもう一度言って~とお願いしたり。
それが、その場にとても貢献していた。
記録に対しても、色を変えたり、線で囲ったり、見やすい工夫が。
慣れないせいもあって、他者の発言を自分なりの解釈で自分の言葉で記録してしまうことは時にあったとしても、それが、上手く機能していたり、「それはちょっと違うかも」
と記録を見たメンバーが訂正の発言をしたりして、相互のかかわりが生まれていた。
グラフィカをするというその役割を負ったことで、彼から自然な、彼らしいファシリテーションが発揮されて、私は彼の新しい一面を見た気がする。
もちろん、ファシリテーター役も、参加者であり、ファシリテーターでありという役割であったにもかかわらず、自分の意見も言いながら、議論をまとめたり、方向性を確認したりして、その場に貢献。気負いなくできたと本人も言う。
メンバーそれぞれも、自分の意見をだしながら、それぞれのスタンスでファシリテーター的な動きもあり、「素敵なチームになったなぁ」と半年担当して、生徒さん達の成長ぶりに感動。
これまで自分が内側で考えている事や感じている事を出すのは苦手だったり、あえてださなかったひとが、自然にそれを出す事が出来ているのは、このメンバーだからだと言っていたけど、なぜ、そういうことが出来るようになったのか。
そんなことももっともっと是非分析して、他の場面でもいかしてほしいなぁ。
グラフィカをする役割から、必然的にファシリテーター的な動きがでてくる効能もある程度あるとは思うけど、いつもとは言えない・・・・
だけど、今回そういうことが起こったのはなぜか?
メンバー同士が信頼し、安心して発言したり、振舞う事が出来る。そういう関係性があるからこそ、役割を負ったときも、「こうしたほうがいいのかな?」と思ったことを試す事が出来るのではないか。うまく出来なくても、誰かがフォローしてくれる・・そんな無意識の安心感からかもしれない。
「役割が人を育てる」というようなことなんだろうか?とうっすら思いながらこの記事を書き始めた。
だけど、「安心してそこにいられる、発言できる、行動できる、信頼感のある関係性」がある、そのなかでだからこそ、「役割」に対しても「こうでなければならない」に縛られてしまうのではなく、役割に必要な事を自分なりに試すことができるのでははないか、と思うにいたった。
そして役割を負うことで新たな自分を発見したり、成長したりすることが出来るのではないだろうか?
下記は私の「記録」という一面をどこで取り入れるのかから、考えた仮説だけど。
★会議ファシリテーションセミナーのように、技術的なことを体験するセミナーでは、たとえば「記録する」ということの実用的な効用を感じながら、話し合いの結果を出す事が出来る。
そして繰り返すうちに、役割の技能があがり、人間関係もすこしづつよくなっていく・・というイメージ。
★人間関係ファシリテーションセミナーからスタートすると
「安心感のある関係作り」から人間関係を先に作るので、話し合いの結果というのは、なかなかでづらい。
しかし、人間関係ができてから「記録」などの技術的なことを導入すると、効果は比較的早く現れて、会議の成果がでやすい・・・
のかなと。
技術が先か、人間関係が先かっていう、鶏と卵の関係かな。
そんなことを考えた日でした。
議題から話し合いが離れず、有効な話し合いとなるための整理ツールとして、
板書したり、ホワイトボードを活用されたり、されているだろうか?
先日の会議ファシリテーションのセミナーでも、参加者の中で、記録経験のあるのは、わずかだったし、いつも活用しているわけではないという。
私自身がこれまで、参加してきた、異業種交流会や、町の会議でも、活用されているのを見たことがない。(私が勝手に書き出すことはあっても)
セミナーでは模造紙の利用をお勧めしている。
私の模造紙活用との出会いは、新潟でまちづくり活動を実施しているファシリテーターの活動で「ファシリテーショングラフィック」の存在を知ってから。
しかし企業や、一般の活動で、「グラフィック」を使わなかったとしても、模造紙の活用は、有効だ。
今回セミナーを実施して、参加者もその効用や利便性にめからうろこのようだった。
* 議論が、離れていっても、テーマを記載してある事で、戻しやすい
* 発言を記録する事で、同じところをぐるぐるしづらい
* 話し合いの軌跡を見ることが出来るので、これまでに出ていた発言を活用しやすい
* 次回の会議の際に、前回の模造紙を見ることで、経過や結論を思い出し、すぐに議題に入りやすい
などなど。
早速、模造紙を活用すること、ペンはマッキーではなく

にじみ・裏うつりなし!基本の8色セット三菱鉛筆 水性顔料マーカー プロッキー8色セット 太字+細字プロッキーねと、メモする人も。
以上は「記録の有効性」についてなんだけど、今回は「記録係をすることの有効性」について。
会議ファシリテーションのセミナーでは「ファシリテーター兼グラフィカ」として、進行役と記録係を兼ねて体験していただくのだが、昨日は、専門学校の授業(人間関係ファシリテーションの切り口)で、記録係と進行役を別れて別々の方が担当した。
今回「記録係=グラフィカ」の役割については「決まったことをまとめて記録するのではなく、議論を有効に進めるためのツールとして記録するんだよ」「テーマと日付だけは最初に書いておいてね」とだけ伝えて、模造紙とプロッキーを渡した。
グラフィカを担当したのは、普段、他者の発言や議題について促進するようなかかわりというのはほとんどみられなかった人なのだけど、グラフィカをしながらの自然なかかわりにびっくり。
記録をする為に、確認をしたり質問をしたり。記録に集中してしまって聞き漏らしたからもう一度言って~とお願いしたり。
それが、その場にとても貢献していた。
記録に対しても、色を変えたり、線で囲ったり、見やすい工夫が。
慣れないせいもあって、他者の発言を自分なりの解釈で自分の言葉で記録してしまうことは時にあったとしても、それが、上手く機能していたり、「それはちょっと違うかも」
と記録を見たメンバーが訂正の発言をしたりして、相互のかかわりが生まれていた。
グラフィカをするというその役割を負ったことで、彼から自然な、彼らしいファシリテーションが発揮されて、私は彼の新しい一面を見た気がする。
もちろん、ファシリテーター役も、参加者であり、ファシリテーターでありという役割であったにもかかわらず、自分の意見も言いながら、議論をまとめたり、方向性を確認したりして、その場に貢献。気負いなくできたと本人も言う。
メンバーそれぞれも、自分の意見をだしながら、それぞれのスタンスでファシリテーター的な動きもあり、「素敵なチームになったなぁ」と半年担当して、生徒さん達の成長ぶりに感動。
これまで自分が内側で考えている事や感じている事を出すのは苦手だったり、あえてださなかったひとが、自然にそれを出す事が出来ているのは、このメンバーだからだと言っていたけど、なぜ、そういうことが出来るようになったのか。
そんなことももっともっと是非分析して、他の場面でもいかしてほしいなぁ。
グラフィカをする役割から、必然的にファシリテーター的な動きがでてくる効能もある程度あるとは思うけど、いつもとは言えない・・・・
だけど、今回そういうことが起こったのはなぜか?
メンバー同士が信頼し、安心して発言したり、振舞う事が出来る。そういう関係性があるからこそ、役割を負ったときも、「こうしたほうがいいのかな?」と思ったことを試す事が出来るのではないか。うまく出来なくても、誰かがフォローしてくれる・・そんな無意識の安心感からかもしれない。
「役割が人を育てる」というようなことなんだろうか?とうっすら思いながらこの記事を書き始めた。
だけど、「安心してそこにいられる、発言できる、行動できる、信頼感のある関係性」がある、そのなかでだからこそ、「役割」に対しても「こうでなければならない」に縛られてしまうのではなく、役割に必要な事を自分なりに試すことができるのでははないか、と思うにいたった。
そして役割を負うことで新たな自分を発見したり、成長したりすることが出来るのではないだろうか?
下記は私の「記録」という一面をどこで取り入れるのかから、考えた仮説だけど。
★会議ファシリテーションセミナーのように、技術的なことを体験するセミナーでは、たとえば「記録する」ということの実用的な効用を感じながら、話し合いの結果を出す事が出来る。
そして繰り返すうちに、役割の技能があがり、人間関係もすこしづつよくなっていく・・というイメージ。
★人間関係ファシリテーションセミナーからスタートすると
「安心感のある関係作り」から人間関係を先に作るので、話し合いの結果というのは、なかなかでづらい。
しかし、人間関係ができてから「記録」などの技術的なことを導入すると、効果は比較的早く現れて、会議の成果がでやすい・・・
のかなと。
技術が先か、人間関係が先かっていう、鶏と卵の関係かな。
そんなことを考えた日でした。
チームワーク育成ワークショップと指導者研修
東京と、長野で、野外教育・体験学習などに携わるかたがた向けの研修があります。
研究発表や事例発表を通して、参加者同士の体験学習についての考え方や、関連団体の活動の交流も行い、さらなるスキル向上の場とするもの・・だそうです。
長野県会場は信濃町のラボランドくろひめであり、私が非常勤講師をさせていただいている国際自然環境アウトドア専門学校も後援しています。
【5/17・5/20-21 ティームワーク育成ワークショップと指導者研修】
アメリカの体験教育とティームワーク育成の第一人者であるジム・ケイン氏を迎えて、野外教育、体験教育、スポーツなどの指導者、そして指導者をめざす人のためのワークショップと研修会を実施します。
キーノートワークショップ
日 程:5 月17 日(日) 10:00~18:30
会 場:ガールスカウト会館(東京都渋谷区)
定 員:80 名(定員になり次第締め切ります)
参加費:一般3,000 円 学生2,000 円
プラクティカルワークショップ
日 程:5 月20 日(水)~21日(木)
会 場:ラボランドくろひめ(長野県信濃町)
定 員:40 名(定員になり次第締め切ります)
参加費:一般15,000 円 学生9,000 円
問合せ:camp-meeting@lep.jp
(ラボ教育センター教育事業局内)
講師紹介
Dr. Jim Cain(ジム・ケイン氏)
ロチェスター大学大学院でPh.D 取得。チャレンジコースの開発に携わるとともに、チャレンジコースを活用した教育・研修プログラムの作成にも携わっている。
teamworkandteamplay.com(Jim Cain氏のホームページ)
プログラムの詳細はこちらのちらしをご覧ください。
研究発表や事例発表を通して、参加者同士の体験学習についての考え方や、関連団体の活動の交流も行い、さらなるスキル向上の場とするもの・・だそうです。
長野県会場は信濃町のラボランドくろひめであり、私が非常勤講師をさせていただいている国際自然環境アウトドア専門学校も後援しています。
【5/17・5/20-21 ティームワーク育成ワークショップと指導者研修】
アメリカの体験教育とティームワーク育成の第一人者であるジム・ケイン氏を迎えて、野外教育、体験教育、スポーツなどの指導者、そして指導者をめざす人のためのワークショップと研修会を実施します。
キーノートワークショップ
日 程:5 月17 日(日) 10:00~18:30
会 場:ガールスカウト会館(東京都渋谷区)
定 員:80 名(定員になり次第締め切ります)
参加費:一般3,000 円 学生2,000 円
プラクティカルワークショップ
日 程:5 月20 日(水)~21日(木)
会 場:ラボランドくろひめ(長野県信濃町)
定 員:40 名(定員になり次第締め切ります)
参加費:一般15,000 円 学生9,000 円
問合せ:camp-meeting@lep.jp
(ラボ教育センター教育事業局内)
講師紹介
Dr. Jim Cain(ジム・ケイン氏)
ロチェスター大学大学院でPh.D 取得。チャレンジコースの開発に携わるとともに、チャレンジコースを活用した教育・研修プログラムの作成にも携わっている。
teamworkandteamplay.com(Jim Cain氏のホームページ)
プログラムの詳細はこちらのちらしをご覧ください。
臨時総会と議長
臨時総会って、もめるって本当? ちょっと前の出来事ですが。
いわゆる「総会」っていうのは、「1号議案」拍手~「2号議案」拍手~って、しゃんしゃんって終わる形だけなものしか、参加したことがなかったから、あんまり考えてなかった。
(ファシリやってるのに、それってどうよと自己突っ込み)
総会の議長は、シナリオどおりに、議事をすすめて、おしまいという役割だと、なんとなく思っていた自分に気がつく。
かといって、この人数をファシリテートしながら、満足する総会にするイメージが、すぐにはわかない。私の中で、「総会」の議長は、まじめくさって、決まったことしか話せないような、これまでの経験からの固定イメージがあった。
で、実際。
M議長。ほれぼれ。
「総会」なのに場を和ませる。「総会」なのに、笑わせる。「誰も意見を言わないと、指しますよ♪」だって。
そういうキャラクターだった?
そんな「総会」でたことない。
丁寧に議事をすすめ、どう、質問していいのか、どう意見を言ったらいいのか、わからないような人もいたように思うけど、そんな人たちの声をちゃんと吸い上げる。
話したそうな人に声をかける。
ここで回答すること、持ち帰って検討することを、区別する。
ああ、ファシリテーターだ。
議長も。
最初に時間を決め、協力を促し、場を和ませ、話しやすい雰囲気を作る。
議案を整理し、自分の言葉で簡潔に聞く。その時間をフルに使って意見をだしてもらう。
話したそうな人に声をかけ、難しい顔をしたひとに、声をかける。
相手の言いたいことを整理し、適切な方にふっていく。
結果、荒れることはなく、ある程度活発な意見交換がなされ、無事可決。
これが、誰も発言もしない会だったら、不満も残っただろう。
参加者の思いも受け取った。
自分が三役で「回答側」に座るなんて、始まるまでわかっていなかったおおぼけだった私だけど、適切な人が適切なわかりやすい回答をしてくれ「ああ、なんてこの会は役者がそろっているんだろう」。勝手に感動。
(昔、60人くらい出席してるのに、議長もいない、レジュメもない総会をやってた組織だったってことは、すっかり忘却のかなた(^^;) ちなみに、その際に私は、ぺーぺーなのに、思わず黒板だしてきて、進行やってました(^^;)
M議長のふるまいに、私もリラックスして、質問者の意図を明確にすることができて、私の役割も果たせたかなぁ。
「総会」ってつまらないものだと思っていたけど、見方がかわりました。
誰も彼も、ひとりひとりが、大切な役割を果たし、参加していた総会でした。
M議長。ありがとう。
新鮮な体験でした。
いわゆる「総会」っていうのは、「1号議案」拍手~「2号議案」拍手~って、しゃんしゃんって終わる形だけなものしか、参加したことがなかったから、あんまり考えてなかった。
(ファシリやってるのに、それってどうよと自己突っ込み)
総会の議長は、シナリオどおりに、議事をすすめて、おしまいという役割だと、なんとなく思っていた自分に気がつく。
かといって、この人数をファシリテートしながら、満足する総会にするイメージが、すぐにはわかない。私の中で、「総会」の議長は、まじめくさって、決まったことしか話せないような、これまでの経験からの固定イメージがあった。
で、実際。
M議長。ほれぼれ。
「総会」なのに場を和ませる。「総会」なのに、笑わせる。「誰も意見を言わないと、指しますよ♪」だって。
そういうキャラクターだった?
そんな「総会」でたことない。
丁寧に議事をすすめ、どう、質問していいのか、どう意見を言ったらいいのか、わからないような人もいたように思うけど、そんな人たちの声をちゃんと吸い上げる。
話したそうな人に声をかける。
ここで回答すること、持ち帰って検討することを、区別する。
ああ、ファシリテーターだ。
議長も。
最初に時間を決め、協力を促し、場を和ませ、話しやすい雰囲気を作る。
議案を整理し、自分の言葉で簡潔に聞く。その時間をフルに使って意見をだしてもらう。
話したそうな人に声をかけ、難しい顔をしたひとに、声をかける。
相手の言いたいことを整理し、適切な方にふっていく。
結果、荒れることはなく、ある程度活発な意見交換がなされ、無事可決。
これが、誰も発言もしない会だったら、不満も残っただろう。
参加者の思いも受け取った。
自分が三役で「回答側」に座るなんて、始まるまでわかっていなかったおおぼけだった私だけど、適切な人が適切なわかりやすい回答をしてくれ「ああ、なんてこの会は役者がそろっているんだろう」。勝手に感動。
(昔、60人くらい出席してるのに、議長もいない、レジュメもない総会をやってた組織だったってことは、すっかり忘却のかなた(^^;) ちなみに、その際に私は、ぺーぺーなのに、思わず黒板だしてきて、進行やってました(^^;)
M議長のふるまいに、私もリラックスして、質問者の意図を明確にすることができて、私の役割も果たせたかなぁ。
「総会」ってつまらないものだと思っていたけど、見方がかわりました。
誰も彼も、ひとりひとりが、大切な役割を果たし、参加していた総会でした。
M議長。ありがとう。
新鮮な体験でした。
コミュニケーション力
某日帰り温泉施設で。
マッサージ20分と温泉入浴で2000円というチケットをもらったので、試してみる事にする。
私は、肩と首のコリがひどいので、ときどき、あちこちのマッサージを利用する。
チケットを差し出し、これでお願いしますと言うと、奥からマッサージ担当の人がでてきた。
「20分じゃなくてもいいんですよ。40分でも、60分でも」という。
「でも60分2000円ってわけじゃないでしょう?」と私。
まぁ、お金を払えば・・・ってことだろうなぁとは思いつつも、念のため、まさか、あまりにも人が来ないからといって、また、お試し一回券だからといって、そんなおいしい話はないよねと思いつつ、笑いながらたずねてみる。
マッサージ師(仮にAとする)「それじゃ、私達疲れちゃいますからね。」
私「(苦笑)・・・・・・20分で。」
マッサージ師Aは、足裏、ボディマッサージといろいろコースはあるけど、勝手にボディマッサージにまるをつける。足裏20分の希望の可能性だってあるのに、訊いてくれないんだなぁと思いつつ。
経験上、私にはボディマッサージというと、全身というイメージがあるので、
「首と肩だけの集中でお願いしたいのですが」というと
マッサージ師A「どうせ20分くらいじゃ、そのくらいしかできませんよ。全身なんかとてもとても。」
私「・・・・・・・。
腰を触ってほしくないのと、凝っているのが首と肩なので、そこを集中してほしいという希望だけです。」
マッサージ師A「腰がなにか?」
私「これこれこういうわけで」
お金を払って、お風呂に向かおうとしたら、おつりをもらうのを忘れた。
私「おつりもらうの忘れちゃった(^^)」
マッサージ師A「私は、マッサージのほうだけなので、レジは担当が違うんで(^^)」
私「・・・・・。じゃ、時間に来ますのでお願いします。」
お風呂に入りながら、ぼんやり考える。
あの人・・マッサージ師Aが担当だったらいやだなぁ。悪気は無いのはわかるんだけど・・
こちらが一言言うたびに、余計な反応をする・・・
ぜんぜんこちらの意図を汲んでくれない・・・
コミュニケーションがぶちぶちっっと切断されて、成立していない・・・
マッサージされながら、話しかけてきたらいやだなぁ。これ以上あの人と会話していると癒されずに、心ササクレ立つ気がするなぁ・・・・
さっき、奥にもうひとり、若い女性(マッサージ師B)がいたなぁ。笑顔で挨拶してくれたなぁ。あのひと(マッサージ師B)がいいなぁ。ここで我慢するのは嫌だな。
と、湯船につかりながら、ちょっとシュミレーション。
どうやって、さっきの人が担当になりそうだったら、別の人に代わってもらうか・・・・
よし、完璧。とシュミレーションを終え、時間にマッサージ室に行くと、誰も居ない。
おかしいなとおもって、振り返ったら、女の人Cとぶつかりそうになった。
「びっくりしたぁ」とその人。
「ごめんなさい」とわたし。
すると、マッサージ室の控え室に入っていく。
え?
お店の人なのに、そういう対応?私になにか声かけてくれても?
すみませーん、とその人を呼び、チケットを見せると、「ああ」と言って、温泉のほうの受付に向かう。その人(マッサージ師C)の対応はそれだけ。
受付からは、さきほど受け付けてくれた、嫌だなと思ったマッサージ師Aが走ってきた。
どうやら、私がお願いしたいと思った人(マッサージ師B)は、時間で帰ったようで、新しくさっきぶつかりそうになったマッサージ師Cが来たようだ。
お風呂でシミュレーションしたことが無駄になった。
マッサージ師Cもいまひとつだったし。
仕方なく、マッサージ師Aの指示に従う。
うーん・・
今まで何箇所か、何人かのマッサージを受けているけど、一番、首と肩の触ってほしいところを触ってくれている。つぼははずしていない。
でも・・・・痛すぎる。
痛気持ちいいのは好きなんだけど・・・
痛いと何度言った事か。
そのたび弱めてくれるんだけど、いつの間にかまた強くなる。
凝ってるから痛いのは私も相手もわかってる。
でもさー・・・・私大分我慢してるんですけど。
力づくで指圧っていうイメージ。
まぁ別の某所では男性が汗かきながら、力いっぱい、つぼじゃないところを押してたっけ。
あのひとも、何度お願いしても痛くて参った。
あそこよりはいいけど・・・・(そこには、二度と行かない。)
たぶん。
この人が、ちゃんと人の話が聴けるようになり、相手の気持ちに焦点があてられるような、コミュニケーションができるようになったら、きっと、もっといいマッサージになると思うなぁ。もったいないなぁ。
マッサージってコミュニケーションだと思うもの。
今は自分の技術に自信があって、相手を見ていないという印象。
相手の体とコミュニケーションしていないかんじ。
いいポイント触ってくれたのになあ、残念。
マッサージ20分と温泉入浴で2000円というチケットをもらったので、試してみる事にする。
私は、肩と首のコリがひどいので、ときどき、あちこちのマッサージを利用する。
チケットを差し出し、これでお願いしますと言うと、奥からマッサージ担当の人がでてきた。
「20分じゃなくてもいいんですよ。40分でも、60分でも」という。
「でも60分2000円ってわけじゃないでしょう?」と私。
まぁ、お金を払えば・・・ってことだろうなぁとは思いつつも、念のため、まさか、あまりにも人が来ないからといって、また、お試し一回券だからといって、そんなおいしい話はないよねと思いつつ、笑いながらたずねてみる。
マッサージ師(仮にAとする)「それじゃ、私達疲れちゃいますからね。」
私「(苦笑)・・・・・・20分で。」
マッサージ師Aは、足裏、ボディマッサージといろいろコースはあるけど、勝手にボディマッサージにまるをつける。足裏20分の希望の可能性だってあるのに、訊いてくれないんだなぁと思いつつ。
経験上、私にはボディマッサージというと、全身というイメージがあるので、
「首と肩だけの集中でお願いしたいのですが」というと
マッサージ師A「どうせ20分くらいじゃ、そのくらいしかできませんよ。全身なんかとてもとても。」
私「・・・・・・・。
腰を触ってほしくないのと、凝っているのが首と肩なので、そこを集中してほしいという希望だけです。」
マッサージ師A「腰がなにか?」
私「これこれこういうわけで」
お金を払って、お風呂に向かおうとしたら、おつりをもらうのを忘れた。
私「おつりもらうの忘れちゃった(^^)」
マッサージ師A「私は、マッサージのほうだけなので、レジは担当が違うんで(^^)」
私「・・・・・。じゃ、時間に来ますのでお願いします。」
お風呂に入りながら、ぼんやり考える。
あの人・・マッサージ師Aが担当だったらいやだなぁ。悪気は無いのはわかるんだけど・・
こちらが一言言うたびに、余計な反応をする・・・
ぜんぜんこちらの意図を汲んでくれない・・・
コミュニケーションがぶちぶちっっと切断されて、成立していない・・・
マッサージされながら、話しかけてきたらいやだなぁ。これ以上あの人と会話していると癒されずに、心ササクレ立つ気がするなぁ・・・・
さっき、奥にもうひとり、若い女性(マッサージ師B)がいたなぁ。笑顔で挨拶してくれたなぁ。あのひと(マッサージ師B)がいいなぁ。ここで我慢するのは嫌だな。
と、湯船につかりながら、ちょっとシュミレーション。
どうやって、さっきの人が担当になりそうだったら、別の人に代わってもらうか・・・・
よし、完璧。とシュミレーションを終え、時間にマッサージ室に行くと、誰も居ない。
おかしいなとおもって、振り返ったら、女の人Cとぶつかりそうになった。
「びっくりしたぁ」とその人。
「ごめんなさい」とわたし。
すると、マッサージ室の控え室に入っていく。
え?
お店の人なのに、そういう対応?私になにか声かけてくれても?
すみませーん、とその人を呼び、チケットを見せると、「ああ」と言って、温泉のほうの受付に向かう。その人(マッサージ師C)の対応はそれだけ。
受付からは、さきほど受け付けてくれた、嫌だなと思ったマッサージ師Aが走ってきた。
どうやら、私がお願いしたいと思った人(マッサージ師B)は、時間で帰ったようで、新しくさっきぶつかりそうになったマッサージ師Cが来たようだ。
お風呂でシミュレーションしたことが無駄になった。
マッサージ師Cもいまひとつだったし。
仕方なく、マッサージ師Aの指示に従う。
うーん・・
今まで何箇所か、何人かのマッサージを受けているけど、一番、首と肩の触ってほしいところを触ってくれている。つぼははずしていない。
でも・・・・痛すぎる。
痛気持ちいいのは好きなんだけど・・・
痛いと何度言った事か。
そのたび弱めてくれるんだけど、いつの間にかまた強くなる。
凝ってるから痛いのは私も相手もわかってる。
でもさー・・・・私大分我慢してるんですけど。
力づくで指圧っていうイメージ。
まぁ別の某所では男性が汗かきながら、力いっぱい、つぼじゃないところを押してたっけ。
あのひとも、何度お願いしても痛くて参った。
あそこよりはいいけど・・・・(そこには、二度と行かない。)
たぶん。
この人が、ちゃんと人の話が聴けるようになり、相手の気持ちに焦点があてられるような、コミュニケーションができるようになったら、きっと、もっといいマッサージになると思うなぁ。もったいないなぁ。
マッサージってコミュニケーションだと思うもの。
今は自分の技術に自信があって、相手を見ていないという印象。
相手の体とコミュニケーションしていないかんじ。
いいポイント触ってくれたのになあ、残念。
便利グッズご紹介~ホワイトボードがないときち
みなさんはホワイトボードがない場所での会議、どうしてますか?
これは簡易版ホワイトボードとでもいいましょうか。
フリーボードといいます。
これは、長い筒の中に模造紙のような紙が十枚入っているんですが、これが壁に貼りつくんです。
でこぼこした壁は一応不可ということでしたが、細かく一様のでこぼこだったせいか活用できました。
ぴったり貼りつきました。
壁にこのシートを貼り付けて、マーカーで書く。
もちろん消せます。
何回くらい使えるのかな?
いずれにせよ消耗品ではありますが、便利です。
ばっちり、問題なく使えました。
ホワイトボードが足りない。
あるいは、会場にホワイトボードがないなんてときに、会議やちょっとした講座、講演なんかでも便利です。
おすすめです~。
これは簡易版ホワイトボードとでもいいましょうか。
フリーボードといいます。
これは、長い筒の中に模造紙のような紙が十枚入っているんですが、これが壁に貼りつくんです。
でこぼこした壁は一応不可ということでしたが、細かく一様のでこぼこだったせいか活用できました。
ぴったり貼りつきました。
壁にこのシートを貼り付けて、マーカーで書く。
もちろん消せます。
何回くらい使えるのかな?
いずれにせよ消耗品ではありますが、便利です。
ばっちり、問題なく使えました。
ホワイトボードが足りない。
あるいは、会場にホワイトボードがないなんてときに、会議やちょっとした講座、講演なんかでも便利です。
おすすめです~。
言いたいことを言うことと、話を聞くということ
悪気は無いんだけど、人の話を聞けない人。
本人は「聞いてる」と思っている。
自分の考えを持っている人。
「こうするのが正しい」と信念を持っている。
だからちょっと自分と違う考えには、「そうじゃなくて」と言いたくなる。
ちゃんと聞いてるよ。でも、こっちが正しいでしょ、と言わずにはおれない。
そんなひと。
目上の人だし、悪気はないし、立場も上だし・・
なんて思うと、不満を抱えてしまう。
全然ひとのはなしを聞いてなくて、なんでも自分の考えにもっていってしまう・・・
それは正論かもしれないけど・・・・
それじゃ言いたいこと、言えなくなりますよ・・・・
こうやって、部下は自分の意見がいえなくなるんですね・・・・
と、実感する。
だけどこの方は、本当は、この場が活性化して、みんなが言いたいことが言える場になるといいと思っているのを知っている。
コミュニケーションのくせが、邪魔をするだけ。
「えー、もう~。ちゃんと話聴いてくれてますぅ?(^^;
今否定するのやめましょうよぉ?まだ、方向性や、具体的に何するかを決定するための話し合いじゃないし・・・
今はとりあえず、言いたいこと言わせてくださいな~」
たぶん、他者の意見をきいて、「否定」の意見をもったことを「あなた」が言うのは「言いたいことをいうこと」だと思っているんですよね。「聞いている」から意見が言えるのよと思っているんですね。
でも、意見を言うたびに、だれかが(あなたが)否定していたら、だれも、「言いたいこと」がいえなくなりませんか?
そして、あなたの意見を誰かが否定のニュアンスで違う意見を言ったら、引き下がらなくてその話だけで終わってしまうのを知っているから、誰も反論しないんですよ・・・・
「ここのひとたち、みんな強いから」
そうですよ。みんな頑張っています(笑)
でも、あなたの周囲の人は、そうじゃないから、自分の意見がいえなくなっているひとが、もしかしたらいませんか?
「最近の若い子は自分の意見が無くて」
本当にそうですか?
「とりあえず、それぞれの考えは、だすだけ出してから検討しましょうよ~」
伝わったかどうかはわからないけど、少なくとも私はすっきり。
相手への不満は抱えていない。
相手のほうも「そうお?だってぇー」
「まぁ、お互い言いたいこといいましょうね(^^)」
「なんだか言われちゃったわ~」というにやにやという雰囲気をかもしつつ、別にいやな雰囲気にはならない。
以前はこういう風には言えなかったな。
言えずに、不満を抱えるか、
言えたとしても不満爆発、否定とか批判モードになってしまったと思う。
だいたい、よくよく考えれば、私もこの方と同じ。
そういう発言をしてきたな。
実は似ているところがたくさんある。
そんなことも思うので、自戒の念もわきながら。
ときには、忘れて、私もこういう振る舞いをしているかもしれないんだよね。
そんなとき、責めるでもなく、きづかせてくれるひとがいることは、わたしにとってはありがたいこと。
だから、あなたもそう思ってくれていると信じている。
私はあなたが、好きだから。
コーチングやファシリテーションを学んで、本当に良かったなと思うのである。
本人は「聞いてる」と思っている。
自分の考えを持っている人。
「こうするのが正しい」と信念を持っている。
だからちょっと自分と違う考えには、「そうじゃなくて」と言いたくなる。
ちゃんと聞いてるよ。でも、こっちが正しいでしょ、と言わずにはおれない。
そんなひと。
目上の人だし、悪気はないし、立場も上だし・・
なんて思うと、不満を抱えてしまう。
全然ひとのはなしを聞いてなくて、なんでも自分の考えにもっていってしまう・・・
それは正論かもしれないけど・・・・
それじゃ言いたいこと、言えなくなりますよ・・・・
こうやって、部下は自分の意見がいえなくなるんですね・・・・
と、実感する。
だけどこの方は、本当は、この場が活性化して、みんなが言いたいことが言える場になるといいと思っているのを知っている。
コミュニケーションのくせが、邪魔をするだけ。
「えー、もう~。ちゃんと話聴いてくれてますぅ?(^^;
今否定するのやめましょうよぉ?まだ、方向性や、具体的に何するかを決定するための話し合いじゃないし・・・
今はとりあえず、言いたいこと言わせてくださいな~」
たぶん、他者の意見をきいて、「否定」の意見をもったことを「あなた」が言うのは「言いたいことをいうこと」だと思っているんですよね。「聞いている」から意見が言えるのよと思っているんですね。
でも、意見を言うたびに、だれかが(あなたが)否定していたら、だれも、「言いたいこと」がいえなくなりませんか?
そして、あなたの意見を誰かが否定のニュアンスで違う意見を言ったら、引き下がらなくてその話だけで終わってしまうのを知っているから、誰も反論しないんですよ・・・・
「ここのひとたち、みんな強いから」
そうですよ。みんな頑張っています(笑)
でも、あなたの周囲の人は、そうじゃないから、自分の意見がいえなくなっているひとが、もしかしたらいませんか?
「最近の若い子は自分の意見が無くて」
本当にそうですか?
「とりあえず、それぞれの考えは、だすだけ出してから検討しましょうよ~」
伝わったかどうかはわからないけど、少なくとも私はすっきり。
相手への不満は抱えていない。
相手のほうも「そうお?だってぇー」
「まぁ、お互い言いたいこといいましょうね(^^)」
「なんだか言われちゃったわ~」というにやにやという雰囲気をかもしつつ、別にいやな雰囲気にはならない。
以前はこういう風には言えなかったな。
言えずに、不満を抱えるか、
言えたとしても不満爆発、否定とか批判モードになってしまったと思う。
だいたい、よくよく考えれば、私もこの方と同じ。
そういう発言をしてきたな。
実は似ているところがたくさんある。
そんなことも思うので、自戒の念もわきながら。
ときには、忘れて、私もこういう振る舞いをしているかもしれないんだよね。
そんなとき、責めるでもなく、きづかせてくれるひとがいることは、わたしにとってはありがたいこと。
だから、あなたもそう思ってくれていると信じている。
私はあなたが、好きだから。
コーチングやファシリテーションを学んで、本当に良かったなと思うのである。
主張の裏側にあるもの
某所での会議にひさしぶりに参加。
事務連絡、報告事項などのあとに、「会議が発言しづらい」→「これを改善していこう」というような提案で、小グループに分かれて、討議した。
会議だけじゃなくて、これからのこの集団のありかたに発展してもいいんじゃないか?というような投げかけも。
久しぶりの参加、メンバーの顔ぶれの違い。この場の提案。
なにやら、不穏なかんじなの?私の知らないところで何がおこっていたのかしら?
なんて若干思いながらも、なんだか新鮮で、ちょっとわくわく。
まずは現状認識・・・ということで、ひとりひとりが話し始める。
さて、この「会議」が本当に発言しづらい場だったのか?
どうもそうとも言い切れないようだ。
個人の役割や参画年数(慣れ)の違いからなのか、発言しづらいと思った人と、そうでない人がいる。発言しづらいと思ったのは一部の人だけ。
でも発言するような内容があった会議だったのか?果たして報告事項ばかりではなかったか?
そんな現状を確認、区別していくと、提案してくれた人の「早く馴染みたい」「参画したい」「なにか自分がメンバーとしてできることを。貢献したい。」という思いが見え隠れしてきた。
「発言しづらい」という思いを肯定的に捉えると
「参画しているという意識を早く持ちたい。→活発なやりとりをするような会議をしたい」
「建設的な議論やプロジェクトなどの場がほしい」
そんなメッセージのように思える。
また進行役(ファシリテーター)という役割から感じる個人的ななにか・・・・
「雰囲気が悪い。誰も承認もせず、感想も話さず、表情も硬い。怒っているのか?非協力的な感じがする。これじゃ、活発な意見なんかだせる雰囲気じゃない」
→「もっとにこやかに雰囲気よく、自由な発言がなされながら会議をすすめたい。そうするべきだ。そうならないのは、問題だ」
みたいな感じがあるのかしら?このあたりは、昔、ファシリテーションの師匠にしばしば言われた事だ。
でも、本当に雰囲気が悪かったのか?
メンバーに確認すると、そうは思わないという人も多数。
私自身も・・・特に役割を背負ったときに、自分の思い描くとおりにならないとどこかで「問題だ」と思って、なんとかしようというエネルギーが働いてしまうことがある。
ときどき、点検したいところ。
もう片方のグループがどんな話をしているのか、詳細はわからないし、時間が短かったので、結論や次のアクションには至らなかったけど、いい現状認識と、意見交換会だった。
それぞれが、どんな気持ちでここに参画しているのかが見えてくる、そんな場でもあった。
そもそも、こういう場を持ちたいと発言できて、しかも時間がもてることが、開かれた場であることのように思う。
提案してくれたAさんに感謝。
事務連絡、報告事項などのあとに、「会議が発言しづらい」→「これを改善していこう」というような提案で、小グループに分かれて、討議した。
会議だけじゃなくて、これからのこの集団のありかたに発展してもいいんじゃないか?というような投げかけも。
久しぶりの参加、メンバーの顔ぶれの違い。この場の提案。
なにやら、不穏なかんじなの?私の知らないところで何がおこっていたのかしら?
なんて若干思いながらも、なんだか新鮮で、ちょっとわくわく。
まずは現状認識・・・ということで、ひとりひとりが話し始める。
さて、この「会議」が本当に発言しづらい場だったのか?
どうもそうとも言い切れないようだ。
個人の役割や参画年数(慣れ)の違いからなのか、発言しづらいと思った人と、そうでない人がいる。発言しづらいと思ったのは一部の人だけ。
でも発言するような内容があった会議だったのか?果たして報告事項ばかりではなかったか?
そんな現状を確認、区別していくと、提案してくれた人の「早く馴染みたい」「参画したい」「なにか自分がメンバーとしてできることを。貢献したい。」という思いが見え隠れしてきた。
「発言しづらい」という思いを肯定的に捉えると
「参画しているという意識を早く持ちたい。→活発なやりとりをするような会議をしたい」
「建設的な議論やプロジェクトなどの場がほしい」
そんなメッセージのように思える。
また進行役(ファシリテーター)という役割から感じる個人的ななにか・・・・
「雰囲気が悪い。誰も承認もせず、感想も話さず、表情も硬い。怒っているのか?非協力的な感じがする。これじゃ、活発な意見なんかだせる雰囲気じゃない」
→「もっとにこやかに雰囲気よく、自由な発言がなされながら会議をすすめたい。そうするべきだ。そうならないのは、問題だ」
みたいな感じがあるのかしら?このあたりは、昔、ファシリテーションの師匠にしばしば言われた事だ。
でも、本当に雰囲気が悪かったのか?
メンバーに確認すると、そうは思わないという人も多数。
私自身も・・・特に役割を背負ったときに、自分の思い描くとおりにならないとどこかで「問題だ」と思って、なんとかしようというエネルギーが働いてしまうことがある。
ときどき、点検したいところ。
もう片方のグループがどんな話をしているのか、詳細はわからないし、時間が短かったので、結論や次のアクションには至らなかったけど、いい現状認識と、意見交換会だった。
それぞれが、どんな気持ちでここに参画しているのかが見えてくる、そんな場でもあった。
そもそも、こういう場を持ちたいと発言できて、しかも時間がもてることが、開かれた場であることのように思う。
提案してくれたAさんに感謝。
その人らしい人生を支える
NHKのプロフェッショナルの流儀・・・が好きで時々観ている。
だいぶ前の放送で恐縮だけど、1月13日の放送では、地域医療に取り組む一人の医師だった。
その言葉で印象的だったのが
「その人らしい人生を支える」
たとえば、症状や痛みを抑えることがすべてという治療ではなく、患者一人一人がいきいきと過ごすためには何が必要かを考える。膝痛に悩まされながらも、グランドゴルフが生きがいのお年寄り。安静を言い渡すより、痛み止めを打ちながら、趣味を続けさせる方を選択する。患者のしこう、趣味、生活、そして人生そのものを知り、共感しているから出来る診断があるのだ。(NHKHPより)
そして「病ではなく人を診る」
コーチングの考え方も「その人らしい人生のサポート」だし
「話とか悩みではなく、その人自身を聴く」
人と関わるって言う事は究極はここなんだなと。人を中心とした関わり方・・・
そして、それが、誰でも、どんな職業においても、原則として当たり前のこととなったら、生きやすい世の中になるし、気持ちよく過ごせるんだろうなぁ。
病や、悩みの渦中にあっても、自分らしく過ごせるんだろうなぁ。
生活の中でも心に留めておきたい。
だいぶ前の放送で恐縮だけど、1月13日の放送では、地域医療に取り組む一人の医師だった。
その言葉で印象的だったのが
「その人らしい人生を支える」
たとえば、症状や痛みを抑えることがすべてという治療ではなく、患者一人一人がいきいきと過ごすためには何が必要かを考える。膝痛に悩まされながらも、グランドゴルフが生きがいのお年寄り。安静を言い渡すより、痛み止めを打ちながら、趣味を続けさせる方を選択する。患者のしこう、趣味、生活、そして人生そのものを知り、共感しているから出来る診断があるのだ。(NHKHPより)
そして「病ではなく人を診る」
コーチングの考え方も「その人らしい人生のサポート」だし
「話とか悩みではなく、その人自身を聴く」
人と関わるって言う事は究極はここなんだなと。人を中心とした関わり方・・・
そして、それが、誰でも、どんな職業においても、原則として当たり前のこととなったら、生きやすい世の中になるし、気持ちよく過ごせるんだろうなぁ。
病や、悩みの渦中にあっても、自分らしく過ごせるんだろうなぁ。
生活の中でも心に留めておきたい。
思い込みの失敗と学んだこと
ホテルにて2泊。
今回は師匠と仲間の講師1名と3人で1チームのお仕事。
初日、ふとんをかけてしばらく寝ていると暑くなって眠れない。
空調の調節を探してみるけど、みつからず、ここは全館統一なのか?
結構ちゃんとしたホテルだぞ?
そんなことないよねぇと思いつつ、暖房がはいっているわけでもなさそうなので、ふとんを剥いで、シーツで寝る。
途中寒くなってふとんをかけたけど。
翌日、上記のことを話すと「更年期じゃないの?」「自分は寒かったよ」とふたりに言われ、「えーっ(^^;」「若いから血の巡りがいいんですよ」と笑いとばす。
「空調の調節ってなかったと思うんだけど?」とたずねてみたら「ない」と仲間のTさんが言うので、同じ全館一斉システムの空調で、私だけ暑かったのかな・・・と少々微妙。
二日目の晩は、冷房が効いていて、浴衣で部屋にいると今度は寒い。
ふとんをかけて寝る。ちょうどいい。
翌朝、「昨日の晩は冷房がきいてて寒かった。更年期じゃないよ」とわけのわからぬ笑顔で言うとふたりとも変な顔をする。
私「? 空調の調節できないんじゃなかった?」
Tさん「ベットのライトの下のところにあったよ」
私「え?だって昨日たずねたら(ない)って言ったじゃない?」
Tさん「暖房と冷房の切り替えがないっていう意味だよ」
私「・・・・・」
師匠「わからなかったらフロントに電話したらよかったのに」
初日は3人とも空調がオフになっていたらしい。
二日目は冷房が入っていて、二人は自分で調整したようだ。
Tさんは初日空調はオフだったけど、寒かったので暖房にしたいと思ったが、全館冷房になっている状態で暖房にはならなかったので、私が空調調節のことについて、たずねたときも「冷房暖房の切り替えが」あるのかないのか、に聞こえたのだろう。
私は自分で軽く探しては見たものの、みつからなかったことと、Tさんが「ない」と言ったこと。そしてふたりが「寒かった」ので「調節した」という話をきかなかったので、各部屋では空調の調整ができないものと思い込んでいた。
私と相手の「思い込み」が重なって、妙な会話。
そして私は結局、特に問題はないものの、本当は手に入れられるはずのより快適な状況が手に入れられなかった。
本当に寒くて、風邪引きそうな困った状態だったら、目的を達成するために、フロントに問い合わせたり、もっとちゃんと探したりしたんだろうけど、まぁどうでもいいかと思うからこその失敗だ。
深読みすると、「その目的を達成するための思い」の強さによって、手に入れられる状況は違うのねっていうことを考えたりする。
コーチングをやっていると、頭ではそういうことを理解していても、こう身近な所で、簡単な事例を実感すると、体に落ちると言うか・・・
貪欲に自分の快適を求めるっていうのも大事ですね。
何事に対しても、妥協しないってこと。
これは自己基盤強化プログラムをもう一回やるといいかもしれないな。
今回は師匠と仲間の講師1名と3人で1チームのお仕事。
初日、ふとんをかけてしばらく寝ていると暑くなって眠れない。
空調の調節を探してみるけど、みつからず、ここは全館統一なのか?
結構ちゃんとしたホテルだぞ?
そんなことないよねぇと思いつつ、暖房がはいっているわけでもなさそうなので、ふとんを剥いで、シーツで寝る。
途中寒くなってふとんをかけたけど。
翌日、上記のことを話すと「更年期じゃないの?」「自分は寒かったよ」とふたりに言われ、「えーっ(^^;」「若いから血の巡りがいいんですよ」と笑いとばす。
「空調の調節ってなかったと思うんだけど?」とたずねてみたら「ない」と仲間のTさんが言うので、同じ全館一斉システムの空調で、私だけ暑かったのかな・・・と少々微妙。
二日目の晩は、冷房が効いていて、浴衣で部屋にいると今度は寒い。
ふとんをかけて寝る。ちょうどいい。
翌朝、「昨日の晩は冷房がきいてて寒かった。更年期じゃないよ」とわけのわからぬ笑顔で言うとふたりとも変な顔をする。
私「? 空調の調節できないんじゃなかった?」
Tさん「ベットのライトの下のところにあったよ」
私「え?だって昨日たずねたら(ない)って言ったじゃない?」
Tさん「暖房と冷房の切り替えがないっていう意味だよ」
私「・・・・・」
師匠「わからなかったらフロントに電話したらよかったのに」
初日は3人とも空調がオフになっていたらしい。
二日目は冷房が入っていて、二人は自分で調整したようだ。
Tさんは初日空調はオフだったけど、寒かったので暖房にしたいと思ったが、全館冷房になっている状態で暖房にはならなかったので、私が空調調節のことについて、たずねたときも「冷房暖房の切り替えが」あるのかないのか、に聞こえたのだろう。
私は自分で軽く探しては見たものの、みつからなかったことと、Tさんが「ない」と言ったこと。そしてふたりが「寒かった」ので「調節した」という話をきかなかったので、各部屋では空調の調整ができないものと思い込んでいた。
私と相手の「思い込み」が重なって、妙な会話。
そして私は結局、特に問題はないものの、本当は手に入れられるはずのより快適な状況が手に入れられなかった。
本当に寒くて、風邪引きそうな困った状態だったら、目的を達成するために、フロントに問い合わせたり、もっとちゃんと探したりしたんだろうけど、まぁどうでもいいかと思うからこその失敗だ。
深読みすると、「その目的を達成するための思い」の強さによって、手に入れられる状況は違うのねっていうことを考えたりする。
コーチングをやっていると、頭ではそういうことを理解していても、こう身近な所で、簡単な事例を実感すると、体に落ちると言うか・・・
貪欲に自分の快適を求めるっていうのも大事ですね。
何事に対しても、妥協しないってこと。
これは自己基盤強化プログラムをもう一回やるといいかもしれないな。
桜
池に浮かぶ桜がとってもきれいだったので。

上越高田城の桜は満開でした。
桜の下に座り、さわやかな風に吹かれ、桜吹雪を感じ、人は大勢でているけれども、のんびりと比較的静かな平日の昼下がり。
カラオケも宴会も、子どもたちのはしゃぎ声もなく、大人たちの談笑と、ぼーっとした空気の流れ。
露店が並び、異国の顔立ちのきれいなおねぇさんのいるドネルケバブを頼む。
トルコ料理なのにロシア人。
だんながトルコ人だという。
どこで知り合ったのかと、直球で訊ねたら、日本だと。
日本人男性は情けないなぁ。こんなきれいなおねぇさんを折角日本にいるのにロシア人にとられちゃうなんて。
「いや、そういうのは、よくわからない。私より彼は背が低いし、年も結構上だし・・・」
と、しばし交流。
ああ幸せ♪
上越高田城の桜は満開でした。
桜の下に座り、さわやかな風に吹かれ、桜吹雪を感じ、人は大勢でているけれども、のんびりと比較的静かな平日の昼下がり。
カラオケも宴会も、子どもたちのはしゃぎ声もなく、大人たちの談笑と、ぼーっとした空気の流れ。
露店が並び、異国の顔立ちのきれいなおねぇさんのいるドネルケバブを頼む。
トルコ料理なのにロシア人。
だんながトルコ人だという。
どこで知り合ったのかと、直球で訊ねたら、日本だと。
日本人男性は情けないなぁ。こんなきれいなおねぇさんを折角日本にいるのにロシア人にとられちゃうなんて。
「いや、そういうのは、よくわからない。私より彼は背が低いし、年も結構上だし・・・」
と、しばし交流。
ああ幸せ♪
お体のほうは大丈夫ですか?
自動車保険は、安いのでA社を使っている。
今回、被害者ではあるが、先方が保険を使わない可能性があったので、念のため、保険会社に
一報をいれておいた。
保険会社が先方と交渉するようなサービスをつけているわけではないので、本当は関係ないはずだけど、「ご連絡ありがとうございます」と詳細を聞いてくれ、注意事項を教えてくれた。
休みがあけて、今日は、担当となる保険会社の方が電話をくれ、なにかあったら、こちらに電話してくださいと番号を伝えてきた。
自分の自動車保険に車両保険をつけているので、たとえ被害者であっても、自分の車をその車両保険でなおすことができる。たぶん、相手が逃げちゃったような場合とか。
だから、そのへんのことも考えて、関わってくれているらしい。
そうか、そういう仕事か・・・と少々思いつつも、こうやって電話をくれるのは、「気に掛けて」くれている「ほおっておかれていない」という安心感がある。
また電話口に出る人が必ず体のことを尋ねてくれるのは、少々マニュアル的なニュアンスもかんじるけど、悪い気はしない。
だって、場合によってはムチウチのように、あとからでてくることもあるものね。
電話対応には各社、気をつけて、研修などしているんだろうなぁ・・・・と、違う視点で考えてる私・・・
私のやっている人間関係や、コミュニケーションに関する研修では、マニュアルのように
「こういうときは、こういうことに気をつけてこんな言葉がけを」というようなことはやらない。
だから、私自身も言葉の選び方が完璧なわけではなく、むしろ苦手なほうだったりする。
だけど、体験学習を通じて、自らの体をとおして、経験を通して感じ取ったニュアンスから出てくる言葉や「あり方」なので、応用が効く。
言葉がまずかったとしてもその「ありかた」が伝われば、カバーできる事もある。
そういう点から考えたら、このA保険会社。マニュアルにないようなことに対する応対は、
もしかしたら苦手かもしれないなぁ。
へんなところに興味がわいてきた(^^;
今回、被害者ではあるが、先方が保険を使わない可能性があったので、念のため、保険会社に
一報をいれておいた。
保険会社が先方と交渉するようなサービスをつけているわけではないので、本当は関係ないはずだけど、「ご連絡ありがとうございます」と詳細を聞いてくれ、注意事項を教えてくれた。
休みがあけて、今日は、担当となる保険会社の方が電話をくれ、なにかあったら、こちらに電話してくださいと番号を伝えてきた。
自分の自動車保険に車両保険をつけているので、たとえ被害者であっても、自分の車をその車両保険でなおすことができる。たぶん、相手が逃げちゃったような場合とか。
だから、そのへんのことも考えて、関わってくれているらしい。
そうか、そういう仕事か・・・と少々思いつつも、こうやって電話をくれるのは、「気に掛けて」くれている「ほおっておかれていない」という安心感がある。
また電話口に出る人が必ず体のことを尋ねてくれるのは、少々マニュアル的なニュアンスもかんじるけど、悪い気はしない。
だって、場合によってはムチウチのように、あとからでてくることもあるものね。
電話対応には各社、気をつけて、研修などしているんだろうなぁ・・・・と、違う視点で考えてる私・・・
私のやっている人間関係や、コミュニケーションに関する研修では、マニュアルのように
「こういうときは、こういうことに気をつけてこんな言葉がけを」というようなことはやらない。
だから、私自身も言葉の選び方が完璧なわけではなく、むしろ苦手なほうだったりする。
だけど、体験学習を通じて、自らの体をとおして、経験を通して感じ取ったニュアンスから出てくる言葉や「あり方」なので、応用が効く。
言葉がまずかったとしてもその「ありかた」が伝われば、カバーできる事もある。
そういう点から考えたら、このA保険会社。マニュアルにないようなことに対する応対は、
もしかしたら苦手かもしれないなぁ。
へんなところに興味がわいてきた(^^;
タグ :接客応対
大学院でコーチング
過去情報ですが、日経ネットによると、
神戸大学の大学院でMBAコースに在籍する社会人を対象に、管理職に部下の指導方法を伝授する「コーチング講座」をを実施したようです。
シラバスはこちら。
コーチAのプレスリリースはこちら。
大学でコーチングの講義は珍しい・・・って日経ネットカンサイの記事にはあったけど、九州の短大で非常勤講師としてクラスをもっているという知人の話を聞いたことが有るような気がするし、私も単発で、新潟だけど、入らせてもらったことはある。
これらの話は社会人対象ではなく純粋に現役の学生さん対象だったけど。
まぁ、珍しい・・・か。
メジャーじゃないっていうことかな。
というか、キャリアに関して著名な金井先生とコーチA(大手コーチ養成機関の法人専門会社)が組んでの授業ですから話題性はたっぷりです。
関連研究もされるとのこと、もう結果はでたのかな?研究結果って読んでみたいな。
いずれにせよ、大学、大学院で、コーチングが取り上げられるっていうのは嬉しいこと。
「なぜコーチングが機能するのか」みたいなところの研究の必要性を、私は感じてはいないけど、そういう学問的な部分にこだわる人もいるらしいし、大学で研究されるのもいいことかもと思う。
個人的には、教育学部にコーチングやファシリテーションを、講義ではなく、体験学習的に学ぶカリキュラムがあったり、これらをどう教育に生かすかというような研究がされるといいのになぁと思う。
学校の先生を目指す人に必須科目になってほしい。
ちなみに南山大学では教育ファシリテーションが学べます。
神戸大学の大学院でMBAコースに在籍する社会人を対象に、管理職に部下の指導方法を伝授する「コーチング講座」をを実施したようです。
シラバスはこちら。
コーチAのプレスリリースはこちら。
大学でコーチングの講義は珍しい・・・って日経ネットカンサイの記事にはあったけど、九州の短大で非常勤講師としてクラスをもっているという知人の話を聞いたことが有るような気がするし、私も単発で、新潟だけど、入らせてもらったことはある。
これらの話は社会人対象ではなく純粋に現役の学生さん対象だったけど。
まぁ、珍しい・・・か。
メジャーじゃないっていうことかな。
というか、キャリアに関して著名な金井先生とコーチA(大手コーチ養成機関の法人専門会社)が組んでの授業ですから話題性はたっぷりです。
関連研究もされるとのこと、もう結果はでたのかな?研究結果って読んでみたいな。
いずれにせよ、大学、大学院で、コーチングが取り上げられるっていうのは嬉しいこと。
「なぜコーチングが機能するのか」みたいなところの研究の必要性を、私は感じてはいないけど、そういう学問的な部分にこだわる人もいるらしいし、大学で研究されるのもいいことかもと思う。
個人的には、教育学部にコーチングやファシリテーションを、講義ではなく、体験学習的に学ぶカリキュラムがあったり、これらをどう教育に生かすかというような研究がされるといいのになぁと思う。
学校の先生を目指す人に必須科目になってほしい。
ちなみに南山大学では教育ファシリテーションが学べます。
できる人の会議に出る技術
現在、群馬県で実施する問題解決会議ファシリテーター一日セミナーの準備をしてるのです。
これは、ファシリテーターを養成するためのもの。
会議企画者、進行者用のセミナーなわけなんですが、ふと思うことが。

できる人の会議に出る技術
上記書籍の執筆者は、ビジネス系ファシリテーションの師匠なのです。
人間関係のファシリテーションを学んで、私は会議のメンバーとしてのファシリテーションを活用し、だんだんファシリテーターをやるようになってきたのを思い出す。
そうだ。
人間関係ファシリテーションの学びの場をベースに、会議参加者のためのセミナーをやったらどうかしら?
副読本として上記師匠の本を使って。
むふふ♪
いいねぇ♪
提案してみようっと。
興味あります?
これは、ファシリテーターを養成するためのもの。
会議企画者、進行者用のセミナーなわけなんですが、ふと思うことが。

できる人の会議に出る技術
上記書籍の執筆者は、ビジネス系ファシリテーションの師匠なのです。
人間関係のファシリテーションを学んで、私は会議のメンバーとしてのファシリテーションを活用し、だんだんファシリテーターをやるようになってきたのを思い出す。
そうだ。
人間関係ファシリテーションの学びの場をベースに、会議参加者のためのセミナーをやったらどうかしら?
副読本として上記師匠の本を使って。
むふふ♪
いいねぇ♪
提案してみようっと。
興味あります?
まちづくりとゆるやかな関係作り
まちづくりファシリテーターが実施する大学生対象のファシリテーター養成講座でのこと。
私はプログラムのひとつを依頼されていたのだが、早く到着したので、前の活動の様子を見学していた。
それはファシリテーター養成講座のスターティングプログラム。
ゆるやかな関係作りとしてペンキ塗りをしていた。
顔見知りではない人もいる、そんな状況から、ゆるやかな関係を作る。その体験だ。
たしかに、共同作業をするというのは、一種の連帯感が生まれる。
だけど、その様子を見て、私ったら、別の時間にこれを私にやらせてくれれば、ひとつの課題達成プログラムとして、その中から人間関係を学ぶ、ペンキ塗りワークショップができたのになぁと、ひとりごちていた。
実際の作業中何が起こっていたかというと・・・
一部の人だけがペンキをぬっていて、そのほかの人は、下準備のさび落としだけ・・・
本当は自分もペンキ塗りをやりたいと思っていたり、はしごを使っている姿に危ないと思いながら手を貸さなかったり。
手袋がほしいなぁとおもっていたり。
すれ違うときに、ぶつかって、あやうくペンキが服につきそうになったり。
いろんなことが個人の内側に、誰かと誰かの間に、グループの中で起こっている。
たしかに人間関係を学ぶための材料にはなるけど、この場で求められていたのは「ゆるやかな関係作り」という体験とその効果を実感すること。
そして、その経験を、そういう場を作っていくということに活かす事。
まちづくりにおいては、わざわざ、アイスブレークと称して、ゲームをしたり、自己紹介をしたりというのも、もちろんありだけど、必然として起こってくる共同作業を、うまく活用しながら、ゆるやかに関係を作っていくっていうことは、現実的なアプローチだなぁと私も学んだのであった。
私はプログラムのひとつを依頼されていたのだが、早く到着したので、前の活動の様子を見学していた。
それはファシリテーター養成講座のスターティングプログラム。
ゆるやかな関係作りとしてペンキ塗りをしていた。
顔見知りではない人もいる、そんな状況から、ゆるやかな関係を作る。その体験だ。
たしかに、共同作業をするというのは、一種の連帯感が生まれる。
だけど、その様子を見て、私ったら、別の時間にこれを私にやらせてくれれば、ひとつの課題達成プログラムとして、その中から人間関係を学ぶ、ペンキ塗りワークショップができたのになぁと、ひとりごちていた。
実際の作業中何が起こっていたかというと・・・
一部の人だけがペンキをぬっていて、そのほかの人は、下準備のさび落としだけ・・・
本当は自分もペンキ塗りをやりたいと思っていたり、はしごを使っている姿に危ないと思いながら手を貸さなかったり。
手袋がほしいなぁとおもっていたり。
すれ違うときに、ぶつかって、あやうくペンキが服につきそうになったり。
いろんなことが個人の内側に、誰かと誰かの間に、グループの中で起こっている。
たしかに人間関係を学ぶための材料にはなるけど、この場で求められていたのは「ゆるやかな関係作り」という体験とその効果を実感すること。
そして、その経験を、そういう場を作っていくということに活かす事。
まちづくりにおいては、わざわざ、アイスブレークと称して、ゲームをしたり、自己紹介をしたりというのも、もちろんありだけど、必然として起こってくる共同作業を、うまく活用しながら、ゆるやかに関係を作っていくっていうことは、現実的なアプローチだなぁと私も学んだのであった。
体験コーチング
某通信教育のコーチング学習システムのひとつとしての、体験コーチングを担当していたことがある。
コーチングを身につけることは必要だけど、自分にはコーチは必要ないと思っている人は多いように思う。
体験コーチングの利用者は少なかった。
かくいう、私も、最初はそうだった。
でも、なんでもそうだけど、勉強するだけじゃ、物事は身につかない。
「わかった」気になるだけ。
コーチをつけて、クライアント体験をすることで、見えてくることや腑に落ちることはいくつもあった。
もっと早くコーチをつけていたら、もっと早く身についたかもしれないと、思ったものだ。
そんな体験もあり、私がコーチングを学んだ二つ目の養成機関、CTIジャパンでコーアクティブコーチングを学んだときは、すぐにコーアクティブコーチングのコーチを雇った。
でも、私が思考型なせいか、どうしてもコーアクティブコーチングにならず、クライアント体験が不十分に思えた。
やはり、体験がないと、わからない。なぜ、そう関わるのか、そう関わるとどうなるのか。
コーチングは、「学ぶ」「実践する」「クライアント体験する」というコーチングをする側、受ける側の両方を体験することで、より深く気づき、さらに学んで、「できる」ようになっていく。と教えてもらっていたが、本当にそうだと実感をもって思う。
コーチングを受けて、「いまひとつ」の体験をすることさえもが、学びになる。
コーチングを受けて、「なるほど」という体験をすることで、意義やクライアントの気持ちが見えてくる。
コーチングを身につけてよりよい人とのかかわりをしようと思ったら、ある程度継続的にコーチを雇うといい。
余裕があったら、3ヶ月ごとにコーチを替えてみるのもいい。
コーチだって個性がある。相性がある。同じやりかたではない。
まずは体験コーチングで、相性のよさそうなコーチを探すのもひとつの方法。
体験コーチングをやっていないコーチにも、だめもとでお願いのメールをだしてみてはいかが?
★クライアント体験をしてみたいかたへ
毎月第一火曜日に長野市内の日和カフェで4人のコーチがお待ちしています。次回は5月12日(火)です。
詳細は此方をどうぞ。
コーチングを身につけることは必要だけど、自分にはコーチは必要ないと思っている人は多いように思う。
体験コーチングの利用者は少なかった。
かくいう、私も、最初はそうだった。
でも、なんでもそうだけど、勉強するだけじゃ、物事は身につかない。
「わかった」気になるだけ。
コーチをつけて、クライアント体験をすることで、見えてくることや腑に落ちることはいくつもあった。
もっと早くコーチをつけていたら、もっと早く身についたかもしれないと、思ったものだ。
そんな体験もあり、私がコーチングを学んだ二つ目の養成機関、CTIジャパンでコーアクティブコーチングを学んだときは、すぐにコーアクティブコーチングのコーチを雇った。
でも、私が思考型なせいか、どうしてもコーアクティブコーチングにならず、クライアント体験が不十分に思えた。
やはり、体験がないと、わからない。なぜ、そう関わるのか、そう関わるとどうなるのか。
コーチングは、「学ぶ」「実践する」「クライアント体験する」というコーチングをする側、受ける側の両方を体験することで、より深く気づき、さらに学んで、「できる」ようになっていく。と教えてもらっていたが、本当にそうだと実感をもって思う。
コーチングを受けて、「いまひとつ」の体験をすることさえもが、学びになる。
コーチングを受けて、「なるほど」という体験をすることで、意義やクライアントの気持ちが見えてくる。
コーチングを身につけてよりよい人とのかかわりをしようと思ったら、ある程度継続的にコーチを雇うといい。
余裕があったら、3ヶ月ごとにコーチを替えてみるのもいい。
コーチだって個性がある。相性がある。同じやりかたではない。
まずは体験コーチングで、相性のよさそうなコーチを探すのもひとつの方法。
体験コーチングをやっていないコーチにも、だめもとでお願いのメールをだしてみてはいかが?
★クライアント体験をしてみたいかたへ
毎月第一火曜日に長野市内の日和カフェで4人のコーチがお待ちしています。次回は5月12日(火)です。
詳細は此方をどうぞ。
タグ :体験コーチング
スキルじゃなくて、まずは根っこの確認を
某NPOのスタッフ向けの研修。
このNPOの活動には共感しているので、もう少しなにかできないかなぁと思う。
そういや、理事をしているNPOやまもりてんこもりでも、共通することだなぁと・・・
一方で某企業の経営者が「パートさんに会社がお金をだすといっても研修を好まない・・」という話が頭に浮かぶ。
それは、環境や、自分の興味範囲や、研修の中身や・・・いろんな要因が絡むと思う。
そして、あるボランティア団体のメンバーや、参画しているNPOのことも想像してみる・・・
プロフェッショナル意識をもってやっているのか、自分の出来る範囲で出来る事をと思っているのか、ボランティアだからこのくらいでいいと思っているのか・・・
それとも、ここからステップアップしていこうとしているか?
この活動でなにを実現していきたいと思っているのか?
それぞれのスタンスは違う。
でも、何を大事にしているのか?
この活動のどこの共感して、どんな役割をになっていこうとしているのか?
それがどのような状態を生み出す事を期待しているのか?
この活動を通じて、社会にどんな影響を生み出していこうとしているのか?
目先の・・・・スキル的なことじゃなくて、
そういう、根本的な・・・個人の根っこと、組織の目指す方向を確認する事が、まずは大事なんじゃないのかな?
それを、伝えていこう。そのための場作りをしよう。
そして、そういう組織やグループを活性化するためのお手伝いがしたいなぁと思う。
このNPOの活動には共感しているので、もう少しなにかできないかなぁと思う。
そういや、理事をしているNPOやまもりてんこもりでも、共通することだなぁと・・・
一方で某企業の経営者が「パートさんに会社がお金をだすといっても研修を好まない・・」という話が頭に浮かぶ。
それは、環境や、自分の興味範囲や、研修の中身や・・・いろんな要因が絡むと思う。
そして、あるボランティア団体のメンバーや、参画しているNPOのことも想像してみる・・・
プロフェッショナル意識をもってやっているのか、自分の出来る範囲で出来る事をと思っているのか、ボランティアだからこのくらいでいいと思っているのか・・・
それとも、ここからステップアップしていこうとしているか?
この活動でなにを実現していきたいと思っているのか?
それぞれのスタンスは違う。
でも、何を大事にしているのか?
この活動のどこの共感して、どんな役割をになっていこうとしているのか?
それがどのような状態を生み出す事を期待しているのか?
この活動を通じて、社会にどんな影響を生み出していこうとしているのか?
目先の・・・・スキル的なことじゃなくて、
そういう、根本的な・・・個人の根っこと、組織の目指す方向を確認する事が、まずは大事なんじゃないのかな?
それを、伝えていこう。そのための場作りをしよう。
そして、そういう組織やグループを活性化するためのお手伝いがしたいなぁと思う。
問題解決型会議ファシリテーション1日講座参加者募集
★ 問題解決型の会議を進行するファシリテーターのための講座です。
最短2時間で、行動まで落とし込みます。
チームの力を最大限に引き出したいチームリーダー、コンサルタント、人事担当者のかたがた、
お客様チームのニーズを引き出したい専門職の方、会社を変革させたい2代目社長、ご参加お待ちしています。
詳細はこちらのHPをご覧ください。
開催日時 2009年4月18日(土) 9時半~18時半
開催場所 (株)ビズクリエイト2階セミナールーム
群馬県富岡市富岡1441-1(上州富岡駅前)
定員 20名
参加費 15000円
申し込み・問い合わせはこちらのHPから
最短2時間で、行動まで落とし込みます。
チームの力を最大限に引き出したいチームリーダー、コンサルタント、人事担当者のかたがた、
お客様チームのニーズを引き出したい専門職の方、会社を変革させたい2代目社長、ご参加お待ちしています。
詳細はこちらのHPをご覧ください。
開催日時 2009年4月18日(土) 9時半~18時半
開催場所 (株)ビズクリエイト2階セミナールーム
群馬県富岡市富岡1441-1(上州富岡駅前)
定員 20名
参加費 15000円
申し込み・問い合わせはこちらのHPから